ヒカリはガラガラの大きな建物の中、所在無さ気に座っていた。
確か一応国際空港だったはずなのだが、と言っても現在国際便はせいぜいソウルと上海行き位なのだろうが、仙台空港ビルは比較的単純な構造の建物で、2階のロビーで待っていれば飛行機を降りてきた乗客に確実に会えるという仕組みになっている。
ヒカリの座っているベンチというかソファーというかは、4×3列ほど自動販売機に囲まれて並んでいるが、現在ヒカリ以外に座っている人は4人程度だった。
ここは出発用のロビーとは別フロアになっているせいもあるだろうが、いや、そもそもヒカリはそんな場所には当然入れないのだが、ヒカリの座る一角はいつまで経っても人影はまばらであった。
やがて何の前触れもアナウンスも無く、唐突に向こうの自動ドアが開き、飛行機を降りてきた一団がわらわらとやって来た。
やってくる人々の大多数はビジネスマンだ。2、3割位、旅行帰りらしい主婦や家族連れもみられる。若者はあまりいない。
ヒカリは立ち上がったが、急な人の多さに少し呆気に取られたような表情を見せていた。腕を組むヒカリ。
「もしかしたらこの便には乗っていないのだろうか」という大分希望的観測の混じった不安がヒカリの頭をよぎった頃、ドアの向こうから右手でスーツケース、左手でボール箱の3つ乗ったキャリアーを引っ張っている大柄の女性が現れた。
「ヒカリ!」
女性は急に立ち止まり右手をスーツケースから放すと、こぼれんばかりの笑顔で手を振った。後ろから迷惑そうによけて通るビジネスマン達。
ヒカリは無言で、何か申し訳無さそうに小さく右手を上げて振った。
数時間後
洞木家の居間兼食堂は大変な事になっていた。
「そんでなヒカリ、その人は、何やったかな、石切美術館?か何や言うとこの人らしいねんけどな、まだ20代やのに世界中飛び回ってはるらしいで。母さんあんな人憧れるわー。」
「マリアさんにはマリアさんの良い所があるじゃないですか。」
テーブルの上に広げられた食材やら土産物やらその他折り込み広告の紙に包まれていてまだ正体の不明な物体やらを眺めながら、降参したように呟くヒカリ。
「何ぃ? もいややなあ、そんなん言うても何も出んよー。あっ。ミチルちゃんやないか?」
玄関の音に顔を向けるマリア。
居間のドアが開き、ピザ屋の箱を持ったミチルが微笑んで現れた。
「ちわ。」
マリアは両手を差し出して立ち上がった。
「あー。ミチル。大きなったなあ。」マリアはミチルを抱きしめ、しばらくするともう一度ゆっくりと見る。
「何、少し痩せたやろ、なあ。」
どことなく矛盾した事を言うマリア。
「あ、ええ、まあ。年頃ですから。」
「あっかんでそんなん。子供の内は、ちゃんと食べとかんと。体に悪いよー。」
ミチルの肩を叩きながら、ヒカリの方を向くマリア。笑顔を作るヒカリ。
「あー、でも2人ともほんまに元気そうやね。安心したわ。」
「電話で充分見てるじゃないですか。」
微笑むミチル。
「それと、こう会って顔見る言うのは全然違う事よ。…あー、速いとこピザ食べんと冷めてまうで。」
「あ、ええ、そうですね。じゃあちょっと…この辺どかせて良いですか。」
立ち上がるヒカリ。
「んん。あヒカリ、お手洗いって、そこの、階段のすぐ下やんな。」
「あ、はい。」
「ああ。」
マリアは居間を出て行った。
一瞬部屋は静寂に包まれた。
姉妹は同時に大きく溜息をついた。
「「お母さん」は、相変わらず「元気」みたいね。」素の表情に戻って、周囲を見回すミチル。
「何なのこの貨物群。」
「「お母さん」に聞いてよ。全く何と言うか…ああ、飲み物用意するわ。」
「姉貴も世間ヅラの良いこって。って言うかさ。いつまでマリアさんはここにいる訳。まさかほんとに同居する訳じゃないでしょ。」
「これから話し合うんでしょ。鈴原がどこに行くかも含め。」
「って、トウジ君の意思は?」
「それはもちろん最優先よ。別にマリアさんだって話の分からない人じゃないんだから。」
ドン、と冷蔵庫の扉を閉めるヒカリ。
「良い人なんだろうけど苦手なんだよねー。」
「ミチルとは合わないタイプなのは分かってるけど。少しは我慢して。」
「ま。話し合うのはどうせ姉貴なんだろうけどさ。一応ここの世帯主な訳だし?
でも、私の希望としては、」
「分かってる。」
ヒカリはにこりともせずにミチルにコーラ缶を手渡した。
「私の事を碇君に言ったのね。」
ヒカリは驚いて顔を上げた。
「綾波さ…碇君が、言ったの?」
やや怒っているらしいものの十分冷静な様子でレイは「いいえ」と答えると、ペンギン室へ通じる廊下へのドアの方に目を向けた。
「葛城さん? ペンギン?」
「ペンペン。」
「ペンペン?」眉を上げ、レイの言葉を繰り返すヒカリ。
「碇君が話したようね。誰かまでは言わなかったようだけど、彼の好きなメスはメスとしかつがいにならない、と言っていたそうよ。」
「よっぽどショックだったんだ。」
ヒカリは手を自分の頬によせた。
「私、一体何やってんだろ。」
結局家から逃げても仕方無いのに。どこへ行っても自分のツケばかり。どこまで行っても自分は自分。
私、自分が嫌いなのかな。でも私は、結局、
「どうして。」
「え?」
「どうして言ったの。」
「ああ。ん、ごめんなさい。その…碇君って、実は凄く、楽観的で、強い人のような気がするの。それが羨ましかったのかもしれない。…ううん、理由になってないわね。うーん…」
「大丈夫よ、洞木さん。」
「は?」
レイはすくっと立ち上がり、ぴと、とヒカリのこめかみの辺りに手を置いた。
「碇君は確かに良い人よ。でも彼に、私達の事が全て分かる訳では無いわ。」
レイは微笑みながらヒカリの耳元に口を近づけた。鳥肌の立つヒカリ。
「あ、あや、綾波さん、ちょちょちょっと待って、だから私と綾波さんはそういう事では」
「お願い。」ヒカリの手を上から包むように握るレイ。
「やっぱり私、押さえられない。」
「そんな事言われても、綾波さん、ひゃあ、綾波さん、許して、あ、く、くすぐったい」
ガタン
「きゃ。」
ドアの向こうから現れたミサトに思わず立ち上がるヒカリ。
ミサトは目にみえて青い顔で目を泳がせながら頭を振っていた。
「あ、の、葛城さん、いや、あの、これは、」
「ヒカリちゃん、レイ、ちょっと、手伝って貰っても良いかな。」
「…何をですか。」
ミサトの無粋なタイミングに不機嫌になっているらしいレイが尋ねる。
「うん、んー、ちょっと、実験…」
ヒカリとレイは目を見合わせた。
ヒカリは内心ミサトに手を合わせながら、レイに肩を上げ、ペンギン室の方向へ首を傾けて見せた。
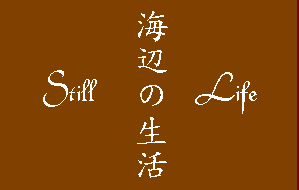
ペンギン室には、いつものペンギン達とカスパー、バルタザールの他に、台にガムテープで付けられたビデオカメラと、髭を生やした男性、それにリツコがいた。
「が。が。」
全員を見回すギンギン。
「入ります。…この2人が、いつも実験を手伝ってもらっている子供達です。綾波レイさんと洞木ヒカリさん。…この方は、この水族館の理事長で、普段は南仙台の大学の方にいらっしゃる碇理事長よ。」
「…」「碇、理事長?」
「ええそうよ。」
「後で説明する」という顔で2人に頷くミサト。
「…」「あ、はじめまして…」
仏頂面のレイと会釈をするヒカリ。
「…」
ゲンドウは顔をリツコに向けた。
「大丈夫です。彼女達は信用できます。」
「…そうか。」
レイの様子はそれほど変わらないが、ヒカリは目に見えてムッとした表情になった。
「それでは始めよう。」
理事長の声に頷くリツコは、子供達2人とペンギン達2匹を見比べた。
「ヒカリちゃん。」
「はい。」
「ピンギと、少し会話をしてくれるかしら。」
「は、はあ…」
リツコは微笑んでみせた。
「理事長は改めて、私達とペンギン達が本当に自由に意思を疎通し合っているかどうか確認されたいの。ここまで劇的にコミュニケーションが可能となった例は今まで無かったでしょう。だから理事長もこの目で見られないと信じられないそうなの。そうですわね、理事長。」
「…ああ。」
「…私なんかで、良いんですか?」
「あなた達が一番ホッパリッシュに熟達しているわ。お願いできる?」
「…」
リツコとゲンドウ、ギンギンを見比べるヒカリ。
ヒカリは軽く息をつくと、バルタザールの「椅子」に座った。
「どういった、会話を…」
「そうね、まあ普段の会話で構わないわ。」
「…」
<こんにちは、ギンギン。>
<こんにちは、ヒカリ。今日はたくさん人間がいるな。あの大きな男は誰だ。>
「ええと…」
<このプールの、「上の人」よ。>
<「上の人」とは何だ。老人の事か。>
<いや、そうじゃなくて、ええと…大切な人なの。このプールを作った人よ。>
「くあ。」
<このプールを作った人か。このプールは人が作ったのか。>
<ええまあ大体、プールは人が作るんだけどね…>
<彼はまたプールを作りに来たのか。>
<いや、そういう訳じゃないんだけど…>
「うむ…」
バルタから赤外線接続された隣りのモニタで会話の逐語訳−例の「<始まる><終わる><ペンペン><終わる>」といった日本語だ−を見ていたゲンドウは呟きを漏らした。
「素晴らしいな。」
「彼等の知能も御存知の通り高いのですが、御覧になるとお分かりでしょうが彼等はほぼ無報酬でこの会話を自ら楽しんでいます。今や彼等同士で常にキーボードの前に立っているような状況です。」
「こちらの命令は聞くのか。」
ヒカリとレイは、ゲンドウの言葉に顔を上げた。
「…ヒカリちゃん、ポコティファに、ちょっとプールまで行って戻ってくるように言ってくれるかしら。」
「…」
「ちょっとお願いするだけだから。良いでしょう。」
「…」
<ペンペン、一旦プールへ行って、それからここにすぐ戻ってきて。>
<何故だ。>
<…とにかく、やってみて。今日は暑いでしょ。>
<暑いが、今日だけ暑いという訳ではない。大体すぐここに戻ってくるのなら意味が無いではないか。>
<とにかく、行って戻ってくれば良いの。それ位簡単でしょ。>
<今は私はここにいたい。何故そんな事をしなければならないのか。>
<…あなたってつくづく強情ね。>
<私は何と言われようとここを動かない。>
「…」ヒカリは溜息をついた。
「![]()
(<ヤリイカ>)
(「ヤリイカ。」)
」
「くあ。」
ペンペンは当然のようにキーボードを離れ、よたよたとプールまで歩き、首から落ちるようにプールの水へと飛び込んだ。
ドアが閉まると同時に、レイとヒカリの視線はミサトに注がれた。
「…あなた達はどう思った。」
3時間30分近くほとんど口を開いていなかったミサトは唐突に2人に尋ねた。
やや疲れたらしい様子のヒカリは、レイと目を合わせた。
「どう、って…一体、今のは何だったんですか。」
「碇理事長と赤木博士。」
「それはもう分かってます。」
ミサトは手を腰につけ、山で熟睡する2匹を見、それからガラスの向こうを歩いていく2人を見た。
「あまり良い感じはしなかったでしょ。」
「…」
返事に詰まるヒカリにミサトは頬を緩めた。
「ごめん。それは誘導尋問よね。私は、良い感じはしなかったわ。」
未だに彼等を、道具みたいに…
「いや、私も同じか…」
「碇理事長は碇君の父親なのですか。」
急に口を開いたレイに少し驚きながら、ヒカリも頷く。
「ああ、そう、そうですよ。全然似てなかったけど、理事長さんの息子だなんて初めて聞きましたよ?」
ミサトは肩を上げた。
「それね。1回シンジ君に聞いたんだけど、何だか、良く分からない、みたいな事言ってたわ。」
「…」「良く分からない?」
「…ほんとにそう言ってたんだもん。」ミサトは迫ってくるヒカリに言い訳するように答える。
「理事長に聞いてみては。」
「…ええ。そうですよ。」
レイの言葉に頷くヒカリ。
「う…今度、ね。」
ミサトは小声で答えた。
「葛城さん、事情を説明して下さい。」
「え、だから良く分からないって、」
「ペンギンの事です。」
「あああ、そっちね。」
「ええ、そうです、それも、一体どういう事なんですか。葛城さんのさっき言ってた事も、それこそ良く分からなかったし…」
「…良いの。あれは、忘れて。独り言だから」
「説明して下さい。何をペンギンにしようとしているのですか。」
ペンギン室を出て行こうとしたミサトの前にレイが立ち塞がった。
「そ、そうです。葛城さん、納得の行く説明をして下さい。いくらボランティアでも、私達にもそれ位の権利はあるはずです。」
「…分かったわ。降参する。」
ミサトは両手を上げて見せた。
「ギンギンは能力確認のテストを受けたのよ。カメラがあったでしょ。あれで撮ったビデオを、ドイツの方の大学に送るの。」
壁によっかかり、腕を組むミサトが言う。
「だからさっき理事長さんが「これなら合格だ」って言ってたんですね。…でも、テストって、何のテストですか。」ビール箱兼椅子に座るヒカリが質問する。
「能力確認のテストよ。」
「…葛城さん。」
「どれだけ自由に意思疎通が可能かのテストね。それはやってて分かっただろうけど。このテストはつまり、どれだけ温泉ペンギンという種が重要かの確認でもある訳。」
「それでは、これから学会に正式に発表するのですか。」
ヒカリの隣りで腕を後ろ組みしながら立っているレイが聞く。
「…多分。」
「多分?」
「いや、これは本当に知らないの。私は一飼育係だから、そこまでは分からないわ。リツコや理事長は知ってるんだと思うけど。」
ヒカリにまた弁解するかのように答えるミサト。
「…でも、だからテストってどういう事なんですか。合格したらどうなるんですか。」
「ギンギンはドイツに送られる事になるわね。」
「…え?」
ヒカリはレイと顔を見合わせた。
ある…ある、研究家が、いたわ。非常に、野心的で、異なる分野の学問や技術を吸収する事に長けていた人だったそうよ。その人は人間以外の動物とコミュニケートする事が夢だったの。彼は、人間以外の種が言語を持っているとは考えていなかったわ。いや、もちろんその当時既に人間以外の動物も種によっては言語的コミュニケーション手段を持っている事は確認されていたんだけど、人間の言語のような抽象的かつ複雑な体系の言語を彼等が独自に持っているかどうかという話ね。で、まあ、今に至るまでそういった例は確かに発見されていないわ。
でも彼は、それが動物との会話の可能性を完全に否定するものだ、とは考えなかったの。つまり人間の赤ん坊も最初は言葉を知らない訳で、動物だって、きっかけさえ与えれば人間並みの言葉を使う事は可能だと彼は考えたのよ。
それまで、チンパンジーやボノボを使って行われた実験では、主に、動物を赤ん坊の頃から人間のように育てるという手法が取られる事が多かったそうよ。でもこれは、結局うまくいかなかったの。そこで彼は、当時格段に進歩し始めていた遺伝子工学を使って種の知性を強制的に底上げする事を考えたわ。確か…エレクトリカリー・バーバライズド・アニマル理論っていった、はずよ。私も実は、それの詳しい内容は良くは知らないんだけど。それで、彼が実験材料に選んだのは猿ではなく、当時はそれほど知能が高いとは考えられていなかった動物だったの。ペンギンね。これには幾つか理由があったんだろうけど、大きな理由として海を泳げるというのがあったわ。つまり…どうやらその研究家は、まあ、今となってはこれも確認は出来ないんだけど、この理論を使って生物兵器を作ろうとしていたようなのね。
「泳ぐだけなら、」レイはミサトの話の腰を折った。
「イルカ等の方が適任なのでは?」
「確かにね。私もだから、どこまでが本当でどこまでが噂なのか正直良く分からないのよ。それにそういった事の理屈は、後からいくらでも付けられるでしょ?」
肩を上げるミサト。
「私が聞いた話では、ペンギンの方が改造しやすかっただとか、ペンギンの場合陸上も歩けるとか、そんな事だったような気がしたけど…でも歩けるったってペンギンだしねえ。」
「綾波さん、座る?」
「…ええ。」
立ち上がるヒカリ。
「そもそもそこまでする意味が軍事的にあるのかっていう意見もあったらしいんだけど、これは、作戦行動のやり方によっては実際効果的ではあるらしいわ。つまり例えばペンギンに何かの人工的な病原菌を持たせて目標の国へ行かせる訳。そうすると、…うーん、これも細かい理屈は忘れたけど、結構その国の生態系がズタズタになるらしいわよ。とにかくそんな内容の研究をしていたらしいわ。」
でも、さっきも言ったけど、この辺りの事は実は噂にすぎないの。何でかっていうとその研究家…動物学者であり、軍事…技術者?でもあったという事なんだろうけど…そのチームは研究中に事故を起こしてね、彼等の記録などは殆ど残されていないのよ。それにその事故の直後に…セカンド・インパクトっていうのがあってね。
「宇宙ステーションが落ちたんですね。」
ミサトはヒカリに頷いた。
「それも色々噂はあるんだけどね…まあ、良いわ。…だって、そんな事ある訳無いもの。」
大体、仮にそうだったとしても、もう全部起きちゃった事なのよ。今更私がどうこう出来る事じゃないのよ。
ミサトの呟きに、レイとヒカリは目を合わせた。
「ああ、とにかくそれで。それでもある別の科学者が奇跡的に遺伝子データのバックアップを日本で見付けたのよ。いや、まあ南極で死んだ研究家は日本人だったから、それが日本で見つかるのは当然といえば当然の話なんだけど。で、その科学者はそれを元にまたその実験を再開しようと考えたのよ。」
ミサトはそこで口を閉じ、ペンギン山の方に目をやった。
「…でも、つまり1回その実験は失敗したっていう事でしょう? 危険なんじゃないんですか?」
ヒカリはどこか上の空の様子でミサトに尋ねた。
「うん…私もそう思うわ。その科学者によると、当時と今では神経制御の技術が全く異なって、えーと、簡単に言うとほとんどエネルギーを使わなくなってるから全く問題は無いって言ってたけど?
どこまで本当なんだか…」
ミサトは首を振った。
そしてその科学者はついに当時そっくりのペンギンを生み出す事に成功したわ。だけどその科学者達のチームはその内に、実は彼等の実験が完全に成功ではなかった事に気付いたの。どういう事かっていうと、遺伝子的に欠陥を抱えていて、だから…短命だし、子供を作る事が出来ないのね。そこで現在彼等はペンギンに更に遺伝子改造をして、人工的なサポート無しに暮らす事が出来る種を作る事を考えているのよ。
「彼等は…」ヒカリが言葉を選んで質問する。
「彼等は、今でもそのペンギンを軍事目的に使用するつもりなんですか。」
「…そうでない事を祈るわ。…少なくとも、彼等はそうではないと言っているわ。」
「あまり、信用していない、言い方なんですね。」
頭を振るミサト。
「元々学者って苦手なのよ。子供の頃から私、学者は嫌いだったの。学問の世界を探求する…っていったら聞こえは良いけど、結局現実の世界から逃げてるだけじゃないか、って、良く思ってたもん。」
ミサトは壁から背中を離すと、ペンギン山で寝る2匹のペンギンに近づいた。
「昔話はもう良いでしょ。とにかく、ギンギンはドイツに行く事になるわ。」
「…」
レイが軽く目を広げた。
「…それでは、その科学者というのは赤木博士で、現在の実験のペンギン達というのがペンペンとギンギンなのですね。」
「…綾波さん、鈍い。」
「鈍い?」
ヒカリに聞き返すレイ。
ペンギン室を出た所で、3人の前に白衣の冬月が立っていた。
「館長。何か?」
冬月はミサトを手で制すると、レイの前に来た。
「君が、綾波レイ君だね。」
「…」
「今まで済まなかった。君には、言い訳の仕様も無い事は分かっている。しかし私も手を尽くして探したが、君の生まれた年はセカンドインパクトの翌年の、一番混乱していた時期だったので分からなかったのだよ。まさかこんなに近くに居るとは知らなかったのだ。」
ミサトとヒカリは急に土下座をした冬月に思わず後ずさった。
「私が、君の父親だ。」
「…あなたの名前は?」
「冬月、冬月コウゾウだ。覚えているかね。」
「いいえ。」
レイは殆ど無関心ともとれる様子で答えた。
そのまま平然と歩いて行こうとするレイの手を冬月は押さえた。まだ用事があるのかと言いたげな様子のレイ。
「済まない。本当に済まなかった。君のお母さんは生前、子供がいるとは知らせてくれなかったのだ。もし知っていたら、私は」
「有り得ない仮定の話をする必要は無いわ。」
「…ああ、済まない、勝手に話を進めてしまって。しかしレイ、今まで起きた事は変えられなくても未来は変えられるはずだ。実際私が館長をつとめている水族館に君が通っていたというのも素晴らしい偶然だろう。どうかね、これからは私と一緒に暮らしてみる気はないか。」
「…」
ヒカリはレイの顔が、見慣れた目には明らかに敵意のある表情になっているのに驚いた。
「…頼むレイ、今までの事は水に流して、一緒に暮らそう。私は、今からでも親としての義務を君に果たしたいんだ。」
「…その必要は無いわ。」
「綾波さん!」声を上げるヒカリを、ミサトが肩に手を置いて止める。
「私はあなたとは今までボランティアと館長以上の関係は無かったし、これからも無いわ。」
「私を…許す事など出来んか。」
「あなたに親としての義務は期待しないわ。」
「…そうか。」
「さよなら。」
レイはすたすたと歩き出し、ふと振り返った。
「洞木さん?」
「あ、う…し、失礼します。」
ヒカリは慌てて会釈すると、レイの方へ走って行った。
ヒカリが振り向くと、冬月館長は廊下で座ったまま動かないでいた。ヒカリは逃げ出すように水族館を出た。
…しかし家と水族館から逃げた先が病院だというのは失敗以外の何物でもなかった。これでは戦術ミス以下の問題だ。自分が錯乱していたとしか思えない。
ヒカリはトウジがベッドを叩くのに気付いて顔を上げた。
[どないしてん。]
「え。」口で答えるヒカリ。
[元気無さそうやで。俺が明日退院するのが、そんなに嫌か。]
「ふん…」
ヒカリは微笑んで肩を上げた。
[自分だって楽しそうに見えないわよ。]
[嘘をつくのは委員長ほどうまないからな。]
「…」「…」
[うまくなったね、手話。]
[それもわいの台詞とちゃうか?]
[ああ、そうか。そうね。]
[…知っとるんか。わいが振られたいう事も。]
[…振られた? 鈴原、誰かに振られたの?]
ヒカリは真顔で尋ねた。
[振られた…って、そもそも鈴原誰かが好きだったの? 前聞いた時は「おかんが好き」とか言ってたじゃない。へえー、鈴原も一人前に恋愛するんだ。]
「…」
[ねえ、どういう子なの? 鈴原の好みって。]
「…」
[あ、ごめん、振られたんだったわよね、ごめん、無神経な聞き方しちゃって。]
[…冗談や。本気にしたか?]
[冗談? そうは、見えなかったけど…]
[ほんまに冗談や。…どや、わいも、大分嘘うまなったやろ。]
[そんな事で私騙したってしょうがないと思うけど?]
笑って見せるヒカリ。
[わいは昔から委員長一筋やからな。]
「…」
[委員長?]
[どおもありがと。]
[…冗談やで?]
[分かってるわよ。鈴原を振った覚えも無いし。]
ヒカリは勢い良く溜息をついた。
「…」「…」
ヒカリは立ち上がった。
[そろそろ行かなくちゃ。]
[あーほんまか。ほんなら…また明日。]
「…」
ヒカリは一瞬口を開きかけた。
[なんや。]
[…あー、今日のおかずどうしようかなあと思ったんだけど。マリアさんが何か作ってくれるって言ってたなと思って。]
[…そうか。]
[じゃ。]
ヒカリは手を開き軽く頭から下げて見せると、ベッドからドアの方に振り返った。
「もっと嘘が下手な方が良かった。」
ヒカリは呟くと病室を後にした。
ヒカリがその夜寝付けなかったのは、マリアの巨大お好み焼きがお腹にもたれていたという事だけが理由な訳ではなかった。
ヒカリは何となく、理屈ではなくあくまで何となくのイメージなのだが、逃げられなくなったら、あえて逃げなくても良いのではないかと思いだしていた。逃げないのと、立ち向かっていくのは違うのではないか。逃げないというのは表現からして否定形、消極的な行為なのだ。ある物事に立ち向かっていくのはエネルギーを消費するが、逃げないというのは違う。波風を立てずに、うまく波を乗り越えていく…
波風…和…調和…日本的な発想ね。
でもそれが私の住む所なの。
ヒカリは自分の頭の中にふと、シンジの顔が浮かんでくる事に驚いた。
私、結構、浮気者なんだな…
…鈴原は姉弟といっても母親が違うし、今は彼は丁度振られた所だからある意味チャンスだわ。それに比べて碇君は、碇君も、振られた所なんだけど、彼の場合私が追い討ちかけるような事を言ったから、今だって恨まれてても文句は言えないような状況なのよね。でそれで碇君が気になるって言う事は、打算の感情じゃないって事?…
ってそれはいくら何でも考え過ぎね。
ああ、もう、糸がこんがらがりすぎなのよ。しかも全部私の所で絡まってるじゃない。
その時部屋に置きっぱなしになっていた子機が鳴った。
「…糸だ。」
ヒカリは呟くと、駆け出すように子機を手に取った。
「綾波さん?」
「…何故、分かったの?」
どうやら驚いているらしい声が受話器の向こうから聞こえてきた。
「…私も丁度、綾波さんと喋りたい気分だったからよ。」
「そう。」
「綾波さん教えて。綾波さんは、どうしてそんなに…強いの。」
「強い?」
「うん。」
「それは間違いだわ。強いのは私ではなく洞木さんよ。」
「…私?」
「ええ。」
「…強いの、私。」
「ええ。それが洞木さんの美しさの一つの理由でもあるわ。」
「…ますます糸がこんがらがったわ。」
「糸?」
「あ、ううん、こっちの話。ねえ、綾波さんは今何してたの。」
「洞木さんの事を考えていたわ。…夜は大体洞木さんの事を考えている事が多いわ。」
「…そう。」
何だか誇らしげに聞こえるレイの声に、ヒカリは溜息混じりで答えた。
翌日の名取市は快晴だった。
「ヒカリ、ヒカリ。」
「あ、はい。」
マリアに呼ばれたヒカリはキッチンから客室にやってきた。
「どう。母さん格好こんなで良えかな。」
「は…あ、はい。ええ。」
「そう? 似合うてる?」
鏡の前で真っ赤なパーティードレスのような物を着たマリアは、そのグラマラス、というか非常に迫力のある体でポーズをつけて見せた。
「え、ええ。」
「…何?」
「…でも、病院ですよ、行くの。」
「ええやん、トーちゃん退院すんねんで。派手な格好で行ってもバチは当たらんて。それよか、」
「あ、ごめんなさい、ちょっと台所見てないと。ミチルじゃ心配で。」
ヒカリは冷や汗を流しながら部屋を離れた。
コン、コン。
「どうぞ。」「どうぞ。」
病室に入ったマナは一瞬目を見開き、そして微笑んだ。
「今日は大入り満員ね。」
病室ではマリア、ヒカリ、ミチルがトウジのベッドを取り囲むように座っていた。
マリアは立ち上がってマナに丁寧に御辞儀をした。
「ああ、はじめまして。あなたがいつも息子の世話をしてはる方ですか。」
「ああ、いえ、私はただの看護婦ですから、普段の世話はむしろヒカリ、さん、の方が、ね。」
「ああ、そうですか…いや今までほんまに有り難うございました。」
[耳が聞こえんようなって一番良えと思うんは、やっぱおかんのうるさい話を聞かんですむいう事やな。]
[何強がってんの。]
「…何2人で話してんの。」
「あ、別に何でも無いのよ。」
慌ててミチルに答えるヒカリ。
マナは微笑んでトウジのベッドに近づき、彼にゆっくり、口をはっきり開いて話し掛けだした。
「鈴原君、これから、すぐにドクターが来て、最後の検査をするから、それが済んだらもう、ここから出てもらうからね。今の内に荷物とかの準備をしておいてね。」
「…」
頷いて見せるトウジ。
「ええと…お母様は、こちらに住んでらっしゃる訳、では無い、んですよね。」
「ああ、それはもうほんまにトウジには悪いと思うてて…そやからこっちに来るようにいつも言うてるのにこれがまた父に似て強情で、」
「ああ、それじゃヒカリさんに言った方が良いかしら。あのー、緊急時用の電話番号、」
「あ、はい、記憶させましたし、」
「ちゃんと控えも取ってあるわね。OKOK。じゃ、」
マナは部屋を見回した。
「お邪魔しちゃ悪いから、私はもうそろそろ」
「いえいえ何言うてますのん、こちらこそ邪魔でしたらいつでも」
「いえ、あの、全く大丈夫ですから。家族、水入らず、で、あの、お楽しみ下さい。あは。は。」
マナは何度も会釈をしながら病室を出て行った。
「ふー。」
マリアはトウジ達の方に振り返った。
[何や、偉いべっぴんさんやったなあ。]
マリアは口と手両方で言った。
[…ただの看護婦や。]
マリアは眉を上げた。
[何や、その言い方。それがおかあちゃんへの口の利き方か?]
「あ、あの、マリアさん、」
「ヒカリは黙っとき。」[ええかトウジ、もう何や、十分か? 二十分近く経っとんのに何もせんとボサーッとして。あんた自分がどれだけ皆に助けてもらてるか分かってるか?
ヒカリも、ミチルも、病院の方々も、みんなあんたの為にどれだけ時間をさいて、心を砕いているか、]
[…病院は別に仕事やろ。]
[あーそや仕事や、そやけどあんたみたいなただの不注意で事故ったもんに構ってはる間、他の怪我人の方々は、いやちょ待ち、そもそもその治療代払っとるのはどこの誰よ。]
[分かった! 分かりました。感謝してます。]
[何や心のこもっとらん有り難うやな。ま、ええ。おかあちゃんがあんたの面倒見るのはこれはま当然の話やからな。]
マリアは至極真面目な様子で口と手両方で話している。
[何を言いたいねん…]
[そやけど、ヒカリやミチルはどうや。自分達かて生活大変やのに、その上あんたの世話もしとるんやで。あー、さっきの看護婦さんも言うとったやろ。ほら、今日は退院の日なんやから、ちゃんとこういう機会お礼言っとき。]
[あ、あのな。]
[何、当然の事も出来んような子に育てた覚えは無いで。]
「…私、ここの病室来たの何回目だっけ。」ミチルがヒカリに小声で囁く。
「4回目…だったっけ?」
「3回目だったと思う。ところでさ。私トウジ君の世話ってした事あったっけ。」
「…」
[何、あんた男やからって何でもしてもろて当然思うとるんちゃうか。]
[あほか。思うてへんわ。]
[そういうのを「甘え」言うんやで。え? 思うてない? そしたらちゃんとここで今、有り難うって2人に言えば良えやろ。]
「…」
トウジは溜息をつくと、2人の方に向き直り、呼吸を整えた。
[何で言われへんの?]
[今言おうとしてたとこやねん!]
がう、がぐご、がが。
「ねえ、さっきからトウジ君、声、」
「分かってる。」
ミチルはヒカリの声の様子に横を向き、彼女の表情に眉をひそめた。
「どしたの。」
マリアはふいに目を細め、頷きだした。
[…あー、あー。はいはい。分かりました。そういう事やな。]
[何や今度は。]
[あんた2人のどっちかに…おかあちゃんこんな事言われへんわ…」
[お前ほんまに殺すぞ。]
「何か…こうやって見ると2人そっくりなのね。」小声で囁くヒカリ。
「…」
手話とは思えないうるさい会話をする2人をしばらく眺め、ミチルは頷いた。
「親子だからね。」
「そうね。」
鈴原にとって、マリアさんは欠く事の出来ない一部なんだ。マリアさんのいない鈴原は鈴原じゃない。
マリアさんはもちろん持っているけど、仮に彼女がグリーンカードを持っていなかったとしても、そんな事は、重要じゃ、少なくとも一番重要じゃ、ない。一番重要なのは、マリアさんが鈴原のお母さんだって事なんだ。
「姉ちゃん。」
ヒカリは隣りにひじで小突かれた。
[あー、有り難う。…えー、いろいろ。]
トウジが何か謝るかのような神妙な面持ちで2人に頭を下げていた。
「あ、う、」[どう、いたしまして。]
姉妹は苦笑いしながら答えた。
ヒカリはベッドの向こう側で勝ち誇った表情になっているマリアにも頭を下げた。
「あ、マリアさん。私も。あの、有り難う。今まで。」
「あ、ちょっとすいません。」
洞木家、のテーブルの皿の数々に盛り付けられたルンピアやらアドボやらシニガンやらの前、からヒカリは立ち上がった。
[どないしてん。]
マリアは聞くトウジに目を細めた。
[あんな、女の子がこういう時は、どういう事か分からんか? ほんまそやから]
「あ、あの、お構いなく。すぐ戻りますから。」
ヒカリはマリアを押さえると、笑顔で居間のドアを閉めた。
コン、コン。
「入るよ。」
ミチルは2階のヒカリの部屋のドアを開けた。ヒカリは小さな窓から、南仙台のこじんまりとした街並みを眺めていた。
「何やってんの。」
ミチルの声にヒカリは振り向いた。
「疲れた?」ベッドに腰を降ろしながら聞くミチル。
「…かもね。」
「じゃ、言っとこう」
「大丈夫よ、もう戻るわ。…今、ちょっと、考え事しててね。」
「考え事?」
「うん。…何て言うか、人には…うーん…人とは、結構、その…仲良くするのは大切だな、っていうか…」
ミチルは首を傾げてみせた。
「姉ちゃん…言ってる事、訳分かんない、っていうか、分かるけど分からないよ。」
「まーあんたには分からないでしょうね。」
「…ねえ、姉ちゃん。…一緒に暮らすの?」
ヒカリは少し真面目な顔になると、ミチルの隣りに腰を降ろした。
「私達がどうかは置くとして…鈴原にとっては、彼女と一緒に暮らすのは、自然な事なんじゃないかな。」
「私達は?」
「…分かんない。まあ、なるようになるでしょ。」
ヒカリはミチルに微笑んだ。
「でも良い人よ。」
「姉ちゃん裏切ったね。良い子になっちゃって。」
「違う、そんなんじゃない。そんなんじゃ、ないの。」
声を強めるヒカリ。
「そんな簡単に割り切れる事じゃないわ…でも、…でも、鈴原にとっては…」
「…好きなんだね。」
ヒカリは驚いて顔を上げた。
「ミチル…」
ミチルは笑顔で腰を上げた。
「いつまで便秘してんの。もう好い加減下りてこないと、私一人じゃとてもじゃないけど」
「ミチル。」
「何。」
「ごめん、私今から綾波さんの所に行ってくる。」
「はあ?」
「綾波さんも…綾波さんも、色々と、問題があるのよ。友達として話したい事があるの。」
「いや、でも、別に、今じゃなくても、」
「今行きたいのよ。ごめん、後頼んだから。」
ヒカリは小物入れの上の小さなバッグを手に取った。
「ちょ、ちょっと! 姉ちゃん!」
「頼んだわよ!」
「あ、あの2人私処理しきれないわよ! ちょっと!」
ヒカリは部屋を飛び出した。
「確か、この辺…よね。」
電柱の街区表示を確認するヒカリは、ふと目の前に黒い影を見つけた。
「あ、あ、あ、ああ。綾波さん!」
「…洞木さん。」
何とも嬉しそうな表情−具体的には、微妙に開いた口、少し外し気味の視線、やや細まる目等が合図なのだが−のレイが立ち止まった。
「え、と、今から、水族館に行くのね。」
「ええ。」
「ねえ、ちょっと、一緒に話しながら行かない?」
「話す?」
自転車に乗せてくれる訳ではないの、と少し言いたげにレイが聞きかえす。
「ええ。」
「何を。」
「綾波さんに、少し話したい気分だったの。あ、友達としてよ。」
「洞木さん…」
「と、友達としてよ?」
ヒカリは少し不安気に繰り返した。
ヒカリは自転車を押しながら話し出した。
「綾波さんは…お母さんも、お父さんも、ずっといなかったのよね。」
「…育てる親がいなかったという意味なら、そうよ。」
レイは不思議そうに頷く。
「でも、本当はお父さんがいたのよね。しかもあなたの事をずっと探してた。」
「彼が今まで、親として、私を養育するという義務を果たさないできたのも事実よ。」
「でもそれは、お父さんはあなたがここにいるっていう事を知らなかった、って事なんでしょう。」
「ええ。それでも、彼が私を育てなかったのも事実よ。私は今まで一人で全てやって来たわ。」
歩きながら、レイはヒカリの方を向いた。
「ただ、その事で彼を責めるつもりはないわ。」
「綾波さん。綾波さんは、今まで一人の力で、ここまで育ってきた訳じゃないのよ。」
「福祉施設の助けという意味では、もちろんその通りだわ。」
「うん。…そうよ。そうでしょ。ん…確かに、今までは、綾波さんのお父さんはお父さんじゃなかったかもしれない。でもこれからは、2人は親子なのよ。」
レイはしばらくヒカリの言った事を自分の頭の中で検討しているようだったが、やがて頭を振った。
「洞木さんの話は分からないわ。」
「綾波さん…」
「彼は遺伝的には今までも私の親だったし、これからも私の親であり続けるわ。でも、生活の上では私と彼は、今までも、これからも別人よ。」
「何で綾波さん、何で、そんな、意気地になるの。」
「事実を述べているだけよ。」
怪訝そうに答えるレイ。
「綾波さん。」ヒカリは言う事を吟味するかのように一旦口を閉じた。
「綾波さん。全ての人は、完璧じゃないの。どんな人にだって良い所もあれば嫌な所もあるわ。その…そういうものなのよ。……何か良い格言とか勉強しておくべきだったわ…その、あー、何て言うのかしら、とにかく。綾波さんは、今まで凄く、良くやって来たと思うし、凄く強いと思う。そういう部分は否定しないわ。でも、その、もう少し、ほんのちょっとだけ、他の人の、汚い所を許せるようになれたら、もっと、楽しくなれると思う。」
レイは首を傾けながらヒカリをじっと見つめている。
「ん、私も汚い所は大っ嫌いなのよ。人のも、自分のも。私、潔癖症だから。」冗談めかして言うヒカリ。
「でも、…でも、ん…少し、少しだけで良いのよ。自分のも、人のも、ね。」
「…」
「今の綾波さんは…損だよ。大きなお世話、なのは分かってるけど…損なのは、良くないよ。」
レイは立ち止まった。
「…綾波さん?」
「…いえ。」
レイは簡潔に答えると、再び歩き出した。
「……強いんだね綾波さんは。」ヒカリはレイには全く聞こえないであろう小さな声でぽつりと呟いた。
水族館に来たレイはためらうことなく館長室に突き進み、ドアを開けた。
「ちょ、ちょっと、綾波さん、」
「おお。レイ。と、君は、洞木君、だったかな。」
「は、はい。」
冬月は一人で本を片手に将棋の駒を置いていた。ヒカリは一人でやる将棋というものは聞いた事が無かったので少し不思議に思ったが、恐らく練習でもしていたのだろうと思い直した。
冬月は立ち上がった。
「お茶でも飲むかね。」
「あ、それでは」「結構です。」
ヒカリはレイを見た。
レイは館長の机の前に進んだ。
「それでは…何か、用事かね。レイ。」
「館長。」
「何だい、レイ。」
「…」
レイは彼女にしては珍しく、しばらく瞼を瞬かせ、困ったような表情になった。レイはやがて口を開いた。
「お、お…お父、さん。…と、呼んでも、」
「レイ!」
冬月は驚くレイの手を取り、自分の額に付け、目を閉じた。
「……不愉快であれば、」
「違うんだレイ、違うんだ。嬉しいんだよ。」
ヒカリは2人の様子を見てほっとしたように微笑んだ。
「レイ、これから君は一人じゃあない。私が誓おう、もう君に、寂しい思いは絶対にさせん。」
冬月は、普段からは考えられないような表情でレイに語り掛ける。
「ああ。ああ、そうだ、実はな。」
冬月は壁面のモニタをパネルで操作しだした。
「今度長町の方に住む事にしたのだよ。」
モニタに瀟洒な一戸建ての家の広告画像が表示される。
「実は、今まで、君のお母さんが亡くなってからずっと一人でやって来たが、新しいパートナーと同居する事になったんだ。これから一緒に、家族として、やって行こう。な。」
レイは初めて、少し微笑んだ。
「それは出来ません。」
「綾波さん!」
「お父さん、ごめんなさい。でも、それは…」
レイは冬月に目を合わせ、ゆっくりと、首を横に振った。
「…そうか。」
「綾波さん、だって、お父さんと、」
「いや、良いんだ洞木君。」
冬月は穏やかな表情に戻り、椅子に座り直した。
「しかしレイ、寂しくなったらいつでも家に来るんだよ。電話だけでも良い。もちろんここにもいつでも来なさい。…家は一室、お前の為に空けておくから、気が変わったら、いつでも、…来てくれ。」
「はい、お父さん。」
レイは頷いた。
「綾波さんなりに…頑張ったのよね。」
廊下に出て、後ろのドアが閉まった事を確認してから、ヒカリは呟いた。
「ええ。洞木さんの助言でなければちゃんと聞きはしなかったわ。」
至極当然、の顔で頷くレイ。
「…そう。」
「…ほら」「あ、ペンギンに、会わない?」
「…ええ。」
どこか残念そうにレイは頷いた。
ペンギン室ではバルタザールに何か別の小型端末を接続したミサトがキーパネルを叩いていた。
ミサトはドアの音に驚いたように立ち上がった。
「あ、ヒカリにレイ! 探したのよ!」
2人は顔を見合わせた。
「何か、あったんですか。」
ヒカリはミサトの後ろを覗き込むように近づいた。
「3人とも電話通じないんだもん。いや、そもそもレイに至っては電話が無いし。」
「必要性を感じた事が無かったので。」
「ああ、そうね。」
疲れたように手を上げるミサト。
「3人とも、って…私達、と…碇君ですか?」
「そうよ。…ああ、ヒカリは通じたけど」
「私はいなかったんですね。でも何でだろう。碇君は携帯持ってたはずだったけど…」
「碇君は今日は、岩沼の学校の方へ練習に行きました。」
「迷惑なるから電源切ってるんだ。」
頷き会うレイとヒカリ。
「とにかく。あなた達を探してたの。ここに来てくれて良かったわ。」
「ええ。で…」
「ギンギンをかくまいたいのよ。」
「…」
ヒカリは再びレイと目を合わせ、ミサトの方へ視線を戻し、その真剣そうな顔に溜息をついた。
「別にかくまわなくても良いのよ。つまり、何とかしてギンギンをドイツに行かせないですむ方法は無いか、考えているんだけど、良い案が浮かばなくって…」
ミサトは指をコンコンコン、と机風の出っ張りの上で叩いた。
「何故ギンギンをドイツに行かせてはいけないのですか。」レイは尋ねた。
「…」ミサトは自分の頭を整理するようにしばらく口を閉じた。
「この前言った通り、彼等は、いや、私達は、ギンギンに遺伝子改造を施そうとしているの。それは成功すれば良いわよ。でももし失敗したら?
これが成功するという保証はどこにも無いのよ。」
「赤木博士は、手術の成功率についてどう言っているのですか。」
ミサトは肩を下げた。
「多少のリスクを負っても実行する価値はある、としか言ってなかったわ。」
「じゃあ…本人にどうしたいか聞いてみたら?」
「…」「…」
「いや、あの、悪い事言いました?」ヒカリは上目遣いになりながら言った。
「その通りだわ、洞木さん。」
「え? そ、そう?」
ヒカリはミサトの方を見た。
「…良いわよ。」ミサトは肩を上げ、端末の接続を切り、バルタザールの前を開けた。
「ギンギン。」レイはプールのへりへ行き、沖合い2メートルに浮かぶギンギンを呼ぶ。ギンギンは聞こえないかのように水中に潜り一回りすると、レイの足元に姿を現した。
ざばーん。ぶるぶるぶる。ぴょこ、ぴょこ。
ギンギンは面倒なのか、山のペンペンを起こそうとしているようだ。
「ギンギン。」
「があ。」
レイはギンギンのフリッパーに軽く触れると立ち上がり、マギの方に歩いて行った。ギンギンはしばらくきょろきょろしていたが、やがてレイの後をついてきた。
<ギンギン、あなたはこれから遠くへ行く事になったわ。>
ヒカリは入力をするレイの後ろから会話を見る。一方ミサトは壁に寄りかかったまま一点を見詰めている。
<前ここに来たようにか。>
「葛城さん。以前ギンギンがいた施設は、これから彼女が行く施設と、」
「別。」
<…ええそうよ。また遠くのプールに行くわ。>
<どうして行くのか。>
<あなたを強くする為よ。それから子供を作ってもらう為でもあるわ。>
<ペンペンと、か。>
「…」
レイはちら、とギンギンを見た。
<あなたはペンペンと子供を作りたいの。>
<別に今は作りたくない。しかし作りたくなる事がこれからあるかもしれない、それは分からない。>
<…意味がよく分からないわ。>
<つまり、このプールにいる雄のペンギンがペンペンだけなので例に挙げたまでだ。>
<そう。>
「ギンギン、ペンペンが好きなんだ。」
レイの背後でヒカリが呟いた。
「そう?」
「ん…多分。」ヒカリは振り返るレイに頷く。
「…」
<もしペンペンと子供が作りたくなった時、今のあなたの体では子供を産めないわ。>
「綾波さん…」
「何?」
「…ううん続けて。」
<何故だ?>
<それを説明するのはこの言葉では難しいわ。>
<そうか。>
<もし新しいプールへ行けば、あなたも子供が作れるようなるわ。>
<別に今は作りたくない。>
<新しいプールへはあなた1匹で行くわ。>
「が。」
<それは出来ない。そうしたらペンペンが1匹になってしまう。>
<何がいけないの?>
<ペンペンは1匹では何も出来ない。プールも汚くなり、言葉もおかしくなるだろう。>
「ペンギンってきれい好きだったの?」呟くヒカリ。
レイは何故か微笑むような眼差しでギンギンに目を向けると、パネルを打ち出した。
<実は、あなたは選ぶ事が出来るわ。私達はあなたを強く、子供が作れるようにしたいわ。でも、もしあなたが1匹になるのが嫌なら、新しいプールに行かずここにいる事も出来るわ。>
ギンギンは急にフリッパーを上げ、頭を何度か振った。
<どういう事だ?>
<つまり、あなたが新しいプールに行くか、ここに残るか決めるの。>
<私が決めるのか。>
<そうよ。新しいプールに行けばあなたは子供が作れるようになるわ、行かない場合は、子供を作る事はこれから出来なくなるわ。一方、もし新しいプールに行く事になるとしばらくペンペンは1匹になるわ。行かない場合は1匹にはならないわ。>
<そもそも新しいプールに行ったら、ペンペンがいない以上子供は作れないではないか。>
「…」レイとヒカリは目を見合わせ、ギンギンに目を向けた。
<それとも違う雄がいるのか。>
ヒカリは軽く息をついた。レイは目をモニタに戻す。
<いないわ。行った場合、あなたはしばらくしたらここに戻ってくる事になるわ。2…回先の夏、にここに戻るわ。>
<それは長すぎる。>
<行かない場合は子供は作れないわ。>
「くぅ…」
<ペンペンはその間1匹になる訳ではないわ。私も、葛城さんも、赤木博士も、碇君も洞木さんもいるわ。>
「くあ。」
<そうだ。>
<何?>
<ミサトがいるからペンペンは大丈夫だ。ペンペンは1匹ではない。>
「ミサトさんの事忘れてたの?」
「何?」ミサトは顔を上げた。
「あ、いえ。」首を振るヒカリ。
<私は新しいプールに行く。私は新しい人間達の中でもここと同じようにうまくやって行くだろう。>
「…」
「不安なんだ、ギンギン…」
何か言いたい事があるが言いにくい、といった雰囲気のヒカリが、レイと妙な沈黙を作る。
「…どうなった?」
<私はいつでも行ける。問題はない。>
ヒカリはどいて、ミサトにバルタザールのモニタを見せた。
「そんな。…」
「一応行く行かないのメリットデメリットは伝えましたけど。」補足するヒカリ。
「そう。」
ヒカリは頷いた。
「葛城さん。」
「…駄目よ。」
「葛城さん…」
「結局ギンギンは、実験の危険性までは分からないのよ。実験が失敗する可能性について話した?」
「いえ、そこまでは。」答えるレイ。
「仮に話しても、理解できないでしょうね。」
「…でも、成功すれば。温泉ペンギンがシンクロナイザー無しで生きていけたり、家族を作ったり、出来るようになるんでしょう?」
ヒカリが言う。
「それも、気になるのよ。…温泉ペンギンは元々軍事用に開発された種よ。それはもちろん、今の研究チームは彼等を軍事目的に使う事は無いと言っているけど、これからずっとそういう事が無いと言い切れる?
本当に、温泉ペンギンにとってそれが幸せな事かしら。」
「葛城さん。」ミサトとヒカリはレイの方を向いた。
「温泉ペンギンの運命は、彼等が決める事です。」
「綾波さん…」ヒカリは嬉しそうに微笑むと、頷き、ミサトへ振り向いた。
「そうです。ギンギンが決める事ですよ。」
ミサトは眉を上げた。
「事情が分からないのよ、温泉ペンギンには。だから、人間が守って、やんなきゃいけないんでしょ?」
「葛城さんの意見は感情論で、温泉ペンギン達を第一に考えた場合適切ではないのではないでしょうか。」
「あ、あの、つまり、こういう事なんじゃないかしら。例えば軍事目的に使われたりとか、そういったリスクも含めて、その、家族を持つような権利も認めてあげるべきだと思うんです。だって、喋れるようになった、っていうだけでここで、ええと、二匹だけで死ぬのを待つ、っていうのは、違うと思うんです。」
「…」
ミサトは腕を組み、口を閉じたままレイとヒカリを見つめた。
ミサトは少しぎこちなく、首を軽く横に傾けてみせた。
「大丈夫ですよ。ギンギンはちゃんと戻ってきます。」
「…」
ミサトはヒカリに微笑んでみせた。
「何ヶ月でもないのに…もう凄く長い付き合いに感じるわ。皆。」
「…私もです。綾波さんもそう思うわよね。」
レイはヒカリを見た。
「え? ええ…」
「…ギンギンに、ペンペン…我ながら変な名前ね。」ミサトは呟いた。
8月31日 月曜日 気温30度
今日はギンギンがドイツに行く日だ。葛城さんの話では、赤木さんがまたしばらく向こうに渡ってギンギンのサポートをするそうだ。それならひとまずは安心だろう。…こんな書き方をしては葛城さんの立場が無いかもしれないが。考えてみれば、向こうの方が亜熱帯のここよりペンギンにとっては遥かに過ごしやすいのではないだろうか、と葛城さんに聞いたが、向こうの場合土壌の汚染がひどく、結構どっちもどっちだという話をしていた。特にギンギンの場合「温泉」ペンギンだけあって寒さに弱く暑さに強いのだそうだ。
ギンギンは特製のトラックに乗せられて仙台空港へ行ってしまった。何とも呆気なかった。もっとも、その後は問題で、ペンペンはしばらく大騒ぎをして暴れていたけど。しきりに![]() と繰り返すのには参った。僕の翼では飛べない、ギンギンの所に行けない、泳ぐ事も出来ない、何も出来ない、とペンペンはずっと繰り返していた。
と繰り返すのには参った。僕の翼では飛べない、ギンギンの所に行けない、泳ぐ事も出来ない、何も出来ない、とペンペンはずっと繰り返していた。
何も出来ないと繰り返すペンペンは自分の姿を見ているようで嫌だった。
一方葛城さんは意外なほどサバサバしていて、「これで一仕事終わったわね」みたいな感じでけろっとしていた。葛城さんも本心が時々出て時々隠れるので私にはどこかよく分からない人だ。「これからは寂しくなるけど、しばらくの辛抱よ」みたいな事も言っていた。まあ、これは本心なのだろう。
明日から学校だ。綾波さんは来るつもりは無さそうだ。これから一体どうするのだろうと思うが、本人も「分からない」としか言ってくれないのには困ったものだ。色々自分の好きな分野の勉強をしてはいるようだが。
私も学校で、何か言われるかもしれないし、言われないかもしれない。もし私も学校をやめるような事になったら、綾波さんは一緒に過ごす時間が増えて喜ぶかもしれないけど。綾波さんは今でも私に気があるようだが、私には答える事は出来そうにない。結局、問題は何も片付いていないし、どれも簡単に片付きそうにもない。
葛城さんではないが、なるようにしかならない、だろう。
水族館では数日ぶりに碇君にもあった。ペンペンを落ち着かせてからしばらく、3人で河畔公園で話していた。碇君は何と言うか、おとなしい人だと思っていたけど、いや、おとなしいのだけど、優しくて、ただ、その優しさがどこか不安定な感じがする。綾波さんのような純粋な人ではないと思う。
何故そんな人が気になるのか、やっぱり疑問だ。
まあ、それは単に友達として気にしてしまうだけなのかもしれないし、何とも言えない。
鈴原だが、とここで引き合いに出すのもわざとらしいが、仙台でも京都でも良いから私達が一緒に暮らすべきだと考えているようだ。私はまだ少し、考える時間が欲しい。いずれにしても来年3月だ。
ミチルは信じ難い事にもう宿題は全部やったそうだ。明日は雪かもしれない。私も今日はもう寝よう。
カタ。
「飛ばない翼…」
シャープペンを置いたヒカリは今日のペンペンが何度も打っていた言葉をふと呟いた。
ヒカリはしばらく天井を眺めていたが、やがて鼻息を漏らした。
「飛ばなくても歩けば良いのよ。」
…何言ってんだか。
ヒカリは笑い、頭を振った。
女性はしばらく無言で周囲を見回し、白い雲に覆われた空を見上げ、両手を上げて深呼吸をした。
「ほんとに、見事に何も変わってないな。…前より寂れたかしら?」
女性は首を振った。
「前からか。」
「あ。」
女性は古びた、何かの倉庫のような建物から歩いてきた女性に気が付き微笑んだ。
「電話で見るより細いじゃない。」
「…そう。」
やって来た女性は特に表情を変える事も無く応ずる。
「ほんとに、無口な所はいつまで経っても変わらないわね。もう10年になるんだから。そういう所も少しは成長しなくちゃ。」
「…」
「冗談よ。」
笑っていた方の女性が、慌てて強調する。
「そう。」
「はあ…それで。様子はどうなの。」
「冷房が入るように、なったわ。」
その答えを聞いて女性は驚いた顔になった。
「嘘。そんな予算が降りたの? 一言も言ってなかったじゃないそんな話!」
「聞かれなかったわ。」
「…そうね。じゃあ、さっそく見に行かなきゃ。ワタキもアタファイも…確か、4匹揃って見た目は同じとか言ってたわね。」
「ワタキではなくタワキよ。」
「あ、ごめんなさい、また間違えたわ。」
「見分けは付かないわ。」
「じゃあ、色でも塗っておくべきね。…冗談よ。」
女性は再び納得しかけたように見えた相手にまた言った。
女性は頭を振った。
「それにしても。碇君も薄情よね。せっかく私が戻って来たっていうのに仕事で会えないなんて普通言うかしら?
全く失礼しちゃうな。」
「…冗談?」
「冗談よ。私浮かれてるかしら?」
「…」
「いや、あの、ちょっと、」
女性は手を取ってくる相手に後ずさりした。
「行きましょ。」
「う、うん。」
入り口に入る手前でヒカリは立ち止まり、ふと後ろの空を眺めた。
「何。」
「…」
ヒカリは真っ白な空をしばらく見上げ、それから目の前のレイを見つめた。
「…」
「…ううん、何でもない。」
「…」
「ほんとに何でもないわよ。行きましょ、綾波さん。」
ヒカリはそう言って微笑むと入り口の自動ドアの前に立った。水族館に入っていくヒカリ。
しばらくするとドアの向こうから歓声らしき音が漏れる。雲は急に切れ間を見せ、太陽の光が差し込み閑散とした道路に電柱型の影を作る。
「…」
レイはヒカリのまねをするようにしばらく後ろの空を目を細め見ていたが、やがて首を傾げると水族館の中に入って行った。
おわり