正直一体何が悲しいのか自分でも整理出来ない。
シンジは、恐らく自分が、お行儀の良い自分が、いつも半ば無意識的に押さえつけているであろう怒りや悲しみや、その他シンジのボキャブラリーには形容する言葉も無いようなドス黒い感情を徐々に押さえ切れなくなっていた。
シンジはついにパネルを打つのをやめ、無言で涙をぬぐいだした。
「くあ。」
「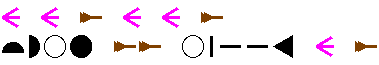
(<話す><話す><終わる><話す><話す><終わる>
<何故><止める><急に><話><終わる>)
(「話せ、話せ、何故急に話を止める?」)
」
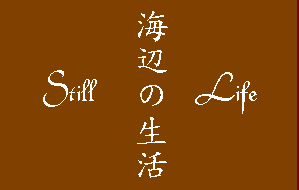
[あー、ちょっとすまん、しばらく外してくれるか。]
トウジは目を合わせずに言う。
「…」
ヒカリはしばらく瞬くと、口を尖らせたままバッグを置いて立ち上がった。
[…何、またエッチな事でもするの? もうすぐ退院でしょ?]
[な、アホか。…ちゃうわ。]
弟の焦る様子に頬を緩めるヒカリ。
[やり過ぎないようにね。変態さん。]
ヒカリは「はーあー。」と声に出しながら病室を出て行った。
「…」
トウジはヒカリが出ていった事を確認すると、深く溜息をついて天井を眺めだした。
ヒカリが廊下に出ると、向こうから看護婦がすたすたとやって来た。暗くて顔がよく見えないがはっきり分かる。この歩き方は彼女だ。
「霧島さん。」
微笑むヒカリ。
「ああ、ヒカリちゃん、良い所に来てくれたわ。ちょっと良いかな。」
「え? ええ。」
病室の前からやや離れた廊下の一角で、マナは周囲を見回すと声を潜めて話し出した。
「あのーさあ、あのー。…」
「…鈴原の事で、何か?」
「ん、まあ、それは、そうなんだけど…」
ヒカリはマナのあまり見ないタイプの表情に顔をしかめ、自分の頭脳をフル回転させだした。
「え…と今月の…入院料は、」
「ううん、大丈夫よ。そうじゃないの。…トウジ君のリハビリももちろん順調よ。もうほぼ完璧。安心して良いわ。」
慌てて微笑んで見せるマナ。
「…えー、と…」
マナは悩むヒカリの様子をちらちらと見ながら、どこか申し訳無さそうに話し出した。
「あの…実はさ。トウジ君に、告白されちゃってさ。」
「え。」
マナは恥かしいのか、早口で続ける。
「うん。あの、まあ、多分一杯誤解もあるんだろうと思うけどね。こっちはほら、ぶっちゃけた話が仕事で全部やっている訳じゃない。でも、患者さんによってはそういうのに凄く感謝してくれる人とかもいて、いや、もちろんそれ自体は凄く嬉しい事なのよ。ねえ。でもそのやっぱり、こういう環境じゃなくても好きになれるような人じゃないと本物じゃないっていうか…あ、ごめん、ちょっと言い訳入ってるよね、ま、とにかくその、どうも私こういうの、うまくかわせなくって。あの、お姉さんの方からも、うまく言ってくれないかな。」
「…」
「…ヒカリちゃん?」
「あ、ああ、ええ、そうするわ。ごめんなさい、うちのバカが」
「良いのよ、全然謝る事じゃないって。でもあの、頼むね。まあ本当は、こういうの人に頼っちゃいけないんだろうけど、私手話出来ないから伝わってるかどうか不安だったりとかするしさ、」
「うん、大丈夫、大丈夫。ちゃんと言い聞かせとく。」
「うん、あの、こっちこそごめんね。変な事頼んじゃって。」
「大丈夫よ。」
ヒカリは表面的な笑顔で頷いた。
マナが向こうに行った事を確認すると、ヒカリはすとん、と廊下の椅子に腰を降ろした。
しばらくするとヒカリはトイレに駆け込んだ。
ミチルは寝過ぎではれたまぶたと寝癖のついた髪で、ムスッと歩いていた。
おならとほぼ同時にお腹が鳴る。時計はもう9時をさしている。
ミチルはヒカリの部屋の前で声を上げた。
「ねえー、姉ちゃーん。もう9時だよー。夕飯まだー?」
ドアの向こうの回答はない。
「ねえー。可愛い妹が待ってるんだよ。お腹を空かせて。姉ちゃん最近冷たくない?」
無回答。
「じゃあ、今夜は寿司でも取ろっかなー。」大声で言うミチル。
全く静かなままのドアに、ミチルは溜息をついた。
ミチルは諦めて廊下を歩いて行った。呟くミチル。
「…姉ちゃんまで変な時間に寝だしたら、この家機能しなくなるっちゅーの。しゃーない。今夜はカップヌードルか。」
「…」
ヒカリは、ミチルがいなくなったのを聞くと真っ暗な部屋のベッドの中で寝返りをうった。
バカね私。一体何やってるのかしら。大体自分は好き放題やってて、何を今更…
…あーやめやめ。
ヒカリは頭を振ると、また出てきた涙をぬぐう為にティッシュをとった。
ヒカリが4、5枚ティッシュを濡らした後薄めの眠りに入って数時間後、彼女は目を覚ました。
「ねー…でん…」
「…」
無言で起き上がるヒカリ。ドアの下から(つまりドアの向こうの廊下から)漏れる光に目が行く。
またミチルの声だ。
「…ちゃん、ねーちゃん、でんわ。」
ヒカリはようやく目が覚めた。
「電話?」
がばっ
「そう、電話。」
ヒカリは部屋のドアを開ける。持っていた受話器を手渡すミチル。
「…」ヒカリは数秒廊下の明りに目を細めていたが、そのまままたドアを閉めて部屋の暗闇に入った。
「…もしもし。」
「洞木さん?」
ヒカリは受話器の向こうの声に溜息をついた。
「何だ、綾波さんか。…どうしたの。」
「…声が急に聞きたくなって、しまったの。」
何か悪い事をしてしまったかのような申し訳無さそうな声が聞こえてくる。
「ふう…」
もう一度溜息をつくヒカリ。
「綾波さん、私も色々忙しいから、今日はまた今度…」
「あ、」
ヒカリの頭の中で、レイが「はかなげで可愛い」声の出し方や話し方や全て計算づくでやっているのではないかという考えが一瞬よぎった。
「…何。」
「…いえ…あ…洞木さんは今、何をしていたの。」
「寝ていたわ。」
「え?」
ぷつっ
ヒカリは受話器の「切」ボタンを押すと、机に置き、そのまままたベッドにダイビングした。
数分後、ヒカリがそろそろ眠りにつきだした頃、机の上の受話器が再び鳴った。
うつぶせの状態だったヒカリはこれ以上無い位大きい溜息を枕の上でつくと、ばっと起き上がり、受話器の通話ボタンを押した。
「もしもし。」
「あーヒカリか。元気でやってる?」
「マリアさん。」
失望というよりはどこか覚悟の決まった様子で答えるヒカリ。
「何ぃ、元気無さそうやん。どうしたの?」
「え、いええ、今寝ていたので。」
「へえ、もうこんな時間寝とんの、はっやいなあー。ちょー疲れとるんやないか、あんな、看病なんかほどほどにやっといた方が良えよ。あんなんほっぽったってどーって事無いからな。」
「あ、はあ。」
受話器の向こうの、さっきのレイとは落差のありすぎる声に頬をひきつらせるヒカリ。
「あーほんま、声疲れてるなあ。まあーそやったらゆっくり寝とき。あーちょ待って、その前に話あんねん。あんな、明後日そっち行くから。トーちゃん退院やから大変やろし、な。うん。したら、また明後日な。じゃおやすみ。」
「…」
「おやすみ?」
「ああ、あ、おやすみなさい。」
「おやすみ。」
「…」
ようやく切れた受話器をしばらくヒカリは眺め、やがてそれをベッドに投げつけた。
「が。」
「え?」
シンジは頬を引きつらせて聞き返した。
「だからあ。そんなに練習してんだったら、私達にも聞かせてくれたら良いじゃん。」
デッキブラシでコンクリの床をゴシゴシこすりながら、ミサトが振り返る。
「が。ぐぅ。が。ごっ」ブラシの杖にときどき頭をぶつけながら纏わり付いているペンペン。
「いや、でも、あくまでそれは合奏用なんで…」
「…じゃあ…その演奏会に連れてってよ。」
「え?」
「別に良んでしょ? 一般の人が入ったって。」
「え、まあ、確かに…」
そうしたら綾波も学校に来るのかな…そうして噂になって、僕も除け者になって…
…いや、綾波はそれを考えててこでも来ないだろうな。うん…それとも彼女に来させるべきなんだろうか…
「どうしたの、シンジ君。」
「え? うわっ」
眼前に広がるミサトの顔に飛びのくシンジ。
「女の人に対してシンちゃんその態度は失礼よ?」
「す、すいません。」
「じょーだん。まあ別に恥かしいっていうなら。無理にとは言わないけどさ。」
どうやら演奏会場に変装して行く事を決めたらしいミサトが言う。
「あのー、ミサトさん。」
「何。」
「綾波…の事なんですけど。」
ミサトはブラシの動きを止め、顔を上げた。
「レイがどうかしたの?」
シンジは正直彼女に言うべきか(特に彼女に、言ってしまって良い物か)かなり悩んだが、やや彼女の声の調子が変わった事に促されるかのように話し出した。
「彼女…学校でいじめられてて…学校に、来なくなってたんですよ。」
ミサトは普段あまり見せないような、何とも微妙な表情で目を泳がせ、ブラシの柄の先に顔を乗せた。
「…うん。」
「多分色が白いからだと思うんですけど。だから彼女は、演奏会には来たがらないと…あ、演奏会、学校でやるんで…」
ミサトは少し微笑んだ。
「じゃシンちゃんはレイちゃんに来て欲しいとは思ってるんだ。」
「え…ええ、それは、もちろん。」
「それっていつから。レイちゃんが学校に来なくなったのは。」
「いや、結構前からなんですけど。」
「…あー、何か分かる感じする。」
「ミサトさん。」
「いや、別にいじめっ子を弁護してる訳じゃなくって。でも…そうねえ。他人事だから言えるのかもしれないけど、いじめられてても、学校からは逃げない方が良いと思うけどな。…って、シンジ君に言ってもしょうがないか。」
「でも、ミサトさんは綾波がどれだけ酷い目にあってたか知らないから…」
「じゃあシンジ君は…」
ミサトの声に思わずシンジは身を硬くした。しかし続きが無い。ミサトを見るシンジ。
「…ごめん。忘れて。…どうも私、昔から子供の事って苦手なとこあんのよね。…私が子供なのね。」
独り言のように呟き、掃除を再開するミサト。
「ミサトさん…」
ミサトは一人で何か頷いている。
「…じゃあ、ここで演奏会を開きましょうよ。あ、ち…チェロだったっけやってたの?」
「あ、は、はい。」
「チェロとかってやっぱり湿気嫌うかしら。」
「え、ええ。」
「そうかあ…じゃあここの駐車場とか、あ、どうせなら河畔公園は? 屋外リサイタルなんてロマンチックよん?」
「は、はあ…」
…この辺どこでも湿気あるんだけどな…
約12時間程惰眠をむさぼっていたヒカリはまたもや電話に起こされた。
「…はい…」
「あの、洞木さん? 碇、なんだけど…」
眠り過ぎのヒカリは頭を押さえながら答える。
「ああ、碇君。どうしたの。」
「あのー、さ。今度、水族館でチェロ弾く事になったんだ。で、洞木さんの予定の良い日とかを教えてもらえると、」
「碇君。」
「う、うん。」
「随分楽しそうだね。」
「…洞木さん?」
「碇君って鈍感じゃない?」
「洞木さん…何か、あったの?」
「何かあったと思う?」
「え?」
「当ててみてよ。分かったらチェロも聞いてあげるわ。」
「え、あの…洞木さん、だよね。」
「そんなの答えじゃないわ。」
「え、あ、え…嫌な事、でも…あ、あの、今都合悪ければ、後でかけ直すけど」
「碇君私振られちゃったんだ。…ずーっと好きだったのに。ずっと、尽くしてきたのに。毎日彼を一番優先して、毎日が、回ってたんだけど。全然伝わんなかった。碇君、努力って報われないんだね。結局、何の意味も、無かったのよ。」
「洞木、さん…」
ヒカリは既に自分のやっている事がまるで理に適っていない事は重々分かっていたが、何故か口を閉じる事が出来なかった。
「私って普段はうまくやってるつもりなんだけど、時々自分の嫌な部分が押さえられなくなる時っていうのがあってね。何なのかな。」
「え、…」
「て、碇君にそんな事分かる訳ないわよね。私の問題なんだしね。」
「…」
「バカみたい。…ふ。でも、これで碇君と同じだね。」
「え、何が?」
「振られたって事よ。碇君は綾波さんに振られたでしょ。」
「え…」
「今更隠さないで良いのよ。…ねえ、良い事教えて上げよっか。綾波さんはねえ、レズなんだよ。」
「…洞木さん?」
「ふふ、嘘だと思ってるでしょ、本当なんだから。だって私、綾波さんに告白されたんだから。…セックスもしたよ。」
「…」
「だから碇君、碇君が振られたのは、別に碇君が悪いからじゃないのよ。良かったわね。…でも、残念ね。裸の綾波さん、とっても可愛かったけど。…綾波さんね、他の人には見せないような表情も私にだったら一杯見せてくれるのよ。でもそれも、碇君にとっては、一生見る事が出来ない物なのよね。」
「…う、う、そ、だよ、ね。」
「本当だって言ってるじゃない。信じられないんだったら本人に聞いてみれば。綾波さんは、…」
電話は急に沈黙した。
「……洞木さん?」
「あや、なみさんは……」
「洞木さん、洞木さん?」
「…綾波さんは、だから絶対に碇君を好きになる事はないから。」
ぷつ。…つー、つー、つー。
「ぐあ。」
<シンジは(話す)やる気があるのか。>
シンジは赤い目で顔を上げ微笑んだ。
「あ、ご、ごめん。」
「くあ。」
「…」
口で答える自分の間抜けさに少し冷静さを取り戻したシンジは、自分の気持ちをペンギン語でどう表現すべきか悩みだした。
「ええっと…「私は今日は、他に考える事がある」だから、持つ、私、事…いや、考え、…えー、見る、考える、私、見る、終わる。」
ペンペンはいつも通りのマイペースな様子で首を振りながら返答を打つ。
<話す事を考えないのか。>
「…えーっと、」
<話す事も考えるが、それとは別に考える事があった。>
「が。」
<それは良くない。ギンギンは前、「話すとは考えを分ける事だ」と言っていた。シンジはちゃんと私に考えを分けるべきだ。>
<人間は、分けたくない考えもあるんだよ。>
<それは良くない。ギンギンならそんな言い方は許さないだろう。>
シンジはペンペンの能天気そうな顔をしばらく見つめた。
<でも、そういう事もあるんだ。>
<それでは楽しくないだろう。人間はやはり変なペンギン…変な動物、だ。>
「…」
<…ペンギンは、いつも心を分けるの。>
<話すとはそういう事だ。>
<そうじゃなくて、ペンギンは、持った心はいつも分けるの?>
<そんな事はない。そもそも心を分けるのはあなた達が教えた事だ。ペンギンは…心はある。それを分ける習慣は本来ない。>
<じゃあ、人間と同じじゃないか。>
<分ける時は話すのだ。いや、話す時は分けるのだ。>
<つまり、この言葉が無いと、君達も心が分けられないの?>
「があ、があ。」
「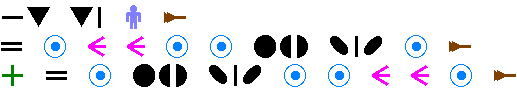
(<低い><考え><シンジ><終わる>
<同じ><見る><話す><話><見る><見る><分ける><心><見る><終わる>
<と><同じ><見る><分ける><心><見る><見る><話す><話><見る><終わる>)
(「シンジは頭が悪い。だから言葉を使うのが心を分ける事であり、心を分けるのが言葉を使うという事なのだ。」)
」
<そう。>
<人間はこんな楽しい事を知っているのにそれをしないというから変な動物なのだ。>
シンジは少し微笑んで、溜息をついた。
<でも、考えるのが大変で話す暇が無い時だってあるんだよ。>
<敵に襲われている時か。>
「いや、そういう訳じゃないんだけど…」
<分かったよ。今はそこまで大変じゃないから、僕の考えを分けるよ。>
<ようやく分かったか。シンジは物覚えが悪い。>
「はは…」
<僕の好きな人がいて、でもその人は僕が好きじゃないんだ。>
<その人とは誰だ。>
「え…」
<…君の知らない人だよ。>
<あなたが何か嫌われる事をしたのではないか。>
「うん…」
<いや、そうじゃなくて、その人は僕は好きだけど、すごく好きでは…つまり、その人は僕と一緒にはなりたくないんだ。>
<一緒になるとはどういう意味だ。つがい(家族)になるという意味か?>
<ああ、そう、そういう事。>
<シンジは歌わないから女が好かないのだ。>
<歌?>
<シンジは頭が悪い。歌わないシンジが好かれるはずがない。>
<いや、ペンギンはそうかもしれないけど、人間にそういう習慣は無いんだ。>
「…たぶん。」
ペンペンは「またか」と言わんばかりにくちばしを広げ、軽くフリッパーを上げた。
<それでは人間はつがいをえるためにどうするのだ。>
<うーん…いや、そういう問題じゃなくて、その人は男とつがいにならないんだ。>
<…それは女なのか。>
<うん。>
<人間は変な動物だ。…それでは、その女は女とつがいになるのか。>
<う、うん。>
<まさか男とつがいになる男もいるのか。>
<あ、うん、そうだよ。>
<それで子供は出来るのか。>
<いや、出来ないよ。>
<…何の為につがいを作るのだ?>
<え、だから、うーん、人間は、子供を作る為だけじゃなくて仲良しの為にもつがいを作るんだよ。>
「くぅ…」
恐らく呆れた表情をしているものと思われるペンペン。
<ほら、ペンペンとギンギンみたいなものだよ。仲良しだろ?>
「くあ。」
<仲良しではない。いや、良い友人だが、つがいではない。ペンギンは仲良しの為だけにつがいは作らない。ただの仲良しはつがいではない。>
<人間は、仲良しの為につがいを作る事もあるんだ。>
<そうか。…それでは、女とつがいになる女とつがいになろうとしたシンジが悪いのではないか。>
<そうだけど、その人がそういう人だって言うのは知らなかったんだ。>
<何故それに気付かないのか。>
<何故って…>
「がぁ、くわ。」
<そもそも、シンジは何が言いたいのか。もし女があなたとつがいにならないなら他の女を探さなければならないではないか。>
<いや、まあ、そうかもしれないけど、その人の事を忘れられないんだ。>
「くあ。」
<忘れなければ良いではないか。>
「え?」
<その人もあなたを友人として好きなのだし、別に忘れる必要は無いだろう。そしてそれは置くとして、つがいになる女は別に探さなければならないではないか。シンジはそんな事も分からないのか。>
<でも、僕はその人とつがいになりたかったんだ。友人じゃだめなんだ。>
<しかしそれが女とつがいになる女なのでは仕方が無いだろう。良い子供を作りたい気持ちは分かるが、それはシンジが間違えた選択をしたのが悪い。>
「…」
シンジはふと画面から目を離し、ペンペンと、向こうのプールでぷかぷかと浮いているギンギンを見比べた。
今日は半袖では少し肌寒い位の気温の曇空だった。
シンジは頭を振った。
<もういいよ。ペンペンに何か答えを得ようとしたのが間違いだった。ペンペンには人間の事は分からないからね。>
「くあ。」
<当たり前だ。分かる訳が無い。私は心を分けるだけだ。>
「…」
<今日のシンジは悪い心だ。>
<言われなくても分かってるよ。>
<シンジ、>
<…何。>
<自分の事は自分で決めろ。特につがいの事は。>
「…」
シンジは画面とペンペンを見比べ、急に目頭を押さえた。
「………うっ、うっ、うっ…」
座り込むシンジ。
「ううっ、うっ、うっ、うっ…痛っ」
背中の痛覚に我に返るシンジ。
「…ペンペン。」
ペンペンはシンジのそばにより、慰めるかのように背中をぽんぽんとフリッパーで叩いていた。
でも、以前みたいに魚を見て心が安らいだりはしなくなったかもしれない。毎日見るからありがたみが薄くなったというのもあるんだろうけど…
特に今日は、何でわざわざこうやってじっと見ているのか、自分でも不思議だ。
洞木さんが嘘を言うとは思えない。綾波に確かめる訳にもいかないし…
…いや、それ以前にそもそもはっきり振られてるんだし、今更そんな事、どうだって良い事じゃないか…
「シンジ君…昨日何かあったの?」
シンジはミサトの声に顔を上げた。
「あ、あー、いえ…」
「何かペンペンが変な事言ってたわよ。レイの事?」
「え? あ、ああ、ええまあ、それも関係あるような、無いような…」
昨日のミサトとの会話を思い出すシンジ。
「え?」
「いや、それもあるんですけど、他にもまあ、色々あって。ペンペン何って言ってました。」
「えー? 何だったっけ、シンジは物分かりが悪いとか、人間とペンギンはつがいまで違うとか、何とか…」
シンジは少し冗談ぽく笑って頷く。
「確かに物分かりは悪いですよ。ペンペンに何度も怒られました。」
笑いがうつるミサト。
「人間はねー。ペンギンほど素直じゃないからねー。」
「ペンギンの方が正直で良い、ですか。」
「うん…まあ、かと言ってペンギンになりたいとも思わないけどね。」
「はは。」
「あのー、ミサトさん、ちょっと…」
職員用の、と言ってもシンジもよく通るドアからマコトが顔を出した。
「どした?」
「どうも冷房装置の調子がおかしいんですよ。」
「それって青葉君の仕事じゃん。」眉を寄せるミサト。
「ええでも、「これはミサトさんじゃなきゃ分からない」って…」
「へえー? 給料貰ってんでしょ?」
ミサトはぶつくさ言いながら歩き出した。
「あーシンジ君、ペンギンはいつも通り10時半からね。」
振り返ってシンジに言うミサト。
「はい。」頷くシンジ。
シンジはうるさい職員から解放され、再び一人になった。
シンジが再び物音に気付いたのは数分後だった。
シンジはガラスに映った顔に息をのんだ。
「…」
振り返らず、そのまま動かないシンジ。
「碇、君。」
「…」
「ごめんなさい。」
「…」
水族館にやって来たヒカリはしばらく目を落していたが、シンジが無反応なので顔を上げた。
「あの…本当に、ごめんなさい。碇君、あの、昨日は私、どうかしてて…あ、の、ごめんなさい。許してなんて言えないよね、本当に酷い事言っちゃったなあって思ってる、私時々、自分がおかしくなっちゃう時があって、あや、」
なみさんが、教えて…
「あ、いや、ん、…その…ごめんなさい…その…出来たら、昨日の事は忘れて欲しい、なんて……無理、よね…許せる訳、無いわよね…」
「…」
ヒカリは振り向かないシンジに向かって頭を下げた。
「ごめんなさい。」
ヒカリは口を開き更に何か言おうとしたが、諦めたかのように向き直り、淡水魚槽の部屋を出て行こうとした。
「洞木さん。」
ヒカリは立ち止まり、ゆっくりと向き直った。
ヒカリの方を向いているシンジは彼女に目線を合わさず、無表情に口を開いた。
「昨日の、事は…あれは、本当の話だったの。」
「え。…ええ。」
「綾波さんは洞木さんに告白したの。」
「ええ。」
「でも、振られたっていうのは、綾波さんにじゃないんだよね。」
「え…」
シンジは顔を上げた。思わず目をそらすヒカリ。
「洞木さん。」
「……ええ。」
「二股を、かけていたって、事だよね。綾波と。」
「…ええ。」
小声で答えるヒカリ。
「で、でも、碇君、あの、聞いて、あの、綾波さんには、私は応える事が出来ないとは言ったのよ。でも、綾波さん、あの…す………ううん、何でもない。…ごめんなさい。」
「洞木さんは、…綾、波と、セックスしたんだよね。」
「ええ…」
「その時に二股をかけていたんだよね。」
「ええ。」
ヒカリは低い声で答えた。
「じゃあ僕は、洞木さんを許す事は、出来ないよ。」
シンジは再び水槽の方を向くと、それきり口を閉じた。
「……ご…」
背後から、ヒカリのいつもより高い、くぐもった声が一瞬聞こえた。
シンジは硬い表情で、水槽の小魚の動きを集中して見ていた。
シンジがふと気付くと、ヒカリは既に水族館から出ていた。
8月下旬の宮城県地方の平均気温は摂氏27度を数える。
というと暑そうだが、いや、実際暑いのだが、これでも第二東京等に比べれば海沿いである事も手伝い遥かに涼しい。
この付近では実は雲一つ無い快晴というのはまれで、いつでも空に一定の量の雲がある事が多い。今日は昨日と同じで雲の方が圧倒的に多く、昼なのに薄暗い日だ。
日本の道路の舗装は悪い。というか、幹線道路の舗装は素晴らしく、それ以外の道路の舗装がひどい。そしてヒカリが今自転車をこいでいる道は当然幹線道路ではないので、常に穴ぼこに気を付ける必要がある。ガードレールは付いたり付かなかったり。下手をすると道路脇の用水路に落ちる危険性も無いとは言えない。
簡単に言うと、日本の田舎道で自転車をこぐのは、結構注意力を消耗する事なのだ。
ヒカリはそんな大変な道を行くのに少し疲れたのか、ふとペダルをこぐ足を休め立ち止まった。
いつもの景色が広がっていた。見渡す限りの水田に、寂れた消費者金融か何か−ヒカリには厳密な業種名までは分からない−の看板、まるで何かの境界線、水際のように遠くに線を引く民家や林、田んぼの中にそびえ立つ精米所、綿々と続く送電線の鉄塔、遥か向こうに稜線を見せ、一部を雲の中に隠している奥羽山脈。
「…」
ヒカリは馬鹿ではない。馬鹿の定義にもよるが、少なくとも人並程度の知性はあるだろう。だから、今彼女がどこに行ったって、彼女自身が変わらない限り意味が無い事位は重々承知している。
それでも、ヒカリは今この景色から逃げ出したかった。
以前から決してここの気候がヒカリは好きではなかった。山脈にぶつかる気流の影響だか何だか知らないが、これだけ曇空が多くかつ蒸し暑い気候はそれだけで人を鬱病にさせるに充分ではないだろうか。
「…」
もちろん本当は、気候も景色もどうだって良いのだった。ただ、ここにはいたくないだけだ。
実際この道は水族館に行く時と閖上の市場に行く時位しか用が無いのだから、本当にもう通る事も無いだろう。市場に行けなくなるのは惜しいが、そうは言ってもただの寂れた市場なので、敢えて遠回りしてまで行きたいともさすがに思わない。
ヒカリは既に充分冷静さを取り戻していたので、結局自分が南仙台を離れてどこか遠く、例えば一番現実的な所でマリアの住む京都辺りに行く、等という事には、少なくともこれが理由では、ならないだろうと薄々気付いていた。
もう一週間でまた学校だ。どうせ綾波さんは学校に来ないし、碇君とはもともと特別仲が良かった訳じゃない。最初の状態に戻っただけなのだ。
ただ一つ心残りなのは、ギンギンにもペンペンにもミサトさんにも挨拶が出来なかった事ね…ミサトさんにはメールですむことだけど、ペンギン達は、直接会わなかったら私の言葉だとは思わないだろうし…
ヒカリは顔を上げた。
ヒカリはもう、涙は出なかった。彼女は自分の強さが恨めしかった。
家では怠け者の妹が待っている。ヒカリは頭を振ると、足で自転車のペダルを上げた。
「…え?」
ヒカリはブレーキの音に振り向いた。
「碇君。」
目の前に自転車を飛ばしてきたらしいシンジがいた。風で髪は乱れ、息は荒く顔は紅潮している。
「はあ…洞木さん。…はあ…僕の方こそ、ごめん。」
「碇君…」
ヒカリはまるで嫌な事を言われたかのような困惑した表情を見せた。
「どうしたの。」
「洞木さん、ごめん。さっきはきつい事言っちゃって。…洞木さんや、綾波さんの事情も知らずに、」
「だって、碇君、碇君それじゃ間違ってる、それじゃ優しすぎよ。」
ヒカリは自分で、自分がどうも妙な事を言っていると内心思った。
「はは。でも僕、優しい位しか取り柄無いから、」
「ちょ、ちょっと待って碇君、碇君はだって、…だって、ほら、…私は、綾波さんと、ん…二股かけてたのよ?
碇君綾波さんの事が好きなんでしょ? そんな、私何言われても言い返せない立場じゃない。そんな、だって、…碇君?」
大分呼吸が普通になってきたシンジはヒカリの様子に少し微笑んで、頭を振った。
「確かに洞木さんが男だったら、僕でも1発位は洞木さんを殴ってたかもしれないね。でもとにかく、綾波は僕に興味が無いんだから僕がどうこう言う事なんて出来ないし、それに、その、えーと。ほら。僕は、洞木さんと友達でいたいんだ。」
シンジは息をついた。
「僕が、こんな、くさい事言うなんて自分でも思ってなかったけど。洞木さんも綾波も大事な友達だから、ここで無くしたくなかったんだ。これはミサトさんに相談したんでも、もちろんペンギン達に相談したんでもない、僕自身の、その、気持ちなんだ。だから、その、」
「有り難う。」
ヒカリは顔を真っ赤にして、両目を瞬かせながら笑った。
「いや、うん…うん。」
泣いているヒカリは、シンジの顔を見ながら何故かずっと笑っている。
「碇君。綾波、さんには、もう一度はっきり言う。でも、もう言っちゃった事は取り戻せないけど、でも、ん、碇君、これからも、私も、その、友達で、いたい。」
「うん。」シンジは何度も頷いた。
「碇君。ごめんなさい。……有り難う。」
シンジはふと、腕時計を見た。
「もうお昼だね。」
「え…そうね。もうすぐ12時。」
「どこかでお昼、食べる。」
「どこで?」
「どこ、って…駅前に行っても、スーパーとコンビニ位しかないか…」苦笑するシンジ。
「あ、ねえ、家に来て。今日はそうめんでもゆでようかと思ってたの。まああんまり、御客様に出すような物でもないけど…」
シンジは笑った。
「うん、じゃあ、そうする。」
「妹が喜ぶわ。姉貴が彼氏連れてきたって。」
「え?」
「そういう年頃なのよ。」
「僕達もそういう年頃だよ。」
「うん、そうね。」
ヒカリは自転車から下りると、手で自転車を押しだした。その横を自転車に乗ったままのシンジが、地面を蹴りながら進んでいる。
「弟さんの調子は?」
ヒカリはわずかに表情を変えた。
「…ええ、絶好調よ。明日退院。」
「明日?」
声を上げるシンジ。
「よかったじゃないか。おめでとう。」
「おめでたくないわよ、またうるさいのが一人増えるかと思うと…」
「本当は嬉しいんだよね。」
驚いたようにシンジを見るヒカリは、無邪気そうなシンジの顔に少し溜息をついた。
「…ええ。そうね。」
ヒカリはシンジを見て、微笑んだ。
「何。」
「碇君って。何か、やっぱり変だね。」
「何が?」
「…ううん、何でもない。」
シンジはヒカリを不思議そうに見つめた。
「洞木さんも、相当変だと思うよ。」
「あ、ひどいな。私は常識人なのに。」
静かに、冗談めかした様子で反論するヒカリ。
「…ごめん。」
シンジも笑って答えた。
「綾波が、」「綾波さんが、」
声を揃えた2人はお互いの顔を見て、吹き出した。
「一番変なのは綾波さんよね、やっぱり。」
「僕はそんな事は言わないけどね。」
「あ、ひどい、碇君引っかけたわね!」
「言ったのは洞木さんだからね。」
「ひっかけられたー。」
笑って首を振るヒカリ。
「まあ、変なのは確かよ。だから可愛いの。…いや、そういう意味じゃなくて。」
シンジは肩を上げる。
「ねえ、碇君。3人とも、ずっと、良い友達でいようね。」ヒカリは呟く。
「それって、何か、変だよ。言い方が。」
「…そういう年頃なのよ。」
ヒカリは何か勝ち誇ったかのように微笑んでみせた。
くちゅん。
「バルタ」の前に座っているミサトは、隣りのレイに振り向き、にっと笑った。
「どしたの。風邪ひいた?」
レイは何か恥かしいのか、普段より硬い表情で顔を上げる。
「いえ。」
「レイ、まさか夜、クーラーかけたまま寝たりしてないでしょうね。あれは体に毒だから止めた方が良いわよ。」
「家にクーラーはありません。」
「あ、…そ。ごめん。」
「何がですか。」
「…ん。何でもないわ。」
「…」
レイは顔をモニタの前に戻した。
「でも、大丈夫なの、その、肌とか弱いのに、暑くて。」
「問題ありません。気を配るべきなのは日差しです。」
「そうなんだ。」
「レイ。」
「何ですか。」レイはまた顔を上げた。ほんの少し目が細くなっているようにも見える。
ミサトは頬杖をついた。
「毎日、楽しい?」
レイは少し眉を上げた。
「…ギンギンの言う通り、この実験はいつもとても楽しいです。」
楽しさを微塵も感じさせない無表情で答えるレイ。
「…そ。」ミサトは微笑んだ。
彼等のいるペンギン室の窓の向こう、つまり建物内の職員用の廊下に、冬月館長が立っていた。
「間違いないな。」
冬月は厳しい表情で、廊下を立ち去った。
つづく