アスカはペンギン室の天井の無い部分に出て、空を見上げた。
積乱雲らしき物が空を威圧していた。アスカはしばらく瞬いて、目を自分の脇のペンギンに向けた。
「くあ。」
「![]() 」
」
アスカは、まだ何やら打っているペンペンの頭を撫でた。
「Sei nicht angst!(怖がらないで。)」
「くああ。」
アスカは仙台に来て以来一番の微笑みを見せた。
レイは壁を見つめていた。
レイは特に壁を見るのが好きだと言う訳ではない。そもそも壁紙業者でもない限り、余り壁をじっくり見たがるという人は多くないだろう。
レイが壁を見つめていたのは、この研究室の他の物はあらたか見尽くしてしまったからであった。
レイは壁の一点、部屋の隅、2つの壁と天井の同時に触れ合う、部屋という四角の頂点にあたる部分を眺めながら、とりとめもない事を考えていた。
雑誌で読んだのだが、私達の世界はミクロレベルでは実は6次元であるという説がほぼ承認されたそうだ。つまり、そうであると考ると説明が付けやすい現象が観測されているという事なのだろう。赤木博士の言を借りるなら、「とかくこの世は分からない事だらけ」だ。レイには4次元でさえ一体どういった世界なのか想像も付かなかった。
レイは「4次元の展開図」という物を見た事がある。仮に3次元の立方体を紙で工作するとすると、のりしろを別として、十字架状に繋がった6つの正方形による展開図が必要になる。これが紙という2次元上に展開された「3次元の展開図」だ。これと同じ要領で、立方体を8つ繋げれば4次元の「展開図」が作れるという事になる。
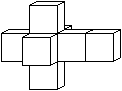
問題はその組み立て方だ。
この調子で行くと5次元はこれを組み立てた「正4次元体」を10個繋げた物を組み立てた世界であり、6次元はその正5次元体を12個位繋げた物を組み立てた世界になるのだろう。
驚くべき事は、そんな頭痛のするような世界が今自分達の目の前に存在しているかもしれない、いやそもそも自分達自身がそういった存在であるかもしれないという事実だった。
そういった事も確かに有り得るかもしれない。仮に2次元の世界があってそこに知的な生物がいるとして、その生物は3次元の世界を概念的に捉える事は出来てもその存在を実際に見る事は簡単には出来ないだろう。つまり3次元の我々にとっては6次元の世界は理解は出来ても見る事は出来ないのだ。もちろんそれ以前に理解するのも難しいが。それにしても、そもそも異なる次元の世界が接するという事でも充分想像を絶するが、自分達の世界そのものが実は3次元であり同時に6次元であるというのは何とも不可思議だ。私は今まで次元というものは、あくまで人間が特に数学の面で作り上げた概念的存在でしかないと考えていたが、これはそれこそ私自身の3次元の存在としての視野の狭さを、
「ごめんなさい、レイ。」
レイが目を降ろすと、トイレから帰って来たリツコがさほどすまなそうにも見えない様子で椅子に座っていた。
「何を見上げていたの。ここに空は無いわよ。」
「次元について考えていました。」
リツコはレイをちら、と見て、レイが今さっきまで眺めていた天井の一角を真似して眺めてみた。
「何か収穫はあったかしら?」
「いえ。」
「そう。残念ね。」
「ええ。」
リツコは足を組んでそのままディスプレイに向き直った。
「それで? 新しい単語を見たというのね。」
「ええ。確か…こういった物でした。」
「![]() (<四角><話す>)」
(<四角><話す>)」
「話の四角? …口じゃないわね。」
「それは「食べる三角」です。」
「そうね。…ミサトに聞いた方が早いかしら。」
リツコはパネルに軽く触れた。入力はしていない。
「どういう文脈だったの?」
「もっと話の四角が必要だ、そうすれば良い友人が増える、とか…」
リツコは軽く目を広げ、「あ」と声を上げた。
「端末の事じゃないかしら。」
「それは、…」
「今までの形の省略形よ。これって<端末>の最初の字と最後の字でしょう。」
ね、と目で聞くリツコに、レイは僅かに頷いた。
自分で大きく頷くリツコ。
「確認しましょう。」
リツコは立ち上がると、数メートル先のペンギン室に向かった。
ペンギン室に入ったレイは、険しい表情になった。
「赤木博士。」
「何。」
レイの声の調子に、リツコはようやく顔を上げた。
「ペンペンがいません。」
リツコは眉を寄せた。
確かにギンギン(と思われる1匹)が山で眠っているが、もう1匹は見当たらない。
「陰にはいないの?」
「音がしません。」と言いながら確認にプールを覗くレイ。
レイは横に首を振る。
リツコは無言で溜め息をつくと、ペンギン室を出て行った。思い出したように振り返るリツコ。
「控室に行って来るわ。ミサトに会わないと…」
「彼女は第一水槽です。」
「…有り難う。」
そう言えば…
レイは周囲を見回した。
「Du hast nichts zu angstigen, Junge.(何も心配する事は無いのよ。)」
「くあ。」
アスカはペンペンに微笑みかけた。
「Es geht! Dein Freund wird bald dir folgen.(大丈夫。あなたの友達もすぐに来るわ。)」
「Nun. Es ist Zeit zu gehen.(さあ、行くのよ。)」
二郷堀海浜公園までペンペンを乗せて自転車を走らせたアスカは、人工の砂浜でペンペンを解放していた。
「くあ?」
「Geh, nun!(今よ!)」
ペンペンの背中を叩くアスカ。ペンペンはくい、っと首を傾げると、トコトコと海の中へ歩いて行く。
「Gut. Du bist sehr weiser Junge.(そう。良い子ね。)」
アスカは頷きながら呟いた。
「くあ?」
もう一度振り返るペンペン。
「Geh.(行きなさい。)」
「が。」
ペンペンはパシャン、と勢い良く水に倒れるように飛び込むと、白鳥かガチョウか何かの水鳥のようにしばらく浮かんで小さな波を越え、やがて十分な水深の所まで来ると水中に潜って見えなくなった。
「Ich tat Gutes. Naturlich!(これで良いのよね。)」
アスカはそのまま、しばらく海を眺めていた。
アスカは、生まれてこの方数える程しか海を見た事が無かった。ベルリン出身で長野に住んでいるのだから当然だ。そして彼女の数える程しかない「海」の景色は、基本的に凍り付いた白黒のイメージだった。
そのせいか彼女はここの青い海を興味深げに眺めていた。
海浜公園と名前が付いているのに−そもそもアスカはここが「公園」だ等とは知る由も無いのだが−ここには設備らしき設備もなく、ただ道路沿いに白い砂浜がこじんまりと広がっていた。素晴らしい事に、夏休みであるにもかかわらず全くの無人だ。
日本人も、まだいわゆる「海水浴」をする気にはなれないようね。
アスカはそう考えると、ペンペンを逃がしたのが果たして良かったのか少し疑問に感じたが、すぐに頭を振った。
「Ich tat Gutes. Brauchte meine Hilfe.(良かったのよ。彼は助けを必要としていたもの。)」
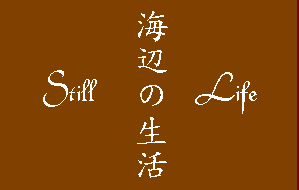
母親の影があった。
「…あな…望まれ…そんな…」
「余裕がありません。今は…でしょう? お宅の…」
母は、教師のような男性−それは今思えばフォスターハウスの管理者か何かだ−に懸命に頭を下げていた。
「ほら、あなたも…さい。」
「お願いします。」
レイも頭を下げた。
「お気持ちは…が、ですから。」
「まあ! 何て…」
言葉がはっきりと聞き取れない。しかしはっきりと、母は狂ったように怒っている。何度も相手の男性は頭を下げているが、母は怒鳴るのを止めない。
レイはまた母が癇癪を起こしたな、とひどく冷静にそれを眺めていた。その頃のレイは、親はこういう物だと思っていたのでそれを悲しむという事は絶えて無かった。
場面が変わり、小学校のクラスメイト達が現れた。皆こっちを恐怖の目で見ている。
意外な事に、と言うべきか、2、3回の例外を除いてレイは小学校ではいじめられた経験は無い。積極的にいじめられたというよりは皆から避けられていた。
最初彼女は半ば憤りのこもった感情で、自分を避けるクラスメイト達を見ていたのだが、いつの日からか自分がいる事が申し訳なく感じられるようになっていった。
レイは寝たふりをしていた。
何故か分からないが、そうしてずっと自分の体をヒカリに付けていたかった。
「かーわいい。」
ヒカリの、何故か泣きそうな呟きにレイは目をつむったまま顔を赤くした。
「鬱陶しいのよ!」しかし突然ヒカリはレイを突き飛ばした。
そこにペンペンとミサトが現れた。
<あなたは良い友達だ。>
<有り難う。>
<ミサトも良いペンギンだ。>
「な、何ですってえ!」
ミサトの声に合わせるかのようにペンペンは消えて、その代わりに白衣に両手を突っ込んだリツコがミサトに食って掛かっていた。
「ミサト、どういう事!」
「…ごめん…」
「ごめんで済む事だと思っているの!」
「…」
リツコは頭を振って、髪をくしゃくしゃとかきあげた。
「ミサト、私が一番不安だったのはこういう事だったのよ。このペンギンは客寄せに公開しているアトラクションじゃないの。誰かれ構わず見せて良いような代物じゃないのよ。今までなるべく口を出さないようにしてきたけど、その結果がこれ?
全く…そうね、ミサトを信用した私が馬鹿だった。」
「…シンクロナイザーの発信機が壊れていたのも私のせいみたいな言い方ね?」
「それは確かに私の責任よ。でも葛城飼育担当、あなたには、いざという時の為の発信機等は無い物という前提で機密管理をして貰いたかったわ。」
「…」
「その粗忽さも父親譲りなのかしらね。」
ミサトはリツコの言葉に驚いたように顔を上げた。
「良いわよね、七光りで研究に参加出来る人は。つくづく羨ましいわ。」
「あんた、本気でそんな…」
ミサトは自分の言葉を飲み込んで、頭を振った。
「…とにかく、何とかして探さないと。」
「何とかして? どうするのよ? 闇雲に探して見つかるとでも思っているの?」
「連絡も出来ないし、発信機も使えない状況でただ待っていろって言うの? 彼は人工種なのよ!」
「ペンギンについて講義をするとは、あなたも随分偉くなったものね。」
ミサトはリツコの言葉を無視して歩いて行った。
「私も行きます。」
「…そう。」ミサトはニコリともせずレイに答えた。
「レイちゃん、今日はもう遅いから帰りなさい。」
やや疲れた表情でミサトはレイに微笑んでいた。
レイが車から降りドアを閉めると、ミサトは「じゃあね。」と微笑むと、レイの返事も聞かずに車を飛ばして行った。
アクセルを踏む時の彼女は微笑んでいなかった。
そして、レイは一人残された。
レイはふと、友人を得るにはかどの自動販売機でビール缶を買えば良い事に気づいた。確か…そう、赤木博士が開発設置した物だ。レイはアパートを飛び出して、そこの角まで走って行った。
そこでレイは、自分が500円玉を(そのビールは1缶500円だった)持っていない事に気づいた。
いやそもそも、レイは現金等今まで持った事が無かったらしかった。
レイは表情を凍らせたまま立ちすくみ、弱くその自販機をゆすぶってみた。
ガシャン。
販売時間が過ぎたらしく、急にその自販機はアルミのシャッターで閉まってしまった。
シャッターか何かに手をぶつけた痛みでレイは目を覚ました。
レイは自分が何の夢を見ていたのか一瞬考えたが、どうやら思い出せそうに無いのですぐに諦めた。
レイは首を傾けたまましばらくじいっとしていたが、昨日「着用後」の山に乗せたワンピースを羽織り、ドアを開けると一目散に駆け出した。
「はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、」
レイは夜の南仙台を、結構な距離走っていた。5分ほど走って、国道沿いの歩道橋の下の電話ボックスに彼女は駆け込んだ。
レイは今時灰色の公衆電話のボタンを押した。
呼び出し音が8回続いた所で、電話が繋がった。
「…え。もしもし…」
寝起きなのだろう、何だか潰れた声が聞こえる。
レイは両手で大事そうに受話器を抱えながら、向こうの声に問い掛けた。
「洞木さん?」
「ええ、そうですけど……綾波さんね?」
ふう、という溜め息が聞こえる。
「ええ、ごめんなさい。何故だか分からないけれど、声が、聞きたくて…」
レイはふと思い出し、続けた。
「これは友人としては普通の事なのかしら?」
「…ええ、うん、まあ、そうかしら。中々眠れない夜ってあるものね。」
「ええ。」
レイは顔を綻ばせ、電話機に頷きながら話を続けた。
午前4時だった。
レイが自分のそんな睡眠に我慢出来なくなって起きたのは6時40分だった。
涼しい風の吹く中、レイは白い無地のパンツとプルオーバーを身に纏い、早足で南仙台から閖上に至る道を歩いていた。
朝の田舎道は蛙と蝉がうるさい。脇に小川のような…というと誉め過ぎな、雨どいに毛の生えたような、用水路が平行する道をレイは歩いている。
私のせい。私が部外者の立ち入った状況で平気で部屋を離れてしまったのがいけない。部外者…私もそう…でも、誰にでも疑いを持たずに接するのが葛城さんのやり方なのだから、それは否定出来ない。赤木博士も常に忙しい身だ。
ただ、ペンギン担当の葛城さんから、一時的にでも部屋の事を一任されたにも関わらず、私は部屋を離れた。それは葛城さんや赤木博士の信頼への裏切り。そして何より、ペンペンの…
レイは自分の胸や眉間の辺りに変な、嫌な気のような物があるのを感じていた。レイはそれの振り払い方が分からず、それでますます不愉快になったまま、見慣れた倉庫まで辿り着いた。
水族館はいつものように静かだった。
まだ開館まで1時間以上ある。駐車場を見ても、スタッフの自家用車もまだ少ない。
レイは自分が開館時間の事も考えずに来た事が自分の傲慢さを示していないか、一瞬考えたがすぐにその考えは否定された。
しかし気持ちだけが解決しても仕方が無いので、レイはスタッフ用の入り口から、彼女としては充分呼びかけに相当する音量で「すいません」と首を出した。
「すいません。」
何かのモーターの音はしているので、既に何人かスタッフがいる事ははっきりしているのだが、目の前の通路には人影が無い。
その時向こうにマヤが現れた。何か書類を持っている。
「すいません。」
マヤは何かの声に不審気に立ち止まる。
「すいません。」
周囲を見回して、マヤはようやくその小さな異音の発生源に気づいた。
「ああ、レイちゃんじゃない。ポコちゃんが心配で来てくれたのね。」
マヤはレイの前まで来て、半ば苦笑のような表情を浮かべた。
「はい。」
「でも、今レイちゃん…いや、私達、に出来る事は、特に無いのよ。昨日も話を聞いたでしょうけど、秘密の研究だから警察とかに連絡は出来ないし、」
「でも、」レイはマヤを遮った。
「もし彼が何処かの岸に着いてそれがニュース等に報道されたら、更に問題です。」
「確かにその通りなのよね。」
マヤは頷きながら、レイが知らない内にどこか雄弁になったように感じた。
「…あ、レイちゃん、もうスタッフの一員みたいなレイちゃんにここにいるなとは言えないけど、今日は赤木博士にだけは会わない方が身の為よ。彼女、おかむんりだから。」
「お冠?」
「とっても怒ってる、って事よ。」
微笑むマヤの説明にレイは無表情に頷いた。
「当然です。」
「あ…うん…」
「それでは、葛城さんは何処にいますか。」
「ああ、ミサトさんは今車で…」
マヤはそこまで言い掛けて、目を大きくした。そして口を閉じレイに微笑んで、手で目の前、つまりレイの後ろを示した。
「ああ、レイちゃん。」ミサトはアルピーヌから降り、軽く頭をかきながら通路に歩いて来た。
「マヤちゃん、何か情報はあった。」
「いえ、何も…それだけを聞きに戻って来られたんですか?」
ミサトはここで初めて軽く笑った。
「電話だと嫌なのよ、赤木博士が取るかもしんないでしょ。」
肩を上げ、無言で頷くマヤ。
「あれから休まず探していたのですか。」
ミサトはレイに頷き、それだけでは足りないと思ったか口でも答えた。
「ええ、そうよ。この辺の海岸は見られる限り見たけど…何しろ道が無いし、明かりも無いしでおよそ捜索らしい捜索にはなってないわね。」
ミサトは自分で自分の言葉に溜め息をついた。
「全く私何やってんのかしら。」
「川…とかは?」
「名取川に広瀬川、七北田川に二郷堀、増田川、五間堀、阿武隈まで調べたわ。」
「そ、そう…ですか。」自分の質問にすらすらと答えるミサトにマヤは気圧された様子で返事をした。
「でも結局彼が水際にいるのかも分からないのよね。アスカちゃんが持って行ったんだとすれば、…状況から見たらそれ以外有り得ないでしょうけど…、彼女の自宅の一室とかにいる可能性も高い訳だし。」
「そう、アスカちゃんも探さないといけないですね。」
「これもペンペンと同じ。探しようがないわ。名字も知らないのよ。一応端末の電話検索で宮城エリアで調べてはみたんだけど…」
「世帯主でない限り下の名前は載りませんからね。」
ミサトは頷いた。
「大体ここの近所に住んでるかどうかも分からないのよ。…まあ、赤木博士が怒るのも当然よね。」
ミサトは腕を組み、大きく息を吐いた。
「私ってつくづくダメね。どうしてこう…うまくいかないのかな。こんなんじゃ失格だわ、飼育担当者として。」
「ミサトさん…普通、飼育担当者に防犯の意識は要求されませんよ。」
マヤの言葉にミサトは頭を振った。
「私は要求されてたのよ。それなのに安全管理に気を配るどころか、積極的に民間人の子供を秘密事項に関わらせたりして…しまいには初対面の子をペンギンに会わせたのよ。これじゃあ、とてもじゃないけど弁解の余地は無いわ。」
「葛城さん、私のせいです。」
口を開いたレイに、ミサトは弱く微笑んだ。
「違うのよ。あなたに場を任せたのは私だから、悪いのは私なの。」
日が昇りつつある通用路の入り口で、3人は無言で立っていた。
「責任を取って辞表を書くわ。」
「そんな、」
ミサトはマヤの言葉を手で止めた。
「そうすべきなのよ。」
「そうすべきかもしれませんが、」
ミサトとマヤはレイに顔を向けた。
「その前に、ペンペンの捜索に全力を尽くすべきだと思います。」
ミサトは頷いた。
「その通りだわ。…じゃ、マヤちゃん、何かあったら知らせて。もう一っ走り行って来るわ。」
「事故らないで下さいね。」
「大丈夫よ。」
「あの、私も乗せて下さい。」
「…分かったわ。」
ミサトもやはり、レイが彼女にしてはよく喋るのに少し驚いているようだった。
人を見掛けで判断は出来ない、とレイは思った。
しかしあの場で油断をしたのは私だった。私には葛城さんを責める資格が無い。
「…レイちゃん?」
情報量の多い3面式モニタの前で、ミサトはレイの押し黙った様子に思わず呟いた。
「何ですか。」
「ああ、いや、うん…」
ミサトは昔カーマニアだった。最近は忙しいのであまり遊べないが、二大時代はバイト代の学費・住居費以外をほぼ全てカーアクセサリー代に回した物だ。ミサトのエンゲル係数は所得に見合わず低かった。ちなみに彼女の最大の屈辱の一つは、この時30万円強を投入してビルトインしたタッチパネル付きバックモニタを、買って2日後後方のカメラを、その時モニタがついていたにも関わらず接触で壊してしまい、使用不能にしてしまったという事である。
「レイちゃんは、音楽とか聞かないの。」
車はミサトが運転しているとは信じ難いゆっくりとしたスピードで、海沿いの仙台東部道路を南下している。
レイはミサトが徹夜明けとは思えない程の集中力でレイの側の窓の向こう−つまり海−に時折り目をやりながら運転を続けている事に少し感銘を受けていた。
「いえ。」
「じゃあこんなのは、どう。」
ミサトがオーディオのスイッチを押すと、歪んだギターの入った、英語の曲が流れ出した。
「Wonderwallって言う、むかーしのロックの曲よ。」
レイはふいにミサトの方を向いた。
「ああ、ごめん、うるさかった?」
「いえ…面白いです。」
「なら良かったわ。」
ミサト達は亘理まで行って、引き返し今度は北上する事にした。既に10時近くになっている。
低速の電気自動車は、無意味にフェイクノイズを上げていた。
「ねえレイちゃん。私、こう見えても大学時代教員免許取ってるんだ。だから、水族館辞めたら学校の先生になろうかなって思って。」
レイは海に目をやりながらも、ずっと音楽に聞き入っているようだった。
「もちろん今は子供多くないし、教師になるって言ったら簡単になれるようなもんじゃないのは分かっているけどね。でも今のこの国は、助けを必要としている子が特に沢山いると思うのよ。」
ミサトは自分の言葉に苦笑した。
「助けが必要なのは、私じゃない。」
「葛城さんは何を望むのですか。」
「…望み?」
ミサトはレイに目をやった。
「…望みね…父親を忘れる事かな。」
ミサトは呟いた。
アルバムが2回終わった所で、ミサトは車を停めた。
レイがミサトの顔を見ると、彼女は珍しく真面目な様子の顔で目を窓の向こうの海岸に向けた。
少女が砂浜に座っていた。
アスカは特に驚いた様子もなく顔を向けた。
「ミサトさん。レイさん。」
ミサトとレイは車から降りて、荒れ地という言い方もする、雑草の茂る土手を数メートル歩き、砂浜に来た。
「どういう事か説明してもらえるかしら。」
「…」アスカは微笑みながら、立っているミサトの顔を見上げた。
「瞼に力入ると、皺の原因です。」
眉を潜めるミサトにアスカは笑った。
「冗談です。」
「冗談で済む状況じゃないの。アスカちゃん、ペンペンはどこにやったの。」
「…」
アスカは答えずに、手を広げて砂の上に置いた。
「アスカちゃん。」
「私は海を多く見なかったです。ここがとても久しぶりです。だから、とても、mmm、嬉しい、です。」
ミサトは降参したかのようにアスカの隣に腰を降ろした。
「それで?」
「日本の海岸は美しいです。」
「…ペンギンは。」
「…」
アスカは黙って水平線を見つめていた。
「…まさか…まさか、海に放した訳じゃないでしょうね!」
アスカは鋭い視線をミサトに向けた。
「もしそうなら?」
ミサトはアスカの肩をつかんだ。
「あんたね! ペンペンは人工種だから、自然で生き残るような力は無いのよ!
ましてやここの亜熱帯の海なんかに放したら数日と持たない内に、」
「温泉ペンギンであるのに?」
ミサトはアスカのとぼけた質問に、手を離し溜め息をついた。
「それは名前よ。イワトビペンギンっていうペンギンがいて、南極付近の…フエゴ島っていう島の間欠泉の近くで発見された物がベースになってるから温泉ペンギンって名づけられただけ。温泉に入れる訳じゃないわ。」
「それは可哀相です。」
「あんたね!」
「何か証拠がありますか。」
アスカはミサトの声をピシャリとはねのけた。
「私は日本が好きでした。日本に興味を持ちました。でも、私は日本に来たら、私が間違っていた事に気づきました。」
「…」
「ここはとてもきれいな所です。そして自然がとても美しいです。でも、」
アスカは左の方向に顔を向けた。ミサトが見ると、そこにはジュースの空缶の山があった。
「日本人はそれが分かりません。私はとても残念です。」
アスカは少し顔の表情を緩めた。
「とはいえ、ドイツ人は悪い所が沢山あります。しかし、自分達の良い所も知っています、そう思います。日本人は、自分達の、ah…大切な…ah、大事な?
ja、大事な、事を忘れています。それはとても残念です。」
「あなたはペンペンを海に放したのね。」
レイが初めて口を開いた。
「…はい。」
アスカははっきりと答えた。
立ったままのレイはアスカを見下ろした。
「あなたはあなたのした事が分かっているの。」
アスカは誇らしげにすら見える表情でレイを見据えた。
「はい。」
レイは傍目にもはっきり分かる程憎悪のこもった目でアスカを睨んだ。
ミサトはこの時、初めてレイが少し好きになった。
「あなたは私がした事が不満に見えます。」
「ええ。あなたのした事は犯罪よ。」
アスカは肩を上げた。
「私は日本の法律の事を知りません。しかしそうかもしれません。」
「…」
「私は私のした事は隠しません。何故なら、私のした事は間違いではないからです。」
「あなたのした事は間違いよ。」
「あなたがそう思うなら。しかしあなた達のした事も間違いです。とても悪い犯罪です。」
腕組みをして2人の話を聞いていたミサトが言う。
「何が言いたいの?」
「Hmp. あなた達が充分頭が良いければ分かるでしょう。」
「私達は間違っていないわ。」
レイの声に合わせるように、アスカは立ち上がった。
「それだったなら私は嬉しいです。」
「アスカちゃん、一緒に水族館に来て貰えるかしら。」
「Warum?(どうして。)」
アスカは続ける。
「あなたは私を逮捕しますか?」
両手首を付けてミサトの前に出す。
「そうなるかもしれないわね。」
「Ah, so! それは大変ですね。」
ニコリともしない2人にアスカは息をつき、両手を腰に当てた。
「良いですよ。私はあなた達と一緒に行きましょうよ。私は悪い事は無いですから。」
ミサトは軽く頷くと、車に戻って行く。
「Hmp. Entspanne sich, die Tussi.(もっとリラックスなさいよね。)」
アスカはボソッと言うと、ミサトに付いて行った。
二郷堀と閖上の間はせいぜい3キロと離れていない。ミサト達の乗った車は2、3分もしない内に水族館に戻って来た。
「もう一度聞くけど、本当にあなたがペンペンを連れ出したのね。」
ミサトは駐車場に入らず、水族館の門の前で車を停め、ハンドルを握ったままアスカに聞いた。
「はい。」
「はあ…」頭をおさえるミサト。
「それで、海に放したと。」
「私達がさっきいた所で私はそれを放しました。」
「ああそう…」
ミサトは助手席のアスカを見つめた。
「どうして放したのか、話してくれない?」
「…水族館には行かないですか。」
「行くわ。行くけど、その前にここで聞いておきたいのよ。」
アスカはその整った眉をやや上げたが、前方の景色−フェンスや塀に挟まれ、それほど見える物も無い−を見ながら答えた。
「Ah…日本語で何と言いますか…Ah、いじめ?」
「いじめ? 何が?」
「ペンギンを虐待していると言いたいのではないでしょうか。」
後ろの座席、と言うより小物を置くスペース、からレイが口を挟む。
「虐待。ああ、そう、それです。そう思います。」
「虐待ではないわ。」
アスカがレイに言い返そうと振り向いたが、ミサトは2人を手で止めた。
「仮にそうだとしても、それでいきなり海に連れて行くっていうのも、随分過激な話じゃない?」
「私はあなた達が私の話を分かるとは思いませんでした。」
「なるほどね。…」
「何故、ここで話しているのですか。」
ミサトはレイの置かれている状況に気づき、慌ててドアを開け、車を降りた。
「あ、ごめん、後ろ窮屈でしょ。ちょっと待っててね…どうぞ。」
レイはアスカをちら、と見て車を降りる。
「私は出て良いですか。」
ミサトは数秒黙っていたが、肩を上げた。
「どうぞ。」
アスカは自分でドアを開けて車を降りた。
「ねえ、アスカちゃん、あなたが私達がペンギンを虐待していると思ったとしても、どうしてその、証拠とかもつかまないまま、来て数秒で持って行こうと思ったの? 前にここに来た事なんか無かったわよね?」
「ここは風が強く動きます。水族館に行きましょうか。」
「…分かったわ。」
ミサトはようやく諦めて車を道路に置いたまま水族館へと入って行った。
ミサトはリツコの研究室にドアがある事を初めて意識した。普段は開けっ放しなのだ。
ミサトはドアをノックした。
返事は無かった。
ミサトは重ねてドアをノックする。
「リツコ、入るわよ。」
研究室にリツコはいなかった。
ミサトはレイ、アスカと目を合わせ、ペンギン室へと向かった。
ミサトがペンギン室のドアを開けると、そこにはリツコ、シンジとぐったりと横たわるギンギンがいた。
「ミサトさん。綾波…アスカさん。」
「何、これは。一体どうしたの。」
リツコはミサトの様子に何か口を開きかけたが、息を吐き、静かに喋りだした。
「見ての通り、眠らせたのよ。今朝これが起きてから、ポコティファがまだ帰って来ていない事でパニック状態になってね。野生種が巣に侵入者が来た時に見せるような威嚇のポーズまでとって…狂ったように首振りや「御辞儀」を始めたのよ。ピンギ自身に危険だから眠らせたの。」
リツコはアスカに目を向けた。
「あなたが、アスカさんね。」
「はい。」
「上の名前は。」
やれやれ、という感じでアスカは微笑んだ。
「惣流・アスカ・ラングレーと言います。」
リツコは立ち上がった。
「来なさい。少し話があるわ。…シンジ君、ピンギをお願いね。」
「はい。」
自分の研究室の椅子に座ったリツコは、折り畳みのパイプ椅子を広げ、隣に置いた。
「座りなさい。」
「とても良い椅子ですね。」
「ありがと。」
皮肉を無視してリツコはメルキオールを立ち上げた。
「あなたがポコティファを持ち出したの。」
「…ポコ…ティファ?」
「…ペンペンの事よ。」
背後から言うミサトに怪訝そうな表情を返すアスカ。
「何故それがポコティファなのですか。」
「ポコティファが本名、ペンペンは俗称なの。」
当然のように言い切るリツコ。
「俗称?」
「…簡単に言うと、あなたが持って行ったペンギンの名前はポコティファと言うのよ、それが正しい名前なの。」
「そうですか。」
「…あなたが、ポコティファを持って行ったのね。」
「はい。」
リツコは、アスカの淀み無い様子に少し驚いたようだった。
「…そう。私はあなたの行動や動機に興味は無いわ。道義的な事を持ち出すつもりも無いしね。」
「道義的?」
「…あなた、日本語に弱いのね。」
「すいません。」
「別に構わないわ。英語で話ましょうか。」
「Ah, it'd be much helpful.」
「OK. What I was saying is that, I do not mind, neither do not care,
your purpose nor intention, neither I don't talk about something of moral.」
アスカは居心地悪そうに目を上げた。
「Ah...if you don't mind, you can speak in Japanese. And I, 'll answer
in English. How's this?」
アスカの後ろで笑いを噛み殺すミサト。
リツコは目に見えてムッとした様子になったが、軽く頭を振って口を開いた。
「ならそうさせて貰うわ。話は簡単よ。私はあなたに、ポコティファを返して欲しいの。」
「Ahh. It's a little hard one to say yes I'm afraid.」
「何故。」
「I mean. It wouldn't be too easy, to get him back from him swimming
over the Pacific.」
リツコはアスカとミサトを呆れたように見た。
「海に放したの?」
「Mmm, to be exact, I just helped him, to back his home.」
「彼のホームは…まあ良いわ。そうなると、見通しは暗いわね。ペンギンの泳ぐスピードは速いわ。もっともポコティファが、そう長距離を移動出来るとは思えないけど。その前にカモメにやられるか、熱さにやられるかでしょうね。…仮に海岸に打ち上げられても発見されない可能性も非常に高いでしょうし…。」
アスカとミサトの表情は中々の好対照だった。赤い虚勢と青い悔悟。
「So?」アスカはリツコを促した。
リツコはしばらく考えてから、口を開いた。
「一週間程待つわ。その間にポコティファが帰って来なければ、あなたに弁償をして貰う形になるわね。」
申し訳無さそうに立っていたミサトは、リツコの言葉に眉をよせた。
「ちょっと、リツコ。」
「当然の事でしょう。」
「冗談でしょ、相手は子供なのよ。」
アスカは平然と頷いた。
「Yap. It's a very natural treat.」
「ちょ、ちょっと、アスカちゃん?」
「In her...彼女の立場では、それは自然の事です。」
「なら話は速いわ。あれは非常に人工的な種でね。開発に要した金額もかなりの物なの。その上現存するのがここの1つがい、2匹だけで、その内の一方をあなたは奪ったの。これがどういう事かは分かるわね。」
「つがい?」
「カップルの事よ。」
「Ah.」
「正確な被害額は算出のしようがないけれど…取り敢えず、ポコティファの開発及び養育に費やした費用で、約2億6000万円位になるわ。最も低く見積もってね。」
ミサトは頭を振った。
「…リツコ、あんたね、」
「I won't pay that.」
リツコとミサトはアスカを見た。
「気が変わったのかしら?」
「No, but remember, I just said YOU'd say the things like that in yah
position, didn't say I appreciate it.」
アスカは立ち上がった。
「Sue me. Take this matter to court. I'M fine with that.」
リツコは深く溜め息をつき、人差し指を額に置いた。
「そんな事は出来ないわ。」
「You say cause it's a secret research? Well then, you really should
know how to keep secret. Really. I warn you.」
「あなた本気なの。」
「Sure.」
「…分かったわ。それじゃあ残念だけど、これで話は終りね。ああそれから、住所と、電話番号、保護者の名前を教えてくれるかしら。」
「Berlin, or Tokyo-2?」
「第2東京、で構わないわ。」
「…長野県第2新東京市、梓川区、梓橋1-5-15、マジェスティ梓橋F-8。電話番号が、02-3732-…」
アスカはさすがに日本語で答えだした。
「…そして、保護者が…」
アスカは言葉を切った。
「…いないです。」
「孤児だと言うの?…日本でも、偽証は大きな罪になるわよ。」
「偽証?」
「嘘の証言。」
「嘘ではありません。…しかし私を育てた親はいますが。」
「それで良いわ。その人の名前は。」
「しかし、もう彼等は、」
「今は名前だけ聞いておくわ。」
「OKAY. Claudia Wierkotter. Ah...」
アスカはリツコの前に身を乗り出し、メルキオールのパネルを叩いて綴りを入力した。
「しかし、彼女が関係の問題では」
「あなたは今、一人暮らしをしているの?」
「…ええ。」
「…そう。まあ良いわ、後はこの、有能な飼育担当さんに一任するとしましょう。ねえ、ミサト。」
リツコはメルキオールをスリープさせた。
ミサトはしばらくリツコとアスカを見比べてから口を開いた。
「で、ペンペンは戻って来るの。」
フン、とリツコは鼻を鳴らした。
「神のみぞ知るといった所ね。ポコティファの帰巣本能に期待するしかないわ。あなたも知っているでしょうけど、普通のペンギンは、必要な時は数百キロの距離でも自分のルッカリーに帰って来るものよ。ただここの海で、数キロでも彼が泳ぐ能力があるかなんて、ましてやシンクロナイザーを背負った状態で…」
「すいません、」
アスカが眉を上げた。
「帰巣本能とは?」
「…自分の巣へ帰ろうとする本能の事よ。」
「Ah.」アスカはリツコの答えに頷いた。
「もしそれが本当にあれば、彼はみな…eh、南極、に帰るでしょう。」
リツコは煙草に火をつけた。
「議論するつもりは無いわ。」
「……それは残念です。」
アスカは彼女に侮蔑の表情を見せ、研究室を後にした。
「…うん。」
アスカは腕を組んで、軽く笑った。
「私は自分がとても魅力的なのだと思いますよ。」
「うん…ちょっと、良いかな。」
頷くアスカ。
「ミサトさん、ギンギンの方を。今、綾波が見てるけど…」
「分かったわ。」
「…前と違う子だな。」
向こう岸でいつものように黒鯛釣りにいそしんでいた時田は、何だか少し感心したような顔で子供達を眺めた。
河畔公園のベンチに座ったアスカは、ジーンズの足を組んでシンジの方を向いた。
「それでは? あなたは、どんな話を私に聞かせますか。」
「アスカさん…が、ペンペンを持って行ったの。」
「又その話ですか。」
アスカは足をぶらぶらと揺らした。
「その話はもう良いです。」
「良くないよ。そのせいで、ギンギンは、ショック状態になってるんだよ。」
「…それは間違いでした。ええ。私はそれも放すべきでした。」
「…放す?」
アスカは少し真面目な表情になってシンジを見つめた。
「シンジさん、あなたは、私が寂しいと言いました。それは正しい。私、寂しいかったです。でも今、ah、今まで、私にそんな事を言う人はいなかったですね。」
シンジは彼女のような美人にこうやって喋りかけられているのに、おととい程は緊張していないのは何故だろう、と少し思った。それはもちろん今は状況が特殊であるという事もあるのだが。
シンジから見て、レイとアスカはとても似ているように思われた。つまり、ごく簡単に言って2人とも同質性を是とする日本ではどこか浮いている。2人ともそれ故の意思疎通へのハンディを持っている。そして2人とも、それぞれのやり方で、毅然としてそれを克服しようとしているように見える。
シンジのように、特にハンディがある訳でも無いのにコミュニケーションへの違和感がある者にとって、彼女達は何か、罪悪感を感じさせる存在であるとも言えた。
現金なもので、最近シンジは自分のレイへの思いが日に日に薄くなって行くのを実感していた。ケンスケの誘いが有ったとはいえ、ここ数日水族館に来ないでチェロばかりやっていたのもどこかに彼女を避ける気持ちがあったから、かもしれなかった。
しかしそれでもシンジはレイが好きだった。少なくとも好きなはずであった。そして彼女に比べると、目の前のアスカは、どうもそんな気持ちになってしまうような危険性が低いように思われた。
「あの、気を悪くしたらごめんね。あの…アスカさんって、結構、気が強そうに見えるよね。だから皆、そういった事は言えないんじゃないかな。」
アスカは苦笑して頷いた。
「ドイツ人は皆傲慢です。私は彼等の中で育ちました。だから私もとても傲慢です。」
「別に、傲慢とまでは、」
「はい、本当の事です。」
アスカのルックスは魅力的だった。髪は綺麗な茶色で、目は青。肌も非常に白い。それも綾波のような病院が似合う白さじゃなくて、何と言うか、テレビドラマとかで見そうな白さだ。それでいて、垂れた目元や小さな鼻を始めとした顔の造りは明らかに日本人の物である。その為アスカのルックスはただの「ガイジン」とも又異なるとてもエキゾチックな物に思われた。
「アスカさんって…」
思わず口に出したシンジは、その後どう言葉を続けようか分からなくなって固まってしまった。
アスカは外交的に微笑んだ。
「何ですか。」
「あ、ん、何でもない。」
「何ですか。」
後ろ上がりの独特なアクセントでシンジに迫るアスカ。
「アスカさんって、もてる、でしょう。」
「持ってる?」
「ううん、その…美人だなって、思って。」
アスカは少年の言葉に驚いたようだった。
「Ah. これから、eh…私に、近づきますか?」
「ああ、別にそういう訳じゃなくて。全然、そういうんじゃ、ないんだけど。」
何でなんだろうな、とシンジは思った。
レイもアスカもとても似ている。そしてシンジから見れば、2人ともルックスは素晴らしい。と言うか、アスカの方が近づきやすい分良いかもしれない。であるにも関わらず、選ぶとすれば、現時点でシンジが選ぶのはレイであって、アスカではない。
これはつまり、いくら自分には無いような強さがあると言っても、基本的にレイはいじめられっ子であり、アルビノであるという事も含め「弱い立場」の人間であるという意識がシンジにある為、保護欲や、もしかしたら支配欲や独占欲が働くのかもしれない、というのがシンジの仮説であった。アスカの場合、少なくともレイ程は厳しい状況には無いようだし、成熟した「大人の」コミュニケーションがある程度出来ているように見える。彼女の自立性が自分を彼女から遠ざけさせているのかもしれない。
つまり僕は自立した女性が嫌いだという事なのだろうか。
アスカは一人考え込んだシンジを面白そうに眺めていた。
「シンジさん、もっと、リラックスしましょう。」
「…あ…あ、あ、ごめん。話があるとか言っといて。」
「シンジさんは面白い人ですね。Ah…ゆっくり、考えるのが、好きなんですね。あなたはそういうタイプですね。」
「う、うん…暗いって分かってるんだけど…」
「Hmmm. 私は、シンジさんは好きです。Ah、もちろん、」
「あ、うん、分かってる。」
アスカは微笑んだ。
「シンジさんは…真面目な人です。Ah、多分、暗い、かもね。でも、hmm、私も、ゆっくり、考えたかった。だから、ah、シンジさん、」
アスカはシンジの手を取った。嫌いなのかと思っているのに心拍数の上がるシンジ。
「シンジさんは私の話分かると思います。」
「…ペンギンの事?」
アスカは頷いた。手を放し川面を見る。
「私は昨日ペンペンを連れて、海に放しました。」
「…そうなんだ…」
「シンジさん、ここでペンギンで実験をするのはペンギンは可哀相です。とても可哀相。」
「…」
シンジはアスカの言葉に僅かに頷いた。
「でも…そんな事言ったら…水族館も、動物園も、全部「可哀相」になっちゃうよ。」
「もちろん全部可哀相です。でも、これは可哀相過ぎます。つまり、ah、ただいるのではありません。しかし実験をしています。これはとてもとても可哀相です。」
「そうかなあ…楽しくやってるように見えるけど…」
「それは本当ではありません。ペンギンは、ペンギンの幸せへの道があります、人間の道は彼等の物ではありません。Ah、あなたは私の言う事分かりますか?」
「あ、うん、大丈夫。うーん…でも、それに、彼等は、純粋なペンギンじゃないんだよ。いや、ペンギンはもちろんペンギンだけどね、その、遺伝子操作?とかで人工的に作られた種だから…」
アスカは少し悲しげに頭を振った。
「ですから、そんな事をするはいけないのです。」
シンジはアスカの言う内容はともかく、彼女の真剣さに思わず口ごもった。
自分が自分の事ばかり、誰が好きとか嫌いとかばかり考えてる間、同い年のこの人は、こんな事を考えていたのだ。
「…そうか…確かに…そうなのかもしれないね…」
「シンジさんなら、分かってくれると思いました。」
アスカは微笑んで頷いた。
「で、でも、アスカさん、確かにそういう風に動物の遺伝子をいじるのはやっちゃいけない事かもしれないけど、とにかくペンペンとギンギンは今ここで生きてるんだよ。それを、その、海に放すとかは…だって、それはペンペンやギンギンが悪い事じゃないんだし…」
「それは…」
アスカは口をつぐみ、軽く頷いた。
「そうですね。」
「で、でしょう? それは、アスカさんの言う事も、分かるけど…」
「…でも。私は許せなかったです。私はここに入った時、eh、とてもショックでした。そして怒っていました。ペンギンがいます、背中に機械を置いています、そして、ah、端末で座…らされて、います。とても可哀相に思いました。許せないですと思いました。そして私は思いました。Ahh…彼等は助けを必要です。はい、自由が必要ですと。…シンジさん、私は間違っていましたか?」
シンジは口を開きかけたが、閉じた。答えようが無い。シンジはペンギンではない。本来何が正しいか等と言う事は、シンジに答えられる事ではないのかもしれない。
今まで自分の事で手一杯で何の疑問も持たないで来たが、言われてみれば確かに何故ペンペンのような物が、特にこんな片田舎の水族館に、いるのか不思議だ。人工種で、背中の重い機械を外すと即生命維持に支障が出る。何故そんな物を作ったのだろう。そもそもそんな一生を彼等は望んだのだろうか?
一方、彼等が最近会話を自発的に行い、とても楽しんでいたのも事実だ。それに…
「…少なくとも、今の彼等にとって、その…悪い事かもしれないけど、あそこの生活が全てだと思うんだ。ペンペンにとっての幸せへの道は…ん…海には、無いんじゃないかな。」
アスカは目を落した。
「本当ですか。…私はここの海では彼は、ah…長く持てないと聞きました。それは本当ですか。」
「…そう…かもね…」
アスカはきらきらと輝く髪をなびかせながら、いつものように頬杖をついた。
「私は…」
Ich bin schrecklich Pappnase gewessen, es scheint...Ich,...Ich...
「それでは、ポコティファに御免なさいと言わないといけません。」
シンジがふとアスカを見ると、彼女は悲しげな微笑を見せていた。気のせいか少し目が潤んでいるように見える。
シンジは何か言おうとしたが、気の効いた台詞が何も思い浮かべられなかった。
「…ごめん。慰められなくて…」
「シンジさんって。やっぱり面白い人ですね。」
すー、ばしゃん。ばしゃ、ばしゃっ。
「ごめん…アスカさん、でも、ペンペンは…見つからないって決まった訳じゃないから…」
「もう良いです。」
ぶるぶるぶる、ぶるっ。ばたばた。
「それに、やっぱり海が彼等にふさわしい場所なのかもしれないしさ、」
「シンジさん、それは…hmm、嬉しいですけど、どうか言うは止めて下さい。」
とこ、とこ、とこ、とこ、とこ。
「ご、ごめん…でも、本当にそう思うよ。その、可能性としてはペンペンは死んじゃう可能性が高いとは思うけど、でも、…正直言って、最初はアスカさんが、お金か何かの為に盗んだのかと思った。でも、アスカさんの話を聞いて、今は何が正しいのか、分からなくなってるんだ。ここでは彼等が、自分で未来を選ぶような選択権が無いっていうのも確かに事実だと思うんだ。その意味では、」
「シンジさん、どうか止めて下さい。」
とこ、とこ、ぶるぶるぶる、とこ、とこ、
「…」
「彼に聞いてからでも遅くはなかった。彼の自由を私は自分で決めましたそれは私が傲慢だからです。そして…私は彼の命を、勝手に…御免なさい…」
アスカは自分の足に何か痛みを感じた。
「くあ。」
2人は目の前のつぶらな瞳の鳥に声を上げた。
「Mein Gott!」「ペンペン!」
アスカはペンペンを抱きしめた。
「があ。」
「Mein...Verzeihung, Junge. Verzeihung...(ああ…ごめんね。ペンペン、ごめんね…)」
「がああ。」
抱き付かれるのが嫌らしく暴れるペンペンと、全く離そうとしない怪力のアスカを見て、シンジは嬉しそうに笑った。
<暑い事を別にすればとても面白かった。>
けろりとした様子の(ペンギンに人間のような表情があるかどうかは別にして)ペンペンに、一同は呆れた様子で息をついた。
<私達はあなたの事を心配したのよ。>
ミサトの入力する文に頷くシンジ。頷かないまでも同意している、と思われるリツコとレイ。
<そうだ。大体ペンペンは勝手過ぎる。勝手に消えないで欲しい。>
加勢がバルタザールのペンギン用キーボードから起こった。
「が。」
<私の意思で消えた訳ではない。あの人間の女が連れて行ったのだ。>
「ぐああ。」
<人間の女と一緒にいてもしょうがないではないか。>
「あ、あのー…」
<だから私の意思で一緒になった訳ではないのだ。>
「ぐあ、くあ。」
<いつも人間の女といるではないか。>
「がー、くあ。」
<あなたもいつもいるではないか。>
「くあっくあっくあっ」
<いつも人間の女と話しているではないか。>
「ちょっと?」
<当たり前だ。その方が楽しい。>
「くああ。」
<私もその方が楽しい。>
「くああ、くあっくあっ、くあー。」
<あなたこそ、人間の女といてもしょうがないではないか。>
<それこそ私の勝手だ。>
「Ahh…」この場で唯一ペンギン語を解さないアスカが尋ねた。
「何を、話していますか。2匹はとても興奮しています。」
「ああ…うん…」気の無い返事を返すシンジ。
「ミサトさん、どうか彼等に聞いて下さい。Hmm、彼等は、どこを家と思っているかを。」
ミサトは入力をしようとして、手を広げたが、そのまま考え込み出した。
「あの…アスカちゃん、「家」っていう単語は無いのよ。普通はその意味で、「プール」って言葉を使うんだけど…」
アスカは申し訳無さそうなミサトの言葉に、ゆっくりと微笑んだ。
「…そうですか。」
もう夕方近くになっていた。
アスカは微笑みながら、頭を横に振った。
「私はこういう物が嫌いです。」
スケルトンテトラの水槽の前でシンジは微笑んだ。
「…そう。僕は…何でだか、こういった魚を見るのがすごく好きで、」
「それは良い事です。でももしそうならあなたが海に入るべきです。」
「あー、スキューバダイビングとか?」
無言で頷くアスカ。
「そうかもしれないね。でも、そんな簡単に出来る事じゃないし、」
「今度一緒に練習しましょう。」
「ああ、うん、そうだね。」
シンジとアスカは笑い合った。
「…私は、まだ分かっていません。Ahh、あなたは日本語で何と呼びますか、ah、hmm、あれらのペンギンが作られた事が正しいとも思いません。」
「…うん。」シンジは先を促した。
「でも、彼等は、とても、hmm、その、自分の、hmm、自分の世界の中で頑張っています。彼等は、悪くありません。しかしはい、彼等は素晴らしいです。」
「そうだね。」
「私も同じです。その、hmm、世界が良いか又は悪いかは関係無い、私は私の世界で頑張らなくてはなりません。分かりますか?」
シンジは頷いた。
「彼は教えました。」
アスカは魚を見ながらしばらく物思いに耽っているようだったが、やがてふとシンジの方を向いた。
「ところで、あの、ah、レイ? 彼女はあなたの好きな女の人ですか?」
「…へ? あ…いや、別に…」
「シンジさん、あなたは、本当に面白い人ですよ。」
アスカは細い目で感想を述べた。
−あたしはいつも通りよ。あんたに社交辞令じみた言い方しても意味も無いでしょうから言うけど、元気な時もあればダメな時もあるわ。ま、誰だってそれは同じでしょ。でもこの前ちょっと、「海浜公園」っていうとこに散策に出てね。良い気晴らしにはなったわね。だから今は、まあ元気かな。バカ日本人共を相手にガシガシ金を稼いでやってるわよ。それにしても、あんたも研究室から少しは出なさいよね。だからドイツ人達から「白い吸血鬼」とか何とか言われるのよ。もうちょっと社交ってもんを知りなさい。それからマルギットとヘレーネには、今はハイネットって言う便利な物があるんだって事教えてやった方が良いわね。…ゲオルグ、会いたいわ。今すぐに。でも、残念だけど、ここしばらくは休みは取れそうにないの、ごめんね。クリスマスは、絶対戻るから…ね。じゃあね。
P.S. その公園には、小さな、白い「渚」があったわよ。その内案内するわよ、悪いとこじゃないわ。
あんたもがんばんのよ。