ふと周囲を見渡すと、後方の右手の席の日本人達がこちらを見ていた。多分手紙が横文字なのを見ていたのだろう。彼女が軽く睨むと、その日本人達は一瞬の内に目をそらした。
彼女は軽く息をついた後、頬杖を突き、左手の人差し指と中指を交互で交互に頬を叩きながら、流れていく民家と木々と看板を眺めていた。
アスカは日本が好きだった。
昔のような変な憧れは無くなった。極東は確かに暖かい所だが、楽園ではなかった。しかし積極的に好きだと言うのは無理があるにしても、アスカは日本を少なくとも電車から外の景色を眺める分には悪い所ではないと考えていた。
しかしこの看板群はどうしたものか。それが日本の景色だと言ってしまえばそれまでだし、複雑怪奇な象形文字のロゴタイプ−一体あの日本語をどう分析すればこんな大層な文字になるのだろう−は彼女にとってエキゾチックな情感をかきたてる物でもあったが、それでもやはり緑の景色に群立する飴や菓子や煙草の看板は、雰囲気を壊しているように思えてならなかった。
煙草の看板? 先進国で未だに公共の場での煙草の広告を認めている国なんて、日本と南中国位の物だ。全く東洋人というものは…
大体日本人は自分達のヘリティジを軽視し過ぎる傾向がある。若者達は西洋の事ばかり追いかけるし、大人達もそうだ。だから、こんな私のやる気の無いバイトでも立派に成立してしまうのだ。こんなの間違ってる。
確かにこっちの仕事は楽で良いけど、…良いけど……まあ、ねえ…生活できるだけ、良いのよね…
まあ、日本人の趣向なんて、「ガイジン」のあたしが口出しする事じゃないしね。
アスカは軽く頭を振ると、AMDの再生ボタンを押し、イヤホンから流れるハードフロアーの曲に耳を傾けた。
ダメね。煮詰まっちゃってる。ホームシックなのかな…どうせアイツはこっち来る金なんか無いんだし、帰ろっかな、ベルリン…
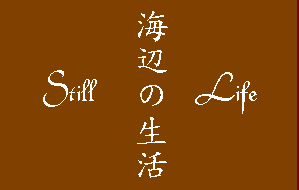
「アスカ、頼むよ。それは今になるまで何も言ってなかったのは謝るけどさ。こういうのは話が来る内が花なんだよ。」
こざっぱりとしたスーツの眼鏡の男が作り笑いをしながらアスカに近寄る。
「来る内が花?」
「ああ、つまり…若い時にしか来ないって事さ。君が花のように美しいから…」
「私は来て欲しいでは無かったです。」
アスカは男の言葉を遮った。
「辺見さん、私は言いました前に。Uh、裸は駄目ですって、私は言いましたね。何故あなたは約束を破りましたか。」
アスカはつくづく、自分の日本語の下手さ加減が恨めしかった。これは喧嘩をしたい時には殆ど致命傷だ。
「アスカ、それでも良いのか。そういう態度でいつまでも許されると思ってるのかい。」
「こういう態度の原因は、あなたです。」
アスカは両手を腰に当て、首を軽く傾けた。
「アスカ…気を悪くしないで聞いてくれ。はっきり言えば、君はモデルとしては十人並みだ。…十人並みって言うのは…」
「分かります。」
「そうか。なら分かるだろう? 君は今仕事を選り好み出来る立場にはないんだよ。」
「選り好み?」
辺見は苛立ったようだった。アスカはその様子を少し痛快に思った。
「選べない、って事だよ。」
「Ah…選べない、そうかもしれない。でも、その話は違う話です。私が怒っているのは、uh、私の相談が無かったという話です。相談が無くて、勝手に決めるから、だから私は怒るのです。」
辺見はやって来たカメラアシスタントに返事をする。口調は軽いが、その実腰を低くさせているのがアスカにも分かる。当然だ。これは自分のせいでもカメラマンのせいでもクライアントのせいでもなく、マネージャーである彼の責任なのだから。
「ああ、もうちょっと待っててくれるかな。ごめんね、もうすぐ終わるから。」
「Klugscheisser...(口ばっかの男ね。)」
「え?」
「何でもありませんね。」アスカは腕組みをしたまま首を振った。
アスカは無表情にカメラマンを見た。彼は口髭をたくわえサングラスをかけ、室内なのに帽子を被っていた。彼は自分の仕事が遅れているのだからムッとした顔になっても良さそうな物だが、特にそういう事も無く、面白そうにこちらのやり取りを眺めていた。
アスカは頭を振った。
「OK. やりますよ。でも、今回だけですね。それをどうか忘れないで下さい。」
「ああ、有り難うアスカ、それでこそプロ」
アスカは辺見の言葉を遮り、彼の目の前に人差し指を突きつけた。
「忘れ、ないで、下さい。」
カメラマンがアシスタントに口を開いた。
「気の強い嬢ちゃんだな。」
アスカは最高に不機嫌な表情のまま何か言おうとしたが、息をついて更衣室へと向かった。
「die Endstation...(終点か…)」アスカは呟いた。
アスカはあの仕事の翌日、つまり今日、朝早くにマンションを抜け出していた。何となく遠くに行きたくなって、第二東京駅からリニアに乗りこんだ。
大半がトンネル区間と言っても良い路線を東北エル・ラインもみじ号は時折差し込む朝日の中、新小諸、前橋、宇都宮、郡山、福島を通過し、終点である仙台に到着しつつある。
アスカは手持ちの荷物、即ちPDA、AMDプレイヤーとガムを、あまり女子中学生らしいとは言い難い事務的な見た目のショルダーバッグの中に突っ込み、眼鏡を外した。
どこへ行こうかな。もっと遠くへ乗り継ごうかしら。このままどんどん北へ行って、新青森からフェリーに乗って、北海道に行こう。北海道は涼しくて良い所らしいし。それからバスで、一番北の町…何て名前だったっけ…まで行って、フェリーでサハリンに行こう。そしてロシア本土へ渡って、シベリア鉄道でモスクワ、そしてベルリンのツォー駅へ…
…それは恒久的な長期休暇を頂いた時に考えなさいね、アスカ。
アスカはリニアの改札口を出て、駅構内を見回した。月曜日の午前中とはいえ、東北一の鉄道ターミナルはやはり相応に混雑している。
今日はここで休むか。
アスカは人目も気にせず思いっきり伸びをした後、目の前にある大きな歩道橋の端に地図板を見付けた。
ふん…目の前のSEIBUがこれか。どこ行ってもあんのよね。松本にも京都にも、別海にもあんのよね。儲かってんでしょうね。
それからそこがホテルで、向こうがLOTTEで?…その向こうにもデパートが何かあんのね、読めないけど…
アスカは地図にいくつかあるローマ字表記のある場所を探し出した。
SENDAI STATION, NTT, SEIYO, TOHOKU UNIV., SENDAI INTERNATIONAL CENTER,
MIYAGI PUBLIC MUSEUM OF ART...
美術館に行ってもしょうがないし…公園にでも行くかな…
その時、軽く彼女のお腹の虫が鳴った。
鳴き声は非常に微かで、彼女以外の人間が聞こえるような物ではなかったが、それでも彼女は思わず周囲を見回した。
「Ich muss erst essen.(まずは食わなきゃダメよね。)」
彼女は言い訳をするかのように呟いて、歩き出した。
彼女は頷くとデパート1階のドーナツ屋に入った。
「これと、これと、これと、アイスコヒーをお願いします。」一個一個シートの写真を指差して注文したアスカは、トレイを持ってカウンターに座った。
アスカはアイスコーヒーを一飲みして、息をついた。どうも頬杖をつくのが癖になっているようだ。
「うーん…」
彼女の隣の席では、自分とほぼ同年代と思われる少年が何か紙を広げながら唸っている。テストの成績でも悪かったのだろうか。
その少年は優しい雰囲気の顔つきだった。しかしアスカは人を外見のみで判断する事位軽蔑する事は無かったので−それでは自分の仕事は何なのかと、いつも自分でも思うのだが−だからこの少年に特に良い印象を持ったという訳では無かった。
少年はふと隣の茶色の髪の女性がこちらを見ている事に気づいた。
女性は少年に向かって微笑んだ。「ふふん」と声に出さんばかりに。
シンジは慌てて視線を戻した。
…僕、英語苦手なんだよな。道聞かれたらどうしよう。
シャイねえ。これだから、日本人ってのはねー。
シンジは恐る恐るもう一度アスカの方に顔を向けた。
「Hi.」
「ハ、ハイ。」
今度はアスカが視線を外し、目の前のドーナツに注目しだした。彼女は別にシンジの視線から逃げたというよりは、単にドーナツに注意が向いただけのようだ。
シンジが再び目の前の紙に集中しだした頃、アスカはPDAを取り出して仙台のホテルの情報を引き出していた。英語情報なので高級ホテルしか載っていないが、どうせお金には困っていないのだから構わない。
っていうか、高いんならそれなりのファシリティを用意しろってーのよ。壁も薄いし、料理もまずいし。…ホテルのレストランで食べる位なら、本当、こういうとこの方がおいしいものね。
「Mmmmm...」
溜め息をつくアスカがふと目を向けると、シンジはまたこちらの方を見ていた。
シンジはすぐに目をそらした。
アスカはニヤッと笑い、PDAのスイッチを切った。
「Boy. Why are you staring at me?」
アスカは隣の席の少年へ、身を乗り出した。
「あ、す…そ…ソーリー。」
「No. No sorry. But why were you staring at me? You're staring at me
like a dog, weren't you.」
比較的穏やかだが物凄く早口の英語に、シンジの頭はパニック状態に陥った。
「あ、ご、ごめんなさい。別に、その、そういう訳じゃ…」
「No sorry. No Gomennasai.」アスカは忍耐強く繰り返した。
「You. Look. Me. ...Why? ...Understand?」アスカはゆっくりと間を置いて、一つの子音も省略せず発音する。
「あー…えっと…うん…」
「Why.」
「あー…うーん……寂しそうって何て言うのかな。」シンジは小声で独り言を呟いた。
シンジは彼女の表情の変化に気づかなかった。
アスカはシンジの広げていた紙を見た。それは楽譜だった。
「えーっと…」
「アンナ・マグダレーナ。」シンジはそのカタカナな発音に顔を上げた。
「日本語話せるの?」
「少し。」アスカは頷き、人差し指と親指で「少し」のジェスチャーをする。
「何だ、もう、びっくりしたなあ。」シンジは少し怒ったような口調で−ただし顔が笑っているのであまり意味があるようには思えないが−その楽譜に頭を戻した。
「あなたは何か、楽器を、演奏しますか。」
「あ、うん。まあ、ちょっとね。」
「何をですか。」
「…チェロ。って言って、分かる?」
アスカは微笑んで頷いた。
「分かります。」
どっちかって言うとあたしの国で良く見る楽器なんじゃないかしら?
「そう、良かった。」
シンジもつられて微笑む。
「これの二重奏をね、今度やるって話があって…付き合いでね。今は違う中学なんだけど、彼の部が人数が足りないからって夏休みなのに無理矢理…」
早口で話し出したシンジは少しきょとんとした様子のアスカを見て、慌てて謝った。
「あ、ごめん。」
アスカは「気にするな」と言うふうに肩を上げた。
「面白いですか。」
「え?」
アスカは苛立つ事も無く繰り返した。
「Ah、チェロの演奏は、あなたは面白いですか。」
「う、うん。面白いよ。」
「それは良いです。」
「…うん、まあ、ね。」
シンジは何となくいづらくなって、そそくさと楽譜を丸めだした。丸めた楽譜を筒に入れ、ぬるくなった紙コップの紅茶を飲み干して立ち上がり、トレイを持ち上げた。
「それじゃあ…」
「Ah...」
アスカは何故か分からないが、思わず手を上げていた。
「お願い、どうかもう少し一緒にいて下さい。」
「あ…ん…」
「暇なら。」
「ああ。まあ…」
丁寧なんだかぞんざいなんだか。シンジは座り直しながら苦笑した。
シンジとアスカは何となく歩いていた。どこへ行くでもなく。
アスカは単にシンジの後をついている。問題はシンジで、彼は心底困りながら、どこへ行こうか思いを巡らせていた。
どうやら何かの勧誘や、セールスではないらしい。だとすればこんな効率の悪いやり方はしないだろう。
「どこでもいいです、あなたは私と面白い所に連れていって下さい。」なんて言わないよな、普通。
面白い所って言われてもな…
話によると、この少女−信じ難い事に同い年らしい−は松本から来たらしい。そんな人に仙台で何を見せるというのだろう。
「残念だったね。先週、七夕祭りやってたんだ。だから、その時に来たら良かったんだけど…」
「七夕って…確か、七月…」
「そう、普通はね。でもここでは、八月にやるんだ。」
「何故ですか。」
「何で…だろうね…理由は知らないけど…」
「あれはそのゴミですか。」アスカが道端に積み上げられた竹飾りを指差す。
「うん、そうだね。ああいうのがたくさん、屋根の上からぶら下がるんだ。結構綺麗だよ。」
「…私は、日本のお祭りを好きです。でも、これは、uhh...」
「何となく違う?」
「はい、そうですね。何となく違う、と私は思います。Eh、これは侘び寂び、が、無いですね。」
シンジはおよそ侘び寂びから遠い外見の彼女からそんな言葉が出る事が何となくおかしかった。
「うん、まあ、そうかもしれないね。」
アスカは仙台の通りを物珍しそうに眺めている。第2東京の整備されたビル街に比べたら、見るほどの物は無かろうに。
大きなショルダーバッグを抱えながら辺りを見回していたアスカは、ふとシンジの視線に気づいて微笑んだ。
「それで。あなたはどこへ行きますか。」
「そうだ、ねえ…」
「まだ決めてないですか。」
「う…ん…」
「だから、いつもあなたが行く場所に行って下さい、と私は言いました。分かりますか?
わざと、どこか、行かなくて良いです。私は、Uh, いつもあなたは行く場所に行きます。」
アスカはシンジの目の前に迫って含めるように言った。
もしかしてこの子、日本語だと丁寧だけど本当はキツい性格なのかもな…
「本当は…もう帰るつもりだったんだけど…」
なにぃ? こんなに可愛い女の子をつかまえて「もう帰る」だぁ? 身の程を知りなさいよね、全く!
「残念です。」
「ごめんね。でも、ちょっとこれから用事があるから」
アスカは立ち去ろうとしたシンジの腕をつかんだ。
「私が、寂しそう、とさっきあなたは言いました。それは正しい。私は、とても寂しいです。私は、あなたと一緒にいたいです。この街の中で、私は1人です。お願いします。」
アスカはうつむいていて、顔はよく見えなかった。
「あ…う…ん……うん。じゃ…お茶でも飲む?」
「有り難う!」
へっ。ちょろいもんよね。
「Hmmm.」アスカはコーヒーのグラスを置いた。
「あの…」
「Hmm?」
「おいしい?」
アスカはカップを上げ、軽く外向的に微笑んだ。
「おいしいです。」
「そう。それは良かった。」
別に僕がいれた訳じゃないけど。
あんたがいれた訳じゃないでしょ。大体うまかないわよ、慣れてるけどさ。
シンジとアスカの前には、それぞれアイスコーヒーがあり、アスカの前には更にチョコレートケーキが鎮座していた。
「それで…アスカさんは、どこから来たの? その、松本の前は。」
アスカはしばらく口をつぐみ、何か気のきいた答えが無いか考えているようだった。
「…シンジさんは、どこから来ましたか。」
シンジは微笑んだ。
「僕は…来たも何も、ここの人間だから。中田…あ、南仙台って言って、ここから電車で2駅なんだけど、そこに住んでて。」
「…その前は?」
「その前は、特に無いよ。ずっとここ。…大体ね。」
「そう。」
アスカはしきりに頷いた。
「それで? アスカさんは?」
アスカはしばらく沈黙していたが、シンジをちら、と横目で見て、それからはっきりとシンジの方を向いた。
「…ドイツ。私はドイツから来ました。」
「へえ! ドイツの人なんだ。…日本語うまいですね。」
アスカは肩を上げた。
「うまくないです。私はうまくないは私は分かっています。Ah、私の家族は、母が日本人で、父が日本と、ドイツの、ハーフで、だから、私は日本とドイツのクオーターですが。Uh、つまり、家族は日本語を使いませんでした。…いいえ、実を言うと…」
アスカはふとシンジが真面目に聞き入る様子を見た。
「ああ、とにかく、私は日本語はうまくないです。…ごめんなさい。」
「そんな! うまいですよ! 僕なんか、ドイツ語はおろか、英語だって全然出来ないから…」
「Heh…ありがとう。」
アスカは自分が意識せずに笑みが出て来る事に少し驚いた。どうもこの少年の無防備なリアクションにつられるようだ。
シンジは必ずしも積極的に話したい訳ではないのだが、かといってこの状態で間が空くのも辛いので彼女に聞いた。
「今日は、何で、ここに来たの?」
「…分かりません。」
「…分かんない…って?」
アスカは眉を上げた。
そういう口語の言い方は良くないって習わなかったの?
アスカはしばらく、きれいにマニキュアの塗られた自分の爪を撫でていた。
「…シンジさんは?」
「僕は…今日はだから、楽器屋を覗きにね。」
「覗く? …それはちょっと見てみる、という意味ですか。」
「あ、ああ、うん。そう。それで、楽譜も買ったし、これでもう帰ろうと思ってたんだけど…」
そろそろ帰って支度しないと、ケンスケとの約束もあるんですけど…
なにぃい? まだ帰りたいって言うか、この身の程知らず!
「シンジさんは…チェロを弾いているのが趣味ですね。」
「うん。そうだね。アスカさんは何か趣味は?」
「…」アスカは頭を振った。
「特に無いです。」
「そう…」
「多分…旅行?」
…笑う所なのかな。
「旅行。」シンジはアスカの言葉を繰り返した。
「うん。…この辺りで楽しい所はありますか?」
「うーん…」シンジは腕を組んだ。
ショッピング街。松本にかなう訳が無い。テーマパーク。そんな気の利いた物はこの付近には存在しない。
「ここなら、お城とか、公園とか…」
2人は苦笑した。
「…何にも無い所だからね。まあ、自然位しか、見る物は無いんじゃないかな。」
「ああ。自然、私は好きです。」
看板さえ無きゃね。
「そう。じゃあ、ここから少し電車とかバスに乗れば…山でも海でも…ああ、松本の人は普段海とか見ないよね。」
「はい。それは良いですね。私は見たいです。そう思います。」
「旅行、か。僕もどこかに行きたいな。」
ふふ。
「私もどこかへ行きたくて、ここに来ました。」
「じゃあ…何か嫌な事があったんだ。」
「嫌な事…はい、嫌な事がありました。」
アスカはサク、とケーキにフォークを突き刺した。
「人生の中には嫌な事が一杯あります。」
「そうだね。」
「…」
「…」
「でも、こうやって、あなたと話す事が出来ました。これは良い事です、ね。」
ってあんたが言いなさいよね。
「あ、ありが、と。」
誰か違う奴に声かけよっかなー。まあいっか、こいつからかうの面白そうだし。
「シンジさんは…今、誰か、恋人がいますか?」
シンジは思わずアスカの顔をまじまじと見た。アスカは微笑んだ。
何でドキドキしてるんだろ。僕ってつくづく、誰でもいいんだな…
節操無いのかな。一応綾波への気持ちは本物だと思ってるんだけどな。
難しそうに考え込むシンジの見てアスカは言った。
「あなたの顔の上に、「いる」と書いてあります。」
「え? う…うん…恋人っていうか…好きな人はね…」
片思い?
「Ahh... それは、あなたは彼女が好きで、でも、彼女は」
「うん、まあ、そういう事。」
シンジはアスカに頷いた。
「Ahh.」
「思いっきりはっきりと振られちゃったからね。…振られたっていうのは、つまり、」
「ああ、大丈夫です。もしあなたがゆっくりと、はっきりと、発音してくれれば、問題無いです。私が分からなかった時は私は聞きます。」
「…そう。うん…」シンジは物思いに沈んだ。
「まあ、嫌いではないらしいんだけど…友達としては好きだけど、でも男としては駄目なんだって。」
「そうですか。」
もうちょっと押し強くすりゃ良いのよ。ま、はっきりダメって言われちゃ難しいだろうけどさ。
「実際、自惚れてるかもしれないけど、はっきり彼女に好かれてるとは思うんだ。その、友達として。でも、それとそういうのとは別らしいんだよね。それはそれで、何か…」
「じゃあ。あなたは友達としても全部、駄目、な、方が、良かったですか。」
「うーん…そう、かなあ…そうかもしれないな……いや…良く分かんないや。」
「そうですか。」
アスカはシンジの返事に好感を持った。
それにしてもアスカさん、何で僕と喋ってんだろう。
「女の人って、そういうの別なのかな。つまり、その、友達として好きっていうのと、愛しているっていうのとは。」
「男の人は同じですか?」
「…うーん…」
アスカは笑った。
「例えば。すごくブスだけど、性格は良いという女の人は、あなたは絶対に友達にならないでしょうか?」
「ああ、そうか。そうだよね…じゃあ、彼女にとって僕は醜男なんだ。」シンジは半ば冗談めかして言った。
アスカはニコ、と微笑んだ。
「私にとって、あなたはハンサムですよ。」
「あ、う…ありがと。」
面白い位に単純な男ねー。悪い奴じゃないんだろうけど。
「どういたしまして。」
アスカの一見天使のような微笑みにシンジは沸騰した。
「あ、あの…ええと、その…」
「私は、今は、恋人はいないです。でも、これからは、出来るかもしれません。」
「…そう。」
「はい、ここで、私は誰か見付けられるかもしれません。」
「へえ…」
アスカさん、どうしちゃったんだろ?
こいつに食事や情報は期待出来そうに無いわね。…まあ、そんなの別にどうでも良いけど。
う…そんなにじっと見られると、また赤くなるよ…
どうしようかな。お城でも見よっかなー…
「アスカさん…」
「はい?」
シンジは上目遣いに言った。
「ん、何か、ごめんね、気を悪くして欲しくないんだけど、やっぱり、ちょっと、寂しそうに見えるんだ。…何か、あったの?」
アスカは少し驚いたかのように、しばらくシンジを見た。
「Eh... 色々、ありました。」
「色々?」
「Hmmm. OK、話します。さっき、私は、私の日本語はうまくないですと言いましたね。つまり、Ah、何故なら、私の家族は、ドイツ人だったからです。」
「え?」
「つまり、本当の家族は、私がとても若い時に離れました。そして、私はドイツ人の家族の中で育ちました。」
「ああ…」
「だからもちろん私の日本語がうまくないです。私は、とても最近、3年前から、日本語の勉強は始めました。」
「そうなんだ…それじゃ、少し僕と、似てるかもしれないな。」
「似てる?」
「うん…うちは、やっぱり若い時に母さんがセカンド・インパクトで死んじゃって、父さんと2人暮らしなんだ。でもうちの父さんはいつも仕事が忙しいらしくて殆ど顔合わせないから…この年で一人暮らしに近い生活だよ。まあでも、そういう人は他にもいくらでもいるだろうけど…」
「はい。」
アスカは頷いた。
「…でも、シンジさんはまだ良いです。何故なら、あなたはあなたの国で生きていますね。私はドイツでも日本でも外人だからです。」
…だから同じガイジンのあのバカスウェーデン人を好きになったのよね。
「そうか…そうだよね、一緒にしちゃいけないよね。」シンジは真摯に頷いた。
「日本で暮らすのは…大変?」
「分かりません。日本でもドイツでも同じです。それに私にはこれで普通です。」
「そうか…ごめん…」
「いいえ。」
アスカはシンジに微笑んだ後、何か思い出し笑いをするかのように自分に微笑んだ。
「私は寂しいとゆより、疲れました。」
あれ? アスカさん、さっきと言ってる事が…
「疲れた?」
「はい、疲れましたです。…私、友達がいないです。」
「…それは、寂しいって言うんじゃないの?」
アスカは苦笑した。
「Ah、そうですね。分かりました。多分私は寂しいです。」
「…」
アスカは自分の言葉にやや瞳を広げた。
「……そう、ですね。寂しかったんですね、私。」
アスカさん、もしかして目が潤んでる?
シンジはゆっくりと黙ってストローを吸い続けるアスカを見ながら、自分が彼女を追いつめてしまったのではないかとビクビクしていた。
アスカは何だかシンジをからかうのが申し訳なくなり、それきり黙っていた。
「私は、私の仕事から逃げてきました。」
「…仕事してるの。」
「はい。…私、寂しかったんですね…今私は分かります…」
アスカは笑って見せた。
「ごめんなさい。本当は私の恋人がドイツにいます。彼に会ってないですから、というのも一つの寂しい理由ですと思います。」
「そう。」
「はい。」
「ねえ、アスカさん。あの、良ければ、僕で良ければ、アスカさんの、日本での友達になっても、良いかな。もちろん、そんな、変な意味じゃなくて…ああ、でも、もちろんアスカさんは魅力的なんだけど、」
「ありがとう。」
「…」
「あなたは私の友達です、シンジさん。」
「あ、うん。よろしく、アスカさん。」
「よろしく。」
やっぱりアスカさんって、何だか大人っぽいな。松本から来てるからそう見えるのかな。
…少しは、仙台に来た意味もあったのかしらね。…何だかなー、何であたし、こんな事で喜んじゃってんだろ。こいつと大してレベル変わんないじゃん…
…あたしもヤキがまわったみたいよ、ゲオルグ…
「今日も暑いわね。」
ヒカリは呟いた。
トウジの病室は個室だった。表向きの理由は患者のメンタルケアの必要性等と言っていたが、ヒカリには患者を1人にしておく事の何がメンタルケアなのかよく分からなかった。さすがに言葉が話せないから「配慮」されているとまでひねくれた見方をするつもりもないのだが…まあ、単純に部屋が余っているというだけなのかもしれない。ここも昔は特別病院だったのだろう。
「そうね。何でこんなに暑いんだろ、冷房入れれば良いのにねえ。やんなっちゃう。」
トウジのベッドのシーツを交換していた、ヒカリとそれ程は年齢の離れていなさそうな白衣の女性が人当たりの良い笑顔を浮かべる。
「霧島さんがそれを言うのは、何か変…」
「だって事実でしょう? 院長がケチなんだ! 全く、27度をちょっとでも下がると冷房切っちゃうだもん。」
冗談めかして言うマナに笑うヒカリ。
[そうか。そんな暑いか。]
ベッド脇の車椅子に座っているトウジは2人の唇を読んで、手話でヒカリに聞いた。
[鈴原はじっとしてるから分からないのよ。]
[そんなん言うたら自分かて動いとらんやないか。]
[…それが姉に対する口の利き方かしら?]
「仲良いわね。」
マナは2人を見て嬉しそうに微笑んでいた。
「な! そ、そんな事、ないのよ。」
どもるヒカリと、手を横に振って、ヒカリと同じ意味の事をマナに伝えるトウジ。
「…羨ましいな。」
「霧島さん!」
マナはベッドをポン、と叩いた。
「終わったわ。ヒカリちゃん、そっち持って。」
「あ、う、うん。」
ヒカリとマナはトウジに肩を貸してシーツの替わったベッドへ移動させた。
「じゃあね。」
まるで友人へ言うような軽い雰囲気で手を上げるマナ。
「じゃあ。」
微笑むヒカリと対照的に、トウジは無視して姿勢を直している。
ドアが閉まると、ヒカリは表情を一変させ溜め息をついた。
[鈴原。挨拶位はしっかりしなさい。]
トウジはやや面倒臭げに返事をした。
[あれは彼女の仕事やろ。]
[どういうつもりよ?]
トウジはヒカリに一瞬目をやると、答えずにベッドの上のテーブルを動かしてビューワーをのせ、スイッチを入れた。
ヒカリは溜め息をつくと、右手を降ろして椅子に座った。
病室は静かになった。
「…元から静かか。」
ヒカリは呟いた。
マナの言った通り、暑いとはいえ、クーラーを入れる程ではないのが問題だ。結果として一番暑くなる。
トウジはむすっとした様子て漫画を読んでいた。別に機嫌が悪い訳ではない。ずっとこの部屋にいるのは苦痛だが、今に始まった事ではない。
トウジが今むすっとしている最大の原因を敢えて挙げるとすれば、今週号に楽しみにしていた連載が載っていないという事だろう。
「ねえ。扇風機も無いのよね、ここ。」
ヒカリは呟いた。
ヒカリは具体的にトウジの看病を何かしているのかといえば、微妙だった。お見舞いには来ているし、病院側と相談してリハビリに付き合ったり、半ば保護者のような事をしてはいる。しかし清拭や着替えの補助、「トイレ」等をするのはマナのような看護婦だし(と言うよりヒカリは頼まれても嫌だ)、その看護婦にお金を出しているのはヒカリではない、マリア、トウジの母親だ。
私に出来る事なんか何にも無いんだ。
「ねえ、返事してよ。…………トウジ。」
ヒカリはトウジから目をそらし呟いた。ヒカリは言ってから、その言葉の違和感に苦笑した。
「ねえ。」ヒカリはトウジの肩をごく軽く押した。
[…今度は何や?]
トウジはビューワーをベッド上のテーブルに置き、指を振った。
「…」ヒカリは眉間に皺をよせ、また目をそらした。
[何や、言うてみいや。]
トウジの手話を横目で確認したヒカリは、答えに窮した。
[何?]
[は?]
[…私、何言おうとしてたんだろ。]
[忘れたんかいな。]
[うーん…]
「…ああ、」
[思い出したんか。]
ヒカリは軽く頷いた。
[鈴原は…今…]
「ふう、」
[今…好きな人とかは、いるの?]
手話にうまく相当するアクションが無いが、露骨に「はあ?」という表情を見せるトウジ。
[例えば、霧島さんとかね?]
[な、何で姉貴にそないな事言わなあかんねん!]
[いや、だから、姉としてそれ位は知っておかないと!]
[せやから何でや言うてんねん!]
[当たり前でしょ! 姉として、弟の交友関係は知っておく義務があります。]
[あるかそんなもん、権利も無いわ!]
[鈴原! …分かったわ、本当の事を言うわね。]
[な、何や。]
[それを知っておかないと、メンタルケアに支障をきたすのよ。]
[どこがほんまやねん、そんなん絶対ふかしや。]
そこまで言って、トウジはふとおかしくなって声を出さずに笑い出した。
[何よ。]
[まあ別にええわ。隠す必然性も無いしな。今は別に、誰もおらんで。]
[…そう。]
ヒカリは立ち上がった。
トウジは少し不思議そうに尋ねた。
[どないしてん、いいんちょ。]
[委員長なんて言わないで。家族でしょ、水臭いわね。]
ヒカリは自分のブラウスのボタンを外し始めた。
トウジは眉を上げた。
[あ…暑いんか。]
[そうね。耐え切れないくらいに暑いわ。]
ヒカリは素っ気無くそう告げると、ブラウスを脱いだ。
「あぐご。」トウジは珍しく声を出した。
[…あ、す、すまん。]トウジは慌てて顔を向こう側に背けた。
ヒカリは慣れた手つきで−当たり前だが−ブラジャーを外し、比較的自己主張の控えめな2つの胸を露わにした。
それから彼女はスカートのジッパーに手をかけ、それを脱ぎ捨てた。
ヒカリはふと違和感に気づき、それから靴とソックスも、それぞれにたっぷり5秒はかけながらゆっくりと脱いだ。
最後にヒカリはパンツに手をかけ、脱ぎ降ろした。
「悪友から変な事教わっちゃったわ。」ヒカリは呟きながら、まだこちらを見ていないトウジに肩をかけた。
恐る恐る振り向いたトウジは、ヒカリの裸体に目を開いた。彼は首を振った。
[何、恥ずかしがってるの。兄弟でしょ。]
「あ。あぅ。が、がん、あ。」トウジは必死に首を振った。
[私が鈴原にしてあげられるのは、これ位しかないのよ。]
「…」トウジはただ首を降り続けたが、ふと気づきナースコールのボタンを押した。
ヒカリは無表情に黒いコードを上げて見せた。
[電源コードが、切れているみたいね。]
「あ!」
「…しいっ。」
ヒカリはトウジの口に優しく指を置くと、次に自分の顔をトウジに近づけた。ヒカリは、
ヒカリは溜め息をつき、頭を振った。
「そんな事出来る訳無いわよね。私が。」
トウジは漫画をまたつまらなそうに、しかし目を離さず、眺めていた。
ヒカリは妄想の言い訳をするかのように内心彼に抗議した。
このマザコン。もう14でしょ、「好きな人」の答えが、何で[しいて挙げればおかんかもな]になるのよ。そんなの絶対おかしいわよ。
マヤは部屋のドアをそうっと開けた。
マヤはドアから首を出し、すばやく左右を見まわしてからさっと出て、ドアを閉めた。
「どしたのマヤちゃん。」
「きゃあ!」
マヤは背後の声に飛び上がった。
「み、ミサトさん驚かせないで下さい。」
「ご、ごめん。何か…様子、変だったから…」
叱られた子供のように口ごもるミサト。
「別に何でもないですよ。」
「そう。なら、良んだけど…館長と、何かあったの。怒られたとか。」
ミサトは館長室のドアに目をやった。
「…別に、怒られるような事、何にもしてませんもん。」
マヤは冗談っぽく頬を張って、微笑んだ。
「はあ。」
「あ、そろそろ給餌の時間だわ。」マヤは大きめの声で呟くと、ミサトと反対方向に足早に廊下を歩いて行った。
ミサトはしばらく彼女の後ろ姿を見ながら、やや首を傾げていたが、やがてまた歩き出した。
ミサトがドアを開けると、レイがペンペンとギンギンが2つのキーボードで「会話」するのを眺めていた。
「まだやってたの。」ミサトは口をへの字に曲げた。
「ええ。…非常に面白いです。」
レイは面白そうな顔一つ見せずに呟いた。と言っても彼女が皮肉を言うようにも見えないので、真面目に答えているのだろう。
「面白いって?」
「話題が、単語の定義に集中しています。特にギンギンからの発話にはそれが多いです。」
「うーん…まあ、最初の頃はそれしか話題に出来なかったし、やっぱり今でもそれが多いもんね。ペンギン同士でもその会話になるか。」
「ええ。」
「それ以外の話題は、何か無いの?」
どこから持って来たのか、プラスチックのビール搬入用容器を横にして椅子代わりにしているレイは、自分の目の前のペンギン−やたらとキョロキョロする方−をちら、と見た。
「ペンペンの発話には、ギンギンへの…個人的な質問が含まれていました。」
「個人的な質問?」
「ええ。お腹は空いたか、とか、自分がお腹が空いたというのではなく、相手に聞いていました。」
「…良く分からないけど、赤木博士が聞いたら面白がりそうな話ね。」
「…赤木博士は、何をしているのですか。」
ミサトは苦笑いをしながら、頭をかいた。
「私に聞かないでよー。んー、何かずーっと睨めっこしてたわ、メルキオールと。」
特に返事のしようもないのでレイは微かに頷いたまま黙った。ミサトは特に気にせず続けた。
「もう12時なのにいないって事は、今日はヒカリちゃんは来ないんだ。」
「ええ。」
「お見舞い、よね。弟の、えっと…」
「トウジ、君。」
「ああそうそう、トウジ君か。ヒカリちゃんも健気な良い子よね。」
「ええ。」
レイは頷いた。
「で、シンジ君は今日はくんのかな。」
「いえ。」
「どうしちゃったの? 昨日も来なかったし。」
「昨日の夜に、碇君から電話がありました。チェロの合奏会の練習で、時々来れなくなるそうです。明日は来ると言っていました。」
「チェロ、なんて彼弾くの? 格好良いわね。」
「…」レイはチェロの演奏を生で聞いた事が無いので、それが格好良い物なのかどうかは判断しかねた。
ミサトは特別、少女への性的嗜好がある訳では無いのだが、何となく物思いにふけるレイの顔を面白そうに眺めていた。
その時、外の柵の向こうから声がした。
「あのー、ミサトさん。」
ミサトは声のした方を向いた。
「あ、何、マコト君。」
「あの、入り口に妙な女の子がいるんですよ。ミサトさんに会いたいって言ってるんですけど…」
「へえ、私に?」
ミサトはレイと目を合わせた。
ミサトがぼーっとした顔のままスタッフ用の通路からドアを開けてパブリックスペースに出ると、確かに入り口の向こうに少女が所在無さげに立っている。
前世紀の美人ね。
ミサトは彼女を見て、相当失礼な初印象を持った。
彼女の髪は赤茶色(「黄土色」では幾らなんでも悪いだろう、とミサトは自分で思った)で、少なくともそれはとても綺麗だった。目の色も青く、エキゾチックだ。
しかし小柄で、顔全体の造りは間違いなく日本人に見える。
もしかして、レイちゃんみたく…
違うか、目赤い訳じゃないし。
「あのお…」
ミサトはその少女に上目遣いに尋ねた。
「ああ、あなたがミサトさんですか?」
アスカは快活に微笑んだ。
「え、ええ、そうですけど…」
私何か悪い事したっけ?…
「Ah、私は、シンジさんの友達です。アスカと言います。彼はここが面白い場所と紹介しました。だから私はここにいます。」
アクセントはかなりおかしいものの、比較的しっかりした発音でぽんぽんと言葉が出て来る。
「ええっとお…」
何か頭の悪そうな女ねぇ…
「Ah、シンジさんが言ってましたね。ミサトさんはとても良い人だと。それはあなたですか?」
「え、ああ、うんまあ、ミサトは私、なんだけど。シンジ君の知り合いなんだ。」
「はい。」
シンジ君って変な子集める才能があるわね。
ミサトは自分の事を棚に上げてそう思った。
「彼はこうも言いました、ここには、とても面白い物があると。Eh...」アスカは話を少し脚色する事にした。
「Ah、そしてミサトさんはとても美しくて、優しくて、又親切な人なので、親切にしてくれるだろうとも言いました。」
「ほんとおー?」ミサトは心底疑わしそうに声を上げた。
まあ…シンジ君がここ教えたって事は、特にマズい子じゃないのかな。
「まあ…良いわ。そこまで言うなら、その「面白い」物を教えましょ。…こっちよ。」
ミサトは少し外人風に、エスコートするかのように手で方向を指してみた。
「ありがとう。」
アスカは「バカね。」と内心断定しながら、笑顔でミサトについて行った。
「シンジ君に、こんな可愛い友達がいるなんて知らなかったな。」
アスカはさっきから何度も練習していた答えを返した。
「直接の親戚ではないですが、しかし私達は殆ど親戚なような関係です。Ah、私の親とシンジ君の親が友人同士で、それで私達もお互いを昔から知っていましたね。」
「へえ、そうなんだ。どっから来たの。」
アスカはミサトのダイレクトな質問に気を悪くする事も無く答えた。
「ドイツの、Berlinから来ました。」
「ばぐりん…ベルリン?」
「はい。」
「でもアスカっていう位だから、ハーフ、とか?」
「ほぼ正しいです。クォーターですね。」
「へえ…」
ミサトはガラス越しにレイがこちらを見て眉を上げるのを確認した。彼女の表情を見ると、ミサトの頭は急に、レイ・アスカのシンジを巡る三角関係の妄想と、「面白そう」の一言で埋め尽くされた。
なに、ニヤニヤ笑ってんのこの大女。気持ち悪いわねえ。こんな辺鄙な場所に面白い物なんか、求めたあたしが馬鹿だったわよね…
「これがその面白い物よ。」
緩む頬を何とか抑えようとしながら、ミサトはドアを開けた。
「くあ。」
ペンペンとビールケースに座るレイが同時にこちらを見上げた。
ペンギンに合わせてバルタザールのモニタが下げられたので、人間用のキーパネルも上の棚から降ろされ、レイは自分の膝の上にのせている。
レイは視線で「誰ですか?」とミサトに聞いた。
「レイちゃん、こちらはシンジ君の「幼馴染み」で、ドイツから来たアスカちゃん。アスカちゃん、こちらはシンジ君の…「親友」で、水族館のボランティアもして貰ってるレイちゃん。それから今レイちゃんの隣に立っているのがペンペン。向こうの山で寝ているのがギンギンよ。」
「Scheint interessant.(面白そうじゃん。)」アスカは頷きながら呟いた。
「よろしく。」アスカは手を差し出した。
「…」
レイは体は動かさず、口を開いたまま微かに頷いた。
アスカは手を開き、軽く上げた。
「あー、レイちゃんは物静か、なんだけど、悪い子じゃないのよ。そういう意味じゃシンジ君に似てるわね。」
そうみたいね。
「Ah...Was war es(何だったっけ)...Ah、あれは、何と言うですか。」
アスカはペンギンを指差した。
「ペンペンと、ギンギンよ。」
「Ah、そうではなく、」
「ああ、ペンギンよ。」
「ペンギン。Ah。」
やっぱ、訛った発音になる訳ね。
アスカは軽く頷いた。
「温泉ペンギンっていうのが、種の名前。」
「…温泉?」
「そ。あの「温泉」よ。」ミサトは両腕を上げ、湯船に浸かるようなジェスチャーを見せた。
「…この端末は何ですか?」
「何なんだと思う?」ミサトはつくづく自慢気に宣言した。
「それで、ペンギンと会話が出来るのよ。」
こいつ絶対機密保持とかに向いてないタイプね。
「それは、とても面白いですね!」
「でっしょー。」
マコトが今度はドアから顔を出した。
「すいません。」
「ん、どした。」
「あのー、第一水槽の掃除手伝ってもらえますか。」
「あ、ああ、うん。…じゃ、レイちゃん、頼んだわ。」
「はい。」
ミサトはペンギン室から出て行った。
アスカはややキョロキョロとしてから、目の前の色白の少女に合わせて腰を下げた。
「ね。」
「が。」
返事をしたのはペンペンだった。
「ねえ。」
「…何。」
レイはようやくその赤い目をアスカの方に向けた。
「あなたは、とても静かです。」
「…」
「何故とても静かですか。」
レイはアスカの質問がぶしつけであると抗議するかのように、黙ったままアスカを見た。
「Oh、別にあなたは嫌でしたらあなたは答える必要は無いです。」
レイは目をモニタに戻した。
「シンジさんとあなたは、親友、なんですか。」
「…ええ。」
「Hmp.」
まあ良いや、どうでも。
「レイさんは、とても肌色が白いですね。」
レイはそんな事を面と向かって言われた事はむしろ少ないので、少し驚いたように目を向けた。
「ハーフか何かですか。」
アスカはミサトの口調をまねして言ってみた。
「いいえ。先天的に色素が足りないの。」
センテンテキ? シキソ?
アスカは今一つ内容が理解できなかったが、何となく聞き返しにくかったので曖昧に「Ah.」と頷いた。
「私も肌色が白い人です。私達は、ここでは友達同士ですね。」
アスカは最大限に微笑んでみせた。
「どうして。」
レイはモニタから目を離す事も無く呟いた。
「…」音にならない溜め息をつくアスカ。
レイはふと、モニタの文字に目を上げた。見た事の無い用法だ。これは恐らく、まめに辞書登録をしない葛城さんが作ったか、ペンギン同士で勝手に生まれた単語に違いない。…赤木博士なら知っているだろうか?
<しばらく待っていて。>
<次は彼女と話すのか。>
<彼女はこの言葉は話せないわ。>
<彼女は言葉が話せないのか。>
<「この」言葉よ、人間にはそれとは別の言葉があるの。>
<音の言葉だ(と言うのだ)ろう? しかしそれはこの言葉ほど便利ではないだろう。>
<そうかもしれないわね。>
「くああ。」
レイは立ち上がり、ペンペンを軽く撫でると、ドアに向かって行った。
「Ah...」
「すぐに戻るわ。」
「そう。」
「…くあ。」
アスカはペンペンの方を向いた。
先程から気づいてはいたが、彼等は何か金属製の物を背中にしょっている。
アスカはしばらく顔をしかめてペンペンを眺めていたが、やがて彼に優しく話しかけた。
「Hey, du tippst dieses den ganzen Tag?(あんた、これずっと打ってんの。)」
「くあ。」
アスカは眉を潜めた。
日本人はどうしてこういう事が平気で出来る訳?
「Scheint interessant.」アスカは呟いた。
つづく