「綾波さん、おはよう。」
いつから「おはよう」が午後4時に使える挨拶言葉になったのかは不明だが、ヒカリは今日も当然のようにやって来たレイに優しさと諦めの中間の表情で挨拶した。
「おはよう。」レイはいつものように周囲を見ずにずかずかとヒカリの家に上がっていった。「目だってはいけないから」らしい。
「ああ。綾波姉さん、ども。」
ボサボサの髪にパジャマのミチルが「姉貴の彼女」を確認して微笑む。
「こんにちは。」レイはミチルに答える。
綾波さん、楽しそうねえ…
ヒカリは一見無表情なレイの顔をつまらなさそうに眺めた。
「洞木さん?」
ヒカリはレイの声にはっとして、外向的な笑顔を見せる。
「あ、ちょっと待ってて。今、飲み物持ってくるから。」
「ええ。」レイは何食わぬ顔で2階へと階段を上っていった。
「毎日毎日、ラブラブよねえ。」
「…歯、ちゃんと磨きなさい。その年で女捨ててどうするの。」
つくづく嬉しそうなミチルにヒカリはぼそっと呟いた。
「この年だと。何にもしないでも肌はピチピチ、女なんか捨てたくても捨てられないのよねー。」
反論するもの面倒臭くなったヒカリは、深く溜め息をついてキッチンに向かった。
南仙台の洞木家は今日も気象庁が発表するところの「夏日」で、扇風機が忙しそうに首を振っていた。
その日もレイは透き通るような声でお気に入りの本を読んで聞かせていた。
「…1961年にローレンツが発見したのは、微少な初期条件の誤差で気象予測の計算結果が見事に変わってしまうという事実だった。小数点以下の僅かな差でも、計算式によってはそれが直ちに答えに影響し、結果として式がまるで用を成さないものとなってしまう。世に言うカオス理論である。ここで留意したいのは、カオスは一般に捉えられがちなように「無秩序」という意味ではなく、あくまで決定論に即した範囲内でしかしその条件の精度の重要性を再確認するものだという事である。またこのカオス理論は複雑系の進化論にも有効に利用されている。それは…」
鈴原の足を作った人が、まるで自分が発見した理論のように嬉しそうに複雑系遺伝子学だかコンプレックスサイバネティックスだか言ってたな…
ヒカリは朦朧とした意識の中、レイの存在も忘れあくびを噛み殺した。
「退屈かしら、洞木さん?」レイが本から目を離し聞いた。
「え、あ、ううん、退屈って事はないんだけどね。ちょっと、疲れてて。」
何故かレイから離れるかのようにすっと足を引いた。
…もう! 一々そんな不安気な目で見ないでよ!
ヒカリはレイの(傍目にはいつも通りの)視線に降伏した。
「…正直に言うわ。綾波さんの読んでくれる本、私には難しすぎて良く分からないのよ。」
「何が。」
「何がって…全部よ。もうちんぷんかんぷん。綾波さん、私平凡な中学生なんだよ、この前の期末、数学54点だったんだよ。因数分解でひいひい言ってる女にローレンツって言われても。」
ヒカリは大きな缶からクッキーを取り出した。
「…難しい?」
「…いや、うん…ちゃんと聞けば、分からない事もないんだけど…綾波さんっていつも、そういう事を考えてるの?」
「ええ。数式ほど美しい物は無いわ。」自信を持って宣言するレイは慌てて付け足す。
「もちろん洞木さんはそれより美しいわ。」
「…ありがとうね。」ヒカリはコーラの缶に直接口を付けながら気の無い返事を返した。
レイが不安気な表情になったのは、今ヒカリが退屈しているという事のみが心配になったからではなかった。レイは特別、人の感情や表情の動きの感覚が鋭くはない。彼女は一見そういった事に無頓着のように見えるが、実際その通りだ。しかしそれでもここ数日、つまり宮城島での休日以来、レイはヒカリの態度が明らかに悪い方向に変化しつつあるのを感じ取っていた。
「洞木さん…」
「何?」笑顔でヒカリは聞く。
「…何でもないわ。」
2人は同じ部屋にいながら、それぞれ喋る事もなく壁面を眺めていた。
「…洞木さんは栄養学に興味が有るのね。」
ヒカリは即それが疑問文である事を理解し答える。
「うん、まあね。」
「…」
ヒカリはいつものように黙り込むレイが何を考えているか、大体想像がついた。
綾波さん。だからって別にあなたに栄養学の話題を期待してる訳じゃないのよ。
ヒカリはそう思ったが、口に出さなかった。
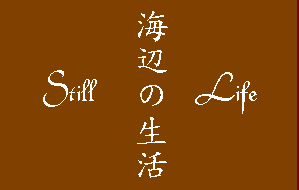
農道に毛が生えたような道で、ちょっと向こうに四郎丸の小学校が見える。荒れ地と水田と住宅地を足して3で割ったようなこの付近でよく見る景色だ。しかし忙しいヒカリは意外と決まった場所以外に外出する事が少ないので、家から何キロもないこの道の景色もあまり見慣れていないようだった。
もっともヒカリは特別景色には注目していなかった。特に趣のある綺麗な景色という程ではない。交通量も結構ある。
ヒカリはただ、頼られるシチュエーションにはどうも弱いらしく、「ふんっ」と鼻息も荒く不敵な笑みを浮かべながら自転車のペダルを動かしていた。
「碇君ってつくづくすごいわね、こんな距離毎日綾波さん乗せて走ってるんですものね。感謝しなきゃだめよ、綾波さん。」
「…ええ。」
ヒカリとレイの乗る自転車は、カーブで危うく倒れかける。
「おーっとっとっと。」
ヒカリは体勢を立て直そうと更にスピードを上げた。
「ねえ、そんなに水族館って面白いの。」3つ編みをバタバタさせながらヒカリが聞く。
「分からない。」
はっきりとは聞き取れないが言葉の長さとアクセントでレイがどう答えたか察したヒカリは、やれやれ、という顔で息をついた。今なら綾波さんに顔を見られる事もないし。
碇君は、やっぱり綾波さんに下心があって水族館なんかに…でも、その前からよく来てたのか。うん…彼、おとなしいタイプの子よね。まあ顔だって悪くないし、あまり強くはなさそうだけど綾波さんは十分自分を守れる強さがあるから問題無いし。
碇君じゃだめなの、綾波さん。
…何としてでも綾波さんを人に押し付けたい訳ね、「洞木さん」。
ヒカリは冗談めかして言う。
「面白くなかったら怒っちゃうよ。今日午後から鈴原の病院に行かなきゃいけないんだからね。」
「…」
ヒカリは漕ぎながら後ろを振り返った。よく分からないがレイの顔は多分に曇っているように見える。
「…冗談よ。私も気晴ししたかったし、ね。」
この前嫌と言う程気晴ししてるけどね。…全く何やっちゃったんだろ…
レイは目をきょとんとさせてヒカリに忠告した。
「洞木さん、危ないわ。」
ヒカリが前を向くと電柱が目の前に迫っていた。
「おっと! 平気平気これ位。ああ! 綾波さん驚いた顔可愛いわねえ。」ヒカリはわざと後ろを向いたまま自転車を漕いで喋る。
「洞木さん、前…」
前をちらちら見ながら、ヒカリはレイの驚いている(と思われる)表情をこれ以上無く楽しそうに眺めた。
「レイちゃんの御友達ね。」
ミサトは何処か機嫌悪そうに見える少女に(無遠慮に)微笑みかけた。
「あ…」
ヒカリは淡水魚漕に来たとたんに自分達の方にやって来た大柄な女性にやや脅えたかのようにレイに目で助けを求めた。しかし鈍感なレイはヒカリの視線に全く気づいていないようなので、ヒカリは諦めてその青い服の女性に挨拶をした。
「はじめ、まして。」軽く会釈をする。
「はじめまして。」ミサトは何処までも快活に答えた。突然彼女は品定めをするかのように腕を構える。
「うーん…」
「?…」口を開け、声にならない疑問文を発するヒカリ。
「やっぱ、類は友を呼ぶって言うのかしら。可愛い子は友達もかぁいいわねえ。」
「…は?」間抜けな声を出すヒカリ。
この人ね、例の飼育係の人って、名前が確か…
「葛城さん。」ヒカリはレイの声が、どうやらいつもより少し苛立っているように聞こえた。
「ん、何、レイちゃん。来る?」
ミサトはレイの声の微妙な変化に全く気づかない様子で、省略された疑問文をレイに投げかける。ヒカリはしかし、ミサトがレイに省略した文を投げかけられるという事は、レイの気持ちをある程度推測可能だという事なのだから、彼女の声の変化も気づいているはずであるという矛盾には、この時気づかなかった。
「ええ。」レイは答えた。
「本当は、誰にも話しちゃいけない最高機密なのよお。世界の先端を行く研究で、どこにスパイが潜っているか、分かったもんじゃないんだから。」
と嬉しそうにべらべらと話すミサトに「はい…」と答えながら、廊下を歩くヒカリはレイに聞いた。
「それで何があるの、綾波さん。」
「知的な友人がいるわ。」ミサトはレイの答えに顔を綻ばせた。
ヒカリ達は半屋外の飼育室にやって来た。
ヒカリは中にいるものを見て、それ程感動はしていないかもしれないが呟いた。
「うわぁ、ペンギン…だ。何なんですか、あの背中に背負っている物は。」
振り向かれたミサトが笑顔で答える前に、レイが的確な答えを返す。
「シンクロナイザーと言って、人工的な種である彼等温泉ペンギンの生命活動をサポートする装置よ。」
名前の妙さに今度は本当に驚いたらしいヒカリが、彼女の言葉を聞き違いでないかどうか確認する。
「温泉…ペンギン?」
「ええ。遺伝子操作で生まれた新種よ。」
「おーい、ギンギン! ったく、どっちか動くとどっちか知らん振りね、一体どうなっちゃってんのかしら。」
「つまらない」という雰囲気を全身で表現しながらペンギン山で横になるギンギンに声をかけていたミサトは、2人の中学生の立つ場所に戻ってきた。
「今、向こうの山で寝てるのがギンギン。それからこいつがペンペン。こう見えても、2匹とも人間以外では最も知的な生き物の一つと言って良いでしょうね。」
「があ、くあ、くあ。」フリッパーをバタバタさせながらヒカリに近づくペンペン。
「か、噛みませんか。」思わず手を引っ込めて後ずさりするヒカリ。
「大丈夫だって、こいつら人間になれてるから…」
「ぐぁあ。」
ペンペンはミサトの腕をくわえ首を曲げた。
「っつ! あんた何やってんのよ!」
「があ、ぐあ、ぐあ、ぐあぁあ」
ヒカリがペンペンとミサトの格闘を見ながら顔を引きつらせる間に、レイはさっさとカスパーとバルタザールを起動させた。
「葛城さん、準備整いました。」
「ぐあああ」
ペンペンの首を絞めにかかっていたミサトはレイの声に顔を上げた。
「あ、サンキュ。じゃさっそく始めましょ。このバカで。」
「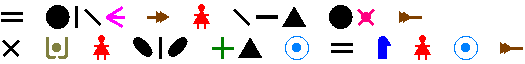
(<同じ><言葉><始める><ミサト><強い><悪い><終わる>
<でない><持つ><ミサト><心><大きい><見る><同じ><ペンギン><ミサト><見る><終わる>)
(「ミサトの挨拶は乱暴だ、ミサトにはペンギンとしてのきちんとした自覚が無い。」)
」
非常に速いスピードでカスパーのキーボードを叩くペンペンを見てヒカリは目を丸くした。
「このペンギンさん…何、やってるんですか。」
「見ての通り、言葉を話してるのよ。」ミサトは仕事終わりのビールを飲む時の次に嬉しそうな顔でヒカリに告げる。
「こ、言葉? 本当に?」
「ええ。」
「くあ。」
「![]() (<誰><これ>)(「こいつは誰だ。」)」
(<誰><これ>)(「こいつは誰だ。」)」
レイは自分の恋人への乱暴な言葉づかいにやや眉を潜めながら、ミサトに聞いた。
「どう答えれば良いのでしょうか。」
「ん、まあ、適当に作ってよ。えっと…まだ名前聞いてなかったわねそう言えば。私はこの水族館で彼等の飼育係をやってる葛城ミサト。ミサトって呼んでもらって構わないわ。あなたの名前は?」
「洞木、洞木ヒカリです。」
初心そうで可愛いわねぇ。
| ミサトは例によって妙にニヤニヤしながらヒカリに言った。
「ヒカリちゃんは、この水族館にこれからも来たいと思う?」
ヒカリは思わず笑った。
|
ペンペンはかっ、と首を上げた。
<何故黙るのか。>
「くあぁ、があ。」
|
ミサトはバルタザールの前で指を踊らせる。
「えーっと…」
<彼女の名前は…>
「うん。ヒ、カ、リと。」ミサトは「![]() 」とキーを打つ。
」とキーを打つ。
<![]() か。>ペンペンはようやく納得したようだった。
か。>ペンペンはようやく納得したようだった。
「…ヒカリちゃんの髪型よ。」ミサトは不思議そうな2人に説明した。
シンジは最近のレイがつくづく妙だと感じていた。もともといじめられるだけあって妙は妙だったのだが、最近の綾波は特にその傾向が激しい。そもそも未だに表情がよく分からないので確信を持っては言えないのだが、どうも心ここにあらずといった雰囲気で、そのオーラもある時は楽しそう、ある時は辛そう、ある時は不思議そうといった感じでころころ変わっている。
何かあったのは間違いない。ただそれが良い事だったのか悪い事だったのか何だか良く分からない。
シンジはイカを要求するペンペンに突っつかれながらそんな事を思っていた。
シンジはその日もある意味全く実りの無い、しかしそれはそれで気に入っていない訳ではない水族館のボランティアを終えて、スタッフ用のバンや彼等の私用車のみ駐車されている駐車場の端から自分の自転車を、4メートル前方の水族館入り口まで押してきた。
「碇君。」
入り口で待っていたレイは、シンジに声をかけた。
シンジは素直に返事をした。「何、綾波。」
レイはしばらく目を瞬かせた。「何でもないわ。」
シンジは何でもなくはない事だけは良く分かったが、「そう。」としか答えようがなかった。
シンジは自転車にまたがらずにそのまま自転車を押して歩き出した。
「綾波、あの、おせっかい、かもしんないけどさ、何か悩んでる事とかあったら、何でも言ってよ。まあ、力になれるかどうかは分からないけどさ。」
レイはやや目を見開き、そして微笑んだ。
「ありがとう。」
「…うん。」当然ながら一緒に歩いてついてくるレイをちらちら見ながら、シンジは曖昧な返事を返した。
レイはシンジの言葉に勇気づけられたのか、心を許せる相手を前に、自分の気持ちを告白した。
「…好きな人の事を考えると、集中力が無くなってしまうの。特にその人と一緒にいると…おかしな事を言ってしまうの。」
レイは困った表情を見せた。
シンジは今度ははっきりとレイの方を振り返り、彼女に優しく微笑んだ。
「それは、誰でも人を好きになる時はそうなるものなんだよ、綾波。」
「そう。それでは碇君も私といると集中力が落ちてしまうの?」
シンジは思わず足を絡ませそうになった。
「う、うん、そうかな。そうかもしれないね。」
「そう…御免なさい。」
「何が?」
「碇君に危険を負わせ、好意には答えられず、そのうえ集中力まで奪ってしまったわ。やはり私は碇君と一緒にいるべきでは」
「そんな事ないよ!」
シンジは慌てて遮った。
「そんな事ないよ。…そんな事…言うなよ。」シンジはサドルを握る手にギュッと力を込めた。
「碇君?」
2人が歩く道を軽トラックが1台追い越していった。風が2人の髪型を乱した。
シンジは歩みを止めた。
シンジはレイに微笑んだ。
「綾波は綾波の好きな人と一緒にいる時、どう感じる? 嬉しいって思ったりしない?」
レイはしばらく考えて答えた。
「その人が笑っている時は嬉しいわ。でも、最近あまりその人は笑ってくれないの。」
「…そう、なんだ。ふーん。」
シンジは予想外の答えに眉を潜めた。「何でも言ってよ」とは言ったが、どこまで聞いても良い物なのだろうか?
綾波の好きな人は、僕なんかに2人のプライベートな事聞かれたら嫌かもしれないし、いや、そもそも綾波って好きな人に告白とかしてるのかな?
「そうか。あの、僕の場合は、綾波と一緒にいられればそれだけで嬉しいんだよ。」
いや嘘だ。
「だから、さ、一緒にいるべきじゃないとか、そんな事、言うなよ、ね、綾波。」
気持ちよければそれで良いのか。綾波の気持ちは考えた事があるのか。
「僕はいつも、綾波の味方だから。」
同じ事を狭山や川島の前で言ってみろよ。
「有り難う。」
シンジは綾波の綺麗な、とても綺麗な顔を見つめた。
綾波は僕が可哀相だと思わないのかな。
シンジは何か急に腹立たしくなった。
「どういたしまして。」
シンジは微笑んだ。
シンジは結局その話題から逃げて、話を変えた。
「ところで…綾波今日、午前は洞木さんと一緒にいたんだね。」
「…ええ。」
「3時近くになっていきなりミサトさんから「今日はレイちゃん迎えに行かないでいい」とか電話が来るから、何かと思った。洞木さん、綾波の友達だったんだ。」
レイは道の右手を流れる名取川の川面を眺めているようだった。レイは口を開き、一旦閉じ、又開いた。
「……ええ。」
「良い人だよね。明るいし、優しそうだし。」
「ええ。」
シンジは数時間前ペンギン室で会ったおさげの少女の驚いた顔を思い出していた。
「真面目そうなイメージがあったんだけど、何か、結構面白い人だね。」
レイは微笑んだ。
「ええ。」
「途中で帰っちゃったのは…」
「…洞木さんの弟が、怪我をしているの。そのお見舞いに行っているそうよ。」
「やっぱりそうなんだ。」
「…知っているの。」
「うん。大変だよね、洞木さんも。弟さんは入院中だし、学校ではクラスの委員長だもんな。…綾波、どうしたの?」
シンジは急に目に見えて険しい表情になったレイを不思議そうに見た。
「何でもないわ。」
「…そう。自転車乗ろうか。」
「…ええ。」
「楽しく、ないのね。」レイは呟いた。
「何でそんな事言うの。」ヒカリは否定するでもなく、静かに尋ねた。
レイは質問の意味が良く分からないのか、ヒカリを見て小首を傾げながら答えた。
「楽しくなさそうだから。」
「綾波さんって面白かったりもするのね。」ヒカリは苦笑した。
2人はやはり黙って河口の穏やかな流れを見ていた。
「別に楽しくなくはないわ。ううん、楽しいわよ。少し遠いけどね。」
レイはヒカリの見た目で一番好きな部分が彼女のそばかすだった。そのためレイは毎回ヒカリの顔を見るたびに心拍数が上がってしまい冷静さを失ってしまうのだった。
レイはいつものように恥ずかしそうに顔をそむけた(ようにヒカリには見えた)。
「そう。」
「だって、私が水族館に来続けてもう2週間近くになるのよ。毎日来てる訳じゃないけど。ペンペンもギンギンも賢いから、教えがいもあるし。まあ、もうちょっと仲良くしてほしいとは思うけどね。」
「ええ。」
ヒカリは一昨日の事を思い出した。
「ねえ。碇君って、良い人だね。真面目だし、優しいし。学校以外の場所で会うのは初めてだったけど、水族館の彼は何だか輝いてるわね。」
ヒカリはレイに微笑んで見せた。
午後2時の新閖上港付近、河畔公園は穏やかな晴天だった。 ヒカリは思った。向こう岸の朝市、白雪っていう豆腐がおいしいのよね。
「…綾波さんと碇君って似合ってると思うよ。」
「洞木さん?」
ヒカリは不機嫌そうになった顔を慌てて打ち消す。
「何?」
ヒカリはレイの表情が分かるようになった自分が少し嫌だった。
「洞木さん…」
もし、あなたが私を嫌いになったのなら、今すぐ言ってほしい。そうすれば私はもうあなたに付きまとったりしないわ。
しかしレイはそれを口に出せず、東屋の時のようにヒカリの前に来てうなだれた。
ヒカリは顔をそらした。
「止めようよ、綾波さん。」
「…」
「止めようよ。」
ヒカリは歩道のアスファルトに視線を固定した。
「止めようよ。」
レイは無言でヒカリの前を動こうとしなかった。
真夏の生暖かい風が2人の服をバタつかせた。
レイは自分の唇を人差し指でなぞり、その手をうつむくヒカリの唇に近づける。30cm、20cm、10cm、5cm、4、3、2、1…
「止めようよ。」
顔を上げたヒカリはレイの右手をおさえた。
「止めよう、ね、綾波さん。」ヒカリは寂しそうに笑った。
レイは再びうなだれた。レイは自分が何故こうも未練たらしく、しつこくヒカリに拘るのか不思議に思った。しかしその非論理性が好ましくも思われた。
ヒカリは立ち上がった。
「…もう私、ここに来るのも止めるわ。 色々楽しか」
「駄目!」
レイはヒカリの両手を押さえた。
「行っては駄目!」
ヒカリはレイを見下ろした。レイの感情に溢れた顔は本来なら滅多に見れない物だったはずだが、彼女はここ数週間で嫌と言う程見続けてきたような気がしていた。
「行ってしまっては、駄目。」
「綾波さん。」ヒカリの口調は怒っていた。
レイは思った。
碇君。私の場合は、やはり自分の気持ちを相手に伝えない方が良かったように思うわ。
「綾波さん。もう止めよう。私は綾波さんが友達としては好きだけど、一つになりたい訳じゃない。」
「行ってしまっては、駄目…」
ヒカリはますます腹が立った。
「泣かれたって、困るわよ! 綾波さん。…何よ、自分はいつも可哀相だって顔して。私だって辛い時は辛いのよ!
都合の良い時だけ、泣かれたって困るのよ!」
ヒカリとレイの十数メートル向こうで釣り人が退散する。
「私は、洞木さんがいてくれれば、それで…」
「それが鬱陶しいのよ! いてくれればって、綾波さん、あなたのいてくれればは一日中でしょ?
24時間、いつでもどこでも家の中でも外に行っても付きまとうんでしょ? 私にも用事はあるのよ!
妹がぐうたらだから家事を全部やらなきゃいけないし、鈴原だって週3日は会いに行ってリハビリに付き合わなきゃいけないし、学校じゃ、クラス代表でこき使われて、子供だけの所帯だから時々役所にも行かなきゃ行けないし!」
「洞木さん…」
ヒカリはレイの体温を感じ、自分の顔がやや緩みだしている事に気づき、あわててレイを引き離した。
「離してよ!」
レイは突き飛ばされた。
「洞木…さん…」
レイは呆然と呟いた。
ヒカリは静かに言った。
「もうこれ以上、私に付きまとわないで。話してくるのも止めて。家に来るのも止めて。」
あまりの驚きでレイは涙も止まったようだった。
ヒカリはほんの少し微笑んだように見えた。
「さよなら。」
ヒカリは河畔公園の遊歩道を歩いていく。
「鈴原君ね。」
ヒカリはレイの言葉に足が止まった。
「あなたは、鈴原君が好きなのよ。」レイはまるで憐れむように言った。
「あなたには関係のない話よ。」
「そうよ、鈴原君が好きなの。でも恐いの。だってあなたと鈴原君は兄弟ですもの…」今度はレイが笑う番だった。
「綾波さん、あなた、何が言いたいの。」
レイはヒカリを嘲笑した。
「何でもないわ。慰めているだけ。何故ならあなたと鈴原君は、一つになる事が社会的に認められていないから。」
レイは微笑みながら、ヒカリの肩に手を置いた。
「寂しいでしょう。心が痛いでしょう。洞木さん、どんなに好きでも、あなたと彼は、決して一つには」
一瞬レイは何が起きたのか分からなかった。左頬の痛みと自分が座り込んでいる事で、自分がビンタを張られたのだと気づいた。
ヒカリは肩を震わせていた。
「あなたに…あなたに何が分かるって言うのよ、綾波さん。…私の純潔を奪っておいて、よくもそんな事を…」
「奪う?」
レイは立ち上り、ヒカリの頬を張った。
「私も初めてだったわ。私はあなただから一つになりたいと願ったし、あなただから全てを捧げたのに。あなたを力づくで奪った覚えはないわ。」
ヒカリはレイの自分に向ける顔が徐々にいじめっ子達に向けていた顔と同じになりつつあるのを見て、寂しいようなほっとしたような何とも言えない気持ちになった。
「…そうね。それは私も言い過ぎたわね。御免なさい。」ヒカリは微笑んだ。
「慰めてくれたのよね。…ありがとう。でもこれからは、お互い干渉しあうのは、もう止めましょ。」
「…」
「さよなら、綾波さん。」
ヒカリは再び歩き出し、もう一度レイに振り返り微笑んだ。
「さよなら。」
「……………………………………………………さよ……………………なら………………」
「ああ、いたいた! ったく探したのよ!」
叫び声に、レイとヒカリはやや上になっている車道を見上げた。ミサトがガードレールに手を置いて肩で息をしている。
はあ、はあ、はあ、はあ…
「……あの…どうかしたんですか?」ヒカリはいたたまれずに聞く。
ミサトは呼吸を何とか整え、運動不足のせいかやや青くなった顔で言った。
「どうしたもこうしたもないわよ! レイちゃん、ヒカリちゃん、急いで来て!」
レイは首を傾げる。
「最近、喧嘩は珍しくありません。」
「そりゃね、今までも小競り合いはしょっちゅう有ったわ。でも互いに異性だし、威嚇以上の事なんてするはずないのよ!
あいつら全くおかしいのよね、普通のペンギンなら、同種を互いに本当に攻撃するだなんて有り得ないわ。」
「今までよりもひどいって事ですか。」
「そうなのよヒカリちゃん。もーったく、こういう時に限ってリツコはいないのよねえ!」
レイは何故ミサトが自分達の頬や目の異変に気づいているのにそれに触れようとしないのか不思議に思った。
車道に駐車場に廊下を横断し、3人は見慣れたペンギン室の中に入った。
「な、何ですか、これ…」青ざめるヒカリ。
「良いから手伝って! レイちゃん、マヤちゃんと一緒にギンギンを押さえて!」
「分かりました。」
「ふえーん、お嫁に行けないー」
半泣きで目をつむりながら、しかし相当に強い力でマヤはばたばたと暴れるギンギンを壁際に押さえつけている。
レイは「助ける必要があるのだろうか」とやや思いながらも、マヤにならってギンギンの胴体を押さえた。
ペンギン室では2匹のペンギンががーがー言いながら互いを攻撃しようともがき、それを人間達が懸命に押さえつけようとしていた。
「ヒカリちゃんはこっちを押さえて。」ミサトはそう言いながらペンギン室から姿を消す。
「あ、ちょっと!」
「があ、ぐぁあ、ぐぁあ。」
押さえつけるマコトをくちばしで容赦無く攻撃するペンペン。この人は、この数分間ずっとこんな状態で押さえ続けていたのだろうか?
ヒカリが呆気に取られて動けなくなっている間に、ミサトが再び走ってやって来た。
「有った、やっぱりリツコの部屋に有ったわよ!」
ミサトはプラスチック製の長さ40センチ程度の箱を抱えて持って来ていた。
マコトは箱を見て失望した。
「…デラックス猫ちゃんハウスって、それですか…」
「良いから贅沢言わないでこれに押し込む!」
「え? あの…」
「くあーっ、があ、くあっくあっくあっ」
「いっせえの!」
唖然とするヒカリの前で、ミサトとマコトはじたばたするペンペンを無理矢理猫ちゃんハウスに突っ込んだ。
「ぐぅあーっ。」
どうやら今回の喧嘩の「首謀者」であるらしいペンペンは寝そべったような状態のまま身動き一つ取れず、猫の臭いが充満する中、くちばしは入り口の格子からはみ出し、開く事も出来ない、という独房以下の環境で、「うーぐー」と唸っていた。
「廊下に放り出しておけば、少しは反省するでしょ。」
ガラス窓の向こうの、廊下に置かれたプラスチックの箱を見ながら息をつくミサト。
「というより、とにかくペンギン室から出さないとギンギンが攻撃しますから…」マヤが苦笑しながら答える。
「があ、があ、があ。」
ギンギンは自分の視点では上のガラス窓が見えないものの、ドアのすぐ向こうの廊下にペンペンがいる事を分かっており執拗にドアをコツ、コツとくちばしで叩いていた。
「くちばしを傷つける危険性があるわ。…マコト君。」
2人はうなずき合うと、2人がかりでフリッパーをばたばたさせるギンギンを何とかカスパーの前まで連れてこさせた。そのまま押さえ続けるマコト。
「<話す><同じ><あなた><動く><少ない><と><話す><少ない><終わる>
(いい加減静かにしなさい。)」
ミサトが打った文をギンギンは見て、「くあ。」と口を開いた。
「<始める><ペンペン><動く><強い><悪い><終わる><同じ><ペンペン><悪い><終わる>
(喧嘩を始めたのはペンペンだ、悪いのは彼だ。)」
<ギンギン、確かにペンペンも悪いけど、あなたもやり過ぎよ。>
<そんな事はない。私は悪くない。>
ギンギンが話に集中し始めたので、マコトはようやくペンギン押さえ付けという危険業務から解放されたようだった。
<あなたもさっき、ペンペンを攻撃しようとしてたでしょう。>
<そんな事はない。>
「![]() (<行く><する><あなた><終わる>)(「してました。」)」
(<行く><する><あなた><終わる>)(「してました。」)」
「![]() (<でない><行く><する><終わる>)(「していない。」)」
(<でない><行く><する><終わる>)(「していない。」)」
「![]() 」
」
「![]() 」
」
「![]() 」
」
「![]()
![]()
![]() 」
」
「こんの腐れペンギンが…」
「があ、くあ、くあぁ。」
「葛城さん。」
「何、レイちゃん。」会話に夢中になっていたミサトが振り向く。
「ペンペンにも、同じように言葉で、喧嘩をするなと教えたらどうでしょうか。」
「駄目よ。」答えたのはヒカリだった。
「今ペンペンが来たら、また大変な事になるに決まってるわ。」
ヒカリの言葉にミサトが頷く。
「それにレイちゃん、ペンギン用の端末はここに1匹分しかないから、一度に2匹とは話せないのよ。それがマズい原因の一つだとは思うんだけどね。」
「いいえ。端末ならもう一台、赤木博士の部屋にあります。」
「え? あ、でも、あれは…」
「博士の部屋が汚れてしまうかもしれませんが、緊急の事態ですから、分かってもらえると思います。」レイの真面目な言葉にミサトは何故かニヤーッと笑った。
「以前使っていたカスパー用のキーボードをメルキオールに繋げれば、会話は可能なはずです。」
「…うん、分かったわレイちゃん。至急赤木博士の部屋に行って、セットアップしましょ。ヒカリちゃん、ギンギンの方、お願いね!」
ミサトとレイは部屋を出て、ギンギンに付いてこられないようにすばやくドアを閉めた。
「え! いや、あの…」
「洞木さん、お願いするわね。」
「え…」
「俺達水族館員が一言もペンギン語が話せないのも情けないけどな。ミサトさんキーボードに触らせてくれないから…ヒカリちゃん、何とか彼等を仲直りさせてやってくれ!」
「いや、でも」
「あー、もう日向君、血が出てるじゃない! もう、早くこっち来て!」
「あ、有り難う、マヤちゃん…それじゃヒカリちゃん、頼んだよ!」
「え?…」
「くああ。」
ペンギン室にはヒカリとギンギンだけ取り残された。
<あなたは行かないのか。>
「…え?」
ヒカリはギンギンとドアを見比べながら呟いた。
「めっ。」ついでに声でギンギンに注意してみる。
<私は何も悪くない。>
<私は見てなかったから今の事は良く分からないけど、最近のあなた達は変よ。何でそうすぐに喧嘩をするの。>
「くあ。」
<ペンペンが勝手な事を言ったり、勝手な事をしたりするからだ。私は悪くない。>
<あなたが悪い事は、全く無いの?>
<全く無い。>
「前途多難よ…」
ヒカリは溜め息をついた。
<それでは、あなたはペンペンが悪い事をする時、それを注意した?>
「くあ。」
<注意? 注意とは、人間のする事だ。>
<人間もするけれど、ペンギンもして良いのよ。ギンギン、ペンペンが何か悪い事をしたら、あなたも注意して良いの。あなたが何か悪い事をしたら、ペンペンがあなたを注意する事も出来るわ。>
<私は悪い事をしていない。>
「文が長すぎたわ。」
<そうね。とにかく、ペンギンも注意をして良いの。いいえ、何か思う事があったら、あなたもいつでもそれを伝えなきゃ駄目。>
<何故だ。>
ヒカリは一瞬詰まった。
<そうしないと、他の人(ペンギン)はあなたの思っている事が分からないからよ。>
<分からないと何故いけないのか。>
「それは、だから…」
<ペンペンが悪い事をしたとして、あなたがそれは悪いと伝えたら、ペンペンはそれを止めるでしょう?>
「くあっ。」ギンギンはまるで人間が首を振るかのようにクイッと首を曲げた。
<止めない。ペンペンは![]() (悪い友人)だからだ。>
(悪い友人)だからだ。>
「まあ、まだ「敵」じゃないだけましか。」
<![]() (敵)ではないのね。>
(敵)ではないのね。>
<![]() (敵)とは自分が食べ物になる他人の事だ。>
(敵)とは自分が食べ物になる他人の事だ。>
「敵って天敵の事か…じゃあ同族としてはペンペンは最悪である事に変わりはないのね。」ヒカリは思わず笑った。
<何でそんなにペンペンを嫌うの。同じペンギンでしょ。>
<ミサトとは仲良くしている。>
<ペンペンとも仲良くしなさい。>
<何故だ。>
<何故って…寂しいでしょ、仲良くしなきゃ。>
<「寂しい」とは何だ。>
「え、だから、」
<自分の気持ちを分かち合う相手がいなかったら、辛いでしょう。それを寂しいって言うの。>
「くぁ。」
<辛くない。その言葉はいらない。>
<いるの!>
<いらない。生まれてからずっと、他人(他のペンギン)と気持ちを分割した事など無い。そんな事は不可能だ。>
<可能なのよ。ギンギン、今あなたは、楽しくないはずよ。イライラしてて、ペンペンに怒ってる。>
「くあ。」
<そうだ。何故分かるのか?>
「あなた達の思考回路って、未だに良く分からないわよ…」
<私とあなたが今、気持ちを分かち合っているからよ。ギンギン。どうしてあなたが怒っているのか、その訳を教えてくれる?>
<何故だ。>
<そうすれば、一緒にその事について考えて、何か解決策が得られるかもしれないわ。>
「くあ。」
<それは新しい(面白い)考えだ。>
「分かってくれて嬉しいわ。」
ヒカリはほっと息をついた。
<一番悪いのは、ペンペンがこれを使う事だ。>
<これ?>
「![]()
(<これ><終わる><四角><道具><言葉><終わる>)
(「これだ、言葉の道具の四角だ。」)
」
「ああ、カスパーね。」
<これをペンペンが使うと、何故いけないの?>
<私が使えない。>
ヒカリは頭を押さえた。
「行儀の良いギンギンでこれじゃ、向こうの状況が思いやられるわ…」
<ペンペンもこれを使いたいのは分かる。しかし彼は、ちゃんとした言葉(ペンギン語)を話さない。>
<少しくらいちゃんとしていなくても、通じているから良いでしょう?>
<良くない。それが一番悪い事だ。>
ヒカリはモニタと、つぶらな瞳の温泉ペンギンを交互に見ながらしばらく考えた。
<それでは、あなたがペンペンに正しい言葉を教えたら?>
<ペンギンが注意をして良いのなら、ペンギンが教えるのも良い(のは確かだな)。>
<そうよ。>
<しかし、2匹では話せない。>
<前に使っていた言葉の道具の四角があるわ。それをここに置けば、会話が出来ると思う。>
<それは楽しい。>
ヒカリはふと怪訝に思った。
<ねえ、ギンギン、あなた本当にペンペンが嫌いなの?>
<ペンペンは![]() (悪い友人)だ。>
(悪い友人)だ。>
<でも、![]() (他人)や
(他人)や![]() (敵)ではないんでしょう?>
(敵)ではないんでしょう?>
<そうだ。>
<本当はペンペンが好きなの?>
「くあ、くあ、くあ。」
<そんな訳が無い。>
ギンギンは大袈裟に、少しフリッパーを上げさえした。
「どうだか。」
<そう。とにかく、![]() (他人)や
(他人)や![]() (敵)じゃないのなら、少しは悪さも我慢して、教えてあげて。>
(敵)じゃないのなら、少しは悪さも我慢して、教えてあげて。>
<分かった。私は正しいペンギンなので、我慢をしよう。>
ギンギンは、「くあ。」と鳴いた後一しきり羽繕いをした。
<本当は、ペンペンは嫌いではない。>
「はあ?」
<嘘をついていたの?>
<何がだ。>
<今までずっと、嫌いだって言ってたじゃない。>
「くぁ。」
<今、考えが変わった。>
<そう。>
<しかし彼は悪いペンギンだ。だから良くないのだ。私の言う事をちゃんと聞けば、彼も![]() (良い友人)になるだろう。>
(良い友人)になるだろう。>
「くあ。」
「問題、解決…したのかな?」
<そうなると良いわね。>
ヒカリは微笑んだ。
<ギンギン、あなたはキーボードを使いたがるわ、そしてペンペンもそう。何故かしら?>
<話すのが楽しいからだ。>
<そうね、楽しいわね。何故楽しいのかしら。>
「くあ。」
<難しい質問だ。>
<もしかして、こういう事じゃないかしら。ギンギン、さっき私は、あなたの考えている事が分かったわ。>
<そうだ。>
<それはどうしてかしら。>
<気持ちを分かち合ったからだ。>
<良く分かったわねギンギン。そうよ。そして私とあなたが気持ちを分かち合えたのは、私とあなたが話をしていたからなの。>
<話をすると、気持ちが分かち合えるのか。>
「うーん…」
<そうね、話は、気持ちを分かち合うためにする事だから。>
「そうじゃない事も多いけどね…」
<話は、楽しいからする物だ。>
<だから、何故楽しいかというと、気持ちを分かち合ってるから楽しいのよ。>
<そうなのか。>
<そうなのよ。>
<話をしないと、気持ちは分かち合えないのか。>
<話をしないで気持ちが分かち合える事もあるわ。>
<どういう時だ。>
ヒカリは優しくギンギンに微笑んだ。ヒカリの微妙な仕草をキャッチして、首を傾げるかのようにヒカリを見るギンギン。
「くあ。」
<私にも良く分からないわ。本当に仲良しだと、そういう事もあるみたい。でも、普通は言葉を使うわ。それが一番確実なのよ。>
<そうか。>
<ペンペンが、嫌いではないんでしょう。気持ちを分かち合える相手を減らしたら、楽しくないわよ。>
<そうか。>
<そうよ。本当に嫌いなら、それは仕方が無いわ。でも、本当は嫌いではないのだったら、![]() (良い友人)にしてあげましょうよ。>
(良い友人)にしてあげましょうよ。>
<その方が楽しいのか。>
<その方が楽しいわ。>
<私もあなたと話して楽しい。>
<有り難う。>
「くあ。」ギンギンは一しきり、頭をブルブルと震わせた。
<私も今のあなたの気持ちが分かる。>
<そう?>
<今、安心して、嬉しい気分になっているはずだ。>
ヒカリはそれを言われて、何故か本当に嬉しくなったような気がした。
<ええ、当たっている。凄いわ!>
<心を分かち合っているからだ。>
「くあ。」
<その通りよ、ギンギン。>
ヒカリは少し、ギンギンを抱きしめてあげたくなったが、どうも彼等がそれは嫌がるらしい事を知っていたので我慢した。
「…ギンギン、あなた達、私達の為にわざと喧嘩をしたの?」
ヒカリはギンギンの頭を軽く撫でながら呟いた。
顔に2個所ほど絆創膏を貼ったミサトが、用心深く10センチ程度だけペンギン室のドアを開けた。
「ヒカリちゃん、ギンギンは、様子どお?」
「ど、どうしたんですかその顔。」
「あはは、ペンペンが、ちょっちね。あ、レイちゃんは大丈夫だから安心して。」
「あ、はい。…こっちは、もうかなり落ち着きましたけど。」
「ああ、そう! じゃ、もう大丈夫かな。レイちゃん、良いわよ、連れて来て!」
「があ、くあ、くあぁ、くあ。」
ミサトが研究室の方向に大声を上げると、レイがペンペンを抱えて持って来た。
ギンギンはペンペンが来たのを確認すると、「私には関係ない」といったそぶりでプールに滑り込んだ。
「があ、くああ、くああ。」
「本当に反省したの?」思わずヒカリに聞くミサト。
「…さあ…」
「ええ。一応効果はあったと思います。」
ヒカリとミサトはレイの顔を見た。
「問題ありません。2匹とも表情がリラックスしています。」
ヒカリとミサトは目を見あわせた。
一しきり鳴いて、何かの自己主張が終わったらしいペンペンは、何食わぬ顔でプールに体を滑らせた。
2匹の温泉ペンギンは、互いに無視しながらも屋外のプールでくるくると水中を泳いでいた。
午後3時30分だった。
「あれ、3人とも揃っているなんて、何かあったんですか? …え?」3人は今頃水族館にやって来たシンジを白い目で見た。
ヒカリはミサトにシンジをペンギン室に引き止めておくよう頼み、レイと淡水魚層の前で座っていた。
「…そっちは…どうだったの。」
レイはヒカリの言葉に振り向き、何を言うべきか悩んでいる様子で口を開きかねていた。
「…何が。」
「ペンペンの様子。反省してた?」
「…ええ。」
レイは顔を和らげた。
「ペンペンは、口は悪いけど根は素直よ。」
「ギンギンは、逆?」
「ええ。彼女はあまり素直ではないわ。でも、人間に比べれば、彼女もとても素直よ。」
「…そうね。」
2人はスケルトンテトラの水槽の前の指定席に座っていた。
「洞木さん。」
声をかけられると思っていなかったヒカリは少し驚いて、レイの顔を見た。
レイはいつものようにとても真摯な顔つきで、ヒカリをまっすぐと見つめていた。
「御免なさい。さっきはひどい事を言ってしまって。」
「…」
「御免なさい。」
ヒカリはレイの視線に思わず耐えられなくなって顔を戻した。
「良いの。そんな、気にしないで良いよ。綾波さんの言った事、全部、本当だから。私の方こそ…綾波さんも分かってたでしょ。…勝手よね。好奇心でそういう事をして、面倒になったからって、わざと嫌われるような喋りかたをしているんだもんね。嫌な女だよね。ねえ、綾波さん、私ってこんなだよ。全然綺麗じゃないよ。」
ここで涙が出れば完璧だったのだが、ヒカリは実感がこもりすぎて却って言葉が淡々と出て来るのだった。
「…それでも私は洞木さんが好き。」
「…綾波さんって、私を何が何でも肯定してない?」
「そんな事はないわ。ただ、その嘘は、恐らく洞木さんの優しさの現れだと思う。それはあるいは綺麗と呼ぶべき物ではないかもしれないけれど、悪い物ではないわ。」
「……………綾波さん、優しいね。」
「…分からない。」
「…」
ヒカリは弱く微笑んだ。
ヒカリは顔を上げた。
「ね、綾波さん。じゃあ、私の嫌な所って何処?」
「嫌な所?」
「ええ。嫌な所。私を何が何でも肯定している訳じゃないなら、何か嫌な所があるはずでしょ。」
ヒカリはレイの本当に困ったらしい顔に表情を崩した。どうも彼女はいじめっ子の素質があるらしい。
「…ええ、あるわ。」
「何?」ヒカリは何故か息せき切って尋ねる。
「お弁当に肉が入っていたわ。肉、嫌いなの。」
「……それだけ?」
「…ええ、今の所は。…もちろん、全体としては洞木さんはとても好きだわ。」何か不満そうなヒカリにレイは慌てて付け足した。
「ぷっ、ふふふふ…」
「…」
「全く、お互い実らない恋よねえ! ふふ、ふふふふ…」
ヒカリはレイの肩に手を置いて、声を上げて笑った。レイは戸惑いながらも、彼女に合わせてぎこちなく微笑んだ。
「…ふー。」ヒカリは息を整えた。
「綾波さん。さっきは御免なさいね。こんな私で良かったら、これからも「良い友人」でいてくれるかしら。」
レイはヒカリの言葉を繰り返した。
「「良い友人」?」
「そう。「良い友人」。赤いハート型。」
レイはヒカリに柔らかな微笑みを見せた。
「同じ、私達、良い友人、終わる。」
「はい、終わる、来る、同じ、私達、良い友人、時間、多い、終わる。」
ヒカリも微笑んでレイに答えた。
久しぶりに綾波さんに本当に笑いかける事が出来た。
そう思いながらヒカリは、水槽に指をコツンと叩いた。
「私、思ったんだけどね、「喧嘩をするな」って教えたのは、私達じゃなくてペンギン達だったような気がするの。」
「…そうかもしれない。」
レイも水槽に指を当てる。彼女の白く細い指に、透明な4cm程度の魚達が集まり出す。
「彼等は、とても知能が高いわ。私たちが教えられたという可能性も確かにあるわ。」
レイの様子にヒカリは聞いた。
「もしかして綾波さんって、その魚達の気持ちも分かる?」
「いいえ。この魚には、感情が存在するとは考えにくいわ。」
きっぱりと言うレイに、ヒカリは思わず「御免なさい。」と呟いた。
「へえ、それじゃあ、時田さんには頭が上がらないな。」
フェンスによりかかるミサトは加持の声に頷いた。
「あのおじさんも、中々あなどれないわよねえ。たーだ毎日川沿いでぷらぷら釣りしてるんだとばっかり思ってたけど。意外な所で機敏だからねえ。」
餌の箱を持ったまま、加持は苦笑する。
「助けてもらった人に、そんな言い方はないだろう。」
「良いのよ、事実なんだから。…でも、一体何が原因だったのかしらね。普段はあんなに仲良い2人なのに。」
「その…シンジ君、だったか? 彼よりもかい?」
サングラスのミサトは鼻で笑う。
「そりゃあ、同性と異性じゃ違うわよ。…でも、言われてみれば、その時までの2人はなーんか意識してたかな…」
「あれじゃないのか? 秘められた、禁断の…うっ」
加持はフェンス越しに背中にミサトのエルボーの直撃を受けた。
「下らない事言わない。中学位の女の子の心は微妙なのよ。言葉を覚えたてのペンギンの心もね。」
「どっちとも、なった経験無いからな。…おっと」
今度は彼はフェンスから逃げた。
「ま、ボランティアのメンタルケアも良いが、あんまり抱え込むなよ、葛城。まあ、疲れた時は、いつでも俺の腕の中で休んでく…」
加持は飛んで来た石をよけた。
「おいおい、魚に当てたらどうする!」
「魚? …分かったわ、今度からは魚に当てるようにするわ。」
いつの間にかミサトは車に乗り込んでいた。
ミサトのルノーはいつものように急発進でカーブの道を走り去っていった。
それで、「悪友」はどういう形なんだ。
加持はさっきのミサトの話を思い出しながら考えた。
つづく
フラン研さんの『海辺の生活』第七話、公開です。
「人に意見をしながら自分を知る」
そこにペンギンを持ってくるとは面白すぎです(^^)/
口から出さない言語であるペンギン語とか、
ヒカリとレイの関係とか、
ミサトの巧さとか、
何だかシンジとか、
いろいろあって
最後にまとまっていって・・
いやほんと、
毎回堪能させていただいています(^^)
ありがとうっ ←谷村新司調に(^^;
さあ、訪問者の皆さん。
フラン研さんにGOODな感想メールを送って下さい〜
へんてこなコメントしか書けない私を叱って下さい・・ (;;)