カスパーとバルタザールの電源を入れる(メルキオールの電源は常に入っている)。カスパーとバルタザールには、それぞれかなり大きなキーの並んだキーボードらしきものが置いてある。バルタザールには、普通のキーパネルも置いてある。
リツコはバルタザールの「普通の」パネルのトラックパッドを滑らせる。
ギンギンが物珍しそうに覗き込むモニタの中に、赤い球の立体映像が映し出された。
「良い、ピンギ。この色は、」リツコはギンギンの爪の伸びたフリッパーを、大きいキーボードの中の青い林檎のような形のマークが書いてあるキーに導いた。
「これなの。」
「![]() 」
」
ギンギン、というよりリツコがそのキーを押すと、赤い球の下にテキストボックスのような長方形が現われ押したキーと同じ物が表示された。
ギンギンは特に嫌がる様子もなく、「くあ」と鳴いた。
「良い、ピンギ、もう1回。この色の時は、」再び赤い球の立体映像。
「このキー。」リツコはギンギンのフリッパーを手に取り、キーへと導く。
「くあ。」ギンギンは首を傾げている。
「これは前途多難ね。」ミサトは後ろからその様子を腕組みをして眺めていた。
「あら、彼女がモニタの前にじっとしているだけでも信じがたい事よ。充分見込みがあるわ。」
早口で反論するリツコ。
「あんた、目、輝いてる。」
思わず笑うミサト。
少し顔を赤くしたリツコは、向き直って更に続ける。
「ピンギ、もう1度やるわよ。これが映し出された時は。」再び赤い球、「このキー。」ギンギンの右フリッパーを![]() のキーまで持って来させる。
のキーまで持って来させる。
「くぅ。」ギンギンは楽しそうに、左フリッパーをリツコの腰に置いた。
「私じゃないのよピンギ。このキーよ、このキー。」リツコは左フリッパーもキーに導く。
両フリッパーを塞がれた形のギンギンは不満気に「があ。」と鳴いた。
「「やってらんない」って、言ってるわね。」
リツコはミサトを無視して、いや、無視しないで、声をかけた。
「ミサト。ここに焼き魚とか、スルメイカとか、シラスとか無い?」
ミサトは眉を上げた。
「はあ? そんなもん、こいつら食べないわよ。」
「彼等が食べなくても良いのよ。緊急を要するの。」
「は、はあ…イカの燻製なら、時田さんが良くビールのつまみに…」
「それで良いわ。持って来て、速く!」
「う、うん…」
リツコの語気に押されて、ミサトは職員控室に走って行った。
ペンペンは山の頂上で仰向けになって寝ている。
「…つまり、私はペンギンと同等だと。」ミサトは肩を震わせた。
「ペンギンは、ペンギンと人間を区別しないわ。」リツコは淡々と答えた。
「いえ、正確には、区別はするけど差別はしないと言うべきね。」にこやかに訂正する。
ギンギンは2人を見比べている。
「…リツコ、あんた単純に面白いからやろうとしてない?」
「そんな事はないわ。」
ミサトは鼻から息を出す。
「…」
「…人類と動物がコミュニケーションを取る、重大な」
「分かった、分かったわよ。私も協力しないって言ってる訳じゃないから。」
「理解してくれて助かるわ。」
マコトはミサトのペンギン室を、殆どいつも無意識に覗きに来ていた。彼に言わせると「仕事の帰りにたまたまペンギン室の前を通る」だけらしいのだが、遠回りをしてペンギン室の前で立ち止まる彼の行為には高度の作為性が見られると言わざるをえない。
ミサトさんは、元々ペンギンの飼育を希望していたけど、今の日本には水族館も多くないし何処も余裕がないしで結局希望する所には行けず、ここで僕と海水魚を担当していた。ミサトさんは口には出さないけど、やっぱりそれで失望する事もあっただろう。だから、非公開とはいえこうやって彼女がペンギンの飼育が担当出来るようになった事は、僕も我が事のように嬉しい。…ミサトさんのペンギンを見る目、優しくて好きなんだよなあ。
ここで日向マコト君はいくつか間違いを犯している。ミサトさんは海水魚の担当になった時、相当文句を口に出していたし、ペンギンが非公開になった事についてもやっぱりぶーぶー言っていた。
それに彼女がペンギンを見る時、彼女の目は優しさのみを現わしてはいない。
マコトはペンギン室のミサトさんを発見した。
彼は首を傾げた。
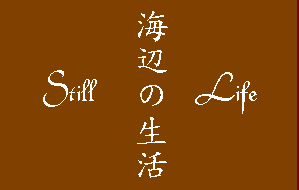
ペンギン室は、半分屋外、半分屋内の構造になっている。コンクリート―ただし所々に人工芝のような物が敷いてある―の陸地、及び「ペンギン山」の部分に屋根がある。学校のプールに匹敵する位大きく、もっと深いプールが屋内から屋外に張り出していて、もちろんこの間に壁は無い。ひさし付きの屋外、と言った方が正しいかもしれないが、「陸地」の奥の方はかなり建物の中に入るので、端末を置く事も可能になる。もちろん、その場合でも端末は特別な防水仕様である事が要求されるのだが。また、屋外のプールは透明な特殊プラスチックの柵で囲まれている。
水族館の魚達は基本的に建物の中で飼われているので、この屋外の周りは浄化槽やら電気設備やら色気の無い建物ばかり並ぶ事になる。
その間の道からマコトは、屋内で壁際に立っている赤木博士と、その隣でしゃがみ込んでいるミサトさんと、更に隣でミサトさんを不思議そうに眺めている温泉ペンギンのどっちか1匹、を見ていた。
リツコは説明を繰り返した。
「良いミサト。ここに赤い球が現われるわね。」
MAGIカスパーに赤い球の立体映像が浮かび上がった。
「この色の時は、このキーを押すのよ。」
青い林檎のキーを指さす。
「うん、分かったよ!」わざとらしく大きな声で答えるミサトは、ギンギンと同じ高さの目線で、カスパーの大きなキーボードの「![]() 」のキーを押した。
」のキーを押した。
「良く出来たわミサト、これ御褒美。」リツコはミサトの口の中にイカの燻製を丸々1個投げ入れた。
「うっ…物凄くしょっぱいけど…有難う、リツコさん!」涙目になっているミサト。
「どういたしまして。」
「…何かの罰ゲームなのかな?」マコトは首を傾げながら、「人をむやみに覗いてはいけない」という教訓を得て海水魚漕東廊下へと戻って行った。
「くあ、ぐあぁ、くあ!」ギンギンはリツコの白衣をつかみ、抗議をしているようだ。
リツコはもう一度説明をしている。
「あら、ピンギも御褒美が欲しいの? じゃあ実験に協力してくれるかしら?」
「くあ。」
「ここに赤い球が…」
「くあ、くあ、くあ!」
ミサトへの厚遇に我慢できなくなったらしいギンギンは、リツコの声を遮ってフリッパーを振り回している。
「もう、今日はこれ位が潮時じゃない?」
ミサトは自身の健康も鑑みて宣言した。
「…演技力が足りなかったのかしらね…」
「何でそこでそうなるのよ!」
「くあ!」
「ちゃんとやっていた?」
「やってたわよ! そもそもね、私はこんな馬鹿な事をするために生物学科を出た覚えは無いわよ!」
「くあっ!」
「失礼ね。あなたは今までの人間と動物が対話を試みる実験が、いかに困難でいかに忍耐力のいる物だったかを理解したうえでそういう事を言っているのかしら。」
「くあ。」
「だからってね、もうちょっとやり方ってもんがあんでしょ。あんたイカの燻製丸々1匹食べさせられた事あんの?」
「無いわね。健康上問題があるわ。」
「くあ。」
「あんたねー!」
「くあ、くあぁ、くあ!」
「ん、何、ギンギン。」ミサトは自分の作業服を引っ張るギンギンに、目を落とした。
「![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 」
」
モニタには青林檎がたくさん並んでいた。
ペンペンはやっぱり寝ていた。
ギンギンは御褒美の子供ヤリイカを口にくわえて上機嫌だった。
「じゃあピンギ、次行くわよ。」リツコは再びトラックパッドを滑らせる。
「この色は、」今度はカスパーの画面に青い球が現われた。
「このキーよ。」ピンク色の、波線のマークのキーを指す。
「くあ。」首を傾げ、リツコの出した手をつかもうとするギンギン。
「…ミサト。」
「そうかあ! このキーかあ!」ミサトが「![]() 」のキーを押すと、その後からギンギンは何食わぬ顔で同じキーに触った。
」のキーを押すと、その後からギンギンは何食わぬ顔で同じキーに触った。
「…つくづく、私の真似をしているだけね。」
「最初はそれでも良いのよ。これだけ飲み込みが速いと、期待できるわ。」
「![]()
![]()
![]()
![]() 」ギンギンは、自分がキーを押すとモニタのテキストボックスに変化が現われる事にどうやら気付いたらしく、何度も打っている。
」ギンギンは、自分がキーを押すとモニタのテキストボックスに変化が現われる事にどうやら気付いたらしく、何度も打っている。
「ピンギ。じゃあ、次の色よ。」リツコは再びバルタザールを操作する。
「この色は、」次はギンギンの目の前に黄色の球が現われた。
「これ。」リツコはカスパーの「![]() 」のキーを指す。
」のキーを指す。
「![]()
![]()
![]() 」
」
「良く出来たわピンギ。凄いじゃない。」
リツコは少し興奮気味に、バルタザールのモニタをクリックする。
「ピンギ、これは?」赤い球。
「![]() 」
」
「これは?」青。
「![]() 」
」
「これは?」黄色。
「![]() 」
」
「リツコ…結構、凄くない?」
「え、ええ…」
ミサトとリツコは、呆気に取られて呟いた。
ペンペンは目を覚ました。
この間来た自分と同じ大きさの女が、いつも餌をくれる青い大きい奴(多分男)とせわしなく動く白い大きい奴(多分女)とつるんでいる。
いや、自分と同じ大きさの黒い奴は、青い奴からイカを貰っている!
俺も貰う!
「くあ。ぐあ。ぐぁあ。」
ミサトは背後から作業服をつまむペンペンに気がついた。
「ん? どしたのペンペン。お前も食事?」
「くあ。」
ミサトを食い入るように見ているペンペン。
未だにしゃがんでいるミサトは顔を上げた。
「どうする、リツコ?」
リツコはしばらくモニタから目を離し、考えた。
「そうね。本来なら、この種の実験は1匹に対し何年もかけて行なうものなのだけど…少なくともピンギの場合、たった、」
リツコはモニタの時計を見た。
「1時間14分でここまで来たのだから、ポコティファを含めて実験を一から再開しても問題は無いと思うわ。」
「そう。良かったね、ペンペン。」ミサトはペンペンの頭を撫でた。
青い奴、また触る。いつも食事くれる。でも気持ち悪い! だから前に軽く手を挟んだ。青い奴、怒った。とても怖かった。だから今はじっとしてる。
「があ。」
「ポコティファ、機嫌悪そうよ。」リツコは我が子のように撫でるミサトとじっとして動かないペンペンを見比べた。
「そう?」
「くあ。」
「![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 」
」
ギンギンはキーで遊んでいる。
「くあ、くあ、くあ!」
「ぐあーぁ。」
ペンペンは、ギンギンの一喝で静かになり、さかんに首を傾げ、自分のフリッパーの辺りを突くような動作をしている。
「…尻に敷かれてるわね。」
ミサトの呟いた事と、一瞬でも同じ感想を抱いたリツコは自分に軽い殺意を覚えた。
「ポコティファ。この色は、」赤い球。
「このキーなのよ。」
「![]() 」もちろんキーを押したのはギンギンだ。結果としてギンギンのみが新たなイカをミサトから得る。
」もちろんキーを押したのはギンギンだ。結果としてギンギンのみが新たなイカをミサトから得る。
「くあ! ぐあーあ!」
「があ。」
ペンペンはギンギンが鳴くと、どうも知らん振りをしだす。
「ミサト。ちょっとピンギを見て。」
「ん。」
まだしゃがみ込んでいたミサトは、ギンギンがカスパーに触れないように、抱きしめるように押さえこんた。
「がああ。」
当然抗議するギンギン。
「ポコティファ。この色の時は…」
結局この後、2時間粘ったがペンペンの反応は思わしくなく、2人は今日の実験を終えて遅い昼食をとる事にした。
今日は全体として、良い1日だった。この地方は温暖で人間には心地良い気候だ。ペンギンにとっては、もう少し涼しい方が好ましいのだが…今日、私は自宅から研究室までの数十メートルを歩いていて、ふと道の向こう側を見ると、民家の庭に大きな桜の木が有るのを発見した。自分が毎日通る道であるにも関わらず今日までその開花に気付かなかった。私は何故か、得をした気分になった。
EVAの実験当初は、ピンギが積極性を見せ、ポコティファはいやいや物真似をするようなレベルに留まっていたのだが、2匹の競い合いによる効果があったのか、徐々にポコティファの発話に積極性が見られるようになってきた。
2匹を同時に研究していると、それぞれの明確な個性の差が露わになって面白い。ピンギは従順でこちらの指示に良く従うが、物事の解釈に柔軟性が見られないように感じる。一方ポコティファはどこまでもマイペースで自分勝手だが、一旦のめり込むとピンギを寄せ付けない集中力を見せる。それぞれがそれぞれの良い部分を学んでくれれば良いのだが、どうも双方とも互いに一定の距離を置いているようだ。生存する個体がこの2匹だけである以上、何としてもこの2匹で繁殖をさせなければならないのだが…いずれにせよ、今の体のシステムではそれが不可能なのは分かりきっている事ではある。碇理事長とも連絡を取り、ドイツやカナダの研究機関への受け入れ要請も考慮に入れる必要があるだろう。
今日のテストでは、まず立体画像イメージによる単語の定着作業が行なわれた。「ペンギン」という単語を覚えさせる為に多様な種のペンギンの映像が映し出される。「ペンギンは音・声で種を知る」というミサトの提言で、ある程度音声資料も同時に出せるように配慮した。今やピンギは要領を心得ていて、私がキーを指さすとすぐにそのキーを押す。ただし単語として定着するまでには時間がかかる。つまり一旦あるキー、例えばこの場合「ペンギン」の「![]() 」キー、を押すとなると、しばらく無条件にそのキーを押し続けるきらいがある。人間の映像や魚(キスだが)の映像を見ても「
」キー、を押すとなると、しばらく無条件にそのキーを押し続けるきらいがある。人間の映像や魚(キスだが)の映像を見ても「![]() 」を押されると、少しやるせない。
」を押されると、少しやるせない。
しかし、別の単語、例えば「人間」、を習わせると、徐々にその使い分けがなされて行く。まあ、現段階では使い分けと言うよりは、全く「映像クイズ」のような状況になってしまっている訳だが。興味深いのは、人間の中でもミサトだけは「ペンギン」と認識されているらしく、何度試してみても「![]() 」ではなく「
」ではなく「![]() 」のキーを押すのだ。ミサトは怒り狂っていたが、ピンギもポコティファも迷わず「
」のキーを押すのだ。ミサトは怒り狂っていたが、ピンギもポコティファも迷わず「![]() 」と言うのだから彼女はペンギンなのだろう。
」と言うのだから彼女はペンギンなのだろう。
「絶対あんたのせいよ! あの時馬鹿な事やって以来、同列に見られてるのよ!」
「くあ! くあ! ぐあ!」
怒るミサトと楽しそうに同調するペンペン。
リツコは映像プログラムをオフにした。
「嫌なの?」
ミサトはきっとリツコを睨む。
「嫌よ。」
「前も言ったと思うけど」リツコは親友の元気な様子に微笑んだようだ。今日の彼女は機嫌が良いらしい。
「ペンギンは人間を差別しないわ。違うペンギンの1種、としか捉えていないの。あなたの場合、彼等と一緒にいる時間が長いから「仲間」、と考えられたのでしょう。」
「…でも、じゃなんで、リツコはちゃんと人間扱いなのよ。」
「知らないわよ。彼等に聞いて頂戴。」
「聞くわよ。」
「え?」
「奴等に、聞くわよ!」
「え、ええ、構わないけど…論理関係や象徴的事柄を示す単語はまだ余り教えていないから、もう少し待たないと、完成した文としては」
「駄目よ! 今すぐ!」
「そう言われても…」
ミサトはリツコを払いのけて、バルタザールの大きい方のキーボードを打ち始めた。今日はペンペンがカスパーの前だ。
「![]()
![]() (<ミサト><人間>)」
(<ミサト><人間>)」
カスパーのモニタの相手方テキストボックスに2つの単語が現われた。
「くあ。」
ペンペンは首を傾げ、キーを押す。
「![]()
![]() 」
」
「違わい!」再び「<ミサト><人間>」と入力するミサト。
「くあ。」「![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 」
」
「ちがーう!」「![]()
(<ペンペン><ペンギン><ギンギン><ペンギン><リツコ><人間><ミサト><人間>)」
「くあ。」「![]()
(<話す><ミサト><多い><食べる><ミサト><多い><ミサト><ペンギン>)」
「あんったねー!」ペンペンの肩を揺らすミサト。
「ぐあっぐあっぐあっ」
「ミサト。」ミサトはリツコの方に振り返った。
リツコは呆然と涙を流していた。
「あなた達、会話しているわ。」
リツコは「今日は良い日だ」と思った。
2週間後
20世紀初頭のドイツの馬のハンス、1940年代のチンパンジーのビキ。60年代のウォシュー、セアラ。70年代のニム・チンプスキー。90年代の、ボノボのカンジ。誰も、ここまで到達する事は出来なかった。しかもこんなに短期間で、こんなに鮮やかに…
「遺伝子操作に、私は感謝すべきなのかしら。」リツコは自分の研究室の天井を見つめた。
ミサトは昼の11時になったというのにリツコがいつものように白衣で映像サンプルの確認に来ないので、やや不思議そうに実験室の彼女を見た。
「どしたの? 今日は実験は無し?」
「ああ、午後にはあるかもしれないわ。」
リツコは研究室の端末、メルキオールを使って発話傾向のまとめ等、普段なら午後にやりそうな整理をしているようだった。
「ふーん。」ミサトは口をとがらせながら研究室を出ようとした。
「わっ」
「あっ、すいません。」ミサトが部屋からふりむくと、走り込んで来たシゲルがぶつかりかけてかわした。
「あー、びっくりしたー。」
「来たのね。」リツコは立ち上がった。
「あ、はい。あの、宅急便が…」
シゲルは段ボール箱を抱えていた。
リツコは段ボール箱をペンギン室へ持って行き、中の梱包をばらしてキーボードを取り出した。
「あれ? それ今までのペンギン用キーボード、じゃない。あれ? 新しい奴?」
「そうよ。一言で言うと、キーが増えたの。」
「へえ。確かにここんとこの彼等の言葉の覚え方は、半端じゃないからねえ。」
リツコが接続するキーボードを覗き込むミサト。
「そうね。」
ミサトは確認するように呟いた。
「ああ、確かに増えてる。」
普通のデスクトップ型端末のキーパネルの2倍程度の大きさのキーボードに、普通のパネル4個分程度の大きさのキーが大体15×6個位並んでいる。ちなみに今までのカスパー(・バルタザール)のキーボードは、キーボードそのものの大きさはこれと同じだがそこに並ぶキーが新しく来たキーボードのキーの更に4個分の大きさがあった。つまり新しいキーボードはキーの数が4倍に増えた訳だ。
「何か、簡単な図柄が増えたわね。」
「あら、鋭いわねミサト。」
リツコは普段通り、全く平坦なトーンで答えた。
「くあ?」
ミサトはやや眉を上げたが、おとなしくリツコに尋ねた。
「で? どういう事なの?」
「つまり、それだけペンギンが言葉を覚えるスピードが速いって事よ。」リツコは微笑んだ。
「彼等のボキャブラリーの吸収力に、キーの数が追い付かないの。もう、表語文字は諦めたわ。」
「何、ひょうご文字?」
「アルファベットのような表音文字でない、漢字のように単語を表わす文字の事よ。今までミサトならこれ(![]() )、ポコティファならこれ(
)、ポコティファならこれ(![]() )のように1単語1文字でやって来たでしょ。」キーを指さしながら話すリツコ。
)のように1単語1文字でやって来たでしょ。」キーを指さしながら話すリツコ。
「象形文字って事?」
「微妙に違うけど、まあそう思ってもらって構わないわ。で、それではもう文字が足りないのよ。」
「はあ。」
「だから、アルファベットを使うの。」
「アルファベットって…じゃあミサトならm、i、s、a、t、oとかこいつらが打つの?」
「彼等なら、それもさほど難しくはないと思うけど。」
リツコはさっそく近寄って来たギンギンを見ながら言った。
「もう少し、彼等にも分かりやすい方法を使うわ。ミサト。例えばあなたの場合、」「![]() 」のキーを押す。
」のキーを押す。
「この記号でしょう。」
「うん。」
「この形を分解するのよ。例えば「![]() 」という具合にね。これでmisatoの代わりになるという訳。」
」という具合にね。これでmisatoの代わりになるという訳。」
「あ、なるほど。」
「ポコティファなら、こういう感じになるわね。」「![]() 」と打つリツコ。
」と打つリツコ。
「面倒臭いわね。」苦笑いするミサト。
「まあ、ミサトとかポコティファとかよく使う名詞は表語文字に残しておいたから、実際には今までどうり「![]() 」、「
」、「![]() 」で構わないわ。新しい単語の時に、これを使うのね。」
」で構わないわ。新しい単語の時に、これを使うのね。」
「ほぉー。」ミサトは半分感心して半分呆れた。
「良く、考え付くわね、そんな事。」
リツコは特に嫌味には受け取らなかったようだった。
「別に。…彼等の学習能力には、かなわないわよ。」
「くあ、くあ。」
「ギンギン。またリツコさんが面倒臭い物を作って、お前達の仕事が増えるよー。」
「くああ。」ギンギンはミサトが頭を撫でると気持ち良さそうに頭を傾けた。
その日はペンペンが元気で、結構広いペンギン室の中をトタトタ駆け回っていた。
「こら! 待ちなさい!」ミサトはペンペンを追いかける。顔に余裕がない。
「お前達は足をチェックしないといけないんだから! こら、待て!」
「くあ、ぐあ、くあ」
ミサトに捕まり、足をバタバタさせるペンペン。
ミサトは彼の足を押さえ付けて、傷が無いかチェックする。
「もうちょっと我慢しなさい。あんた達の足に傷があると、アスペロロルス病になって体が腐っちゃうらしいのよ。」
「…アスペルギロシス病。」
ミサトは訂正しながらペンギン室に来たリツコを見て数秒黙った。
「そう、それ。アスペルロロス病。」
再び足をチェックする。
「問題無いわね。大丈夫、アスペロルロス病にかかる心配は無いわ。」ペンペンを解放するミサト。
ペンペンはプールへと逃げ出した。
「今日は?」
「そうね。いつも通りの単語定着だけど。」
端末の電源を入れるリツコ。
「この子達、この実験どう思ってるのかな?」
「嫌がってはいないわよ。餌をあげなくても、積極的に発話しているわ。」
「まあ、そうだけど…」
「「まあ」? あなたそれがどれだけ凄い事か…」
「分かった、分かった、分かってる。…でも、どうなんだろう。喜んでやっているのかな。」
リツコは軽く汗を拭うミサトに微笑んだ。
「質問してみたら? 今なら、充分可能と思うわ。」
ミサトはバルタザールのキーボードで悪戦苦闘していた。良くしたもので彼女達が端末の前に居ると、ペンペンかギンギンかどちらかが当然のような顔をしてやって来る。今日は、ペンペンが今プールに退避しているので来たのはギンギンだ。
「![]()
(<始める><話す><あなた><と><どう><思う><あなた><終わる>)
(「話す事について、どう思う?」)」
ギンギンは首を振り、しばらく考えるような素ぶりを見せた。
「![]() 」
」
「嬉しい?」ミサトは呟いた。
「<か?><嬉しい>」ミサトはキーを打つ。
「くぉー。」ギンギンはミサトとリツコを見比べる。
「<でない><嬉しい>」
「あのねえ。」顔のゆるむミサト。
ギンギンはふいに思い付いたかのようにカチカチとキーを押しだした。
「<始める><思う><私><見る><話す><私><見る><嬉しい><考える><終わる>」
「えーと? 「私は思う、私が話す事は、考える嬉しい」?」解読するミサト。
「何、これ? こんな単語あった?」ギンギンがしきりに打っている「![]() (<嬉しい><考える>)」という記号を指すミサト。
(<嬉しい><考える>)」という記号を指すミサト。
リツコは「まだ、分からないの」と言いたげに笑った。
「ピンギは文法にうるさいから、この場所で<と>抜きに動詞を重ねる事はありえないわ。つまり後ろは前を形容する形容詞。「考えて、知的に嬉しい」という事よ。」
「くあ。」頷くギンギン。
「え?」
「つまり、「楽しい」という事よ。」
「くあ。」カスパーとバルタザールの立体画面には、たくさんの「![]() 」が並んでいた。
」が並んでいた。
つづく
フラン研さんの『海辺の生活』第三話、公開です。
ペンペン・ギンギン・・・か、賢い(^^)/
機械的にキーを押すことに始まり、
意味を理解し、
文を作り・・・
会話を始める。
記録映画・ドキュメンタリー的な面白さも堪能させていただきました(^^)
実に![]() !
!
↑ この絵文字がいい感じ!!
むっちゃ楽しい(^^)
![]() を
を![]() と打ち込むのはハングルキーボード?! ←違ってました?(^^;
と打ち込むのはハングルキーボード?! ←違ってました?(^^;
この絵文字を表示するためのGIFファイルが14個。
投稿全ファイル869の内、フラン研さん1人で97ファイル!
投稿ファイル容量12.3MBの内、1.32MB!!!
フラン研さんは”10%の男”ですね(^^)
・・・どこぞの銅取引を思い出す・・・
さあ、訪問者の皆さん!
次々新アイデアを発揮するフラン研さんに感想メールを送りましょう!