どちらかと言うと人付き合いが得意なほうでない彼は、クラスに特に友人が居る訳でもなく、彼女や、幼馴染が居る訳でもない。昼休みは、彼はいつもここで何かを読んでいた。
別に彼は文学少年、ではなかった。彼は好きで本を読んでいるのではなく、ただ時間を潰しているのだ。ちゃんと書いてある内容を頭に入れたりはしない、ただ字を眺めてページをめくっているだけだった。
この日、彼は新聞の昔の年鑑を机に備え付けられたノートパソコンで見ていた。前世紀の、更に前の時代の、その日その日の事件が画面に現われる。15年前、ある国の宇宙ステーションが故障、衛星軌道から落下。大半は大気圏突入時に燃え尽きたが、一部の欠片が南極地表に到達。俗に「セカンド・インパクト」と呼ばれる大爆発を引き起こし、水位は上昇、世界はカオスの海に巻き込まれた。
これが、誰かの作為なら、1本面白い小説が書けるところだろうが、残念な事にこれは全くの偶然の所産だった。
昔は、今より世界が大きかったのだ。
少年は空想した。日本に「第2」や「新」の付かない東京が存在した時代。車がガソリンで動いていた時代。韓国が2つで、中国が1つだった時代。中近東に砂漠が、アマゾンには森が有って、カイロはまだ、ただのエジプトの首都で…日本人の名前に漢字が使われていた時代。
ここから海も、もうちょっと向こうに有ったのだろう。
彼は昔の省略された字体の漢字で書かれた新聞を、無表情に眺めていた。
「碇君。」
シンジは顔を上げた。
彼はこういった演技力には自信を持っていた。事実、ヒカリはシンジの返事に不自然な印象を受けた様子は無く、用件を伝えだした。
「あの、碇君。綾波さん…って、知ってるでしょ。」
「ああ、うん。」
未だにクラスの全員の顔と名前が一致しないようなシンジだが、そんな中でもある程度言葉を交わすのは、この学級委員長の洞木ヒカリ位であった。
そうは言っても別にシンジとヒカリが特に仲が良いという事ではない。それどころか、口や顔にはもちろん出さないがヒカリは特にシンジに対して良い印象は持っていなかった。特に悪い人ではないのだろうけど、何かひねくれていて、周りの人達との協調性があまり無さそう。暗くて、いつも図書室にいる静かな人。大体こんな評価である。別に嫌いという事ではない、そこまでの関心は無いのだ。ただ事務的な連絡などをする機会が多いし、ヒカリは人を「差別」したくはなかったので彼と話す事を厭わない、というだけの事であった。
一方シンジも彼女の感情は何となく感じ取っていたので、いくらヒカリ位しか学校で話す相手がいないと言っても、彼女に対して「変な勘違い」を起こすような事は無かった。
シンジは、ヒカリ以外のクラスの人間ではっきり顔も名前も声も分かるのは彼女、綾波レイ位だった。
「綾波さんが、どうかしたの。」
「う、うん。碇君、週番でしょ。で、この2ヵ月、溜まったプリントがあるんだけど、彼女の所に届けてくれないかな。」
「ああ…良いけど…」
「ごめんなさいね、嫌な仕事押しつけちゃって。」ヒカリは申し訳なさそうに謝る。
この週、もう一人の週番は彼女だ。
「うん、別に良いよ。委員長は、色々大変なんだし。」
2人の目が合った。
「うん…」
「今は、調子はどうなの?」優しい顔を演技してシンジが尋ねる。
「うん、全然大丈夫、元気そのものよ。食欲が有り余って困っちゃってるの。」
「へえ、そうなんだ。」
シンジは「早く良くなると良いね」という言葉を、言いかけて飲み込んだ。言って状況が良くなる類いの事ではないだろう、と彼は思った。
5時間目を告げるチャイムが鳴った。
「あ。」
「いけない!」
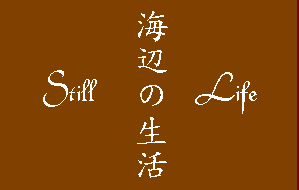
2ヵ月前
理由は、良く分からなかった。
いや、後から理由を考えるなら、まず彼女の見た目が他の生徒と異なっていて、また彼女の態度も無愛想だったから、という事になるのだろうが。
とにかく新クラスになってからすぐに、彼女は一部の生徒からは注目され、大部分の生徒からは見て見ぬふりをされていた。
太白区立仙南中学校2年A組の綾波レイは、自分の靴を脱ぎ、下駄箱から上履きを取ろうとした。
上履きには土が詰まっていた。
レイは赤い瞳でその上履きをしばらく見つめ、手を止めた。1時間目の始まりまで時間が無い。仕方がないので彼女はソックスのままで教室に入る事にした。
教室に入ると、クラスの生徒達は一瞬こちらを見たようだったが、皆気にする様子もなく互いに話をしているようだ。
レイは窓際の自分の机を見た。
机の上にはネズミの死体、引き出しの中にはやはり土。
まあ、少なくとも昨日の使用済みコンドームよりはいくぶん増しな気がする。
レイは教科書を全部持って帰っていて良かったと思った。本来机の上にあるべき端末は4日前に使用不能になっていたので、彼女が片付けていた。30近く机の並ぶこのクラスで彼女の机の上にだけ端末が無い。
椅子に座ろうとして、彼女は何か光る物に気付いた。
椅子には20個位の画鋲が瞬間接着剤で付けられていた。
レイは椅子の画鋲を取ろうとしてみたが、完全に付いていて取れそうにないのを見て諦めた。周囲の生徒達はクスクスと笑ったりもしない。あくまでこちらを見ずに、雑談を続けようと努力している。
彼女はネズミの死体をつかみ、窓から投げ捨てた。
「ちょっと、綾波さん。」
さっきからレイの様子を眺めていた、後ろを結んだ3つ編みの女子が咎めるように声をかけた。
「あなた、何て物を窓から投げているの!」
レイは全く表情を見せず、ただ赤い瞳をそのおでこの広い女子に向けた。
「あなたがやったの?」
「何馬鹿な事言ってるの。綾波さん、自分の机が汚ないのを人のせいにしないでくれる?」
その女子の隣に立っていたセミロングで小柄の、腕を組んだ女子が加勢する。
「そうよ。ナミがそんな事する訳ないでしょ。あんたなんか、相手にもしてないわよ。」
「そう。」
レイは、取り敢えず椅子をどうするかを考えていた。
「そう、じゃないわよ。どうするつもりなの。こんなに汚して。それに、窓からゴミを投げて許されると思ってるの。いますぐ取ってきなさい。」
レイは顔を向けた。
「何、その反抗的な目は!」ナミはレイの襟を取った。
「止めてやれよ、それ位で。」レイの横、ナミの後ろで2人を眺めていた長髪の男子が言った。
「ヨシモト君! だけど…」
「まあまあ。所詮妖怪変化に人間の常識は通用しないって。」ヨシモトは人に威圧感を与えることを計算した微妙に短い距離感で2人の前に立った。
「ヨシモト君の言う事にも、一理有るかもね。人間の言葉で話し掛けたのがまずかったんじゃない?」ナミの隣の女子が面白そうに合槌を打つ。
ナミはやれやれ、と言うかのように両手をあげた。
「ま、それもそうね。兎の生まれ変わりさんに所詮何を言っても無意味だわ。」
レイはほんの少し目を細めてヨシモトとナミを見た。
「私は、人間よ。」
ナミはレイの机に唾をはいた。
「あれ? 今何か聞こえた?」
「さあ…俺達人間の言葉しか分からないからなあ。」レイの肩をポン、と押すヨシモト。ふいを突かれレイはよろけかけた。
「そうよねえ。」ガンッ、とナミはレイの机を蹴った。
2年A組の担任教師が入って来た。
彼は顔をしかめた。
「こら、綾波、毎日毎日お前は何をやっている! 早く片付けなさい。返事は!」
レイは生徒に向けるより遥かに冷淡な目でその男性教師を見た。冷淡などころか、彼女の赤い瞳には憎悪と軽蔑の炎が宿っている。
「返事は。」
そう教師には見えた。
「返事は!」
教師はレイの頬を打った。
こんな日が2週間続いていた。3日後、彼女は学校に来なくなった。
こんなの読みたいって思う生徒がいるのかな…
シンジは少し首を傾げた。
緊急連絡簿の住所によると、彼女の家はこの辺りらしいのだ。3-5-27、3-5-27と…
「ここ、かな?」
結構綺麗なアパートだった。「敷金・礼金ゼロ」という無粋な看板がぶら下がっているのを別にすれば。
でも、何か建て付け悪そうだな。
グレーのそのアパートは、趣味は悪くないが、シンジは余り良い印象を持たなかった。ここは若者の独身向けといった風情なのだ。中学生が普通いそうな住所ではない。
彼は「コーポ中田5」の3号室に表札を見付けた。ペンの手書き文字で「綾波」と書いてあった。
ドアの新聞受けには、新聞のサンプルやDM、通販のカタログがこれ以上入らないほど詰め込まれて、そのまま土埃を被っていた。
シンジは少し眉を潜め、チャイムを押した。
「綾波さん。」
何の音もしない。
もう1度押す。「綾波さん?」
やはり、何の反応も無い。埒が明かないと思ったシンジはドアノブに手をかけた。
ドアは当然閉まっていた。
「何だよ、折角届けに来てやったのに。…まあ、どうせこんなのいらないだろうけどさ。」愚痴をこぼすシンジ。シンジはレイのワラ半紙も入っている自分の膨れきった鞄をドサ、と自転車のカゴに投げた。
「…走ろ。」シンジは呟いた。
でも、やっぱり、人に迷惑を掛けるのはあんまり良くない気がする。
シンジは遠慮がちに頭の中で提言した。
シンジの場合、何かあった、あるいは特別無くても何となく「溜まった」時は見晴らしの良い道をキコキコ漕いで、海沿いの倉庫のような建物に行くのが常だった。
自転車を漕ぐ道では、たまに何かの営業のバンや大きなトラックがスピードを上げて走って、自分をかすめて行く。シンジは敢えて道の右側を走っていた。この方が精神的には安心感があるのだ。
背後から音もなく車に来られるのは、あまりぞっとする物ではない。ガードレール位付けて欲しい。
といつもの事を思いながら、シンジはヒットチャートで最近よく耳にする女性歌手の歌の鼻歌を歌っていた。
まあ、色々あるけど、この垢抜けない景色はいつも同じだ。
シンジは並木道を横手に見ながら、倉庫に向かった。
シゲルは両手をドン、と机に置いて立ち上がった。
「す、凄過ぎっすよそれ! 今度何か質問しても良いっすか!」
「だあめ。」
得意満面のミサトはつくづく嬉しそうに返事をする。
「い、良いじゃないですか少し位!」
「んー、私としては駄目とは言いたくないんだけど、赤木博士が結構うるさいのよー。その、何て言うの、被験者の心理状況に影響が出るとか何とか…」
イカの燻製(の一きれのみ)を右手に持ち、左手はテーブルの上でクネクネ遊ばせながら、出任せを言うミサト。
「そ、そうっすか…」
「お前、ペンギンに何か質問したい事あるのかよ。」
マコトは隣で力無く座る長髪男に聞いた。
「あ、ああ。やっぱり、今の環境破壊についてどう思うか、とか、人間の他の生物種への傲慢さについてどう思うか、とか…あ、何で吹き出すんですか!」
マコトもミサトも我慢できずに吹き出したのだが、彼が敬語で言った所を見ると最後の言葉はミサトに向けられた言葉なのだろう。マヤも苦笑いしている。
「い、いや、ごめんなさい。真面目な青葉君らしい質問だな、と思って。でも、「環境」も「傲慢」も、多分彼等のボキャブラリーに無かったと思うけど…まあ、言い換えは出来るかもしれないけどね。両方とも彼等には、今の所まだ高度過ぎる質問ね。」
「そうっすか…」シゲルはつくづく落ち込んでいるような素ぶりを見せた。まあ、半ばふざけている。
「でも、あの子達の言葉は結構凄いのよ。」ミサトは少し声のトーンを上げた。
「何か独自の文法とかがあって…リ、赤木博士は「ホッパリッシュ」って呼んでるけど。つまりペンギン語ね。2匹の会話用にカスパーの…ああ、ペンギン用の端末の事ね、のキーボードが2個になってから、あの子達とリツコの間で急速に整備された言葉なの。そうね、例えば…」
ミサトはマヤをピシッと指した。
「飲む、マヤ、お茶。」
マヤはビクッとして動きを止めた。
「は、はい。」
「みたいに、えっと、動詞、主語、述語の順番で言うのよ。」
「動詞、主語、目的語じゃないんですか?」自信無さ気に聞くマコト。
「あれ、そうだっけ?」
「はい、多分…」
「じゃあ、それで良いわ。」
「はあ…」マコトは見る人が見ると、少し照れ臭そうにしているのが分かる。
「とか、そうだな、後、<でない>を2度繰り返すと…あ、文頭に<でない>が来ると否定文なんだけどね。それが2度あると、疑問文になるのよ。でない、でない、飲む、マヤ、お茶。」
「え、ええと、飲む、私、お茶。」
「そう、そういう感じ。」
「呪文みたいですね。」
シゲルの呟きと共に1時の時報が鳴った。各スタッフは控室を後にした。
シンジは300円を支払って入館した。
彼はここで他の客を見た事が殆ど無かった。自分は他人が苦手なのでその方が静かで良いといえば良いのだが、これだけ人が居なくても潰れる事の無いこの水族館は少し不思議だ。たまに、近くの幼稚園の子供達が「遠足」に来ていたりすると大変な事になっているのだが。
今日は、有難い事にいつも通りの静かな日だった。
シンジは壁際の水槽を眺めていた。大きいが、せいぜい家庭用の水槽だ。
何度名前を見ても覚えられない長いカタカナの名前と、ラテン語の学名と、体長と原産地が水槽下の白いプレートに書かれている。
シンジはそれこそやろうと思えば1時間でも2時間でもこうやって無心になって、悪く言えばポカンと口を開けて、水槽を眺め続ける事が出来た。
別に哲学的な意味とか、専門的な興味がある訳ではない。単に魚を見るのが好きなのだ。
ゲームをしたりアニメを見たりする時にまずその事の意味を考えてからテレビをつけたりはしない。それと多分同じだ。
だから、シンジは「溜まった」時は300円払ってここに来ていた。
そして、10日に一遍位の割合で顔を見せていると、ただでさえ客の少ないこの水族館では職員と顔見知りになるのは自然の成り行きだった。
「お、シンジ君、楽しく青春してる?」
「あ、こんにちは。」
バケツを持ちながら片手で手を振るのはミサトさん、ここの職員の中でも指折りの人あたりの良い職員だ。ただ、それだけにシンジは少しうるささも感じるのだが。
シンジの声に義務感の冷たさを感じたのか、彼女は「んもう、相変わらずつれないわねえ。」と言いながら職員用のドアの向こうに消えた。
と思ったら、背中を反って顔だけ出して来た。どうやってドアを開けてるんだろう。
「あ、そういえば。今淡水魚漕の方に、キュウートな女の子が座ってるわよ?
最近よく来てるんだけど。」
「はあ?」思わず地声を出すシンジ。
「結構シンちゃんの好みのタイプかもよん?」
ミサトはニターっと目を細めて言った。
「な、何でそうなるんですか!」駄目だ。やっぱりこの人と話してると、どうも向こうのペースに乗せられてしまう。
「なーに照れちゃってんだか。先輩の常連さんとして、挨拶位でもしてあげたら?」
シンジはそっぽを向いた。
「何でですか。常連さんって、いつから水族館はスナックになったんですか。」
「そう言わない。…それに、何かあの子、ちょっち寂しそうなのよ。」ミサトの声の変化にシンジは顔を上げた。
シンジが見た時には、既にミサトはいつもの「明るいお姉さん」の表情に戻っていた。
「会ってみなさいよ。お兄さん、損はさせまへんでぇ!」
バタン。
今度こそ、ミサトの顔はドアの向こうに消えた。
シンジは5分位、まだそこでじっとしていた。それから腰を上げて、淡水魚漕に向かった。別に会うわけではなくて、こっちの水槽が見飽きただけだ、多分。
淡水魚漕と言うのは、ごく簡単に言ってしまうと「向こうの部屋」の事である。ただしそれなりに一部屋一部屋が大きいので、移動に少しくらいは時間もかかる。水槽達の間を抜けて、少し重い足取りでシンジは淡水魚漕の部屋の入り口に来た。
そこで彼は綾波レイを見た。
「あ、綾波、さん。」シンジは驚いて呟いた。
レイはこちらに振り向いた。生気の無い白い肌に、充血したような赤い瞳。白髪のような髪で全くの無表情。確かに妖怪変化だ。
シンジは、「でも、公平な目で見ると、実は彼女は美人なのかもしれない」とも少し思った。もし彼女が明るい性格だったら、いじめられずにクラスの人気者になっていたのかもしれない。
「あ、あの、僕、碇、碇シンジって言うんだ。綾波さんと、同じ、クラス、の。」
シンジは「演技に失敗した」と思った。
レイは全く無関心そうに、再び自分の目の前の水槽を見ていた。近くの休息所の椅子を持って来て、ちょこんと座って見ている。
シンジはレイの見ている水槽の魚を見た。
小さな魚が、6匹位泳ぎ回っていた。
「「スケルトンテトラ」。」シンジはプレートの名前を読み上げた。
再びレイは、ちら、とシンジの顔を見た。そして表情を変えることなく、水槽の前に顔を戻した。
「あ、あの。きれいな、魚だね。」
「そう?」
シンジはレイからの答えを全く期待していなかったので正直かなり驚いた。
「うん。」
「新世紀の、新種。」こうしていると、レイは結構綺麗な声をしている。…好意的に見れば、顔の造りだって綺麗だと言える。まあ、愛想に欠けるのは事実だけど。
「そ、そうなんだ。」
「そう。…私と、同じ。」
シンジは顔を上げた。
「へ? 何が?」
「何でもないわ。」
シンジは少しむっとした。
「あ、そうだ。プリントがあるんだ。今日頼まれたんだよ。綾波さんに渡すように。」思い出して、シンジは鞄からがそごそ取り出した。
「いらないわ。」レイは見向きもしない。
「…ああ。」思わず納得するシンジ。
「…でも、一応見るだけ見てみてよ。いらなかったら後で捨てればいいしさ。」言いながら、シンジはレイの部屋のドアの溜まった新聞類を思い出していた。およそ自分のやっている事は実りが無さそうだ。
…綾波さんは相変わらず小さな魚達を見ている。本当に僕の話を聞いているのだろうか?
「あの…そう、委員長に頼まれちゃってさ。どうしても渡してくれ、って。」
「委員長?」レイは振り向いた。
「そう、学級委員長の洞木さん。って言っても、覚えてないか…」
「知っているわ。」レイはシンジからワラ半紙の束を引ったくるように取った。
そしてレイは何を話す事もなく、水槽の魚を眺めている。
シンジは「悪いけど、やっぱりこの子はいじめられる素質があるのかもしれない」等と考えていた。
シンジはその日はそれで帰った。
4日後
シンジはちょっと、ムシャクシャしていた。体育の時間に体育教師に「ボサボサするな」と怒られたのだ。
別に、特に他の生徒の注目を悪い意味で集めた訳ではないし、教師が自分に注意した事もある程度理解できる内容だった。
だから、ちょっとだけ、ムシャクシャしていた。
白い曇り空の中、シンジは自転車を走らせていた。
畑の中を貫く一本線。たまに車やトラクターが通る道。
びゅんびゅんびゅんと漕ぐが、対向車が来ると自分は無意識にスピードを落とす。シンジはそんな事にすら何だか腹が立った。
その日、シンジは意外な目標を前方に発見した。
シンジは急停車した。
「綾波さん。」
「何。」
この間と同じ黒のワンピースのレイは驚く様子もなく、立ち止まり、学校指定のシャツのシンジを見た。
「あの、もしかして、水族館?」
レイはコクン、と頷いた。
「まさか、歩いて行ってるの? あ、綾波さんの家、中田の方だよね?」
「ええ。でも、2時間もかからないわ。」淡々と答えるレイ。
「2時間も歩いてるの?」
大声を出すシンジ。レイは少し驚いたようだった。
「…ええ。歩くの、遅いから。」
シンジはクス、と笑った。
「いや、そういう意味じゃ、ないんだよ。」
シンジは自分の自転車の後輪上の荷物台を叩いた。
「乗りなよ。」
「え?」
「ここに。僕も行こうと思ってたんだ、水族館。や、まあ、ちょっと危ないかもしれないけどさ。」シンジは演技でなく微笑んだ。
「良くないわ。」
全く無表情に、レイはシンジから顔を背けた。
「私と一緒の所をクラスの他の人に見られたら、あなたがいじめられる。」
レイはシンジを置いて、さっさと歩きだした。
「ま、待ってよ。」シンジはレイの手をつかんだ。
レイは少しむっとしたような顔で振り向いた。
「そ、そんな悲しい事言うなよ。僕は綾波さんを乗せたいから、そう言ったんだよ。そんな、後で何言われたって良いじゃないか。自転車乗った位で、何も言われる筋合なんて無いよ。まだここから3・4キロあるよ?
歩いていったら大変だよ? 乗ろうよ。」
レイは、シンジの熱を帯びた調子に少し目を見開いたようだった。どうやら驚いているらしい。
「でも、」
「良いじゃないか! 僕は乗って欲しいんだ! 綾波さんは、別に構わないんだろ?」
「え、ええ、でも」
「じゃあ速く乗って!」
レイは強い口調に思わず従って、荷物台の上に横向きに座った。シンジは自転車が重くなった事を確認するとのたのたと漕ぎだした。
最初はスピードが遅かったが、それでも自転車は段々加速を付けて行った。
シンジは自分のお尻のあたりにレイの荷台をつかむ手があたって、何だかくすぐったかった。そのくすぐったい感触は、何故だか自分の胸に伝わる感じがした。…でも、何で胸なんだろう?
脳じゃないんだよな。感じているのは脳のはずなのに。
「綾波さんは、いつも歩いて水族館に行ってるの?」
シンジは大声で聞いた。
返事がない。
シンジはちら、とレイを見ると、彼女は必死に「うん、うん」と頷いていた。どうやら答える声が小さくて聞こえなかったらしい。
綾波さんって、やっぱり意外と可愛い。
シンジは思った。
同時に自分を客観的に突き放して見るもう一人の自分は、「お前はいじめられっ子を少し助けて良い気になっているだけだ。」と冷淡に言っている。
お前は綾波さんを弱い存在だと考えている。だから自分が守る、いや、自分の物に出来ると考えているんだ。大体仮に綾波さんがまたいじめられるのを見たとして、お前に止める自信はあるのか? 無いだろ。お前は少しも彼女を助けていないんだぞ。
そうだよ。お前は、彼女が学校に居た時にどうしてたんだ。一度でも、目の前で起こっているいじめを止めようとした事があったか。
それどころか、無言で見過ごして、事実上彼女へのいじめに加担していたじゃないか。
お前は加害者だ。悪質なね。しかも彼女に一言も謝罪をしていない。お前は彼女を乗せる資格なんて、無い。
シンジは自分に反論できなかった。冷淡な彼の指摘する言葉は全て正論で、反論の余地が全く無かった。
今だってそうさ。心のどこかで綾波さんはいじめられても仕方の無い存在だと思っている。綾波さんにも、ある程度責任があると考えている。被害者を罪人扱いしているんだ。大体、「意外と」可愛いって、何だ。思いっきり、他の人と差を付けた表現じゃないか。謝るべき相手を、お前は未だに見下だしているんだよ。お前は…
その時、ふとシンジは後ろで何か声が聞こえた気がした。
シンジは「急ブレーキ」にならないぎりぎりの範囲の制動力で自転車を止めた。後ろを振り返る。
「何? 何か言った?」
レイは、横を向いていた。シンジの声に反応して、少し目を開き、少し顔が赤くなったように見えた。
「あの…あり、が、とう。」
「………どういたしまして。」
シンジは、はっきりと顔を赤らめて、自転車を急発進で漕ぎだした。
リツコとペンペンは鼻歌を歌いながら水質チェックをしているミサトを不思議そうに見た。
<楽しい事とは、何なのか。>
「くぅー。」
<分からないわ。少し気持ち悪いわね。>
<物事が分からないというのは、気持ちが悪い物だ。>
「そういうつもりで言ったんじゃ、ないのよ。」リツコは微笑む。
<もしかしたら、男女の事かもしれないわ。>
「くあ。」
<繁殖の事か。>
<それも含むわ。でも、「仲良し」の事ね。>
「ぐああ。」
<男女の「仲良し」が楽しいのか。>
<そうね。人間はそう考えるわ。>
<人間は、変なペンギンだ。>
<人間はペンギンではないわ。>
「くあ。」
「<でない><記号>![]() <今><ペンペン><と><ギンギン><終わる><記号>
<今><ペンペン><と><ギンギン><終わる><記号>![]() <今><ペンペン><と><ギンギン><と><リツコ><と><ミサト><終わる><同じ><それ><全て>(今の
<今><ペンペン><と><ギンギン><と><リツコ><と><ミサト><終わる><同じ><それ><全て>(今の![]() はペンギンという意味ではなく、私もギンギンもリツコもミサトも全員の事、つまり動物という意味だ。)」
はペンギンという意味ではなく、私もギンギンもリツコもミサトも全員の事、つまり動物という意味だ。)」
「そういう分かりにくい事をしないの。」
<その意味の![]() は、別の記号にするわ。>
は、別の記号にするわ。>
<どういう記号にするのか。>
リツコが新しい単語定着に没頭しだした頃、ミサトはニタニタ笑いながらペンギン室を後にし、いつもの淡水魚漕の裏口に顔を出した。
「よっ、マヤちゃん。元気。」
「それ、40分前も聞きました…」
「固い事言わない。あー、2人はやっぱり青春してるねえ。」
水槽越しの斜め向こうに客の影がぼんやり見える。心底嬉しそうなミサトに呆れる淡水魚担当者。
「可愛いわねえ。マヤちゃんは、一緒に魚を見るような男の子はいないのかしらん?」
「は、わ、私ですか?」
慌てるマヤ。
「いや、今の所、別に…」目が何故か寄っている。
「おおう、照れちゃって、コノコノ!」ここ数日、ミサトは何か1タスク終えると必ず淡水魚漕に文字通り「お邪魔」して、こんな事をやっていた。
「でも本当、毎日よく来ますね、あの2人。」
「で、ずーっと椅子に座って見てるのよね。で、話を聞くとさ…」
「盗み聞きまで、してたんですか?」目が細くなるマヤ。
「ち、違うわよ! そうじゃなくて、通りがかりとかに聞こえた分での話なんだけどさ、いっつもシンジ君がレイちゃんに話し掛けてるのよね。」
「レイちゃんは、答えないんですか?」意外と話に乗るマヤ。
「うーん、そんなにはね。でも、嫌がってるようでもないから、」
「仲が悪いって事でも、ないんですね。」
「うん。」
マヤは、休めていた手を動かしだした。水槽に薬品を注入する仕事だ。
「でも、レイちゃんって不思議な見た目ですよね。神秘的というか…」
「ああ、彼女、多分アルビノね。」
「アルビノ?」
「白子の事よ。」
「白子? あの、魚の…」
「いや、そうじゃないの、それは全然違うわ。」慌てて遮るミサト。
「そうじゃなくて、その、生まれつき色素の欠落した子なのよ。良くトラとか馬とかで聞かない?
真っ白い奴。」
「ああ…」
「それと同じ…って言うのも言い方として何だけど、まあそういう事ね。」
「じゃあ髪を染めたり、コンタクトを入れたりしたんじゃないんですね。」
「う、うん、多分ね。」
「松本とかの方の流行なんだとばかり思ってました…」しきりに納得しながらピペットで薬を注入するマヤ。
「あ、あははは…」
ミサトはマヤに時々近寄りがたいものを感じていた。
その日もシンジとレイは淡水魚をずっと眺めていた。
よく見ると、本当によく見ると、レイにもちゃんと表情がある事が最近のシンジには分かりつつあった。ただそれがとても微妙、あるいは抑圧されているので、中々ぱっと見に分かりにくいだけなのだ。
そして、魚を見ているレイは、シンジの解釈によると、どうやら微笑んでいるらしかった。
レイはふとシンジの方を見た。
「何。」
「あ、ううん、別に、何でもないよ。何でも。」パタパタと手を振るシンジ。
「そう。」
レイは視線を戻した。
「綾波ってさ…その魚、好きなんだね。」
「ええ。」
ぱっと見には全く無表情だが、シンジにははっきりレイが笑ったのが分かった。
「スケルトンテトラ…何で、好きなの?」
「私と同じなの。」
「何が?」
「…」
前にも何回か同じ事を質問した事があった。シンジも、答えはそれほど期待していなかった。
「色が。」
「色?」
「色が無いの。透明でしょ、彼等。」
「あ、うん。」
「私も無いから。」
シンジは何と返事をすればいいのか、全く分からなかった。
「そう…」
「そう。」
シンジの目には、レイの表情は曇っているように思われた。
「でも、それって、」
「御二人さん、悪いわね。そろそろ看板なのよ。」部屋の入り口の方から、いつもの作業服のミサトの脳天気な声が聞こえて来た。
「え、あ、もう5時だ。」
自分の腕時計を確認するシンジ。
「…ごめんね。実質1時間しか、見れなくて。綾波は、もっと早くから本当は見れるのに、わざわざ僕の時間にあわせてもらって。」
「構わないわ。」レイは立ち上がった。
「碇君と話すの、楽しいから。」
レイはぱっと見に見ても笑っていた。
シンジはとても嬉しかった。
2人は、水族館の駐車場に出ていた。初夏の夕刻。海辺のひんやりした風が気持ち良い。
「ねえ、綾波、もうちょっとだけ、付き合って貰っていいかな。」
「何。」
「海、行かない?」
「海?」
レイは、少し怪訝そうな顔をした。
「うん。」
「碇君は、海に用事があるの。」
「いや、別に用事は特に無いんだけど…ちょっと、行きたいなと思って。駄目かな。」
「構わないわ。」
レイは荷物台に飛び乗った。
そもそも水族館が事実上「海沿い」にある訳で、海そのものは徒歩でも数分で着くのだが、シンジは無粋なテトラポッドを特に見たかった訳では無かったので、ここから2キロ程南下した小塚原の浜辺に行く事にした。まあ、そこも浜辺という程の浜辺ではないのだが、一応「海水浴場」だ。
シンジは正直、レイを後ろに乗せて自転車を漕ぐのがスリリングな「背徳の逃避行」みたいで結構気に入っていた。と同時にそんな事を考える自分がとても醜くも思えた。
シンジは自転車を漕ぎながら、決して大きくはない声で言った。
「ねえ。綾波は、自分が白い事が、気になるかもしれないし、それで嫌な思いも実際してるかもしれないけどさ。僕は、その、綺麗だと思うよ。凄く、綾波の事。その…変な事言ってるね。」
シンジの声はどんどん小さくなっていった。シンジは後ろを振り返らずに漕いだ。
小塚原に近付くと、それまで殆ど見えていなかった海がいきなり左手に広がった。
シンジは突然現われる(つまりその砂浜沿いにしか無い)歩道のスペースに自転車をとめた。
2人はコンクリートの5段ほどの階段を降り、10メートルは無いであろう幅の砂浜に降りた。
かなり向こうで犬の散歩をしている人がいる以外は誰もいないのは、かなり、その、何と言うか、好都合であった。いや、別に、その、そんな事が、ある訳はないけれど。
シンジは波打ち際から遠く離れた、少なくとも5メートルは離れた場所に腰を降ろした。
レイもすぐ隣に座った。
シンジは唾を飲み込んだ。
レイの今の顔の表情は、シンジには判読不能だった。
「あの、さあ。」
「何。」
「2人で話してると、楽しいよね。」
「ええ。」
「僕の話、聞いてくれるかな。」
「何。」
「…うん。」
モノトーンな景色だな、とシンジは思った。夕陽が輝く景色なら、もっとロマンチックだったのに。
「今、僕…」
シンジはレイの顔を見た。
「好きな人がいるんだ。」
良く分からないが、レイは穏やかな微笑を見せたように見えた。
「そう。」
「うん。その、とても、可愛くて、心も綺麗な、人だと思う。」
「良かったわね。」レイははっきりと微笑んでいた。
「あ、あの、綾波は…綾波は、今好きな人とかいるの。」
聞かれた瞬間、レイは目を見開き、ほんの少し口を開けた。それから視線をさまよわせ、どう答えるべきか言葉を熟孝するかのようだった。
レイはしばらく瞬きをした。
「ええ。」
「…そう…」シンジの声は、何故か気落ちしていた。
「碇君。」レイの声はやや硬かった。
「何?」
「碇君が人を好きになるというのは、とても綺麗な心だと思う。」
「あ、ありがとう…」きょとんとするシンジ。
「でも、私が人を好きになるのは、決して綺麗な心では」
「駄目だよ!」驚いたシンジはレイの言葉を遮って叫んだ。
「駄目だよ綾波! どうしてそう自分を卑下するんだよ! 綾波はとても良い子じゃないか!
綾波より綺麗な心の人なんて、何処にもいないじゃないか! どうして、そう…なるんだよ!
綾波は、綾波は何にも悪くないじゃないか! 綾波は何も悪くないんだよ! 綾波は、綺麗だよ!」
シンジはレイの肩を揺らした。はっきり驚くレイ。
「碇君?」
「醜いのは、醜いのは僕だ! 綾波がいじめられても、見て見ぬ振りをして、その癖今こうやって、2人きりになって君に」
「碇君、大丈夫? 碇君?」
不安気に聞くレイ。
シンジは再びレイに顔を向けた。
「僕は、君が好きだ。」
シンジはレイに言った。
つづく
フラン研さんの『海辺の生活』第四話、公開です。
ペンペン、えらい流暢に意志疎通できるようになっていますね(^^)
水族館でのレイとシンジの時間。
チョットちょっと近づいていっていますね。
表に薄い表情を読みとれるほどに、
中にある感情を感じられるほどに。
ここには正義感のトウジはいないんですね・・
アスカがいないことよりも今回は流石にそっちの方が気になってしまう(^^;
ヒカリもそれ程ですし・・
これが本当かなぁ (;;)
そう明るくはいけないのが本当。
シンジに期待できたらいいなぁ・
さあ、訪問者の皆さん。
感じることを作者のフラン研さんに伝えましょう!