「全く、何のお迎えも無しとはねえ…」
一応ベージュのスーツで決めた彼女は、軽く溜め息をついて辺りを見回した。
ひなびた、は言い過ぎかもしれない。付近は想像よりは建物も多く、一応商店街らしき物が目の前に見える。
自分の目の前に、タクシー等がぎりぎり回れる程度の小さなロータリーがある。バス停もあるが。それらのある鉄道路線に平行に走る道の向こう側には、それぞれ2階建ての饅頭屋とタバコ屋、もちろん店舗は1階。タバコ屋と前世紀からの民家の間に「サンロード」なる看板があり、その向こうに布団屋、中華料理屋、やっぱり民家がある。更に向こうに、1棟だけ近代的なマンションがあり、1階にヤマザキデイリーストアと理髪店が入っている。
「ひなびた」が言い過ぎなら、「つまらない」位が適切な形容詞だと言える。
彼女は大きな「観光案内図」の下に一台止まっている黒いタクシーをつかまえた。
「すいません。新閖上港の南まで行って下さるかしら。」
50代の気の良さそうな運転手は振り返った。
「港の、南、ですか?」
「ええ。…南仙大学付属水族館にまで行きたいのだけど。」
「え、大学ですか? 大学だったら、ここから北の太白区に…」
「いえ、大学ではないの。その、とりあえず港の南まで行ける。」
「ああ、はい。じゃあ、河畔公園辺りで。」
「お願いするわ。」
本当に一流のスタッフと設備を備えた研究施設なのでしょうね。
彼女は自分の小皺がまた増えたような気がして、それで更に不機嫌になった。
簡単な街並はすぐ途切れ、窓の向こうには野菜の畑が広がる。タクシーは10分も走らずに停車した。
「あ、領収書頂けるかしら。名前は書かないで良いわ。」運転手に声をかける。
彼女はタクシーから降りる。タクシーはUターンで戻って行く。
河畔公園は、公園と言うよりは遊歩道に近いものだった。目の前をそこそこ大きい川が流れていて、目の前の海に注いでいる。つまりここは河口だ。
日差しは穏やかで、海もとても静かだ。向こうで何か輝いてるのは漁船だろうか?
少しだけ風が吹いている。
彼女は自分の小皺が減ったかもしれないと思った。
「海ね…」
彼女は呟いた。
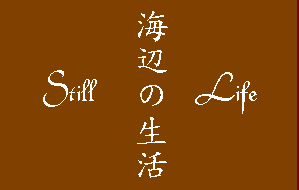
そして今日は月曜日で、特に祝日ではなく、現在午前10時40分。つまり開館中。
であるにもかかわらず、ほぼ全員の職員達が、自分達の持ち場をうっちゃって水族館前の駐車場に集合していた。
ミサトとマコトとシゲルは、本来は魚を運ぶのであろう冷蔵車の荷台から檻が動かされ、クレーンで運ばれていくのを手伝いもせずに眺めていた。
「まさにVIP待遇ですね。松本から研究者まで付く訳でしょう?」
シゲルの言葉に少し誇らしげなミサトを、マコトは不思議そうに覗き込んだ。
「しかし、その研究者は何処へ行ったんでしょうね。」
「ああ…そう言えばそうねえ…」
「どういう人なんでしょうね。その方。」
ミサトに聞くシゲル。
「そ、そうねえ…」ミサトの声はやや上ずっている。
マコトは向こうで、運送業者と話している館長に呼びかけた。
「館長! 研究者の方は、まだいらっしゃっていないんですか?」
その頃彼女は道に迷っていた。
海沿いの道を南下する。海沿いと言ってもこの道から海は殆ど見えない。たまに高台のような所で見えて来るが、大体において畑とそこに刺さったパチンコやスーパーやモーテルの看板と、ガードレールしか見えない。
もう3kは歩いた。
ある道を歩いていて、その道が間違いかどうかを判断するのは実は難しく、慎重を要する。何故なら、実は正しかった道を「間違えている」と考えて、違う道に入ってしまう為に道に迷う、というのが一番多い道に迷う原因だからだ。
彼女は努めて冷静になって考えた。
結果、自分の歩いているこの道は間違えていると思った。
「ふう…最初は何処でもこれなのよね…」
彼女は誰にも教えていない自分の方向音痴を呪いながら、歩いて来た道をまた戻りだした。
彼女は結局1時間歩いて、最初タクシーを降り立った地点に戻っていた。
おかしな話だが、彼女はここに来て、少し機嫌が良くなった。この遊歩道には何か彼女の機嫌を良くさせる成分か、匂いか何かがあるらしかった。
彼女は30m程向こうに「レジャーマップ」の看板を見付けた。駅前の「観光案内図」と、まあ同じ物だ。
名取市と仙台市の間に名取川という川が流れている。川が太平洋に注ぐ河口の北側、つまり仙台側に新閖上港がある。これはここから本当に見える。おもちゃのような、それこそ「ひなびた」漁港だ。そして南側にはこの河畔公園、それから郵便局、それから食堂、ちょっと南に海水浴場があって、もっと南に仙台空港。
「ああ、ここにあったわ。」
それから、水産研究所。確かに現在地のすぐそばにある。この辺りでは、水族館とは呼ばれていないのだろうか?
彼女の後ろを、はっきり言って汚ないシャツを着た、40代か50代のうだつの上がらない男が通り過ぎようとした。平日の昼間だ。
彼女はしばらくためらったが、すぐに営業的な微笑で男に尋ねた。
「すいません。ここから水産研究所へは、どう行ったら良いのかしら?」
男はニコリともせず、珍しそうに彼女を一通り見てから口を開いた。
「水族館の事ですか? ここからすぐですよ。御案内しましょうか。」
彼女は助けてもらっているはずなのにますます機嫌が悪くなった。
館長はおいしそうにお茶を飲み干した。
「博士は、まだいらっしゃらないようだな。」
モニタで科学雑誌の論文を眺めながら、お茶の感想のように呟く。
「え、ええ。何処に行かれたのでしょうか…」マヤは何時もながらの悠然とした館長の態度にやや顔を引きつらせながら、湯呑をお盆に乗せる。
「今日は天気も良い。多分散歩をされているのだろう。」
「は、はあ…」
「これは分からないはずだわ…」彼女は思わず呟いた。
「何か?」
「ああ、いえ、何でもないの。あまり水族館らしい建物ではないな、と思ったので。」
「ああ。ここは良く港の倉庫と間違えられますね。」男はやはりニコリともせず答える。彼女は自分が愛想笑いをしているのが段々馬鹿らしく思えてきた。
檻が台車に乗ってから、ミサトとマコトと運送業者の計5人はうんうん言いながらそれを押し、スロープや段差も乗り越えようやく「特別室」までの移動を完了した。
早速檻から飛び出し、プール付きの部屋ではしゃぐ新種に2人は顔を思わず綻ばせた。
「やれやれ。とうとう始まっちゃったわね。」ミサトは何か照れているようだった。
マコトは何時も通りの率直さで言った。
「しかし、こうして見るとつくづく不思議な生き物ですよね。」
「そうね。まあ、まさに水族館向きの生き物でしょうね。昔の探検家達が彼等の事を「2本足の魚」と表現したのも無理無いと思うわ。」
「魚、ですか…誰が言ったんですか、それ?」
「え? 名前までは、ちょっち…」
「ビューリュー提督? それともトーマス・ロー卿かしら。」
2人は顔を上げた。
「あれ? 時田さん。」
「リツコ!」
「おや、2人は知り合いなのか?」
「え、ええ…」
「まあ良かろう。」
水族館の休日の保守担当、時田シロウは真面目腐って、休日の自分を捕まえた女性を紹介した。
「こちらが第二東京大学生物学部から当水族館にいらっしゃった、日本の生物言語学の権威、赤木リツコ助教授だ。」
ミサトはリツコを肘で突いた。
「道に迷ったわね。」
「…私は一度覚えたら、もう大丈夫なの。何処かの人とは違うわ。」早口で言い返すリツコ。
リツコはやや呆気に取られたマコトと時田に向かって軽く会釈をした。
「初めまして。私がこれからこちらで研究をさせて頂く赤木です。それから彼が」リツコは4人を興味深げに見上げてじっと立っているペンギンを目で指した。
「ポコティファです。よろしく。」
彼女はペンギンを見下ろした。
「しかし相変わらず、変なルックスしてるわね…」
リツコは「そう?」と素っ気無く答えた。
「これ、イワトビなんでしょ? でも顔は白いし、どっちかって言うとロイヤルペンギンに似てるわよね。」
「イワトビではないわ。新種の温泉ペンギンよ。」
「はいはい…」
どうやら博士とミサトさんは仲が悪いらしい。
マコトは半ば確信した。シゲルから殆ど恒常的に、たまにマヤからすら指摘される事だが、彼女はミサトに近付く人間は全て一様に否定的に評価するきらいがある。
「あの、博士、よろしいでしょうか。」マコトは手を上げた。
「温泉ペンギン…とは? すいません、初めて耳にしたもので。」マコトはペンギンが自分の管轄外である事もあり、正直に尋ねた。
「謝る事はないわ。文字通り、新種。南極での遺伝子実験中に突然変異的に生まれた種よ。」
マコトは気付かなかったが、ミサトは少し顔を落とした。
「ミサト…葛城さん、の言った通り、既存の種の中ではイワトビペンギンに最も近いわね。いずれにしても、まだ学会で承認されてすらいない種よ。」
「はあ…爪が、はえているんですね。」
「そうね。これがある以上、温泉ペンギンを他種と同等に見る事は出来ないわね。ペンギンと呼ぶ事にすら問題があるかもしれないわ。」
「フリッパーからこんなの出てるペンギン、確かに他にいないわよね。泳ぐ時に邪魔じゃないの?」口を挟むミサト。
リツコはややペンギンを見て考えた。
「折り畳めなくはないけど…邪魔よ。…ただ、温泉ペンギンは泳ぐ必然性が無いから。」
「確かに。」ミサトの顔は何故か厳しい表情になった。
リツコはマコトの「さっぱり分かりません」と言いたげな顔を見て微笑んだ。
「爪が生えている、というより、骨が長すぎて短いフリッパーを飛び出した、と考えた方が分かりやすいかもしれないわ。」
「はあ…」
マコトは「それは、意図してそういう作りにしたのですか」と聞きたかったが、言うのに躊躇した。
「安心して。乱暴な事をしない限り、爪で引っ掻かられたりはしないわ。」
「引っ掻いたじゃない!」
「あなたは別よ! 何処の世界にビールを飲ませようとする飼育者がいるのよ!」
マコトは少なくとも2人が仲が悪いという事だけは揺るがぬ事実であるとはっきり認識した。
「ところで、この背中に背負っている機械は、私達は気にしないで良いのだな?」
「え? え、ええ。」
リツコは時田の質問に答えた。
「シンクロナイザーのチェックは私が責任を持ちます。気になさらなくて結構です。」
ペンギンは銀色のリュックのような物を背中に背負っていた。
ミサトは腰を降ろし、4人を見上げるペンギンの頭を撫でた。
「おーう、久しぶりだな。元気してたか? ペンペン。」
リツコはきっとなってミサトとペンギンに言い放った。
「だから! それはペンペンじゃなくてポコティファ!」
「良いじゃない、ペンペンって名前の方が可愛くて。ペンギンだからペンペン、正に単純明快じゃない。」
ペンギンは約1ヵ月振りに会った旧友のミサトに頷くように、「くあ」と鳴いた。
「皆が皆あなたのような単細胞という訳ではないの。彼にはポコティファという立派な名前があるのよ。」
ペンギンは今までずっと付き合って来たリツコにも頷くように「くあ」と鳴いた。
「ポコティファ? 何かそれ、語呂が変で馴染めないわあ。」
「くあ。」
「ペンギンだからペンペン、なんて言うあなたの子供じみた感覚よりは数段増しよ。」
「くわぁ。」
「若いと言ってよ、若いと。学者のセンスを一般人に押しつけて欲しくないわよね。」
「くあ。」
「学者で悪かったわね!」
「くあ!」
「そろそろ、戻りましょうか?」
「ああ、そうだな…」
やはり呆気に取られたマコトと時田は、言い合う2人と1匹の「ペンギン室」からそうっと抜け出した。
1週間後
リツコは上機嫌だった。自分の研究の為の端末が今日ようやく入ったのだ。これで、長年の夢だったEVAの研究が可能となる。3つ入って来た端末は、MAGIと名付けた。東方より来たりし三賢者だ。MAGIカスパー、MAGIバルタザール、MAGIメルキオール。それぞれ画面の壁紙の猫の色が微妙に変えてあるのだ。…それからプログラムも変えてある。しかし一番それぞれが違うのはその置き場所だろう。
カスパーは、ペンギン室の壁際に置いてあり、丁度温泉ペンギンの目の高さに3D型のモニタが来るようになっている。バルタザールはそのすぐ左隣にあり、これはモニタが人間の目の高さの所にある。しかし両方ともラップトップ型なので、持ち運ぼうと思えば違うところへ持って行く事も可能だ。一方メルキオールはここから約20秒程のリツコの研究室に置いてある。こちらはラック型なので、一人で持ち運ぶのは多分難しい。
リツコが準備を終えてペンギン室に来ると、飼育担当のミサトがモップ掃除を終えた所だった。
「どう? 彼等の調子は。」
ミサトは一種のプラスチックで出来た岩石風の丘、通称「ペンギン山」を見た。
「ペンペンは始終ぐーすか寝てるわね。でも、」ペンギンが2人と話すかのように「くあ」と鳴いた。
「見ての通り、ギンギンの方はいっつも飛び回ってるわ。」
「くあ。」
だから、それはギンギンじゃなくてピンギ…
リツコは心の中で訂正した。口に出さないのは、彼女が無駄な労力を徹底して嫌うからである。聞く耳を持たない相手に何を言っても仕方がないのだ。
現在ここ南仙大学付属水族館には、雄のペンペンと、3日遅れて到着した雌のギンギンの、2匹の温泉ペンギンが非公開で飼われていた。この水族館にペンギンはこの2匹だけであり、赤木博士の弁によれば、「温泉ペンギン」は全世界にこの2匹しかいないそうだ。
ペンギンというものは、およそ雌雄の区別が付かない。それどころか個体の区別がなかなか付かない。ミサトやリツコも、たまに名前を間違えたり、「BX293A」「BX167F」といったプレートを見ないとペンペンとギンギンの区別が付かなかったりした。
「この子達、意外とリラックスしているわ。」ミサトは目を細めて言った。
「そうね。東北とはいえ、冷房が無い分、前の研究棟に比べれば遥かに気温は高いのだけれど。」
リツコは視線をモニタに戻した。
「問題は無さそうね。」
「EVA理論って…本当にうまくいくの?」
「それはやってみないと何とも言えないわ。ただ、賭けてみる価値はある。温泉ペンギンの知能の高さは、多くの類人猿は凌駕していると思って貰って構わないわ。」
ミサトは思わずリツコを見た。
「嘘!」
「本当。彼等の大脳の全身に占める割合は、ゴリラ、オランウターンより高く、チンパンジー、ボノボよりは下ね。ただし温泉ペンギンは、シンクロナイザーで常に脳の活動を活性化させている…これは、知っている事でしょうけど。」
「こいつら、頭良いんだ…」
「ええ。行動の的確さ、多彩さ等の比較は、温泉ペンギンについてのそれが研究不足である以上他種と比較は出来ないけど。少なくとも実験にエントリーする資格位はあるでしょうね。」
「くあ。」
ミサトは、リツコの微妙に嬉しそうな表情に顔を和らげた。
「実験、うまく行くといいわね。」
「うまく行くわ。」
2人は軽く目を会わせた。
「でも、正直、やっぱり信じらんないな。ペンギンが言葉を喋るなんてー。」
リツコはやや眉を潜めた。
「現実に彼等が声帯を使って人間の声を出す訳ではないわ、分かっていると思うけど。」
「嘘!」
リツコは溜め息をついた。
「あのねえ。出来る訳無いでしょう。物理的に。ペンギンが。」
「…じゃあ、どうするの?」
「それで、これを使うのよ。」
ギンギンは不思議そうに目の前の2人を見上げていた。
つづく
フラン研さんの『海辺の生活』第二話、公開です。
水族館。
と言えばやっぱり出てくるペンペン!
そして・・・・ギンギン・・・・(^^;
ミサトの命名センス・・・泣けてくるほど素晴らしいです(^^;;;
主人公はこの”新種のペンギンズとその研究者リツコ女史”なのかな?
ペンペンが主人公のマンガはたまーに見かけるけど、
小説となると・・・・無いですよね?
主人公は本決まりですね(^^)
・でも・・・作者はフラン研さん、油断は出来ない・・(爆)
さあ、訪問者の皆さん。
私をドキドキワクワクさせるフラン研さんにメールを送りましょう!