防寒具、と言うには余りに大袈裟な装備で彼はヨタヨタと建物に近付く。
やはり大袈裟な手袋でドアを開けた。玄関にはもう一つドアがあり、それを開くと「研究所」内だ。
中には、パイプの椅子に座ってパソコンに向かう、長袖シャツの男がいた。40代で、不精髭を生やし、眼鏡をかけている。
彼は顔を上げた。
「そんなに着飾って、暑くないのかい?」
彼は冗談だか本気だか分からない雰囲気で聞いた。
「この吹雪の中、平気でシャツ一枚で外に出られる教授の方がどうかしてますよ。」
訪問客は帽子と手袋、ゴーグルを取りながら言う。
ぶ厚い二重窓の向こうは叩き付ける白の嵐。
「しかし何mもない住居と研究棟の間でその格好か? マイナス何度もあるわけじゃあるまいし。ルッカリーでも怖がられるぞ、北原君。」
「だから、それが普通なんですって。」北原は脱いだそれらを空いている椅子に置く。
「それに、ルッカリーの方は、もう良いんでしょう。」
北原はパソコンの画面を覗いた。地図が表示され、多数の赤、黄色、青の点が付けられている。
「ああ。一応候補は決定済だ。」2人は自然と後ろのドアに目が行った。
「ああ、もういるぞ。会ってみるか?」
「ええ、もちろん。どんな子供が選ばれたのか、私も興味有ります。」
「研究員が、興味が無かったら困るからな。」2人は笑った。
北原はパソコンを離れ、インスタントコーヒーを入れにテーブル兼机のはじの瞬間沸騰器に向かった。
彼は手帳に挟まれた写真を見付けた。
「これ、葛城教授の御家族ですか?」
プラスチック製の、電熱で数秒で湯を沸かす四角いポットから湯気が漏れる。
教授は振り返って「ああ、そうだ。」
「奥さん、きれいですね。」
北原は惚けたように、その遊園地で撮ったらしい写真を見つめた。ショートカットでふっくらとした顔だちの女性と、やや青みがかった髪の遠慮がちに微笑む少女が写っている。
「それに娘さんも、本当に可愛らしい。」
「君はその気があるのか。」指を忙しくさせながら、葛城は無関心そうに言う。
「別に、そんな意味じゃありません。」
写真を置く北原。
「振られたよ。」北原は、無表情な教授を見た。
「ずっと研究の毎日だったからな。自業自得さ。今頃日本で、新しい「家庭」でも作ってるだろ。」
教授はじっと画面を見つめている。
「その頃、振られた方は南極で吹雪の中、ですか。」
北原はまともに慰めるのもためらわれて、そう混ぜ返した。
「違うぞ。亜南極圏、だ。」
「あ、それ俺が飲もうと思ってた!」教授はコーヒーを飲む。
突然警報が鳴った。
「何だ。」すぐにそれぞれパソコンの前に立つ2人。
「エンジンですね。動力源に異常発生…出力上昇!」
「出力カットだ!」
「受け付けません! シンクロナイザーと呼応しているのでしょうか?」
「知るか! …駄目だ、何故止められない!」
単調なビープ音が研究棟内に鳴り響く。
教授は叫んだ。
「…このままでは爆発するぞ! 北原、彼等だけでも救助ポッドに乗せろ!」
「分かりました!」
数分後、研究所一帯は、轟音と熱風、そして全てを焼き尽くす炎に包まれた。
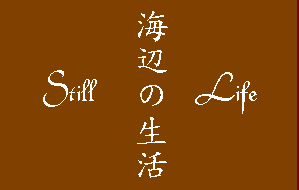
加持リョウジは、いつものように池と池の間の細い通路を歩き、粉末に近い状態の餌を投げ与えていた。
「ほら、お前達、一杯食って大きくなるんだぞ。」
小魚相手にお決まりの台詞を言いながら、水面に口を突き出し集まる彼等を見渡す。
フェンスの向こうの国道で、車から苦虫を噛みつぶしたような顔つきでこちらを見つめる女性がいた。
彼女を見て、彼はほんの少しだけ眉を上げた。
「よっ、葛城。こんな時間から俺に会いに来るなんて、珍しいじゃないか。」
軽薄そのもの、といった風情で緑色のフェンスに近付く。
お気に入りの赤いジャンパーに身を包んだ彼女は、車から降りようともせずフェンス脇に停車したままの状態でそっぽを向いた。
「そんなんじゃないわよ。」
「よっぽど俺の顔が見たくなったか。男冥利につきるねえ。」
「ああそうですそうですどういたしまして。」その女性、葛城ミサトは目も合わせずに単調に言った。
「だいたいあんた気持ち悪いのよ。魚相手に声かけて、はたから見たらただの変質者よ。」
「はたから見たら、ただの養殖業者だろ。」餌の入った青いプラスチックの箱をコンクリートの床において、加持はフェンスに寄りかかった。
「まあ、そうとも言うわね。」ミサトは何故か、嬉しそうだった。
「ま。私も人の事は言えないか。」
「葛城の方がおかしいだろう。」
「何がよ!」
「別に食べる訳でもない魚を飼っているんだ。刺身にしたらうまそうとか、見てて思わないのか?」
ミサトは気色ばんだ。
「思う訳無いでしょ、この残虐主義者!」
「お前だって刺身、食うだろ…」何故か目を合わせず、声も小声になる加持。
「しっかしねえ。ここもホンット、静かよねえ。」
ミサトは自分の周りを見回した。国道のはずだが、さっきから車が一台も通らない。だからこそ、平気で停車して、国道沿いの職場で働く男に油を売る事が出来るのだが。
彼女の左手に「宮嶋養殖」がある。コンクリート張りの釣堀をやや大きくしたような屋外漕が6個。この辺にはいくつかある、魚の養殖池だ。一方自分の右手は丘。中腹程度までコンクリートブロックで固められ、その上から申し訳程度に林が顔を出している。
ここはやや眺めが良く、後ろを振り返ると少しだけ、灰色に近い青の海が見える。
「田舎だからな。」加持は目の前の池を見回す。
「だから、魚達が育って、旨い刺身になってくれる訳だ。」
「はいはい…」
「でもそろそろ、嵐が来るな。」
加持の口調はいつも通りの、軽薄な物のように聞こえた。
「…そうね。」ミサトは結局、その事が嬉しくて加持に報告に来ただけのようだった。
「あいつ、貸した金があるのよ。請求しないと。」
「意外だな。葛城が借りるなら分かるが…」
「どうしてよ。…ともかく、明日ね。」
「…そうか。また3人でつるめるな。」
「誰があんたなんかと!」
葛城は一睨みすると、愛車の青いルノーを飛ばして消えてしまった。
「あいつ、何しに来たんだ。」加持は呆れたふうに呟いた。
「お前にロッカーの心が分かってたまるか。」いつもの言葉にいつもの返事を返すもう一人の男。
2人が座っているのは職員控室。青い作業服の2人はお互いの担当する給餌・保守が終わり、一息ついているところだった。パイプイスに折り畳み可能なテーブル。乱雑に書類やら薬品やらぬいぐるみやらが散らばっている。
「なあ、マコト。お前さんのスイートハートは、今日はどうしたんだ。」隣の椅子の上に足をのっけて、お茶を飲んでいた機械設備担当者はふいに、本当にふいに思いだして、控室に一つあるテレビをザッピングしていた海水魚担当者に尋ねた。
マコトは自分が飲み物を飲んでいなくて良かったと思った。
「ぶっ、ふざけるな。…葛城さんは…今日は大学へ行って、例の引き受けの手続きとかをしているんだろう。多分。」
自信無さ気に答える。
「ああ、何やらいわくつきの奴な。」
「いわくつきでもいわしつきでも何でも良いさ。ここにも人が呼べたらな。」
テレビは結局、昼間の定番の当たり障りの無いバラエティーショーになっている。マコトはテレビに構わず、スポーツ新聞を広げ始めた。
青葉シゲルは日向マコトの言葉に少し笑った。
「お前、本当にここの水族館が忙しくなって欲しいと思ってるか?」
「思っているさ! 自分達が大事に大事に飼育している魚達なんだ、出来るだけ多くの人達に見て欲しいと思うに決まってるだろ!」
マコトは、どこか楽しそうにシゲルの皮肉な口調に抗議した。
「こんな田舎で人が呼べるかよ。」
2人は、乾いた笑いを漏らした。
「まあ、保守担当の俺には、客が多かろうが少なかろうが関係無いがな。…いや、」シゲルは椅子の上にのっけていた足を降ろした。「嫌いじゃないんだ。今の、静かな雰囲気。」
「まあ、人員整理をしないですむ程度にはお客様に来て欲しいですけどね。」手持ちのPDAを折り畳みながら、淡水魚担当者がお茶を飲みにやって来た。
「よっ。」
「あっ、マヤちゃん。」
シゲルは、「スイートハート」が別にいる癖に、いつもマヤの前でも何やら姿勢を正すマコトを非常に胡散臭げな目で見た。
マヤは2人に軽く微笑んで、繋がっている大机の、比較的整頓された一角に向かう。
「どうなんだろうな。…でも、ここってレジャーランドというより、研究施設だろ? 彼等が来たからって、たいして宣伝する訳でもないだろうし…」
「静かなままかな。」シゲルの言葉を継ぐマコト。
彼は何故か女性の裸体のイラストのある紙面をスキップし、競馬情報を見ている。
「でも、日向君はこれからは大変よ。今度からは海水魚は、全部一人で受け持つ事になるんでしょう?」
軽く頬杖をついて、マヤはマコトに向く。
「ああ…でも、今までだって一人でやって来たような物だから。」
「あ、ひどーい。葛城さん聞いたら傷つきますよ、それ。」
「「すった」とか「眠い」とか、あの人の欠勤理由って全部一言なんだよな。」シゲルの呟きに吹き出す一同。
「ま、なるようにしかならんさ。」
シゲルは、マコトの「ロッカーの心って、要はあきらめ主義って事なのか。」という返事を無視して仕事に戻った。
それから、目の前に居る水族館の理事長も苦手だ。
「問題は無かろう。」色眼鏡と顎髭で素顔を隠した、およそ堅気の生物学者には見えない碇ゲンドウ理事長は、「南仙大学付属水族館 新種受け入れ体勢について」という最終報告に軽く目を通し、判をおした。
「有難うございます。」
「後の細かい事は新任の研究員に一任してある。彼女に聞いてくれ。」
「はい。」
ミサトは理事長が本当に報告書を読んだようにはとても見えなかったが、自分がそれを追及する事でもないので触れなかった。
理事長室はスチール製の本棚が壁をびっちりと埋め尽くしていて、入り口の向いの方向だけ窓があり、春の暖かな日差しを確認する事が出来た。
ミサトは軽く御辞儀をした。部屋をたとうとして、彼女は立ち止まった。
「あの…理事長。」
「何だ。」
「ここの研究所は何故、大学構内にあるのでしょうか?」
「他の研究室と連絡を取りやすいからだ。それ以上の理由は無い。」
「はい…失礼します。」
ミサトが出ていった事を確認すると、碇はやや自嘲気味にほくそ笑みながら図鑑を手に取り眺め始めた。
5年前
ミサトは、駅前のひなびた景色に思わず眉を潜めた。
しかしそこから5分程「サンロード」を歩くと、ようやく一軒、酒屋を兼ねたコンビニを見付け、そこで弁当と缶ビールを買っててくてくと歩いていた。
向こうから、昔松本で良く会った男に似た男が歩いて来た。何をする風でもなく、ジーパンにTシャツのいたってラフな格好だ。
ミサトは「まさか」と思ったが、思わず店の軒先に隠れる。
無粋にも、男は御丁寧に回り込んでミサトの前に立った。
「あれ? 葛城じゃないか。こんな所で何してんだ。」
奴だった。
「へえ、今度から俺の街で働く事になったんだ。2人の運命って奴を感じるね。」
2人は加持の所有する軽トラックのキャビンに座っていた。農道脇に停車している。
「いつから名取市はあんたの街になったのよ。」助手席で幕の内弁当をかきこむミサト。
「はは…でも、俺がここ出身だなんて大学時代に話したか?」
ミサトは沢庵をつまんで食べようとする箸の動きを止めた。
「…話してないわよ。」
加持は口調の変化に目を上げた。
「あなた、自分の事は何も話さないじゃない。」
「俺は本職はスパイだからな。」
しれっと言う運転席の男。ミサトは、一瞬、いや数秒、割り箸で挟んでいる沢庵を奴にぶつけようかどうか迷ったが、沢庵が勿体無いので止めた。
「でも、あんた、宮城出身だったんだ。」
「ああ、生まれも育ちもここ「第2新仙台市」だ。」
「へ?」
ミサトの箸が又止まった。
「自称な。首都が遷都された時、「新」何々って地名に付けるのがはやったろ。だからここは「第2新仙台市」だ、そうだ。」
ミサトは周りを見回した。
周りは水田と自動精米所。ジュースの自販機が1台と缶捨て場。電柱と水路がたくさん、かなり向こうに山。少し向こうにパチンコパーラーと温室がちらほら。
「ビル、無いわよ。」
「無いな。」
2人はしばらく沈黙した。
「で? どこで働くんだ?」
「あんたに言う義理は無いわよ。」
「つれないなあ…ま、どうせ、ここは田舎なんだから、言わなくともじきに分かるぞ。」
「それもそうね…水族館よ。」
「水族館?」
「そ。南仙大学付属水族館。知らないの?」
「大学は知っているが…水族館なんてあったのか?」
ミサトは自分の就職先の知名度の無さに頭を押さえ始めた。
「まあ…俺、そういうの良く知らないからな。熊本の葛城が知っていたって事は、その世界じゃ有名な施設なんだろ。」
やや声を上ずらせる加持。
「まあいいわ…あんたは? あんたは今何やってんのよ。」
「俺か? 俺は、サーファーだ。」
親指で自分の顔を指す。
ミサトは運転席の男に注意を向けず、人工的に白いご飯をぼそぼそと食べている。
「…仕事は?」
「そして、養殖業者でもある。」
「養殖? 何の。」
「おいおい、この辺で養殖って言ったら、魚に決まってるだろ? カイコでも養殖していると思ったか?」
「魚…でも水族館は、」
「知らないな。」
「そう。養殖…」
「ああ。」
「ごちそうさま。」
ミサトは割り箸を容器に入れ、透明の蓋を被せた。
「私、降りるわ。」
ミサトは軽トラックのドアを開け、飛び降りた。
「おい、急に何だ、葛城! ここからまだ2・3kmあるぞ!」
「魚を食べる為に育てている奴なんかと、同じ空気は吸いたくないのよ!」ミサトは肩を怒らせて、農道を歩いて行った。
加持はしばらく唖然としていた。それから助手席のビニール袋を見て溜め息をついた。
「ゴミ位持ってけよ…」
マルボロを取り出す。
「まあ。ここで暮らすのなら、急ぐ事もないか。」
加持はカーステレオをつけた。東北放送のラジオ番組が流れ出した。
再び、2015年
「そうか。彼等の運送は、研究所の方で手配してくれるから問題は無かろう。君は、明日午前11時に着くのか。…それでは、名取駅からタクシーで、新閖上港の南に行くように言ってくれ。ああ、新閖上港だ。そこから水族館はすぐに分かるだろう。それではな。歓迎するよ。」
南仙大学付属水族館館長は受話器を降ろした。
「ついに明日か。」
老人は独り言を漏らし、端末に目を戻した。
メールが届いている。ミサトからの、理事長の承諾を得たので、これから水族館に戻って最後の設備調整をする、という内容の物だった。
「全く碇め、面倒な物を押しつけおって。」冬月館長は心底楽しそうに言った。
「あいつが水が怖くて南仙台の大学構内に研究所を置くから、連絡に手間がかかる。」
館長は目を細めた。
つづく
「エヴァ小説史上最も珍しいキャラが主人公」小説、
ついに連載開始ですね(^^)
主人公はまだ登場していない・・ですよね?(^^;
南極・・ではなくて、亜南極圏で出ていた「彼ら」?
ミサトが受け入れようとしていた新種?
新任の研究員?
・・・誰だろう・・・人なのかなぁ・・
続きが気になるぅ(^^)
さあ、訪問者の皆さん。
貴方の感想をこの新連載に送りましょう!