
「コンピューター、ホログラム解除。」
電子音と共に、スグルを始め2人以外の全ての景色が文字どおり消える。
「見苦しいわよ。続きはいつでも出来るでしょう。」
立ち上がった老シンジ。ことドクターは至極冷静に答えた。
「だあって、ここまでずうううっと前振りだったのよお? これからようやく盛り上がるって時にわざわざ呼び出すなんて、もうあんのヘボアンドロイド…」
「疲れたわ。ずっと私の出番ばかりであなた、最後に立ってただけじゃない。」
「だからこれから2人で良いシーンになる所だったのお!」
「へえ。」
ずーん。
マギデッキのドアが開き、リツコとミサトは廊下に歩き出た。
「ね、ねえ、とりあえずさ、どんな感じだった?」
リツコは眉を上げた。
「このホログラム? 何でこんなものが流行ってるのか、良く分からないわね。ただの安っぽいお涙頂戴のメロドラマでしょう。」
「はあ。どうしてそうあんたって、こう、つめたーい意見しか言えない訳? この二人の愛が分からないの?」
廊下を歩く2人。
「愛、ねえ。」
「そうよ、愛よっ! リツコだって。本当は、寂しいくせに。」
ドクターは立ち止まった。
「…ミサト。」
「あ、いや、ごめん、言い過ぎた。」
「…あなた…本気なの。」
「何よ、急に。」少し声の上ずるカウンセラー。
「私はいつだって本気よ。」
「私、理系だからこういう事には疎いのよ。…やっぱり、副長に報告書位は出してから、」
「ほ、報告書ぉ?」
「…少なくとも断ってから、私達の事は進めるべきだと思わない。」
「ふふ…」
ミサトは頭を振って笑う。ちょっとムッとした様子のリツコ。
「ミサト?」
「リツコ。怒るわよ? 私達の気持ちは私達のこと。副長とは、別に関係無いでしょ。今は、二人の気持ちを…ね、リツコ。」
ドクターはやや目を広げ、やがて細めた。
「ミサト…」
「リツコ…」
ドクターとカウンセラーは唇と唇をゆっくりと近づけた。目をつむるカウンセラー。
「あああっ! カウンセラー!」
「ひいいいっ」背後の声に慌てて唇を離すカウンセラー。
ぴぎぎぎぎ…
「うぎゃあああっ」
「…あら、艦長。」
紙オムツ一丁姿の艦長は、リツコのアイビームを軽くくらって卒倒したが、それでもあふあふ呼吸をしながら言った。
「か、か、カウンセラー。きょ、今日の日付は…」
「う、うええう宇宙暦47988っすけどお。」
「47988…47988…うむ。間違い無い。」
紙おむつ姿で倒れたままのキューピーちゃん(艦長)が2人に言う。
「カウンセラー、私は、どうやら、過去と現在、未来の違う世界を、行き来しているようなのだピー。」
リツコとミサトは目を見合わせた。
―宇宙。そこは最後のボランティア(意味不明)。これは、宇宙戦艦エバンゲリオン号が、新世代のクルーの下に、24世紀において概ね任務を続行し、未知の世界を探索して、新しい生命と文明を求めるふりをしつつ、人類未踏の宇宙に、アバウトに航海したりしなかったりする小話である―


「バター茶、ぬるめで。」
レプリケーターの前で言うピカード。
「で? その症状は、いつから始まったっすか?」
ミラーボールと回遊魚のくるくる回る自室で、ミサトはソファーにどっかと腰を降ろし足を組んで尋ねた。雰囲気はカウンセラーというよりはマフィアのドン(しかも静かなる)だ。
「さあ…良く分からんが、この数時間だ。」
お茶を持ってミサトの前にやってくるピカ。
「その…過去と? 未来。それぞれ、どの位昔なり後なりの世界なんですか。」
「それも良く分からん。ただそれぞれ、かなり前、後だ。下手をするとそれぞれ全く違う時代といった方が良いかもしれん。ただどの世界にも、ああ…連邦は、あるようだが…」
「つまり、私達が産まれる前とか、あるいは死んじゃった後みたいな、全然別の世界って事っすか。」
「かもしれん。」
頷く艦長。
「しかし、どうも、私も含め皆いる…ような気がしたな。それもまたおかしな話なのだが…」
「…」
艦長は急に汗をかきだした。
「小野ヤスシは関係無いぞ。」
「分かってます。」ニコリともせず頷くカウンセラー。
「うーん…はっきり覚えていないっていうのは、夢だから、って事は、ないっすか?」
「それは有り得ん。あれは夢などではない。見る事も、聞く事も、触る事も感じる事も出来た。あはうふあはーんとな。」
「…」
回転する巨大ドクター中松像を背後に困ったような表情を見せるカウンセラーに、艦長は言葉を足す。
「うむ、つまりだな、最初、それぞれの世界に行く時はまず、めまいがして、ふいに視界がおかしくなる。そしてすぐに今までとは違う世界に自分がいる事に気付くのだが、やがてすぐに、まるでそこに自分が前からいたかのように
ぺったん、ぺ。
「…」
老人がふと周囲を見回すと、そこは饅頭工房だった。
やや呆然とした様子で立つ白い髭の老人。
「…」
そうだ、自分は今餅つきの真っ最中だった。顔が80代の老人はもう一度半屋外の工房をゆっくりと見回すと、やがて頭を振り、ぺったん、ぺったん、ぺったん、ぺ。と目の前のうすの餅つきを再開しだした。
工房に、老人が餅をつく音が響き渡っていた。
「ここからじゃ干渉魚雷は発射できません!」
老人は向こうからふいにしてきた声に手を止めた。
「了解、座標343、マーク265に退却! 後ろに敵艦! アードナイ砲で対処! 直ちに人員転送をお願いします!
え? 転送機が故障?」
老人は声の主に嬉しそうな表情を見せた。
「なんだね。シンジ君じゃないか。」
「…ははは。懐かしいでしょう。」老人のもとに歩いてきた、30代の男性が快活に答える。
「もう何年ぶりだ。」
「えっと、確か4年ぶり」
「ああ、いやそうではない。使徒を倒した後この25世紀の世界に連れてこられて、ボーグ・ドミニオン連合と戦っていた時から数えてだ。」
シンジはしばらく考え込んだ。
「…それだと…15年位前になりますね。」
「もう15年か! ほう…シンジ君も、随分大人びてきたなあ。まあ、君の場合はお父さんには似なくて何よりだったがな。」
笑い会う2人。
「いやあ。冬月大佐も、」
「シンジ君。大佐と呼ぶのは、恥かしいんでやめてくれ給え。大体私は、あー、艦隊にいたのは何年でもないしな。」
冬月は遮った。
「じゃあ、副司令。」
「それも違う…どうかね。フユっちというのは。」
「ふ、ふ、ふゆっち? そ、それはちょっといかがな物かと…」
「そうか?」
肩を上げる冬月。
「あー、せっかく来たんだ。饅頭造りを手伝ってくれるか。わしがつくから、その合間に手で水を餅につけてくれ。」
「こ、こういう感じですか。」シンジが自信無さそうにそばのバケツの水をつける。
「そうだ。じゃあ始めるぞ。」
ぺったん、ぺったん、ぺったん、ぺ。
二人は餅つきを再開した。
「…それで。何しに来たんだ。」
シンジは目を広げた。
「え。…ちょっと、近くによったので、顔を見たいと思って…」
冬月は頭を振った。
「ライジェル3号星と地球は、近いとは言わんぞ。シンジ君。」
「…ええ。」
シンジはうつむきがちに頷いた。
ぺったん、ぺったん、ぺったん、ぺ。
「聞いたのか。」
「サラスの友人に、艦隊の医療部に勤めている人がいて、そこで…」
「…シンジ君。フェイズイルモディック症候群は、発病してからが長い病気だ。実際発病して10年、いやそれ以上、何の問題も無く生活している患者も大勢いる。残念だが、私が今すぐ死ぬという訳じゃあないんだよ。」
「それはそうですけど、急に、顔が見たくなって…」
「…そうか。」
ぺったん、ぺったん、ぺったん、ぺ。
「大佐、思いっきり僕の手ついてるんですけど…」
「ん? ああメンゴ。」
冬月はきねを上げ、横に置いた。
「まあ良い。この工房も寂しいものだから、お客はいつでも歓迎だ。ああ、時にシンジ君、うまいほうじ茶があるんだ。それは、サラス君のハスペラートには負けるかもしれんが…まあ来なさい。」
冬月の言葉に微笑むシンジ。2人は家へ歩き出した。
冬月はシンジの方を向く。
「ああ、この前の小説、読んだよ。今度の話は、主人公とその恋人達がややドロドロすぎるきらいはあるが、その点を除けば家族論という意味においても…」
くっくっ、こっこ。
「こっこ(Cocco)?」
「…どうか、しました?」シンジが、急に立ち止まった冬月の顔を覗き込む。
「…いや…」
「…」
再び冬月の耳に何かの音が聞こえてくる。
こっこ、こっこ。卵のおやじゃピー。
「何年前のネタだ!!(今の中高生にはさっぱりだぞ!)」
思わず叫ぶ冬月。
冬月とシンジの周囲、10メートル程度先の、工房のあちこちにニワトリやヒヨコの扮装をした人々が踊り、2人を嘲笑っている。
「な、な、な、な、」
「大丈夫ですか? 大佐、大佐!」
冬月の肩を揺らすシンジ。
「副提督!」
はっ
「大丈夫ですか、副提督ぅ。」
童顔で黒髪ショートカットの士官が心配気に尋ねる。
「あ、ああ、大丈夫…だ…」
士官と副提督の2人は、かなり旧式のシャトルに乗っていた。
何とも恐ろしい事に、副提督にはフサフサと銀色のヘアーがのっかっている。
「そうですか。…ところで、副提督はぁ、ネルフに乗船されるのは初めてですか。」
「マヤちゅん…」
「はい?」シャトルを操縦していたマヤっぺは、副提督の様子に戸惑った表情を見せた。
「…あのー、私の顔に、何か?」
「…い、いやあ、君のように美しい士官が乗っているとは驚きだと思ってぐばあああ」
「いやっだあそんな事を言っても何も出ませんよお蹴り以外ぃい。」
「蹴りも出さんで良い! …ぐはっ。あー、何を話していたのかすっかり忘れたぞ。」
「…ああ、副提督はネルフに乗られるのは初めてかと伺ったんですけどぉ。」
「あ、ああ。初めてだ。もちろん事前に情報を見てはいるがな。」
汗をかきつつ頷くフユっち。
「乗られたら驚かれますよ。ネルフは最高の船です。」
「碇が息子の為にぶんどった戦利品だからな。」
「あ、あははは…あ、ほら、見えてきましたよ。」
シャトルのビュースクリーンには、基地のドックに係留されている元エンタープライズ、現USS-NERV、NCC1701Aの、白鳥が翼を広げたかのような優美な姿が現れた。カークの中古品とはいえ中々の物だ。副提督の顔は自然と綻びだした。
「艦長、艦長。」
にたあああああっ。
イエキコーヒー片手のミサトが尋ねる。
「大丈夫っすか?」
「…あ、ああ…今、マヤ君と会っていたよ。…いや、あれはマヤ君であってマヤ君ではない、何と言うか、微妙に異なるのだが…」
ぶひっ。
「ううむ…」
「人の部屋でみは出さないで下さい。」
「いや、今のはすかしだ。」
「「すかし」の意味間違えてますよ。」ミサトは肩を上げた。
「ま、私には手に負えません。やっぱ、ドクターに見てもらった方が良いと思うっすよ。」
きーっ、きーっ。ばさばさばさ。
「まだ検査をやるのかね。」
何かコウモリのような、しかしそれともまた異なる不思議な動物の群れが飛び交っている動物園医療室の寝台でフユツキは愚痴をたれていた。
「次ので終わるわ。」
医療用トリコーダーをかざすドクター。
「異常は無いようね。」
「先程のスキャンの結果が出ました。」
パッドを受け取るリツコ。
「有り難うアリサ。そうね、どこにも異常は見られないわ。脳のカワシマナオミンの残留量も正常値。もしこれが高かったら、幻覚を見たという兆候なんだけど。」
「…この数時間の間に船を離れた記録も無ければ、幻覚を見た訳でもなし。もしかして艦長、単に私達にかまって欲しいだけなんじゃないっすかあ?」
軽口を叩くミサト。
「実は私は愛に飢えた貴公子なのだよ。もちろん白馬にも乗るぞ。」
「もし本当に冗談なら上のをけしかけるわよ。」
きーっ、きーっ。
「う、ううううう嘘だよ、じゃなくて本当だよ、すんじてくれよお。」
「ま。艦長に私をからかう度胸は無いでしょうけどね。」
頭を振るドクター。
「ああ、ミサト、少し外してくれる。」
「ん? うん。」
ミサトはやや不思議そうに、医療室から出ていった。
ミサトが歩いていった事を確認すると、リツコは軽く息をついてフユツキに言った。
「言われた通り脳を重点的に調べてみたわ。そうしたら…艦長、あなたの脳にほんのかすかではあるけれど傷がある事が分かったの。今は全く問題無いけど、将来的にイルシノディック症候群の原因となる可能性があるわ。」
おむつ一丁ことピカードは尋ねた。
「今までの検査では見つからなかったが?」
「今回、レベル4のスキャンをかけたら新たに発見されたのよ。それ位に微少な傷であるという事ね。」
リツコは何かに苛立つように、指をパッドに叩いた。
「問題は無いわ。こういった傷は誰でも持っているものだし、持っているからと言って、皆が皆イルシノディック症候群にかかる訳ではないのよ。むしろかからない人の方が圧倒的に多いと言っても良い位ね。」
「その割には…まるで死の宣告をしているようだっちゃ?」
苦笑するリツコ。
「ごめんなさいね。…微少とはいえ自分の作品に欠陥があるのは、やっぱりあまり気持ちの良い物じゃないから…」
「ああ、なるほどなあ…え?」
はっ
「わ、私の、クルーの健康管理に欠陥があったら、という話よ。何か疑問でも?」
きーっ、きーっ、ばさばさばさ。
「い、いいやあ、滅相もございませぬだ。」
ぴろりろりん。
「ゲォーフより艦長。」
「ああ、何でごぜえますだ。」
おむつに染みを作りながら(おむつに付けた通信機で)答えるピカ。
「ナチェフ提督より通信が入っている。」
「分かった。医療室で受け…て良いでごぜえますか?」
無言で肩を上げるドクター。
「…受けるでごぜえます。」
「…了解。」
ピカは医療室をヨタヨタ歩いて壁面のモニタにやってきた。モニタ横のスイッチを押す艦長。
「まあ、又今日は…情熱的なファッションじゃない。」
モニタの提督はフユツキを見るなり頬を赤らめた。
「いやあ、提督には負けますよ。ところで今日は?」
背中に付けたクジャク羽が何とも鬱陶しい提督はマジ顔になった。
「うーん。実はね、ロミュラスカにどうも不穏な動きが見られるのよ。」
「不穏な動き…と言うと?」
「情報部によると、非武装地帯のテフロン星系近くの国境に突然ロミュラスカの戦艦が20隻以上集まりだしたそうよ。」
「そんな露骨な行動を取るとは…not穏やかbut物騒ですな。理由は、目的は何なんです?」
「まだ分かんない。ただ…」
「ただ?」
「ただ、テフロン星系に何らかの空間の異常が発生しているのがこちらの基地で観測されているわ。それがロミュラスカによるものなのかどうかはまだ、何とも言えないけど。」
「我々の任務は?」
頷き、鱗粉を散らすナチェフ。
「ええ。私達も黙って見ている訳にはいかないでしょ。既に船を15隻程向かわせているわ。あなた達も合流して、国境地帯へ先頭に立って何が起きているのか探って欲しいの。」
「なるほど。国境を越える許可は下りるんでしょうか?」
レミはちょっと考える様子を見せた。
「んー、まだ。ロミュラスカより先に手を出すのはやめといてね。分かった?」
「了解しました。」
ちゃらーららーらーらー。
「通信終了。」
「…」
ピカは今度は目を押さえつつ、医療室の出口へ歩き出した。
冬月はつまづいた。
「ああ。」
「大丈夫ですか、大佐?」
皺だらけの、しかしやっぱりハゲ頭の冬月は、シンジを見て、しかめっつらになり頭を振った。
「違う。」
「は?」
饅頭工房を見回す冬月。
「ここは違う。ここはわしの世界ではない。」
シンジは少し辛そうな表情になった。別に手がはれているからではない。
「大佐…気持ちは分かりますけど、今更20世紀の世界に戻った所で…それに、あの時彼等が現れなかったら僕達人類は使徒に滅ぼされていたから、今度は、ミサさんの力を受け継いだ僕達が彼等に協力してあげようっていうのは、あの日皆で決めた事じゃないですか。第一今の技術でも、人工的に元の時代には」
「そういう事を言っているのではないのだ! 20世紀であろうが25世紀であろうが、とにかく、ここの世界は私の住んでいる世界ではないのだ!
良いか、今さっきまで、私は全く別の世界にいた。あれは…」
冬月は考え込んだ。
「…ああ、そうだ、エンタープライズだ。エンタープライズの中にいた。いや…エンタープライズではない…何か、違う名前だったはずだ。あれはエンタープライズだが、エンタープライズではない…あれは、つまり…」
「大佐、早く家に戻りましょう。医者を呼びますから。」
「違う、その必要はずぇんずぇん無いのだ! むぅ、わしがフェイズイルモディックのせいで変な事を言っていると思っておるな。そうではないのだ! そう思っておったら、それは大きな間違いだ。まだ、そこまでもうろくはしておらん。わしを年寄り扱いするのはあっ! ダメでちゅよー。」
やや忍耐力の切れてきたらしいシンジは頬に突かれた冬月の指をはらって答えた。
「分かりましたよ。…じゃあ、どうします? どうされたいんですか?」
冬月翁は考え込んだ。
ポク、ポク、ポク、グジュ。
「レイ君だ。」
「綾波?」
頷く冬月。
「ああそうだ、レイ君なら、明晰な分析で何とかしてくれるに違いない。」
「綾波だったら…確か、今はケンブリッジでしたよね?」
「そうだ、ケンブリッジだ。レイ君なら助けてくれる。今から行くぞ。」
シンジは肩を上げた。
「分かりました。じゃあ、ケンブリッジに行きましょう。」
2人は歩き出した。
こっこっ。こけーこっこっこ。ぴーよこちゃんじゃぴーよこちゃんじゃ。
「…」
再び工房の周囲にニワトリやピヨコの格好をした人々が現れ、彼等を指差し嘲笑いながら踊り狂っている。と思ったら数秒で消える。
冬月はますます不機嫌な様子になって言った。
「…君も見たかね。」
「何をですか?」怪訝そうなシンジ。
「…あいつらだ。何故笑う。何がおかしい? そんなにトムヤムクン(トムヤム君。)味の饅頭は嫌いか? 食わず嫌いが。1回食べてから言ってみるんだ。関係無いが食わず嫌い王で一時間潰すというのは、異常に安上がりな番組だな。」
「大佐、大佐。さあ、行きましょう。綾波の所へ。」
シンジはいたわるように元艦長に手をかける。
「ああ。そうだな。レイ君なら、何とかしてくれるだろう。」
2人はナンプラーの臭う饅頭工房を歩いていった。
「しかし、随分良い屋敷に住んでいるじゃないか。」
色白銀髪の上品な物腰の女性が、冬月の言葉に嬉しそうに微笑んだ。
「ここは代々ケンブリッジの、物理担当の教授の住居となってきたわ。ニュートン、ホーキング、デイタさん、皆ここに住んでいたの。」
3人はケンブリッジのレイの部屋にいた。昔ながらの重厚なイギリスの調度品が並んでいる。壁には一枚、月の写真が掲げられている。
「でも綾波、本当にすごいよ。」
「碇君はいつもそれね。」
「だってすごいじゃないか! 20代に入ってからの勉強で、500年もの進歩を飛び越えてケンブリッジの教授になっちゃうだなんて、常識じゃ考えられないですよね!」
肩を上げて同意する冬月。
「物理は発想とひらめきの問題よ。」
笑って、自分の頭を指して見せるレイ。
「25世紀の人間も、ほとんどの人は科学の法則なんて知らないのよ。知る必要が無いもの。500年もの進歩と言ったって、人類の身体そのものが飛躍的に発展を遂げている訳ではないわ。要は努力と、センス…かしら。」
レイは背後の本棚に目をやった。
「私から見れば、500年の感性の進歩を飛び越えて一線の作家になっている碇君の方がすごいと思うわ。」
本棚には、「愛と死の断章・第二幕」と書かれた古びた単行本が置かれている。
「やめてよ綾波。恥かしいじゃないか。未だに処女作を持ってるんだもんなあ。」
「あら。その口振りはデビュー当時からのファンへの冒涜じゃない?」
シンジとレイは笑い合った。
こん、こん。
「お茶の準備が出来ましたよ。」
イギリス人なのであろうメイドのオバサンが部屋にワゴンを引いて現れてきた。
「あー、日本茶はあるかね。」
「ええ。マダムがたまに飲まれますから。」
「じゃあ、ほうじ茶を頼むよ。」
「はい。」
メイドは乱暴に頷いてお茶をきゅうすに入れだす。
「もう、お客さんからも言って下さいよ。そんなに沢山ピアスを空けるもんじゃない、って。あれじゃまんま恋人プレイの奥野だわ。」
レイは微笑んだ。
「ハドソンさんは、いつもこんな感じで私を笑わせてくれるのよ。」
「でも、綾波。ほんと、どうしてそんなにピアスしてるんだい?」
お茶を配るハドソンから茶碗を受け取りつつシンジが聞く。
「絆、だから?」
「絆? 何との?」
「さあ?」
「…(振るだけでボケなしかい、綾波…)」(TT)
冬月はお茶を一口飲むなり顔をしかめた。
「何だこれは? こぶ茶じゃないかね?」
「…フン。」
鼻息で答えるメイド。
「それで綾波。大佐の事なんだけど…」
レイは頷き、真面目な、どこか昔の彼女を思い起こさせる表情になった。
「副司令…この前に、フェイズイルモディックの診察を受けたのはいつ。」
冬月はうんざり、の表情になった。
「三週間前だ。ツェンケティペダクソンを処方された。」
「でも、」
「分かっておる、ただの気安めだ、根本的な薬ではない。どんな薬も、神経シナプスの崩壊を止める事は不可能だよ。…私が病気のせいでおかしな事を言っていると思っているな? ああ、おかしと言っても、」
「誰もそんな事言ってないじゃないですか。」
遮るシンジ。
「副司令の話を聞いて…最初は私も、年を取った副司令は幻覚か、あるいは夢を見ているのかとも思ったわ。」
「…」顔をしかめる冬月。
「でも、そうではなく、本当に副司令は異なる時空を行き来しているのだ、という可能性も、否定は出来ないわね。」
元大佐の表情は一変した。
「そうだ、レイ君、君ならそう言ってくれると思っていたよ!」
レイの手をとる冬月。
「え、ええ…」思わず一歩後ろに下がり、表情筋がややピクピクするレイ。
「それでとりあえずラボの実験機具を使って副司令の脳をスキャンするわ。ハドソンさん。今日明日の講義はウェザーブレイク(キャンセル)よ。…いえ、今週一杯。」
「…フン。」
レイは微笑んだ。
「副司令、一緒に謎を解明しましょう!」
冬月は喜んで立ち上がった。
「それじゃ副提督、お願いします。」
シンジが改まった様子で、立ち上がる冬月に何やら紙を渡した。
「あ…ああ。」
冬月は頷き、ネルフ内のシャトルドックにやってきたクルー達の前で壇上に立ち、紙を読み上げだした。
「本日、宇宙暦2015…」
こっこっ、こけーこっこっ…
思わず顔を上げる冬月。シンジを始めクルー達は不思議そうな様子だ。
「…当船は、名称をエンタープライズAからネルフへと改名。同時に船長として、」
けーこっこっ、ぴーよこぴーよこ雌雄鑑別ぴーよぴーよ。
シャトルドックのあちらこちらで例の妙な格好の人々が冬月を嘲笑う。冬月の隣で何故か「じゅーす」とマジックで書いてあるエビチュをかっくらっていた保安担当官は、急に押し黙る冬月の異様な様子に手を止め、周囲を(ゲップをしながら)見回した。
冬月は顔をしかめつつ再び口を開く。
「…船長として、碇シンジ名誉大佐をここに任命するものである。スターフリート副提督冬月コウゾウ。かっこユイ命かっこ閉じ。」
文を読み上げた冬月は、壇を降り、中央のシンジへ微笑みながら歩み寄り、握手の手を差し出しかけた。その時。
こけーっ。こけーっ。こけーっ。こっこっこっこっクックドゥードゥル。クックドゥ! こっこっこっこっ小さい事からこつこつと。
3たびドックの周囲で妙な人々が騒いでいる。脅えるように周囲を見回す冬月(髪フサフサ)。
ぴーよぴーよ。卵クラブひよこクラブまむしクラブオカピクラブ。
こっこっこっこっこけーっ! ぴよぴよぴよ。むりっ。けーっこっこっこけーこっ(KEIKO)。
冬月はシンジに顔を向けた。
「シンジ君、いや船長。全デッキ戦闘態勢だ。」
「え? でも…」
「早くし給え、私の言った事が聞こえなかったかね!」
「は、はい! 全デッキ戦闘態勢、全デッキ戦闘態勢!」
船長の言葉に、慌てて持ち場へ駆けていくクルー達。
副提督個人日誌、宇宙暦2015.07.01。機密ロック、オメガ・ドライブのもとで記録。現在の私の身に起きている事をこの世界のクルー達に伝える訳にはいかない。いくら状況の異なるパラレルワールドであるとはいえ、未来の人間がこれから起きる事を予言するのはタブーである。足の臭いのプンプンする人間がゴーダチーズ好きの人間に接触するのもタブーである。糖尿臭のプンプンする人間(以下略)
上級士官達は船の会議室に集合していた。
「状況はどうだった、綾波。」
「全艦特に、異常報告は無かったわ。」
ヴァルカン人と地球人のハーフだが、地球人の血が比較的強いらしく耳の尖っていない副長が、シンジに答える。
「大体こんなオヤジの言う事なんかまともに信用できるのー? 偉そうに言ってるけどお。」
「あ、アスカ、副提督なんだから一応、ね?」
当船の医療及び嫉妬方面主任のドクター・惣流アスカは髪をかきあげた。
「フン。ねえシンジ、あんた船長なんだから、こいつの指図なんて受ける必要全然無いんだからね?
別に階級が上だって言ったって、ここの船長はあくまであんたなんだからさ。」
「う、うん、分かってるよアスカ。だから会議中に靴を脱いで足を絡めてくるのは止めてくれないかな。」
2人をスルーして冬月が聞く。
「ゲオ…げおっほごっほごっほ。…あー、葛城保安主任、この船に侵入者が入った形跡は?」
「うっひ。別に無いっすよぉ。げふ。」
「それではレ…いや、綾波副長、何かこの船に、異種の知的生命体を感じたりはしないかね。」
「いえ。私達以外に特別な物の存在は感じないわ。」
「船長。」
「や、アスカそこはちょっと、あ、いやもうちょっと右、」
「船長。」
「あ、あああはい。」シンジは我に帰って冬月に返事をした。
「じゃあ、ミサトさんは警備の徹底をお願いします。」
「げぷ。」
「綾波は、何か異常な物が無いか常に注意しててね。」
「了解、船長。」
クルー達はブリッジにやって来ていた。
ブリッジ後方でネコ耳型ヘッドホンに片耳を当てている通信士が言う。
「船長、宇宙艦隊司令部より通信です。デブロンギヌス星系に空間の異常が観測されたそうです。その為、第16宇宙基地への任務は中止となりました。代りにロミュラン帝国との中立地帯の国境へ向かい、異常現象を観測しろとの事です。」
「そうですか、じゃあ日向さんそうして下さい。」
くっくっく…くすくす…くっくっくっくっ…
「あ、あの、日向さん?」
ぽか。
「漫画読んでないで早く進めなさい。」
ミスター日向はフサ髪冬月に顔を上げた。
「あ、す、すいません副提督、えーとどちらへ?」
「…デブロンギヌス星系に近い、中立地帯への国境。」
「あ、はい、只今!」
「…何故「スズキ」でそこまで笑える?」やや冷や汗で呟く冬月。
冬月はふとメンソールの臭いに気付き、後ろを振り向いた。
「ああ、君がこの船の機関主任の赤木リツコ君だな。話は聞いてる。」
暇だったらしく、煙草をふかしつつぼーっと船長と医療主任の漫才を眺めていた機関主任は、突然自分の方に近づいてきた冬月に少し驚いたように眉を上げた。
「ええ、そうですけど。」
「あー、もしかして今、ディジリウムの結晶劣化について困っていたりはしないか?」
「え?」慌てて振り返り、後方のモニタを確認するリツコ。
「あ、ええ、その通りです。この船は中古品なので欠陥が多くて困ります。」
「そうだろうと思っていた。私が直しかたを知っている。機関室に付いてきてくれ給え。」
「え、ええ…」
リツコはやや驚いた様子で頷くとタバコを(アスカ・シンジ方向に)投げ捨て、冬月と一緒にターボリフトに乗り込んだ。二秒後ブリッジ炎上。
「ふんっ」
しゅー。
ドクターは自分が念じて接近させた火の玉を艦長の顔面から消滅させた。
「大丈夫、艦長。」
「大丈夫な訳あるかよおおおっ」
「また違う時空にいたのかしら。」
「あ、ああ、そうだ、そうでごぜえますだよ。」
「…ん。」
リツコは医療用モニタを見て、眉をひそめた。
「一体何かね。」
「今の数分間の間のビリビリパルス量が、通常では考えられない数値を示しているわ…この数分間の間に、艦長の大脳には、数日間分の記憶が蓄積されたという事が示されているのよ。」
ドクターの言葉に、髪の無いフユツキは、息をついた。
会議室に士官達が集まっていた。
スカパー!こと副長が尋ねる。
「結局理由は何なんでしょう?」
「分からん。レイタ、何か意見は。」
「情報が少なすぎるので何も言えないわ。」
「ゲォーフ、この船の警備は大丈夫か。」
「万全を期している。今の所侵入者は無い。」
「うむ。カウンセラー。」
「なあんも感じません。」
「これじゃあ手の打ちようがありませんね。」
スカパー!が肩を上げる。
じゅくじゅく。ことマコトはクルー達を見回した。
「艦長の時空移動と、テフロン星系で起きている事は何か関係があるんでしょうか?」
「それについても情報が少なすぎるので何も言えないわ。」
「そうか…」
ピカは自分の腕をくるくるねじりつつ(何かの体操らしい)言った。
「まあ、その話は置くとして、ロミュラスカの動きも重要だ。予定通りテフロン星系へ進路を進めるとしよう。解散。」
士官達は席を立った。
「あー、トロイ。」
副長は最後におもむろに立ち上がると、会議室を出て行こうとしたミサトに声をかけた。
「え、何、ライカー。」振り向くミサト。
「これから、クワガタのナイトレース、どうだい?」
カウンセラーは目をしばらく泳がせた。
「あ。ライカー、ごめーん。今日、ちょっち先約が。」
カウンセラーの向こうに、ドクターが立っていた。
「…ああ! すまん、気付かないで。」
「また今度ね。」ミサトは部屋を出ていった。
「…失礼、副長。」
「あ、ああ、ドクター。」
「という訳で、今度私が時空をスリップしている時はブリッジを頼むぞ副長。」
「…」
ぎりぎりぎりぎりむかむかむかむか…
艦長席のピカードは、隣の副長の様子に眉を上げた。
「副長?」
「あ、ああ、はい。その時は、ブリッジを。」
「大丈夫かピー?」
「大丈夫です。大丈夫に見えないって言うんですか艦長ぉ!」
「あ、い、いやあ別に…じゃあ艦長室にいるピー。」
「了解。」
「ああ、ゲォーフ、一体何だね。」
艦長室に逃げてきたフユツキは、ゲォーフが立っているのを見付けた。
「艦長、保安部主任として一言言いたい。」
「ああ。」椅子に腰掛け、促すピカード。
「ゆっくり休め。他の時空でどうかは知らないが、ここの艦長はずっと働きづめではないか。」
艦長は溜息をついた。
「ゲォーフ。わざわざそんな事で」
「私は本気だ。何なら保安部から正式に要請しても良い。」
「…分かった。考慮しておこう。」
むう。
「考慮ではなく、今すぐ休めと言っているのだ。」
ゲォーフはフユツキの手を取った。思わずのけぞるフユツキ。
「艦長。心配なのだ。艦長が疲れているようでは船の安全に関わるし、私も悲しい。ガチャピンが宇宙を飛ぶ所が全く見れなかった事並に悲しいのだ。」
「そ、そうか。」
「ああそうだ。俺の一番星を、こんな所で失いた…いや、何でもない。」
恥じらいの表情になるゲォーフ。
「…(油汗)」
「…艦長。」
「な、何だねゲォーフ。」
「率直に言って、私は動揺している。艦長は戦場で死ぬべき男だ。イルシノディック症候群などで死ぬような男であってはならない。」
レイちゃんチップスがダンボール箱で山積みしてある隣で、艦長は微笑んだ。
「ゲォーフ。あの未来は私達の住む世界とは全く別の世界だ。それはまあ確かに、人物に共通性はある程度見られるが、あそこの私はここの私とは違う。…それに。ゲォーフ、私が思うに、未来というものは自分の力でいくらでも変えられるものなのではないかね。」
ポッ
「艦長はやはり勇敢な戦士だな。」
「有り難う。」
「…艦長。」
「何だね。」
「か、か、かんちょおおおおおおおお」「うわああああああああああ」
「あああああああ」
「だ、大丈夫ですか大佐!」
「あ、へ、は?」周囲を見回す冬月。
シンジがいたわるように言う。
「綾波が、実験室の調整を終えました。いつでもスキャンできますよ。」
冬月は寝ていたソファーから起き上がった。
「ああいや、その必要は無い。今からロミュランとの中立地帯のテフロン星系へ向かうぞ。」
「テフロン星系?」
不思議そうに聞き返すシンジ。
「ああ、いや、デブロン星系だ。」
「デブロン星系…」
「今すぐ行かねばならんのだ! 良いか、他の二つの時空では、それぞれのデブロン星系に相当する地域で異常が発生しているのだ。この世界でもきっと、そこに何かあるに違いないのだ。」
「は、はあ…」
ぽかぽかぽか。
冬月はシンジの胸を叩いた。
「分からんか! これは非常に重要な事なんじゃぞ!!」
「でも、大佐。そもそも、デブロン星系に中立地帯なんてありませんよ? あの辺は8472種族の領域じゃないですか。」
冬月はシンジの言葉に目を広げ、頷いた。
「そうだ。その通りだった。この世界では、8472種族がロミュランを支配していたんだった。」
「それに最近は、彼等も以前ほど友好的じゃありませんし…」
「うむ…」
「まあ…どうしても行くって言うんなら、遮蔽装置のある船をまず見付けないと…」
冬月はシンジの言葉にニヤリと笑った。
「ふ。ふっふっふっはっはっはかはっごほっぐぼっ。おえ。いや、シンジ君、それについては、やはり昔のよしみを頼るとしようじゃあないか。」
「お助けしたいのは山々ですが、危険が高すぎます。」
連邦の制服姿の50代の女性が、困った表情でモニタの向こうで腕を組んでいる。
「しかしだな、デブロン星系に行かなければ何が起きているか分からんのだよ。」
「今朝その星系の観測結果が送られてきています。が、何の異常も探知されませんでした。」
「信用出来ん! 直接行かねば分からんではないか!」
「それでは国境付近にいるウルサン号に無人探査機を発射させましょう。」
「いや駄目だ、自分の目で確かめん事にはな。」
「ですけど、危険な領域ですし、あそこに今連邦の船は行く事は出来ないんです。」
「良いか赤木君、事態は」
「残念ですが、」リツコは冬月の言葉を遮った。
「私に出来る事は、これが精一杯です。通信終了。」
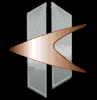
横倒しの矢尻のような形の、連邦のマークが「通信終了」の文字とともに現れる。
「コンピューター、ホログラム再生。」
冬月の横で立っていたレイが言うと、モニタ画面のあった場所は他と同じように19世紀イギリス風の暖炉に姿を変えた。
「まったく。赤木君も年を取るとともにますます融通が効かなくなりおって。あれだから結婚出来んのだ。まったく、艦長になったとたんに、性格が変わりおった。」
冬月にシンジが苦笑する。
「そんな事はないですよ。ただ、ここでは多くの人命を預かる身ですから、」
「第三東京の頃はそれどころではなかったぞ。」
「ええ、それは、まあ、そうですけど…」
老冬月は溜息をついた。
「しかし、これでは、デブロン星系への道は絶たれたも同然だな。まあ、今となっては、ウルサンの報告を待つしか…」
「いや、ちょっと待って下さい、医療船で行くっていうのはどうでしょう?」
レイは指を鳴らした。
「そうよ碇君! 医療船なら、最近ロミュラン星でケルバン熱が流行っている関係上連邦の船でも領域に入る事が許されているわ。」
「そうか。医療船か。」頷く冬月。
「でも、どこの医療船に乗るかが問題ですけど…」
「USSマッコイという船は、どうかしら?」レイの言葉にシンジと冬月は顔を上げた。微笑むレイ。
「あそこの艦長とは、少し、コネがあるの。…いえ、以前はあった、というべきかしら?」
「大佐!」
ブリッジのドアが開くと、艦長席の女性が立ち上がり、冬月達の方にやってきた。
「艦長、君も随分と熟熟してきたなあ。今などもう両胸の果実が熟しきってまさに食べぐふっ」
かかと落し。
「アスカ。」
「ああ、シンジ。」艦長はシンジと抱き合った。
「変わってないわねえ。…お腹が少したるんできたかしら?」
「まだ大丈夫だよ。」
アスカは最後に、(老人の屍を踏みつけつつ)銀髪の女性に近づいた。
「レイ。」
「アスカ。」
抱き合おうとする2人だが、どうもタイミングが合わない。
「ああ、いつもこうなのよ。」ようやくアスカとレイは抱き締め合った。
「レイ、もう話は聞いたわ。でも今、デブロン星系に行くだなんて無茶よ。…あなたの頼みじゃ断れないけど。」
「あら、だからプロポーズも受けたのかしら?」
レイとアスカは微笑み合った。
「それでは行ってくれるんだな。」
(復活した)冬月にアスカは「ええ」と答えた。
「でも、差し当たっての問題は、国境をどうやって越えるかよね。」
アスカに頷くシンジ。
「加持さんに頼んでみるのはどうだろう?」
「そうだ、加持君だ! 8472領域で力のある地球人等彼以外にはいまい。」
「綾波、加持さんは今も、政府でクリンゴンとの折衝役をやってるのかな。」
レイは眉を寄せた。
「どうかしら…最近8472領域の政治情報はあまり入ってこないので、確かな事は言えないのだけど…最後の情報では、ハドゥルスの知事になったと聞いた事があったわ。…国境付近の小さなコロニーよ。」
「至急連絡をつけるようにするわ。」
アスカが答える。
「じゃあ、大佐はゆっくり休んでて。少尉、彼を客室まで御案内するのよ。」
「あ゛ーそんな物はいらん。一人で行けるわい。それこそ、GSスタジオ8階社長の江藤ですって奴だ。不愉快極まりない。」
昔に比べて大分忍耐力の付いたアスカは溜息をつきつつ頷いた。
「そうね。今のは、私が悪かったわ。」
「…うむ…じゃあ…ちょっと、休んでくる。」
冬月翁はターボリフトに乗り込んだ。
「「「…」」」3人は溜息をついた。
「…最後にフェイズイルモディックの診察を受けたのはいつ?」
「三週間前だって言ってた。でも、もうあんな診察二度と受けるか、時間の無駄だ、とも言ってたよ。」
シンジはアスカに答えた。
「…皆、アイツの言う事、どれ位本当だと思う?」
「「…」」伏し目がちになるレイとシンジ。アスカは唇をかみつつ頷いた。
「うん…私も分かんないのよ。…でも、我等が冬月大佐が最後の任務をお望みとあれば、かなえてあげましょうよ。」
ターボリフトの中では、先程のアスカの蹴りが効いたらしく老冬月がけほけほ言いながら胸を叩いていた。ターボリフトのドアが開く。
リフトからブリッジに現れた冬月はスタスタと歩き、船長席の横に来た。
「船長、今までの所何か異常はあったかね?」
シンジ船長が振り返る。
「いいえ副提督、特に異常は見当たりません。」
「葛城保安主任。かつら…」
ぐー。ぐー。ぐー。
「…」
溜息をつく冬月。
何故かブリッジにいるドクター惣流は、シンジの座る船長席近くで何やらパッドを見て、うっとり頬を赤らめている。
「ねえ、シンジ。つくづく思うんだけどさ、この人の小説っていつも、感動的に素晴らしいわよねえ。」
「え? ああ、最近アスカのはまってる、K-tarowさんの小説?」
「うん。やっぱりこの、主人公二人の台詞のみちゃんと色付きなのがとっても分かり易い、っていうか…」
「は、はあ…(これってやっぱり、迫られてる、って事か?…)」
椅子の肘掛けに腰を降ろしているアスカはシンジの方にもたれかかる。
「うーん。ねえシンジ、今度ここにのってるこのプレ」
「…そうか、奴の仕業か!!」
「「え。」」
何かを思い付いた様子の冬月はレイに顔を向けた。
「…綾波副長。何か特殊な障害物や現象、高エネルギー反応などは無いか。」
冬月の言葉に、セルロイド製の潜望鏡風のものを覗き見るレイ。
「いえ。」
「あるいは異星人の存在を感じたりはしないか。非常に高度な知性を持つ生命体だ。」
「クルー以外の生命体の存在は一切感じないわ。」
「うむ…」
冬月は船長席の前、ブリッジ中央に進み立った。
「私はもう切れたぞ! もうお遊びはこれまでだ!」
副提督は突然叫びだした。呆気に取られた様子のクルー達。
「お前の仕業である事はもう分かっている。出てこい、K! もう好い加減隠れているのは止めろ!」
「…K? Kって、K-tarowさんの事かな?」ぽかんと呟くシンジ。
「K先生を呼び捨てにするなんて、…って、先生がこの船に乗ってんの?」シンジに聞くアスカ。
「いつまでこんな事を続けるつもりだ、K、出て来給え!」
冬月はレイに聞く。
「何か異常は起きていないか?」
「いいえ。唯一あなたの行動が意外性を伴っているわ。」
「私は大丈夫だ。…おかしい。これは間違いなく奴のはずなんだが…船長、何かあったら知らせてくれ。私は自室にいる。」
冬月はターボリフトに乗り込んだ。
そして彼は集会所のような建物の中に出てきた。
「…」
やや教会にも似た作りの建物の中央にフユツキはいた。そして周囲の「客席」には、ニワトリやヒヨコの扮装をした人々が大入り満員で騒いでいる。皆「舞台」のフユツキを嘲笑っているようだ。
「待ちくたびれましたよ。」
フユツキが振り向くと、向こうから銀髪の超美少年が、何もない空中で、椅子に座るかのようにぷかぷかと浮いていた。
「ようやく辿り着きましたね。あなたはもう、ここまで来れないんじゃないかと心配していたんですけどねえ。」
Kの言葉に観客達はどっと沸いた。
「…K。この妙な空間は一体何だ。」
「知らない訳はないでしょう? 人類の野蛮さ、乱暴さ、醜さ、愚かさを示す一番の空間じゃないですか。」
「21世紀初頭、有精(卵)戦争時代の魔女裁判という訳か。」
「ぴったりの場所でしょう?」
こっこっこっここけーっこっこっこっ。ぴーよこちゃんぴーよこちゃん。
沸き返る傍聴人達。
Kはふいに(空中だが)立ち上がり、手を上げ傍聴人達を静めた。
「これより人類に対する裁判を再び始める。起訴状。人類は野蛮かつ傲慢、自己中心的な種族であり、これ以上の発展は宇宙全体にとって危機である。」
こっこけーこっこっこっこっぷりっ。
再び盛り上がる傍聴席。
「一体何のつもりだピー!」
「これより被告に10の質問を認める。ただし僕の答えはイエスかノー。それ以外の質問をした時は、その場で質問は打ち切りますよ。」
ピカは困ったように周囲を見回し、やがて口を開いた。
「また君は、私達を試験にかけようとしているのかね。」
Kはしばらく考えるようなそぶりを見せ、両手を広げた。
「いいえ。」
ブーイングの起こる傍聴席。
「7年前の事と今回の事に何か関係は?」
「…まあ、強いて言えばイエスでしょうね。」
「今回の事とテフロン星系の現象は、何か関係あるのかね。」
Kは微笑んだ。
「それはもう、まぎれもなくイエスでしょう。」
コスプレ達は沸きに沸いた。
「これは、ロミュラスカの罠か? 戦争の前触れか?」
「どちらもノー。これでもう残りは5つ。」
「まだ4つしか質問をしていないぞ?」
Kは美しすぎる顔で指を振る。
「ロミュラスカの罠か? 戦争の前触れか? …残りは5つでしょう。」
「ブチコロス…テフロン星系の空間の異常を作ったのは君かね?」
「とんでもない! …事実を知ったら、艦長は驚くでしょうね。」
「私が時空を動くようにさせたのは君かね?」
Kはふっ、と笑った。
「もし誰にも言わないなら教えましょう。」ゆらー、とピカードの耳元に近づくK。
「イエス、です。」
「何故だ?」
「残念! イエスかノー以外の質問をしましたね、これにて質問は打ち切りとします。」
「何故だ…何故タモリはああも子供嫌いなんだっ!」
「あー、艦長?」
「え?」
「質問、打ち切りです。」
ピカードは頭を振った。
「K、我々に対する裁判は、既に無罪と判決が出たはずだ。」
「状況が変われば再び起訴される事もある、当然の事でしょう? シンジ君をついに212体全部使い切っちゃったから、暇だし…とにかく、この7年間はあなた達人類がどれだけ進歩の跡が見られたかを見る、いわば観察期間だったんですよ。しかしあなた達は7年間を無駄に過ごした。この7年の間にあなた方のした事といえば? 変な食べ物を作ったり、掲示板でもめごとを起こしたり、妙なスクリプトで遊んでいたりしただけじゃないですか?」
「我々は宇宙を探索し、新たな文明や星々との交流を深めた。今や量ではめぞん一(タブン)だ。我々のこの宇宙に対する理解は、以前よりも遥かに深まっている。」
「この先待っている事も知らずに良く言いますね。」
沸き立つ会場。
「残念ですが、そう悠長な事を言っている訳にもいかないんですよ。もうそろそろ、あなた方のお話も終わりにしないと。」
Kは微笑みつつ頭を振って見せた。
「我々が宇宙を旅するのを否定するというピーか。」
「まだ、分かっていないようですねえ。」再び浮かび上がり、傍聴人達に言うK。法廷はバカウケだ。
「あなた達は存在を否定された。この宇宙から、いなくなるという事なんですよ。」
フユツキ・コウゾウ・ピカードは、信じられないといった様子で顔を上げた。
「確かにK、君の、その…力、には良く驚かされる。しかしいくら君でも、人類を消滅させるような力は無いだピー?」
微笑んで頭を振るK。
「フユツキさん。あなたはいつも僕の事を悪者扱いしていますね。でも自分の事も、少しは振り返ってみる必要も、あるんじゃないですか?」
Kは両手を広げた。再び艦長の耳元に近づくK。
「今回人類滅亡の危機を作るのは僕じゃない。艦長。あなたですよ。あなたと作者の罪だ。まったく、過去や未来のあなたは何の罪も無いのに、現在のあなたのお陰で同時に滅ぼされてしまうんですよ?」
「K、その訳の分からない言葉遊びはやめてくれないか。そもそも「作者」とは何だね。」
「まだ、分かってないんですねえ。」
大騒ぎして、冬月を嘲笑う観客達。
「これは僕の見込み違いだったかな? 冬月さん、僕はあなたなら分かってくれる、あなたなら、この状況から人類を救えるんじゃないかと、密かに期待していたんですけどねえ。」
冬月に近づくK。
「7年前の判決は仮の物でした。今、本当の判決をあなた方リリンに下しましょう。有罪。…これにて本法廷は閉廷とします!」
気付くとフユツキはエバンゲリオン、艦長室のレイちゃん人間椅子に座っていた。立ち上がりブリッジに行く艦長。
「副長、全艦非常態勢だ。」驚き立ち上がるライカー。艦長は頷いた。
「事態は思ったより深刻だっちゃ。」副長は艦長の言葉に表情を変えた。
後編へつづく
前編おまけ・衝撃のオフ会レポート
これは某ウェブサイト「E○cyclopaedica Franke○a」のオフ会に赴いた作者のノンフィクション記録である−
8月9日(日曜日)
私は、カザフスタンの首都、アルマトイの空港に降り立っていた。成田からソウルを経由しての2日がかりの旅である。私はここで「Саба
миникаб(鯖ミニキャブ)」という表示の車を探すよう言われていたので、カザフ名物焼きリンゴ売り達の人波をかきわけ懸命にその車を探していた。
あった。あの車がそうに違いない。
私が見つけたのは、間違いなく旧ソビエト連邦時代から活躍していたのであろう古ぼけたトラックであった。何やら丸から3つの扇型が出るような黄色地に黒のマークがたくさん描かれている。何かのロゴなのだろうか?
私はトラックのドライバーに尋ねた。
「あ、あーゆーみすたーでざーとばれー?」
「No. But he is my master, sir.」
「あいむ、ふらんけん! あ、英語だから…けん・ふらん!」
「Oh! You are Ken! Салам! Take a ride, now!」
「お、おーけー。」
私はトラックに乗り込んだ。
ドライバー氏の話では、カザフスタンは民主化後も比較的治安がよかったのだが、最近事情が変わりつつあるとの事。「日本人は歓迎だよ、何しろ昔ロシアを負かした奴等だからな。」どうやらカザフ系らしいドライバー氏はそういうとニカッと笑うのだった。
車はアルマトイの郊外に出、ひっそりとした森の中にやがて入った。
「あ、あれは!」
「Yes. This is the Palace.」
私の目の前には、高さ20メートルはあろうかという巨大な全裸綾波像が神々しい光を放ち立っていた。そしてその向こうには巨大な大理石作りのお屋敷。そう、これが遠く極東でも噂に聞く鯖御殿である。
既にこの連載を読んでいる読者で知らない者もいないだろうが、砂漠谷氏は鯖を原料としたフルーチェでユトレヒト地方を中心に大成功を収め、その後セクシーアイドルグループの一員となったりイカすバンド天国に落選したり触る者皆傷つけたりして(フミアート)、現在はこの国の大統領となったのである。ここは砂漠谷氏のいわば隠れ家的な別荘であるらしい。
トラックを降りると、建物から白髪の老人が杖を突いて現れた。
「アヤ・ナミ・イチ・バン。(良く来たな。)」
「マユー!(始めまして。)」
(以下日本語)
「どうじゃったか、わしを見て驚かれたのではないかの。」
「いえ、とんでもありません。閣下。」
「無理を言うでない。顔に出ておるぞ。まあ、くつろいで行くのじゃ。…ああ、すまん、レイたんへの祈りの時間だ。」
「はああああレイたんレイたんレイたーああん!!」
周知の通りこの国では一日に五回のレイの神への祈りが欠かせない。…「レイの神」というのは厳密には不正確な表現であろう。ここでは「レイ」即ち「神」なのだ。私は仏教徒のような無宗教のような、いわゆる普通の日本人なので祈りに参加はしないが、やはり彼等の敬虔さを改めて目の当たりにすると心を打たれるものがあった。
「もう他の者どもは向こうの客室で酒盛りを始めておる。お前も早く行くが良い。」
祈りの後という事で服が乱れ、頬の少し上気した大統領はそうおっしゃられた。
「ははー。閣下。」
客室に行くと、3人の仲間達が飲み食いをし、半裸の女をはべらせていた。しかし3人とも雰囲気がおよそバラバラで、統一性は無い。
一人の男は、私は既に以前パラグアイで会っていたので顔を覚えていた。
「SOUさん、お久しぶりです。」
「いやあ、研君じゃないか。久しぶりだね。」
30代の若者(と、まだ言って良いだろう)が、快活に微笑んで答えた。彼は髭を生やしていて、おまけに背中にカラシニコフか何か、私は詳しくないので良く分からないが、間違いなく本物の機関銃を背負っている。しかし間違いなく全体としては姫宮のコスプレだ。
「最近調子はどうですか。」
「どうもこうもないさ。もはやだるいっちゅーの! だ。はは、今の、パイレーツだぞ。ナウいだろ。」
「はは、は…」
彼は20代の頃はお笑い芸人として因島地方では有名だったらしい。…全国区にならなくて良かった。
「セルゲイどん、だっちゅーのは今や古いでごあすぞ。」
その隣、エヴァトレのミサトよろしくMyプールを室内に持ち込みプカプカ浮きながら話すのは齊藤りゅう氏だ。ちなみにセルゲイというのはSOU(セルゲイ・オルチェディン・上田)氏の本名である。
「何だと! 俺様のギャグセンスに文句を付けるつもりか!」
「今や時代はつながりグランプリでごあああす! 鳥と餅で焼きつながり!!
くーっ、ちょマブってかんじでごあすうっ!」
「「「…」」」
こぽこぽこぽこぽこぽ…
言い忘れたが齊藤氏は人間ではない。コンピューターに接続されているがれっきとしたマンボウだ。はためにはぽか。と口をあけて水槽の中を漂っているだけのように見えるが、その知性はここに集まるもの達の中でも段違いに素晴らしいに違いない。
また彼は愛犬家としても知られ、下落合の御自宅には7万8千頭のプードル(のみ)が可愛がられているそうだ。と言っても犬畜生は頭が悪いので、飼育係にはなつくが水槽の巨大マンボウには常に歯をむけてうなるらしい。不幸な話である。
「何だか、どっちもどっちって感じだわ。」
最後に口を開いたのはまっこう氏、こと赤木リツコ氏だ。気付いていない読者が多いようだが、「まっこう」氏という現実に存在する男性が「りっちゃん」氏を演じているのではない。その逆なのである。「りっちゃん」氏が架空の「まっこう」氏を演じているのだ。未だに騙されている…と言っては何だが、勘違いしている読者が多いのだが、本人は気にしていないようだ。
今年でまだ13歳のりっちゃん氏だが、既に充分大人になっているらしく周囲には飲み干したウォッカ(もしくは「ヴォトカ」)の瓶が散らかっている。
グラストロンをかけっぱなしのリツコ嬢はふいに私の方を向いた。
「研君、研君は最近のアジア株は下げ止まったと思う?」
「え? いや、その、僕は学生だから、あんまりそういう事は…」
「そう。…まだまだ余談を許さないわね。でも私は、やっぱりユエジャオのいるセルパガングループを応援しない訳にはいかないわ。」
「は、はあ…」
「りっちゃんも大変だな。経営する企業がたくさんあると。」
「あら、そんな事は無いわ。私は資本を出して応援するだけ。基本的には現地の経営者まかせ、好い加減なものよ。」
りっちゃん氏はSOUことセルゲイ氏に答えると、(13歳のはずだが)すぱーっとハバナ産の葉巻を吸う。もちろんグラストロンはかけっぱなしだ。
「君達仲良くやっているかね。」大統領がやってきた。
「君達には、ここ特産の川鯖フルーチェ料理を振る舞うとしよう。ああ、斉藤君にはカスピ海特産のプランクトンを御馳走するとしよう。」
「ああ、それはありがたいでごあすうう。」
「…何でコンピューターで訳してるのに方言なんだろ…」
食事の席ではSOU氏はお得意のエヴァ小説論(いつものように高橋覗は時田と結ばれなくてはならないというLTT論を熱く語られていた)、鯖氏は林原めぐみのアゴの秘密やロズウェル勤務時代の裏話、りっちゃん氏は子供らしく、好きな漫画について、齊藤氏はモーニング娘。の今後等について、それぞれ語られていた。私はそれぞれの濃い内容についてただただ圧倒されるばかりだ。特にりっちゃん氏が最近はまっているという漫画「サンワリ君」についてはその形而上学的意味についてりっちゃん氏・砂漠谷氏の間で鋭い議論が交わされた。
雰囲気がおかしくなったのは午後になってからだった。朝からずっと飲んでいたSOU氏が、再び酔いが回ってきたらしくやたらと鯖氏に絡むのだ。
「それにしてもエライよ、あんたは。こんな立派な国の大統領さんなんだもんな。まったく、出世したもんだよ。」
「セルゲイ、少し飲み過ぎたな?」
「ああそうさ、そもそも俺は、最初から今日は飲むつもりだったんだ。」
「セルゲイどん、ここはあくまでオフ会、祝いの場でごあすぞ。」
「そうよセルゲイ、私情を挟むのは止めなさい。」
「うるさい、お前等に分かってたまるか! …麗馬、お前には、聞かなきゃならない事がある。…何故俺を捨てた。」
「「「…」」」「こぽこぽこぽ…」
「…怖かったのじゃよ。何と言うか…まだお前の責任を、全て取るような自信は無かったのじゃ。」
「俺はあの日フィフス・アヴェニューの丸越デパート前で、」
「言うな。それ以上言うでない。」
「いや、言うさ。俺はあの日、丸越デパートの子供用品売り場でずっと待っていた。ポピンズショーが始まっても待っていた。ポピンズには目もくれずにな!
何故だか分かるか? それは、俺はあんたを愛していたからだったんだよ!」
「昔の話じゃよ。セルゲイ。全て昔の話じゃ。」
こぽこぽこぽ。
「そうでガスよ。ワタァシのクニィではぁ、元恋人達も皆カコォにとらわれぇずに再会スルゥものデェス。」
「口調変わってるわよ?」
SOU氏は機関銃を手に立ち上がった。
「俺はこだわる。麗馬、俺がこの国でゲリラ活動をしているのは、建前は民主化の為等と言っているが、本当はそんな事じゃない。お前が憎いから、なのさ。」
そう、SOU氏はコメディアン上がりの現解放軍ゲリラだったのだ。オフ会とはいえ、こうして彼がちゃんと会場に現れた事がむしろ奇跡と言えたであろう。
「…何故、一思いに殺さん?」
「その方が俺を捨てたあんたを、より苦しめる事が出来るからに決まってるだろ?
りっちゃん、行くぞ。」
「何、もう帰るっていうの?」
「ああ、所詮大統領閣下と俺なんかじゃ格が違う。お呼びじゃないのさ。」
「そう簡単に帰ってもらう訳にはいかん。」
すちゃ。
「何?」
そう、ゲリラとしてのSOU氏の唯一にして最大の問題点は、人に甘すぎるという所だった。彼(と私達)は大統領の私兵達数十人に囲まれてしまったのだ。
「野郎、勝手な事をしやがって!」
ずだだだだ
SOU氏とりっちゃん氏は逃走を開始した。
「セルゲイ、あそこに通り抜けループを設置してるわ!」
「了解!」
ずだだだだ
かしゃーん
「ああっ、斉藤さん!!」
流れ弾で水槽が割れ、齊藤りゅう氏が流れ出てしまった。
「だ、大丈夫でごあす…」
「大丈夫な訳無いじゃないですか、早く水槽を!」
「おいどんには構わずに、君も早く逃げるでごあす!」
「そ、そんな…」
「オフ会は、」
ぴかーん
浜辺の夕陽にさんさんと輝く齊藤さん(マンボウ)の笑顔。
斉藤さん、あなたの事はいつまでも忘れな」
ぴく、ぴく。
「まだ死んでないごあす!!」
「あ、まだね。」
「フランどん、この国を救うには、彼等の仲違いを解消させるしかないでごあすよ。」
「で、でも、両方とも愛憎絡んでるからややこしいし…せめて冷静なりっちゃんさんが中立になってくれれば…」
ひゅーーーずがががーん。
「わあああああ」
ぴく、ぴく。
「彼等は元は、同じ甑島大学落研出身の仲間だったでごあす。…おいどんもそうだったでごあすが。」
「え、えええ」
「彼等の仲は、そしてカザフの平和は、フランどん、あなたの肩に…」
ぴく。
「齊藤さああああああん!!」
ぴかーん
浜辺の夕陽に(略)
その後の私の逃避行は省略しよう。内乱の勃発したカザフを何とか脱出した私は、今こうやって成田エキスプレスの車内で文を書いている。…え? 1回のキッチンでお前のママがチャーハンを作っている音が聞こえる? それは気のせいだ。とにかく私は帰国した。オフ会は途中までは楽しいものだったが、最後には斉藤さんを失ってしまう&カザフ内戦勃発という悲しい結果に終わってしまった。しかしこれでは我等があおぎり派は空中分解だ。こんな事では5代目あおぎり様も悲しまれるに違いない。
大統領閣下、セルゲイ、りっちゃんへ。考え直して欲しい。私達が求めていたのは流血ではなかったはずだ。皆さんの力で真の友情(パワー)を、そしてカザフの平和を取り戻して欲しいと心から願う。
前回のあらすじ
「私は、どうやら、過去と現在、未来の違う世界を、行き来しているようなのだピー。」
「俺様の暴れん坊将軍をパイルダー・オン!!」
「せんだ、みつお、ナハ、ナハ!」
「農業の基本は、土壌だ。」
「全寮制予備校。通学も出来ます。」
「将軍、向こうから綾波ランの軍隊がウインドサーフィンで攻めてきます!」
「せんだ、みつお、ナハ、ナハ!」
「この中に一人、コスモ星丸がいる!」
「せんだ、みつお、ナハ、ナハ!」
−謎は深まるばかりだ。
―宇宙。そこは最後のボランティア(意味不明)。これは、宇宙戦艦エバンゲリオン号が、新世代のクルーの下に、24世紀において概ね任務を続行し、未知の世界を探索して、新しい生命と文明を求めるふりをしつつ、人類未踏の宇宙に、アバウトに航海したりしなかったりする小話である―


「しかし、そもそも彼の言う事がどこまで本当かが問題ですね。」
クルー達は会議室に集まっていた。酢だこさん太郎スペシャルを口からたらしつつ副長が言う。
「Kの言う事なんか信用できませんよ。艦長をからかっているだけなんじゃないですか?」
ラ=フォージの言葉にピカードは首を振った。
「どうもそういう感じではない。今回のKは、いやに…ギャグや性欲が少なかった。どうも私には、彼の言っている事が本当のような気がしてならないのだ。」
トロイが聞く。
「じゃあ、Kは艦長に、危機を知らせる為にわざとパラレルワールドを移動させてるって事?」
マコトは肩を上げた。
「でも、何でそんな親切をKがする必要が?」
「いや、その可能性は確かにあるな。元々Kは人間という生命体にひどく興味を抱いているように見える。我々がこの危機をどう乗り越えるか、彼はそれを見たがっているのではないだろうか。」
「ええ。彼と人間、特にピカード艦長の関係は、サドマゾにおける女王様と奴隷のようにも見えるわ。つまり一見突き放しているようで、実は愛情を持っているのではないかと推測されるという点において…」
「「「「「「…」」」」」」
「比喩表現よ。」レイタは無表情に付け足した。
「それでは仮にそうだとして、我々は一体どうすれば良いんだろう。人類滅亡の原因が艦長だとして、拘禁室に拘禁しますか。」
ゲォーフがリョウジに答える。
「しかしそうして、艦長がいるべき時にいないという事が悪い結果を引き起こすのかもしれん。」
「ここでこうやって議論をしててもしょうがないじゃん。その場その場でベストを尽くすしかないっしょ。」
「ああ、確かにカウンセラーの言う通りだな。とにかくテフロン星系へ向かうとしよう。解散。」
フユツキが艦長室からブリッジにやってくると、ミサトが困ったように腕組みして立っていた。
「どうしたカウンセラー。」
「…いやあ、何か、星系に近づくにつれて船全体のクルー達の気持ちが凄く感じられるようになってるんっすよ。」
「どういう気持ちだ?」
「いや、良く分からないんすけど、何か…凄く強烈な、どこか甘ったるい感じの…現在の緊迫した状況とはあまりそぐわないような…」
「うむ…より詳しい事が分かったら言ってくれ給え。」
艦長席に座る髪無しフユツキ。
「星系付近の国境に到着しました。」
「分かった副長。ゲォーフ、付近の船は?」
「連邦の船が19隻、ロミュラスカの船がウォー・バーグを主力に27隻だ。」
「多いな…」呟く副長。
「旗艦に通信を呼びかけてくれ給え。」
パネルを操作するゲォーフ。
「応答があった。スクリーンに出す。」
「おう、艦長、久しぶりじゃないか。」
意外にも普通の地球人の部屋と変わらない雰囲気の執務室で、加持は微笑んでいる。右目に人工レンズ独特の模様がある以外は、昔と殆ど雰囲気は変わっていない。
「加持さんに艦長なんて呼ばれたら、調子狂うわ。」モニタを見て微笑むアスカ。
「で、話の方は聞いてくれた?」
「ああ、その事だが、残念だが国境通過を許可する事は出来ない。」
アスカは表情を一変させた。
「なーんでええ!」
「現在ここの情勢は非常に危険だ。いつ君達をバイオシップが襲うとも限らない。そんな場所に君達を通す訳にはいかないのさ。特にそんな、戦闘能力ゼロの医療船ではね。…正直赤木大佐が何故遮蔽能力のある船を貸してくれなかったのか不思議だな…」
「今そんな事を言っている場合ではない。とにかく我々はデブロン星系へ行かねばならんのだよ。」
「お言葉ですが大佐、その星系からは、今朝報告が入りました。何の異常も無かったそうですよ。」
「この目で確かめなければ分からん!」大佐はモニタの向こうの加持を一喝した。
「国境通過を許可する事は出来ません。」加持は頭を振った。
「…ふん、全く。君も変わってしまったな。以前の君は普段はスイカを違法栽培するただのムダ飯食いだが、いざという時にはチルドレン達の安全を守る、そういう男ではなかったのかね?」
「「「(今危険に冒そうとしてるのあんただろ…)」」」チルドレン達が全員心の中で突っ込む。
「だから今、こうやってあなたを止めようとしているんですよ。」
「あ、そうか。」納得する冬月。
「「「(おい。)」」」
「加持さぁん。」アスカは恐らく前頭葉右16度位から発生されるのであろう甘ったるい声で加持に言う。
「そんなつれなくしないでえ。お願ぁい。」
両手を組み、目をウルウルとさせるアスカ。
「駄目だよ艦長、そういう訳にはいかないんだ。」
「お願あい。」まねして甘ったるい声を出すレイ。
「う…駄目、だよ。」体の動きがぎこちなくなる加持。
「む。」ピク、と額の動くアスカ。
「お願ああい。」更に真似をするシンジ。
「う、いや、その…」
ピク、ピクピク。
「お願ああああああいいいい。」
「ふー。」加持は頭を軽くおさえ、溜息をついた。
「分かりました、許可しましょう。」
がーん。
「(か、かか加持さんの趣味ってふゆ、ふ、ふ、ふゆ、ふ(略))」
ぷしゅー。
何やら燃え尽き、へたりこんでいる艦長。
「ただし、私をガイドとして連れて行く事が条件です。」
「願ったりだよ。」冬月翁は加持に微笑んだ。
「お、お客様を転送室にお迎えして。」
何とか意識を取り戻したらしい艦長が命令する。
「う゛ぅ。ああ、それから大佐。一つはっきりさせたい事があるわ。この船には火力は殆ど備わってないから、何か危険があればいつでも退却するわよ。」
「…分かった。」
「それじゃあ少尉、デブロン星系へ、ワープ27…」手を上げ、口を開きかけたアスカは、ふと冬月に微笑んだ。
「久しぶりに、言ってみる?」
「あ、ああ。…それでは…発進。」
「発進? どこへですか?」
ミスター日向が顔を上げた。
「デブロンギヌス星系へだよ。空間の異常をより詳しく知りたいからな。」
マヤが後ろから口を挟む。
「え、でも副提督、国境はあくまで越えてはならないという指令が本部の方から」
「しかし空間の異常の原因は何としても突き止めなくてはならないだろう。」
マヤに答える冬月。
「は、はあ…」
「中立地帯の中ですよ?」尋ねる船長。
「分かっている。行き給え。」
「分かりました…日向さん。」
「了解。デブロンギヌス星系へコース設定。」
「あの、副提督。会議室の方で少し、良いですか。」
「…ああ。」
会議室に入ると、シンジは首を振った。
「一体、何なんですか? それは確かに副提督が立派な人なのは知っていますし、尊敬もしています。でも僕が船長であるにも関わらず、ああ頭ごなしにああしろこうしろ言われたら…この船は、僕の船になるはずじゃなかったんですか?」
冬月はシンジの抗議に頷いた。
「確かに君の気持ちは分かる。」
「それとも、やっぱり僕じゃ船長不適格だっていうんですか。まだ14歳だから? 親のこねで船を持ったから? 実はアカデミーにも落ちてるバカ息子だから? 実は東京少年の熱烈なファンだったから?」
「違う、別にそういうつもりではないんだ。私としても、君が船長である事は充分尊重したいと思っている。ただ今は状況が非常に特殊で、その状況を理解しているのはこの船では私だけなのだよ。」
答えるフサフサ冬月。
「じゃあ、その状況を説明して下さい。」
「今は出来ない。」
「…」ムッとした様子のシンジ。
机の三面式モニタに、マヤの顔が写った。
「船長、碇提督より通信が入っています。」
「こっちに回して下さい。」
「了解。」
モニタに、碇提督の手と口と髭付近のみが映し出された。
「シンジ、元気か。」
「と、父さん…」
「む。そこは小型モニタだな。つまらん。」がばっ
「「うわあああっ」」
アップの映像が急に横に流れていったかと思うと、普通のズームの提督が映し出された。
「ってあんた最初の映像書き割りだったんかいいいっ!」
「そうだ冬月。時にお前、私のらぶりぃシンちゃんの船で一体何をしている。とっとと帰ってこい。」
「いや碇、そういう訳にはいかん。」
む。
「シンちゃんの船を乗っ取るつもりか。」
「父さん、真顔でシンちゃんシンちゃん言うのはやめてよ…」
「そうではない。今は特別な事態なのだ。デブロンギヌス星系の空間の異常は君も聞いているだろう。」
「冬月、そこに行くつもりか。ますますいかん。もう絶対にいかん。いかんと言ったらいかん。マイ・リトル・シンちゃんを危ない目に合わせるなんてとんでもない話だぞ。」
「と、父さん、僕、じゃあ何で船長になってるの?」
「惑星ゼーレ。」
ぼそ、と言った副提督の言葉にふいに提督の動きは止まった。
「…何だと?」
立ち上がり、大声で何かを暗唱しだす副提督。
「宇宙暦2015.05.24。今日はユイに内緒でここの「聖ゴムずれ学」
「冬月。」
「何だ。」
「今回の作戦に限り船の指揮権はお前のものだ。」
「了解した。」「えええええーっ」
シンジは態度を豹変させた。さすが連邦一のドラ息子と陰で言われているだけの事はある。
「ちょ、ちょっと待って下さい父さん、何でこんな変な人の言う事なんか聞かなきゃいけないんですかあっ!
国境を越えようとしているんですよこの人! 大体「今回の作戦」って何なんですかあっ!」
「問題無い。通信を切るぞ。」
「ちょ、ちょとおおお」
「それじゃあな。」冬月はにっ、とゲンドウに微笑んだ。
フユツキの表情にモニタの向こうのロングヘアーのロミュラスカ人はビク、となった。
「気持ち悪いわねピカード。何ニヤニヤしてんのよお。」
エバンゲリオンのブリッジに立つフユツキは頷いて見せた。
「ああ、ラングレフ。君に呼びかけたのは他でもない。いつまでもお互い、こうやって睨み合いを続けていても仕方が無いだろう。そこで提案だが…両方とも目的のものは同じだ、ここはお互いに1隻だけづつ国境を越えて、調査する事にしようじゃないか。」
ラングレフはフユツキの提案にしばらく考える様子を見せる。
「むー。まあ良いわ、ただし互いに! 1隻づつよ、もし1隻でも多くあんた達が侵入してきたら」
「我々は戦いを望んではいない。そんな無益な事はせんよ。」
「そゆこと。」人差し指をさして、ラングレフの映像は消えた。
「それでは国境を越えて星系へ向かうとしよう、少尉、ワープ5だ。」
「了解、ワープ5。」
「テフロン星系に到着しました。」
「分かった副長。レイタ、時空の歪みをキャッチできるか。」
「目の前よ。」
「ビューワーに出してくれ。」
「了解。」
ぴっ。
「…これは…」
モニターには、恒星に匹敵する大きさの巨大なピンク色の渦状のガスのような物が浮かんでいた。
ピカードは思わず立ち上がっていた。
「レイタ、ビームを使ってフルスキャンしてくれ。」
「了解。」
「何ですか、これ…」
デブロンギヌス星系に到着したUSSネルフの前方にも、同じ渦が浮かんでいた。
「センサーの反応によるとこれは、「未知の物質」よ。」報告する副長。
船長の横に立つ副提督はふと呟いた。
「大きさが違うな…向こうの方が大きかった…」
「え?」
「ああ船長、何でもない。副長、物質のスキャンをしてくれ。」
「了解。」
「モニタに映すんだ!」
老冬月が言うのと同時にUSSマッコイのモニタにデブロン星系の映像が現れた。
「…」冬月は息を飲んだ。
「…見ての、通り…」
「何も、無いわ。」
どこか申し訳無さそうに言うシンジとレイ。
画面にはただの虚空が映し出されていた。
「スキャンには何か、出ていないかね。」
「いえ。」
レイが答える。
壁沿いのコンソールで指向性スピーカーに耳を傾けていた加持が冬月達の方を向いた。
「8472種族の通信を傍受。4隻のバイオシップが侵入者を追跡しているとのことです。」
「…」
「引き返すのかね。」アスカに聞く冬月。
「ここには何も無いのよ。」アスカは諭すように言う。
「そんなはずはないのだ。他の二つの世界ではちゃんと空間の異常があった。ここでも必ず、何かあるはずだ。レイ、何か空間の異常をスキャンする方法はないかね。」
レイは肩を上げる。
「方法はいくらでもあるんだけど。マッコイの設備では出来る事が非常に限られてしまうわ。」
「帰るわよ。」
「ちょっと待って。もし、ディフレクターを調整してマルチタキオンパルスを発射すれば、時空の歪みや亀裂等のスキャンが、可能になるかもしれないわ。」
「それだよ綾波!」
頷くシンジ。
「さっそく調整を始めるわ。」
「待って、それ、時間はどれ位かかるの。」
「約20分で調整は可能よ。」アスカに答えるレイ。
「分かったわ。」
アスカは頷きつつ艦長席に戻った。
「少尉、12分ほどここで待機、その後連邦の領域に戻るわよ。」
「いかん、そんな短い時間ではスキャンも出来んではないか!!」
「彼等のバイオシップは1時間で広大な領域内をジャンプ出来るのよ! それ以上は待つ訳にはいかないわ。…命令を遂行。」
少尉に伝えるアスカ。
こぶしを震わせつつ、アスカは顔を上げた。
「大佐。言わせてもらうけど、これは私の船よ。私の命令に、一々ケチを付けないでくれるかしら。」
「す、すまん…しかし、分かってくれ、事は人類の存亡にかかわる問題なんだ!」
アスカは溜息をつく。
「これだけは、言わないでおこうと思っていたけど…冬月大佐、あなたの、フェイズイルモディックは以前より進行しているの。全部、あなたの見ている夢かもしれないのよ。」
「…」
「…でも、大佐。皆、あなたの言う事だから、ここまで来たの。皆あなたの事を思っているわ。…それだけは、分かって。」
ぶり。
「あ、いや…」
アスカが青筋を立てて近づいた。
「今のを返事と受け取って良いのかしら?」
「これは言わば、時空の亀裂と呼ぶべき現象ね。サイズは直径約400億キロメートルよ。」
レイタが報告する。
「良く分からんな。ここが一番サイズが大きいのは何故だ。つまり過去に発生してこの時代に拡大し、更に未来になる前に消滅したという事か?」
呟くピカード。
「艦長、この亀裂は、通常のスキャンには反応しないわ。」
フユツキは思い出したように頷いた。
「ああ、そうか。ではレイタ、マルチタキオンパルスを使って、」
「マルチタキオンパルス?」振り返るレイタ。
「ああ、言い直そう、逆伝書鳩光線で、この亀裂のスキャンが出来るか。蟻動力ディフレクターを改造すれば、空間の亀裂を越えて伝書鳩を送れるだろう。」
レイタは無表情ながら、かなり感心したような様子でフユツキを見た。
「それは素晴らしいアイディアだわ。逆伝書鳩光線に、そのような使い方もあるのね…艦長がそれほどまでに時空理論に精通しているとは知らなかったわ。」
「いやあ、結構大した物だろう、はっはっはっは。」
「それでは逆伝書鳩の配合はこのサイズではどのように調整すべきかしら。」
「あぅうう、レイタ、作戦の細かな設定は君に任せる。さっそく始めてくれ給え。」
「了解。」
レイタは立ち上がり、ブリッジを後にした。
機関室にやって来たレイタは壁面のパネルの操作を始めた。
「ラ=フォージ少佐、それでは始めるわ。まず蟻動力ディフレクターの接続をバイパスする作業よ。」
「分かった。」頷くマコト。やはりパネルを忙しく操作し、リアクターの様子を確認しにレイタの近くにやってくる。
「あ、れ、れ、レイタああああ」
がすっ
「何。」
レイタを見るなり、マコトは急にレイタに抱き付こうとしてきた。沈めてから静かに尋ねるアンドロイド。
「す、好きだ、僕は君に会う為に生まれてきたんだああっ」
ぴぎゅん。
「フェイザーで撃つなあああ」
「少佐、大丈夫? 私はカウンセラーではないわ。」仕事の手を休めずに言うレイタ。
「ミサトさんなんかどうでも良い、僕は、僕は君のふくらはぎとチーズの臭いのする足の親指がああ」
ぴぎゅん。
じゅーっ。
「うぎゃああ」
「(少佐の脳に何か異常が?)…レイタより医療班、ただちに機関室へ急行。」
燃えかすを前にバッジを叩くレイタ。
「栄転神経という、脳にある、愛情をつかさどる神経のビリビリパルスが異常な勢いで発生しているわね。」
昆虫館医療室のドクター・クラッシャーはガムテープでグルグル巻きに拘束された患者を前に診断を下した。
「…ふう。」
リツコはお気に入りのヴァージニアスリムウルトラスーパーライトメンソールマイルドピアニッシモをふかすと、日立館医療室にやってきていたピカの方を向いた。
「これだけじゃないわ。さっきからここに、痴話喧嘩で怪我をしただの、膣痙攣で抜けなくなっただの、100トンハンマーで潰されただの、妙なクランケがひっきりなしにおしかけてきているわよ。」
ぴろりろりん。
「トロイより艦長。艦長、助けてくださぁい、私の部屋にカウンセリングを求めるクルー達が大挙して、た、う、うわあああ」どっぽーん。
ばしゃあっ。がぶ。がぶ。がぶ。
「きゃああああごぽごぽ、リンチンチン、私は餌じゃごぽごぽぽぽ」
ぶちっ。
通信を無言で切り、ピカードは隣のレイタに聞く。
「これは亀裂と何か関係があるのだろうか。」
「その可能性が高いわ。」頷くレイタ。
「恐らくあの亀裂は、私達の世界とは異なるパラレルワールドの入り口なのではないかと推測されるわ。」
「しかし私がタイムスリップしているのも一種のパラレルワールドだ。」
「でも、艦長がスリップしている過去や未来の世界は、聞く限りでは全ての世界にある程度の共通性が見られるようだわ。一方今亀裂で私達が対面している世界は、艦長の行き来している世界、ここも含めて、とは全く異なる異種の世界なのではないかと考えられるわ。おそらくその世界では、生命体は常に愛を中心に生活しているものと推測されるわ。」
フユツキは溜息をついた。
「だから、ここでもその影響が現れているという事か。しかしそんなラブラブワールドがどうして亀裂となって現れてきたのだ?」
「ラブラブワールド?」
「ああそうだ副長。あの空間の亀裂は、我々の世界とは別個のパラレルワールドとの接触で生まれた亀裂だと考えられないかね? そうするとセンサーに反応が無いのも頷けるだろう。しかし、逆タキオンパルスを使えば、亀裂を越えてスキャンが可能になると思わないかね?」
綾波副長は片方の眉を上げた。
「それは大変斬新で興味深い考えね副提督。どこでそのような」
「今説明をしている暇はない、出来るか?」
「…赤木博士の力を借りれば出来る可能性が、28.6%あると言えるわ。」
「やってくれ。」
「了解。」
「うむ…やはりここではサイズは向こうの半分も無いな…」
冬月はネルフの画面を眺めて呟いた。
「…船長、何かあったら呼んでくれ給え。自室にいる。」
「あ、アスカ、歯立てないで、あ、りょ、了解…」
ほっぽって歩いていく冬月。
ずががーん。
「一体どうした!」
ブリッジにやって来た冬月に、艦長席のアスカが怒鳴りかえす。
「バイオシップが来たのよ! 少尉、方位287、マーク321。最大ワープでだっ」
ずががーん。ずがーん。
「シールド34%にダウン! 船は4隻、全船損害は無い模様!」叫ぶシンジ。
「ワープエンジンに被弾、発進できません!」少尉が振り返る。
ずがーん。ずがーん。
「シールド15%! 後一撃でシールド消失!」
「加持さん、チャンネルを開いて。」
「どうぞ、艦長。」
「こちらはUSSマッコイ艦長綾波・アスカ・ラングレー、当船は医療船であり攻撃の意図は無い、繰り返す、こちら」
ずがーん。ずがががーん。
「きゃああっ」コンソールの火花に吹き飛ぶ操舵手。
「しょ、少尉!」
アスカが倒れた少尉に手をかける。彼女の息は既に止まっていた。
シンジがパネルを睨む。
「もう1隻船が現れた! …エンタープライズだ。」
クルー達がモニタを見る。そこには、遮蔽を外して現れた、限りなくヘラゴテに近いような形のエンタープライズGが颯爽と飛んでいた。
「艦長、通信が入ってるよ。」
「繋いで加持さん。」
苦みばしった表情のリツコの顔が現れた。
「副司令、やっぱりあなたは言う事を聞かなかったわね。今彼等の注意をそらすから、その間に逃げるように。」
通信は切れる。
エンタープライズからバイオシップに次々と遺伝子砲が発射される。途端に動きがフリーズし、数秒後爆発するバイオシップ達。しかし最後のバイオシップから、爆発の直前にマッコイへビームが発射された。
ずがががーん。
「エンジンへ被弾、ワープコアが変形していきます!」シンジが叫ぶ。
前触れ無しにマッコイに再び映像通信が入った。
「今、そちらの船のワープエンジンの異常をキャッチしたわ。全員こちらの船に直接転送します。…やって。」
立ち上がり転送に備えるマッコイのクルー達。
ぴぎゅいいいいいいん。
クルー達は無事エンタープライズのブリッジに転送された。
「ふう。」リツコは溜息をついた。
「副司令。あなたが言っても聞かないのは想像していましたわ。…でも、あなたは何?」
加持に向くリツコ。
「子供と副司令を危険にさらすような事にどうして協力するの!」
模様付きの目を細め、肩を上げる加持。
「元はと言えば、君が遮蔽能力のある船を貸さなかったから危ない事になったんじゃないのかい?
そりゃまあ、エンタープライズの艦長さんともなればそう簡単に規則を破る訳にもいかないだろうがねえ。」
「何ですって。私はあなたと違って、」
「言い争っている場合か! マッコイが爆発するんだぞ!」
「あ、そうね。大尉、エンジン全開で退却!」
「了解。」
ず、ずが、ずがあああん。
エンタープライズが発進すると同時に、マッコイは爆発した。
「…ねえ、アスカ。」ぼそ、と呟くレイ。
「え?」
「あなた、名字戻してなかったのね。」
「え? ああ、うん…」
「大尉、ワープ最大でここを脱出、連邦領域に引き返すわよ。」
「了解。」
冬月翁は赤木艦長に迫った。
「ま、待ってくれ! 連邦に引き返す訳にはいかん! 人類存亡の危機がかかっているのだよ!
ああ、もう絶対にいかんぞ! 赤木君、君には事の重大さが…ああ…」
冬月は背後からアスカにハイポスプレーを注射され、気を失った。
がた。
フユツキはけつまづきながら、習字の並ぶエバンゲリオンの廊下を歩いていた。
ぷしゅー。
彼はソ連館医療室に入った。
「ドクター、どくたあああ、無視しないで下さい、好きなんです、愛しているんです、本気なんですうううううくいっ。」
ドクターの「念」で気を失うナース。
「見ての通り、とうとうアリサもやられたわ。」
「うむ…」
「この調子でどんどんクルー達が色恋沙汰にだけのめり込むようになっていったら、船のコントロールはじき不能になるわよ。…今まで恋愛に縁の無かったクルー達が恋に落ちたりしても、喜んでいられるのは最初のうちだけ。このままでは全員変態プレイで死ぬか、その前に艦が乗っ取られるわね。」
「何としてでもこの亀裂の影響を止めなければならん。」
会議室に場を移し、フユツキはクルー達に言っていた。
「しかし、現在のこの亀裂はますます広がりを見せ、縮小する気配はまるでありません。」
「しかしそれでは困るのだよ。」副長に言う艦長。
「レイタ、スキャンには、後どれ位かかる。」
「約2時間20分かかる物と推測されるわ。」
「しかしもうこれ以上待つ訳にはいかん、スキャンはもちろん続行するが、君は至急あの亀裂をふさぐ方法を検討してくれ給え。」
「了解。」
「解散。」
クルー達は会議室を出ていった。
こきゅ、こきゅ。ぎゅるぎゅるぎゅるぎゅる…こきゅこきゅこきゅこきゅ。
「…」一人、腕をクルクル回しながら考え込むピカード。
「本当に、それで良いんですか?」
フユツキが顔を上げると、連邦の制服姿のKが机の向こう側に座っていた。
「一体亀裂の正体が何なのかも分からない状態で、下手に手を出して本当に良いんでしょうかねえ。」
「…それでは、手を出す事がこの世界が滅びる原因になるというのか?」
「そうかもしれませんね。」Kは例の信用性の無い微笑みを顔に浮かべた。
「あるいは逆に、手を出さない事が滅亡の原因になるのかもしれないし。…まあ、中々悩む所ではありますね。…この際少し気分を変えてみましょうか。」
Kは指を鳴らした。
2人は何も無い空間で、空中に唯一浮かぶディスプレイの前に立っていた。
「何だこれは? 私が昔良く読んでいた、エヴァ小説のページではないかね。…確か、めぞんEVA、だったか…」
「そうですね。まあ、あなたに分かり易くする為に、僕が例えていると考えて下さい。この世界は、ここの小説の一つなんです。」
フユツキは溜息をついた。
「何を言いたいのかね、K。我々は小説の、しかもアニパロ小説の、架空のキャラクター等になった覚えはないぞ。」
微笑んで頷くK。
「あくまで物の例えですよ。まあ、これは言わば、あなたの住む世界の物理等の法則を象徴化した物、と考えて下さい。全てのパラレルワールドには全ての異なる自然法側があります。そう、全てのめぞんの部屋に全ての異なるエヴァ小説があるようにね。」
Kはマウスを動かし、一つの部屋へのリンクにポインタを合わせた。
「603号室。ここの部屋の小説があなたの世界だとします。あなたの世界は、ラブラブ小説な世界ですか?」
「いや…しかし、あの亀裂の向こうはラブラブ小説の世界だという事だな?」
「あの亀裂から、ラブラブ小説の世界があなたの世界に混じりだしているんですよ。さあ、今のあなたの世界の部屋を見てみましょう。」
Kはマウスをクリックした。