シンジのノートパソコンのコール着信音が鳴った。実は、ごく一部の真面目な生徒以外は、授業時間とは即ちパソコンで交信をする時間だったりする。
シンジは、周りを見ながらそうっとキーを叩く。
「シンジ君、さっきはゴメンネ! でも、私がシンジ君を好きだって事だけは、ホントの気持ちなの。それだけは分かって。それから休み時間に、ちょっと。byマナ」
シンジが右手方向を見ると、マナが「ニコッ」と手を振っていた。
シンジは苦笑いをしながら、ごく小さく手を振り返した。
1時間目が終わった。
シンジはチャイムが鳴って、先生が「今日はここまで。」と言った途端に立ち上がり、アスカを追いかけに行こうとした。
はしっ
しかし、今、走ろうとして振り上げたシンジの右腕を、レイがつかんだ。
「碇君。」
「…あ、綾波?」
「行っては駄目。」
普段のレイからは想像も付かない、「積極的」な行動に周囲は表面的には知らん振りしつつ、皆、耳をそばだてていた。約1名はビデオを極秘裏に。
「あの、いや、アスカが。」
レイは、理由は良く分からないが今シンジがアスカを追いかけて行ってしまったらもう自分の所に戻って来ないような、とても嫌な直感に突き動かされてシンジの腕をがっちりと止めて動かさなかった。
「いや、あの…」
「碇君!」叫んだのはヒカリだった。
「ご、ごめん綾波!」委員長の言葉に促されて、シンジはレイの手を振り切り、教室を出て走って行こうと…
「駄目! シンジ君!」
マナが戸の前に立ちふさがった。
「き、霧島さん!?」
さすがに立ちふさがれては簡単に振り切るのは難しい。
マナはシンジの言葉に何故かムッと来たようだった。
「シンジ君、私が「シンジ君」って名前で呼んでるのに、どうして私の事を名字で呼ぶの?
第一話の最後では「マナさん」って言ってくれたから、私とても嬉しかったのに。」
「そ、それは多分へぼ作者さんが間違えただけなんじゃないかな…」
自分の言った台詞の責任も取ろうとしないシンジ。
委員長は自分の苦労が今までの100パーセント増(当社比)になった事をはっきり自覚して、肩でため息をついた。
「あの、霧島さん。碇君を通してあげてくれないかしら? その、アスカは…」
「シンジ君の親友なんでしょ?」出入口で大の字に両手両足を広げ、他のクラスメイト達に多大な通行の迷惑を掛けながら有無を言わせぬ調子で言うマナ。
「うっ…」ヒカリは一応アスカがそう言い切った以上ここで表立って否定するのもアスカの顔に泥を塗るようで、言葉に詰まってしまった。
突破口は最も意外な人物から開かれた。
「ごめん、霧島さん。僕とアスカは別に付き合ってるとか、そういうんじゃない。…ただ、ただの幼馴染なんだけど…だけど、その、アスカには、僕のせいで悲しんで欲しくないんだ。…何でアスカが怒ったのか、僕には良く分からないけど、多分、僕が悪いんだと、思う。だからアスカに謝らなきゃいけないんだ。通してくれないかな。」
マナは内心「分からない状態で謝っても、しょうがないんじゃない?」とも思ったが、シンジの真剣な顔に思わずシンジを
「むぎゅーっ」
抱きしめた。
「碇君!」殺気だつレイ。
「き、き、霧島さんふふふふ不潔よっ!!」電流を発生するイナヅマ委員長。
「き、きりしまひゃん」呼吸困難に陥るシンジ、何とかマナを引き離した。「ごめん、霧島さん、話は後で聞くから!」ようやく廊下に出て、アスカを探しに駆け出して行った。
「…馬鹿…話があるって、言ったじゃない…」マナは呟いた。
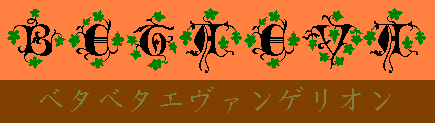
ここ第3新東京市立第壱中学校は市の高台に建っているので、ここの屋上からは市の高級住宅街が一望出来る。
しかしアスカには、そんな美しい景色も殆ど目に入らないようだった。
校庭では、体力の余っている野郎達が多分次の時間の体育のサッカーの準備をしている。皆楽しそう。
何であたし、こんな所で一人、バカみたいに柵によりかっかってんのかな…
アスカは顔を落とした。クオーターの彼女自慢の栗色の髪の毛が、きらきら輝きながら風に揺れている。
何で…飛び出しちゃったんだろう。シンジは、ただの幼馴染なんだから。あの無表情女だろうが変な転校生だろうが好きにさせれば良いじゃない。あたしは、別に、ただの…
ぽた、ぽた…
うっ…ヤだな、何であたし泣いてんだろ。こんな所シンジに見られちゃったら、勘違いされちゃうじゃ、ない…
「アスカ!」その時一番聞きたくない声が、アスカの耳に響いて来た。
アスカは今、あいつにだけは自分の顔を見せたくなかった。見せたくなかったので、声があいつの物であるかどうかを確認する必要があった。
アスカはシンジに自分の顔を見せてしまった。
「あ、アスカ…」
シンジはこんなに弱々しいアスカの顔を見るのは、本当に久しぶりだった。7才の、あの時以来だ。
アスカははっとなってシンジに背を向け、景色を見るような体勢をとった。
「な、何よ…」声が涙声になっているのは、如何ともしがたかった。
「アスカ…その、ごめん。」
アスカは思わず振り返った。
「あ、あんた何に謝ってるのよ。」振り返るときに、アスカの涙が頬から飛んで、キラリ、と輝いた。
「その…」シンジはアスカの見慣れぬ雰囲気に口篭もり、上目使いに彼女を見た。
「分からないんだ。」
「はあ?」
「分からない、けど…アスカが教室を飛びだしたのは、多分僕の責任だろ?
僕は、その、アスカが、僕のせいで嫌な思いをしたら…嫌だし、アスカが泣いたりしたら…僕も、何か、悲しいし」
何故かシンジは泣きそうになっていた。
「ば、バカね。別に、これはただ、ちょっと目にゴミが入っただけよ。」
アスカは心なしか顔を赤くして、また顔を背けた。
「ねえ…」アスカは、シンジがやっぱり今まで聞いた事の無いような調子で呟いた。
「え?」アスカに近寄るシンジ。
「私達って、ただの幼馴染だよね?…」
「う、うん。」
アスカの横顔は、既に2時間目のチャイムが鳴りだした事も、周りの状況も、今までの経緯も、吹いている風も、全部を一瞬忘れさせる程、周囲から浮き出て美しく見えた。
シンジは自分が唾を飲むのを意識した。
「ただの幼馴染、なんだけどさ…」アスカは自分の柵に掛けている腕に顔をうずめる。
「幼馴染が落ち込んでいる時は、ちょっとの間で良いから、抱きしめて、慰めてくれないかな…」
「うん。」
シンジは何故か、何の疑問も抱かずに、ごく自然にアスカを背後から包み込んだ。
「その…屋上だから寒いのよ。」
「…うん。」
確かにアスカの声は震えていたが、それが寒さによる物なのかどうかシンジには良く分からなかった。
…よっしゃよっしゃよっしゃよっしゃぅよぉっしゃぁーっ!
内心ガッツポーズを何度も繰り返すアスカ。
「やっぱり良くないよ、こういうの。」
「あんたバカぁ! さっきから説明してるでしょ、あんな後で、のこのこと教室に戻れる訳無いじゃない。鞄とかはヒカリが何とかしてくれるわよ。」
「で、でも…」
「しーっ! 静かに! 乙女の貞操の危機なのよ。」
「…間違えていると言うより、何が言いたいのかも分からないよ、アスカ。…作者さん、コメディ寄り過ぎ。」いかん間を空け過ぎて感覚がつかめん。
2人は教室の戸の、ガラスの入っている部分に頭が出ないように引っ込めながら、そろりそろりと下駄箱に到達した。
「でも、校庭には体育やっている生徒が居るし、大体1階の教室からは丸見えだし…」
「別に問題無いわよ。体育は私達のクラスじゃないし、1階は3年生のクラスだし、堂々としてれば別に怪しまれないわよ。」
「そ、そうかな…でも保健室が…」
1階の保健室には、2人が顔見知りの先生がいるらしい。
「うっ…そ、そうね…リツコの目には、入らないようにした方が無難ね…」
「何やってんだか…」
たまたま廊下を通りがかりに彼等を見付けた当学校の保健教諭、30才とは思えない端正かつ知的な美貌を誇る赤木リツコ先生は思わず自分が隠れて、彼等には聞こえない大きさの声でごちた。
「いいシンジ。脱出は、大胆、かつ素敵によ。」
「アスカ、間違えっぱなしだよ…」
「Gehen!」
2人の機敏な動きや、ごたごたを持ち込みたくない保健教諭に助けられ、2人は見事、誰にも気付かれずに中学校の無断早退に成功した。
あの人、嫌がる碇君を無理矢理連れ去ろうとしているわ…
完全な成功ではなかった。
「おや? 碇と惣流はどうした?」
「あ、あの…2人とも風邪で早退しました。」
「そうか。この時期に風邪とは、珍しいな。」
「え、ええ…」
ヒカリはその内アスカにフォロー料を払って欲しいと、少しだけ本気で思った。
レイはシンジ達を窓からでも呼んで彼女の行動を阻止しようか、と迷っていた。
呼び止めようかしら。でも今呼び止めると、あの人が糾弾されるわ。碇君は、あんな人でも、一応幼馴染だし糾弾されるのは悲しいはず。碇君、優しいから。でも悲しんでいる碇君は、私が慰めてあげよう。「気を落とさないで、碇君」「ありがとう、綾波」そして碇君は私の肩を抱いて、ああ、でも碇君、そんな事をしてはいけないわ、だって私とあなたは親族なのよ、「そんな事は関係無いよ綾波、これが禁じられた関係であろうが、僕は君の事が、君の事が!」「碇君!」「そこまでだシンジ。」「父さん!」「今だから話そう。彼女、綾波レイは実はグリューネ王国の姫なのだ。」「そんな!
綾波がお姫様?」「う、嘘…」「嘘ではない。シンジ、所詮お前と彼女では、身分が違うのだ。」「そんな事は関係ないわ碇君、愛さえあれば、私は」「あ、綾波…姫。」「碇君!!」(以下420k略)
アスカは屋上での寂しそうな表情は何処へやら、いつも通りの、いやいつも以上に元気な様子を見せていた。
アスカは北湖尻のデパートでショッピングをしようと提案したが、「補導されたら、この連載?までダーク物になっちゃうよ」というシンジの強硬な反対にあい断念、2人で学校に程近い北緑化公園を歩いていた。
公園と言ってもここは一目で見渡せてしまうような児童公園等ではなく、森のように広大で子供の頃からこの街に住んでいる2人でもたまに道に迷ってしまうような所だった。
「ねえ、アスカ。」
「なーに、シンジ。」
「あ、あの、手…」
アスカは(やっぱり)繋いでいた手を上げた。
「何、何かおかしい。」
「い、いえ、その…」
「あんたこうしとかないと絶対、道に迷うでしょ。あたしだって好きでやってる訳じゃないのよ。ただ、こんな近所で幼馴染が遭難して死亡したら、泣くに泣けないじゃない。」
「公園で、死亡はしないと思うんですけど…」
「うっさいわねえごたごたごたごた。」
2人は森を抜けて一種の小さな広場、歩道のロータリーのようになっている部分に出た。ロータリーの中は花時計になっている。
シンジは左手前のアスカの横顔が、とても眩しかった。
日差しの問題もあるし、もちろん元々(黙ってさえいれば)美人であるというのもあるのだが、それと共にほんの少しだけはにかみの入った、しかし全体としてはとても生き生きとした表情が彼女を見る者の心と時間を奪った。
「ね、ねえ、アスカ」
「あ、時計の向こうにアイス屋はっけーん!」ぶち。
アスカは20m先のロータリーの歩道に停車している、軽バンを改造したのであろうアイス屋を見ると、シンジと繋いでいた手をいとも簡単に振りほどいて一目散に駆けて行った。
「何だよ、もう。」
不満顔のシンジ。ケンスケ辺りに言わせればそもそも中学校をサボって女の子と2人で歩いているだけで死刑に値するのだが、シンジのより罪深い点はその有難さを本人が自覚していないという事に尽きる。
「碇君、ですよね。」
「え?」
目の前には、知らない女の子が立っていた。
シンジは、思わず額に手をやった。相当困っているらしい。
今、岸に戻ろうとすれば戻る事は出来るのだ。いや、まだ岸で何か叫んでいるアスカの為には、戻ったほうが良い。
しかし、今戻ったらこの子との約束を破る事になるし、最悪この子に危害が加わる危険性もある。いや、本当はそれより何より今、自分が岸に戻ったら自分の生命の保証が皆無に等しい。
「あ、あの、碇君?」
「ん、何?」
慌てて振り向き、愛想笑いをするシンジ。
「やっぱり気になりますか、惣流さんの事。」
「い、いやあ、そういう訳じゃ…」
相手はシンジの言葉に目を輝かせた。
「そうですよね! 碇君と惣流さんって、ただの幼馴染、なんですものね。」
「あ、う、うん…」
シンジはアスカの声に気付かない振りをしながら、池でボートを漕いでいた。
数分前。
シンジの目の前の女子はシンジに気付くと、顔を赤くして御辞儀をした。
「2Cの山岸、山岸マユミです。」
彼女はストレートのサラサラとした黒髪の美少女だった。レイやアスカ程ではないが色白で、「大和撫子」といった形容詞がぴったり来る。眼鏡をかけていて、小脇に本を抱えている。今までここの芝生に座って本を読んでいたのだろう。
「あれ? 今日は、学校は良いの?」
シンジは言ってしまって後悔した。自分達は何だというのだ。
「ああ、朝は私、熱が有ったんです。でも、しばらくしたら大分調子も良くなったので、公園で日に当たりながら本を読んでいました。」
嬉しそうに話すマユミ。
「へえ、そうなんだ。」シンジはマユミに自分達が何故ここにいるかの話を振らせないため、間髪を入れずに話題を変えた。
「本、好きなの。」
「え、ええ。」
「今は何読んでたの。」
「いや、恥ずかしいですよ、」シンジはマユミの持っている本の表紙を見ようとした。マユミと手が触れる。
「ご、ごめん! そそそんなつもりじゃなかったんだ。」体が引けるシンジ。
マユミは深呼吸をした。
「碇君、あの、話があるんです。2人きりで話せるところで、ちょっとだけ私の話、聞いて貰えませんか。」
「へ?」
マユミは言うなりシンジの手を引っ張って、駆けだした。アスカがニコニコしながら両手にバニラアイスを持ってシンジの居たところに戻ると、シンジは既に失踪していたのだった。
「で…話って、何なの?」
「…あのう…」
シンジは忍耐強く微笑んだ。
「どうしたの、山岸さん。」
「ええ…その…」目をしばたかせて、ユラユラ揺れる湖面を眺めている。
日本人形みたいだな…
シンジはそう思って彼女の横顔にしばらく見惚れた。まあ、昔の日本女性は眼鏡なんか掛けなかったのかもしれないけど。
「あの…私は、確かによく本を読みますけど、それは本当に本を読んでいるのでは、ないんです。」
「え?」
「ああ…変ですよね、私、言ってる事。その、読んでいても、ページをめくっていても、いつも頭にあるのは、碇君、あなたの事だけなんです。」
「へえー……………え、えええ?」
「はい。」
目をウルウルさせながら頷くマユミ嬢。
「そ、そう、なん、だ。」
「はい。」
「碇君は、今、好きな人は…」
「ああ。」シンジはようやく固まっていた体をほぐした。
「うん…良く、分からないんだ。皆僕に良くしてくれてるし、皆、僕に優しくしてくれる(そういう話だからね)。…僕も、皆の事が好きだよ、でも、それが、本当の、その、男の女の間の恋愛の感情なのかって言われたら、」
シンジはマユミの目を見た。
「良く分からないんだ、正直言って。僕は…まだ、人を愛した事は無いのかもしれない。」
「そうですか…」
既にアスカは怒って帰ってしまったらしく、ただ船が水面にぶつかる音のみが周囲を満たしている。
マユミはシンジの持っていたオールを取った。
「帰りましょう。」
「うん…」
「でも、これだけは覚えておいて下さい。碇君、私は、いつもあなたの事を思っています。これからも、ずっと。」
マユミの目には、何かキラキラ輝いているものがあった。
「…有難う。」
マユミは、ボートを漕ぎだした。
「僕が漕ぐよ。」シンジはマユミの方に手を差し出し、オールを受け取った。
「有難う。」
「どういたしまして。」
2人は微笑んだ。
岸に着いて、2人は別れた。
いや、そもそも誤解を招くような行動は頑として拒めば良いのだが、碇シンジの思考回路にそういう思考パターンは最初から組み込まれていないらしい。
女子からの頼みにはっきりいやと言えず、結果として他の(名前の無い)男子達の「あいつは壱中最悪のプレイボーイだ」という評価を受ける事になるのである。
しかし、それでもシンジの心にはさっきの公園での怒り狂うアスカが、ずっと引っ掛かってはいた。
まあ、まだ互いに良く見えない位の距離だったのが不幸中の幸い、だったんだろうか…
シンジは溜め息をついた。
さすがに一旦街中に出た後だと、アスカの行ってしまった場所はなかなか特定できない。それでもまわった事はまわったのだ。うららかな春の陽気の中、シンジは第3新東京中を走り回った。
アスカお気に入りの喫茶店、デパート、前に来た、街が一望できる丘…
どこにも彼女は居なかった。
そして、シンジは憂鬱な顔をしながら自分の家の前まで戻って来ていたのだった。
茶色の壁に焦げ茶の切妻屋根の自分の家。もちろんお隣は、コンクリート製の3階建ての惣流家だ。碇家と対照的に惣流家は非常に現代的なデザインなのだが、地域の条例があるらしく、色はシックなブラウンで周囲と調和が計られている。
シンジはもう走り疲れていたが、どうせここまで疲れたのだからやれる事は全部やろうと考え、アスカの家のインターホンを押した。
返答は無い。
しかし、よく考えてみればあの状況でアスカが家に帰ってしまったのだとすれば、アスカがインターホンに出るはずが無い。
「まさか」とは思ったがシンジは玄関まで歩いて行き、一応ドアを開こうとしてみた。
鍵は掛かっていなかった。
「アスカ、いるの?」シンジは家の中に入り、玄関から声をかける。
「すいません、誰かいませんか? …不用心だな…」
シンジとアスカは、お互い、家が共働きな事もあり、互いに相手の家にいついてもおかしくないような生活をしていた。とはいえ、最近はシンジがアスカの家に入る事は余り多くはないように思われた。
「ねえ、アスカ、いないの?」
平気で家にあがるシンジ。
シンジは2階のアスカの部屋の前に来た。一応ドアをノックする。
「アスカ、いないの? 入るよ?」
シンジは部屋のドアを開けた。
アスカがいた。
「あ、アスカ?」
アスカは自分の机とベッドの間の壁際で、床に体育座りをしていた。制服を着たままで、腕時計も外していない。顔は俯いていて、表情は分からない。
微かに肩と赤い髪飾りが揺れている。
「かえ、ってよ…」
「あ、アスカ、誤解なんだよ、ボートの事は」
「帰って。」
「アスカ、聞いてよ。僕は別に山岸さんとは、何にも無かったんだ。」
「帰って。」
「アスカ…」
「帰ってって言ってんでしょお!」
アスカはやおら立ち上がると、ベッドの上にあった猿のぬいぐるみを投げ付けてきた。それから机にある文房具やら、本やら手当たり次第。
シンジはショックで抵抗もせずに、ただ立ち尽くしていた。
「ご、ごめん…」
「そうよ、悪いのは全部あんたよ! 何にも分かろうとしないバカシンジよっ!
あたしの…あたしの心なんかちっとも分かっちゃいないのよ、あんたは! いっつもいっつも周りの女の子に愛想振りまいてニヤニヤしちゃってさ。その癖いざとなると「僕には良く分からないんだ」とか言って逃げる!
エヴァトレで他の作家さんに偉そうな事言ってる癖に自分の事は「ヘボ作家」とか自称して批判から逃げてるのよ!!」
「…アスカ、もしかしてまたボケてるね?」
「あんたは、あたしの事なんか分かってない、分かろうともしないのよ!」
「分かろうとしているよ!」
「してないわよお!」
近付くシンジをアスカは押し返す。
「しているよ!」
「嘘よ!」
「嘘じゃない!」
「嘘! 絶対嘘!」
「嘘じゃないよ!」
「じゃあ、じゃあ何であたしの気持ちに全然気付いてくれないのよお!」
大量の涙と若干の鼻水にまみれながらアスカは泣きじゃくってシンジを押した。
押されたシンジはアスカのベッドに座り込んだ。
「ア……スカ?」
「ずーっと好きなのに、こんなに好きなのに、どうしてあんたは気付かないのよう…」
興奮しているアスカは恐らく状況を把握していない。
「うう。う、うう…」
「あ、アスカ…」シンジは立ち上がって、アスカを抱きしめた。アスカも泣き疲れたのか既に抵抗しなくなっていた。
「あ…アスカ…」
「うう…」
「ごめん…アスカがそう思ってくれているなんて、今まで、考えた事も無かった。でも、アスカがそう思ってくれているのはとても嬉しいよ、本当に。……でも、今はまだ、僕はアスカの期待には、答えられないんだ。…ごめん。」
シンジはアスカの顔を見る。アスカは俯いていて、じっと動かない。表情は見えない。
「アスカが嫌いって事じゃないんだ。ううん、アスカは、僕は大好きだよ。…別に他にアスカより好きな女の子がいる、って事でもないんだ。ただ…分からないんだ。その、アスカへの感情が幼馴染としての「好き」なのか、恋人としての「好き」なのか。それに、僕は確かにアスカが好きだけど、それは他の人に対する物とは違うただ一つの、絶対的な、感情ではないんだ。だから、その…まだ、そういう期待には、答えられないと思う。」
自分で言いながら、抱きしめているアスカの体温と、胸の膨らみの柔らかい感触を意識してシンジは顔を赤くした。
「こ、こんな答え方しか出来ない自分がとてもふがいないよ。…でも、アスカには、嘘はつきたくないんだ。」
さっきから自分の腕の中でじっと動かず、一言も発していないアスカがシンジは心配になった。
「あ、アスカ?」
アスカ抱きしめていた手をやや離す。アスカは顔を上げた。
「すぴー」
アスカは寝ていた。だらしなく口を開けて。
シンジはしばらくこめかみが面白い具合にピクピク動いていたが、「ふう」と溜め息をつくとアスカをそっとベッドに寝かせ、タオルケットをかけて、自分の家に戻った。
翌朝。
シンジは昨日の夜から今朝にかけてぐっすり寝ていた。あの後鞄を届けに来たヒカリに気付いて大急ぎで外に出て、「アスカは今寝てるから」と説明したり、ヒカリに30分以上小言をブチブチ言われたり、その鞄を持って又アスカの家に入って鞄を置いて来たり、マナが怒って電話をかけて来た(緊急連絡簿で電話番号を調べたらしい)のをなだめたり、まあ色々有ったのだ。
マナは、自分が「霧島さん」と呼ばれるのが力士みたいでイヤだ、という事らしく、シンジに自分を「マナさん」と呼ばせる事を数時間かけて説得したのだった。これも当初の「マナ」「マナちゃん」「マナっち」「ナっちゃん」「マーナ」「マナ2000」「スーさん」「社長」(この辺ウソ)等の案よりは大分妥協・後退した呼称だ。シンジは特にこの電話の相手で疲れきったと言って良いだろう。
シンジはしかし、意外にも頑丈であるらしく、朝にもなるとその眠りも比較的浅いものになりつつあった。いわゆるレム睡眠だ。
「アスカ、ごめんよ…僕も、アスカの事は好きだ…けど…むにゃ」
シンジのベッドの隣に立っていたアスカ(いたのだ)は沸騰した。
「し、シンジ今何て言ったの? あ、「アスカ、ごめんよ、(僕なんかが君を好きになるのは身分不相応だとは知っているけど、)僕はアスカの事が好きで好きでたまらない」って、言った?」
言ってない。
「し、シンジが、そんな事を思っていただなんて…」
思ってない。
のだが、アスカは目が少女マンガになっている。
「山岸…さん…マナ…」間の悪い寝言を放つシンジ。ベタである。
「ぬぁああんだとコラ、今なんと抜かしたああああああぁ!」パジャマの襟首をつかみ、シンジの首をグラグラ揺らすアスカ。
「正義の拳をお見舞いしちゃるきに!!」
ごすっ、と言う中途半端に低い音と共に、シンジは崩れさった。
「きゃー、シンジ、大丈夫?」
何故か周囲の背景を含めて真っ白に燃え尽きているシンジを慌てて揺さぶるアスカ。
「あ、あ、アスカか……あ、アスカ!?」飛び起きるシンジ。
「ど、どどどうしたの?」
「朝だから起こしに来たのよ? 全く、少しは感謝して欲しいわよねー。毎日こんな美人の幼馴染が起こしに来てやってるんだからさ。」
シンジを燃え尽きさせた事は既に忘却の彼方、ニコニコ答えるアスカ。便利な性格である。
シンジの返事は、いつもと少しだけ異なるものだった。
「あ、ありがと。」シンジはアスカから目を外し、顔を少し赤くした。
「あの、昨日は、ごめん。」
アスカは眉を上げた。
「はあ?」
腕組みをするアスカ、やがてポンと手のひらを叩いた。
「そうそう、あんた勝手に公園から帰るんじゃないわよ、何があったか知らないけどさ。レディーに対してそのような無礼は、死に値するわ。」
「あ、はあ…覚えてないの?」
「何をよ?」
「あ、うん、いや、その…アイス、僕の分も買ったんでしょ? まだ、お金払ってないから、ね?」
どうやらアスカはアイスを買って以降の事を覚えていないらしい。それもそのはず、ここのアスカは、都合の悪い事は全部忘れてしまう「キーホルダー」アスカだったのだ!(ってオイ!)
「シンジ大丈夫? 汗かいてるわよ?」
「だ、大丈夫だよ、全然。」声が裏返るシンジ。
「なら良いけど…お金は、気にする事無いわ。」アスカは天使のように微笑んだ。
「既にあんたの財布から利子付きで抜き取ってるから。」
「え。」
「抜き取る」、という動詞に紙のお金の連想が浮かび、青くなるシンジ。
「もちろんそれとは別に今日の放課後はおごってもらうから。精神的ショックの慰謝料としてね。」
いずれにしてもシンジが今日も苦労するのは明らかなようだった。
呆然とするシンジは、ふと机のデジタル時計を見た。
「あ、もうこんな時間だ!」
「ああっ! もう遅れたらあんたの責任よっ!」
「ごめんよ、すぐ準備するから!」
「きゃーっ! あたしの目の前で着替えださないでよ、エッチバカ痴漢変態オナキング(株)ー!」
「ここは僕の部屋だろ! それから(株)ってどう発音してるんだよ、「かっこかぶ」か?」
「あんたこそ今どうやって発音したのよ!」
ユイは今日も溜め息をついた。
「しょうがないわねえうちの子ったら。今日もアスカちゃんに迷惑をかけているわね。」
「ああ。」
ゲンドウは新聞を開いたままだ。
「今日は、私達の出番はこれだけなのかしらね。」
「問題無い。」
「問題有ります。」
ユイは洗い物をする手を止めて、きっとゲンドウを睨んだ。
「うっ、し、しかし、冬月先生やオペレーター上がりの中学校教師達に比べれば、まだ出番が有るだけ増しと言うものだ。」
「それはまあ、そうですけど…」
アスカとシンジは1階に駆け込んで来た。
「おはよう。」ユイに(のみ)言うシンジ。アスカはもちろん既に2人へ挨拶を済ませている。
「おはようシンジ、はいお弁当。じゃあアスカちゃん、今日もシンジをお願いね。」
「は、はい…(何を?)」
「シンジの将来の妻として、しっかりシンジの監督を」
「「行ってきます(、おばさま)。」」シンジとアスカはユイの返事を聞く前に逃げ出して、いや登校して行った。
2人は今日も大きめの歩道のある並木道をダッシュで走っていた。
「あーもう今日もこのままだと遅れちゃうじゃなーいー!」
「ご、ごめんよアスカ。」
「ごめんですんだら警察とモサドは要らないわよ!」
「な、何故モサド…」
2人はそもそも常に走らないと遅刻をするようなぎりぎりの時間に家を出るのだが、今日は2人の漫才が長めだった為に特に厳しい状況だ。2人とも脇目もふらずに走っていた。
シンジは昨日「マナさん」とぶつかった交差点の前まで走って来た。
待てよ、「ベタベタ」って事はやっぱりここで誰かに…
ごっちーん。
「あいったー。」
ぶつかった。
「大丈夫かい、君。」
まだ焦点の座らない目で見上げると、彫りが深く、レイのように肌が白く目の赤い、銀髪の美少年が優雅に手を差し伸べていた。
シンジもまあそれほど悪い顔ではないのだが、特別「美少年」とは言えない。しかしこの少年は正に「美少年」という言葉がぴったりだった。顔の作り、微笑を浮かべた表情、物腰、何処にも隙が無く、むしろその為に不自然さを感じさせた。
「あ、す、すいません。」
「構わないさ。僕も不注意だったんだ。急いでいるものでね。」
その割には余裕のある態度で話す少年。
「あ、そうなんだ。でも、僕が不注意だったよ。ごめんね。」
「君は自分が痛みを覚えている時にも、相手の事を気遣ってくれるんだね。」相手は更に微笑んだ。
「いや、その…」
シンジの手を取る美少年。
「好意に値するよ。」
「へ。」
「好きって、事さ。」ニコ、っと微笑む少年。
「あ、有難う…」何故か照れるシンジ。
「だー、もう何やってるのよシンジ、遅れるわよ!」
「あ、そうだった! じゃあ、ごめんね!」
アスカにずるずると引きずられて行くシンジ。
「ああ、君! まだ名前も聞いていないのに!」
彼は名残惜しそうに手を差し伸べた。
「お、今日も2人は重役出勤、もとい社長出勤か。羨ましいやっちゃなー。」
何とか朝のホームルームに間に合ったらしい2人をいつも通りからかうトウジ。
しかし今日彼に反論したのはアスカではなかった。
「ジャージ君! シンジ君に何て事言うの!」
「な、何や転校生。」
「シンジ君と惣流さんはおーさーなーなじみよ、ただのね。」
誇らしげに言い放つマナ。クラス全員の目がアスカの反応に注目する。
「ぜえ、ぜえ、ぜえ」
アスカは走り過ぎてへばっていた。
「そうでしょ、ねー、シンジ君。」
「あ…ハア…ええと…ハア…そうだね…ハア…き」
「き!?」
「あ、あー、マナ、さん。」
シンジの返答にビク、っとするアスカとレイ。
「碇君。」
「な、何、綾波。」
「わ、私も…」
自分の机を立ち上がったまま動かなくなっているレイ。真っ白の頬と耳が見る見る紅潮して行く。
「何でもないわ。」
「そ、そう…」
「あーっもうあなた達2人の会話っていらいらするわねえ。とにかく。シンジ君と恋愛関係にあるのはわた」
「ち、違うよ、そんな事無いよ!!」
アスカが最後の力を振り絞ってシンジの首絞めにかかるのを逃げようと懸命のシンジ。
「むー。まあ良いわ。少なくとも恋人候補よね、私が唯一の。」
「碇君は渡さないわ。」
「あれ、綾波さんもシンジ君の事が好きだったっけ?」
「好き? 分からないわ。」
うっ、この子と会話ってやりづらいのよね…って、別にアテレコ大変って意味じゃなくってよ…
「でも、分かる事は、碇君は私が守る。そしていつか、碇君と一つになる…」
「「「えええ!!!!」」」
逆にそう言った所までは想像の回らないらしいレイは周囲の絶叫にきょとんとしている。
「僕も、混ぜてくれないかな、その、碇シンジ君の恋人候補に。」
教室の入り口から少年が入って来た。後から疲れた表情のミサトが着いて来る。
「紹介するわ。今日、新しく入って来た転校生よ。」
少年は黒板に自分の名前をローマ字で書いた。
「渚カヲルです。よろしく。」
「私だけ違うクラスで、何だか不利だと思います…」
その頃マユミはA組の様子をノートパソコンから傍受していた。
山岸マユミちゃん登場(^^)/
数多いEVAキャラの内で、
世間の知名度に対して私の中での知名度が低いのが彼女です・・(^^;
何しろ彼女の出演作【SAGAゲー:セカンドインプレッション】って。あれでしょう・・
きちんと最後までやることが出来なかったんですよ。
一応数回はしているんですが、
私のプレーは何しろ「アスカちゃん!アスカちゃん!」なもんで(爆)
EVAに踏まれそうになっていた姿をチラッと見ただけです。
ベタベタと言いながらも
パロディを折り込み、
さりげなく喧嘩を売り、嘘嘘(^^;>
そこはかとなく自省をこめ・・・
クリスマスが待ち遠しいですね(^^)
さあ、訪問者の皆さん。
様々な作品を書くフラン研さんに感想メールを送りましょう!